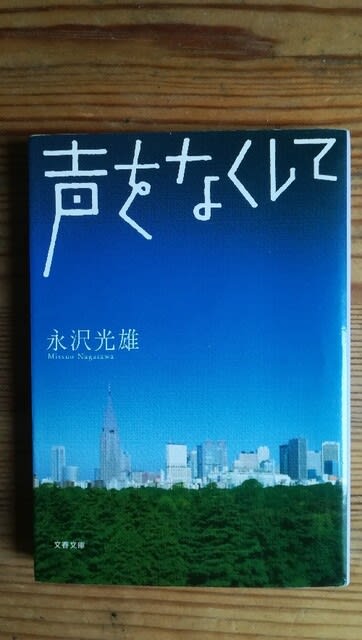本日読了。
原題「Laëtitia ou la fin des hommes」
著者 Ivan Jablonka
邦訳『歴史家と少女殺人事件―レティシアの物語』
アマゾン、書評つき
日本語目次
『文藝春秋』(2020年10月号、評者:佐久間文子氏)
“…… 失踪現場から始まり、最後にまた事件の夜に戻っていく。調査の過程を明らかにしながら徐々に真実に迫る構成は、上質のミステリを読むようにゾクゾクさせられる。
本書をこんなふうに評するのは、僕には到底できない。
そうするには、僕は、この物語とあまりにも時空を共有しているから。
2011年、ナント、サン・ナゼ―ル、レンヌ、アンジェ、車がないと生活できないフランスの地方都市、冬の朝、真っ暗な中、学校へ通う子供たち、幾度も繰り返される児童相談所の職員たちとの話し合い、家庭裁判所のどうしようもなく重苦しい雰囲気、判決、里親、児童養護施設・・・。
そして僕にとって、本書はむしろ、この事件と共に歩む著者の内省にこそ、その本質がある。
彼の「私小説」と言ってよいほどの側面こそが、大切なのだ。
そのことは、書物のタイトルとしては非常に日本語に訳しづらい、副題に現れている。
ペーパーバック版383頁から384頁:
「人間(homme)として、レティシアの苦しみを我が身に引き受けることは難しい。レティシア…シェパードに子守りされていた赤ん坊…あちこちに引っ張りまわされた子供時代…自分のトラウマを言葉にできない…回りの嘘に耐えかね、死後、一冊だけ持っていた本を贈り、臓器提供をしようとしていた若者…彼女の胴体は、幾度もナイフで傷つけられ、池に浮かんでいた…。
男(homme)としては、もっと酷い。ジェシカの前でしばしば気まずさを感じたのは、私が一人の男だからであり、男たちが、彼女の人生を通してずっと彼女を痛めつけてきたからだ。男たちとは、口論の果てカッターナイフで切りつける者であり、拳で殴り顔を腫れ上がらせる者であり、自分が持たされたペーパータオルに射精する者であり、自分を刺し殺し、自分の首を鶏のそれのようにへし折る者である。男たちにとって、自分は快楽の対象か、そうでなければ嬲り物にすぎない。あるいは、男たちとは、大臣や指導者、テレビに出て、物知りで、命令し、常に正しく、自分について、自分に覆いかぶさって、自分の中で、自分を通して話す者である。結局、自分は男たちの望むモノにされるのだから、勝つのはいつも男たちなのだ。
私は生まれて初めて、私の性を恥じた。」