初詣でに信濃國一之宮の諏訪大社へ。神位は正一位で末社含め全国25,000社に及ぶ諏訪神社の総本社です。下社春宮と秋宮が有名ですが、大混雑必至なので上社前宮へ行くことにしました。その前に、すぐ近くにある世界的建築家の藤森照信氏の神長官守矢史料館・高過庵・空飛ぶ泥舟へ寄りました。藤森さんは、私にとっては建築家というより70~80年代に赤瀬川原平さんの「路上観察学会」のメンバーのひとりという記憶のほうが強いのです。白夜書房の『写真時代』とかセルフ出版の『ウィークエンドスーパー』などはよく買っていました。カメラマンの荒木経惟さんの作品が見られる貴重な雑誌でもありました。「超芸術トマソン」は、一世風靡したので覚えている人も多いのではないでしょうか。

「神長官守矢史料館」(左)。江戸時代まで諏訪大社上社の神長官をつとめた守矢家の敷地内にあります。正月なので残念ながら休館でした。諏訪産の鉄平石の屋根を突き破って延びる木が印象的です。外壁は椹(サワラ)の割板。守矢家の史料だけでなく、武田信玄や村上義清、真田昌幸などの史料もあるそうです。
2010年に米国 Time 誌が発表した「世界の危険な建物トップ10」にも選ばれたという世界で最も危険な茶室「高過庵(たかすぎあん)」(中)。ハシゴは外されていて登ることはできませんが、どんな景色が見えるのでしょう。こんなところで一服いただくのも緊張感があっていいかもしれません。右は「空飛ぶ泥舟」。空飛ぶ茶室ですね。一坪で重量は600キロとか。6人が入れるそうですが、うむ。千利休に見せたい。茶道は元々戦国時代に本陣で死に向かい合う武士が嗜むものでした。浮遊する茶室は、諸行無常の形而上的な表現にも繋がるのかも知れません。まあ実際は微妙に揺れて一服どころではなく、「いいお手前でした。ブワッ!」っと鼻から茶を吹き出す爆笑茶会になるのかも知れませんが。それも一興。

「空飛ぶ泥舟」。左下に小さな入口(にじり口)があるのですが、これは中で動くとかなり揺れそうですね。手前には畑というのもお洒落です。バックには茅野市民の憩いの山、永明寺山(1119.6m)が。山頂付近は永明寺山公園として整備されています。左手前の小ピークには、武田信玄由来の上原城址があります。背後にあるソーラーパネルの違和感が顕著。クリーン・エネルギーの様にいわれていますが、実際は製造や廃棄の際に、カドミウムやカドミウムテルル、鉛などの有害物質を出します。安全な廃棄方法さえ確立されていないのが実情です。加えてパワーコンディショナから出る有害な電磁波の問題もあります。こちらの記事のように個人差があるのも特徴です。人間は人工電磁波に耐性がありません。電磁波も放射線の一種。リニアモーターカー? 電子レンジに乗って旅をしたいと思いますか。

神長官(じんちょうかん)守矢家(左)。諏訪大社の祭神・建御名方神 (たけみなかたのかみ)が来る前からこの地にいたという一族です。土着神の洩矢神(もりやしん、もれやしん)や守矢家については、子孫にあたる方が『私の諏訪考』という非常に詳細な興味深いサイトを開いています。「神長官守矢史料館」から「空飛ぶ泥舟」へ行くには、大祝(おおほうり)諏訪家の墓所を抜けて行きます(中)。この上には守矢家の墓所もあります。
墓所のすぐ上に鎮座する御左口神(ミシャグジ神)信仰の中枢とされる御左口神社(右)。社の近くには二本のカジノキ(クワ科)があります。カジノキは諏訪大社の御神紋でもあります。
---諏訪地方では特に諏訪の蛇神であるソソウ神と習合されたためか白蛇の姿をしているともいわれており、建御名方神や洩矢神(モレヤ神)と同一視されることもある。(wikipedia)

諏訪の祭祀の発祥地とされる諏訪大社上社前宮へ(左)。ここは大祝(おおほうり)の始祖といわれる有員(ありかず)が初めて大祝の位について以来、同社大祝代々の居館であったところと書かれています(中)。ここに書いてある1483年の内訌ですが、時は戦国時代で大祝も武士化し、祭政分離のため惣領は兄の諏訪信満が継ぎ、大祝は頼満が継承したのですが、対立し諏訪氏は分裂。この対立はそれぞれの子の政満(惣領家)と継満(大祝家)の代にも継続し、ついに文明15年(1483)に、継満は一族の高遠継宗や金刺興春と組んで、従兄の政満らを謀殺しました(文明の内訌)。しかし、惣領家の家臣の反撃に遭い、継満は伊那に逃亡しました。この最中、隠居の頼満は病床にあったため逃げ遅れ、討ち取られています。
鳥居をくぐって更に200mほど登りますが、脇に民家があり、なんだか不思議な感じがします。境内には水眼(すいが)川が流れていますが、ペットを洗わないでくださいという看板が妙にリアルでした。

諏訪大社上社前宮拝所。江戸時代までは「前宮社」として上社境外摂社筆頭の社格を有して鎮座していたのですが、明治以降上社の前宮と定められたということです。下社や上社本宮に比べると参拝者も少なく、静かに詣でることができます。

神社の四隅に立つ御柱(左)。この裏山は、守屋山へと続いています。次に上社本宮まで歩きました。道中の道路は参拝者の車で大渋滞です。歩くにかぎります。旧杖突峠への入り口道標(中)。「従是北 高島江 一里二十丁」「東 金沢宿 二里二丁」「南 御堂垣外宿 二里二十丁」と刻まれています。本宮(ほんみや)東側の入り口前のお洒落なカフェ(右)。正月で休みでしたが、八ヶ岳連峰が綺麗に見えるはずです。

本宮は、赤石山脈北端の守屋山北麓に鎮座します。神橋を渡り本宮に入ります(左)。入口御門の木彫は、文政十二年(1829)建立。上社宮大工棟梁である原五左衛門親貞とその弟子藤森廣八(諏訪立川流)が構築し巧微な彫刻が施されている。とあります(中)。ちなみに秋宮は諏訪立川流の立川和四郎富棟で、神楽殿は子の富昌。春宮は大隅流の伊藤長左衛門です。布橋(右)は、古くは大祝のみが渡り、布が敷かれたことからそう呼ぶのだそうです。

本宮摂社 出早社(左)。祭神・建御名方神の御子で、長野市松代の皆神山山頂にある皆神神社の祭神で、出速雄命(いずはやおのみこと)とも書きます。その御子が妻女山の麓にある会津比売神社の祭神・会津比売命(あいづひめのみこと)で、ふたりは科野国(埴科更科)の産土神(うぶすながみ)と呼ばれています。会津比売命の夫は神武天皇の後裔といわれる武五百建命(たけいおたけのみこと)で、崇神天皇の御代に初代信濃國造に任命された人で、森将軍塚古墳に埋葬されているといわれています。関連記事は、右上のブログ内検索でどうぞ。
本宮摂社 大國主社(中)。祭神・建御名方神の父で、大国主命(おおくにぬしのみこと)。出雲大社の祭神です。右は布橋から見た神楽殿。大きな太鼓が目を引きます。

こちらが参拝者が詣でる表参道(左)。もの凄い人です。重要文化財の四脚門(中)。慶長13年(1608年)、徳川家康が大久保長安に命じて建立させたもので、かつては大祝だけが最上段にある硯石へと登るために使ったそうです。拝殿の木彫も入口御門と同じく諏訪立川流の素晴らしい木彫です(右)。

杖突峠の展望台から俯瞰する諏訪の街と諏訪湖。左に高ボッチ山、その右に鉢伏山。右奥には美ヶ原の王ヶ頭。この暖冬では、諏訪湖も結氷しませんね。新年の信濃毎日新聞に、諏訪大社上社の旧神宮寺の本尊が確認されたという記事が載っていたのでスクラップしました。神仏習合の貴重な遺物で、明治の廃仏毀釈の難に遭うも住民が守りつづけたものだそうです。

右を観ると左に蓼科山。右へ八ヶ岳連峰が続きます。真冬だというのに本当に雪が少ない。これからどうなるのか本当に気がかりです。今年は諏訪大社の御柱祭りがあります。大変な賑わいになるでしょう。それにしても、なんだか妙に胸騒ぎのする新年です。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。陣馬平への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
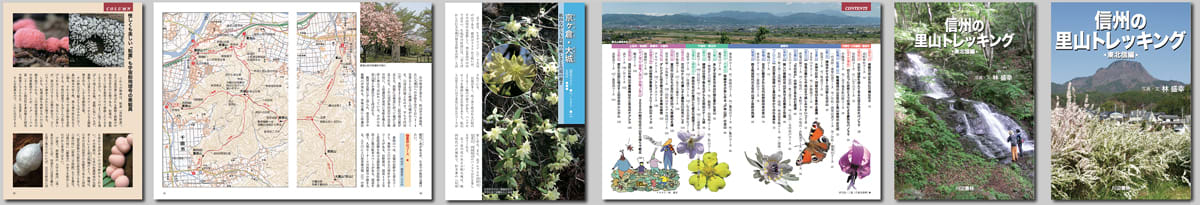
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。







「神長官守矢史料館」(左)。江戸時代まで諏訪大社上社の神長官をつとめた守矢家の敷地内にあります。正月なので残念ながら休館でした。諏訪産の鉄平石の屋根を突き破って延びる木が印象的です。外壁は椹(サワラ)の割板。守矢家の史料だけでなく、武田信玄や村上義清、真田昌幸などの史料もあるそうです。
2010年に米国 Time 誌が発表した「世界の危険な建物トップ10」にも選ばれたという世界で最も危険な茶室「高過庵(たかすぎあん)」(中)。ハシゴは外されていて登ることはできませんが、どんな景色が見えるのでしょう。こんなところで一服いただくのも緊張感があっていいかもしれません。右は「空飛ぶ泥舟」。空飛ぶ茶室ですね。一坪で重量は600キロとか。6人が入れるそうですが、うむ。千利休に見せたい。茶道は元々戦国時代に本陣で死に向かい合う武士が嗜むものでした。浮遊する茶室は、諸行無常の形而上的な表現にも繋がるのかも知れません。まあ実際は微妙に揺れて一服どころではなく、「いいお手前でした。ブワッ!」っと鼻から茶を吹き出す爆笑茶会になるのかも知れませんが。それも一興。

「空飛ぶ泥舟」。左下に小さな入口(にじり口)があるのですが、これは中で動くとかなり揺れそうですね。手前には畑というのもお洒落です。バックには茅野市民の憩いの山、永明寺山(1119.6m)が。山頂付近は永明寺山公園として整備されています。左手前の小ピークには、武田信玄由来の上原城址があります。背後にあるソーラーパネルの違和感が顕著。クリーン・エネルギーの様にいわれていますが、実際は製造や廃棄の際に、カドミウムやカドミウムテルル、鉛などの有害物質を出します。安全な廃棄方法さえ確立されていないのが実情です。加えてパワーコンディショナから出る有害な電磁波の問題もあります。こちらの記事のように個人差があるのも特徴です。人間は人工電磁波に耐性がありません。電磁波も放射線の一種。リニアモーターカー? 電子レンジに乗って旅をしたいと思いますか。

神長官(じんちょうかん)守矢家(左)。諏訪大社の祭神・建御名方神 (たけみなかたのかみ)が来る前からこの地にいたという一族です。土着神の洩矢神(もりやしん、もれやしん)や守矢家については、子孫にあたる方が『私の諏訪考』という非常に詳細な興味深いサイトを開いています。「神長官守矢史料館」から「空飛ぶ泥舟」へ行くには、大祝(おおほうり)諏訪家の墓所を抜けて行きます(中)。この上には守矢家の墓所もあります。
墓所のすぐ上に鎮座する御左口神(ミシャグジ神)信仰の中枢とされる御左口神社(右)。社の近くには二本のカジノキ(クワ科)があります。カジノキは諏訪大社の御神紋でもあります。
---諏訪地方では特に諏訪の蛇神であるソソウ神と習合されたためか白蛇の姿をしているともいわれており、建御名方神や洩矢神(モレヤ神)と同一視されることもある。(wikipedia)

諏訪の祭祀の発祥地とされる諏訪大社上社前宮へ(左)。ここは大祝(おおほうり)の始祖といわれる有員(ありかず)が初めて大祝の位について以来、同社大祝代々の居館であったところと書かれています(中)。ここに書いてある1483年の内訌ですが、時は戦国時代で大祝も武士化し、祭政分離のため惣領は兄の諏訪信満が継ぎ、大祝は頼満が継承したのですが、対立し諏訪氏は分裂。この対立はそれぞれの子の政満(惣領家)と継満(大祝家)の代にも継続し、ついに文明15年(1483)に、継満は一族の高遠継宗や金刺興春と組んで、従兄の政満らを謀殺しました(文明の内訌)。しかし、惣領家の家臣の反撃に遭い、継満は伊那に逃亡しました。この最中、隠居の頼満は病床にあったため逃げ遅れ、討ち取られています。
鳥居をくぐって更に200mほど登りますが、脇に民家があり、なんだか不思議な感じがします。境内には水眼(すいが)川が流れていますが、ペットを洗わないでくださいという看板が妙にリアルでした。

諏訪大社上社前宮拝所。江戸時代までは「前宮社」として上社境外摂社筆頭の社格を有して鎮座していたのですが、明治以降上社の前宮と定められたということです。下社や上社本宮に比べると参拝者も少なく、静かに詣でることができます。

神社の四隅に立つ御柱(左)。この裏山は、守屋山へと続いています。次に上社本宮まで歩きました。道中の道路は参拝者の車で大渋滞です。歩くにかぎります。旧杖突峠への入り口道標(中)。「従是北 高島江 一里二十丁」「東 金沢宿 二里二丁」「南 御堂垣外宿 二里二十丁」と刻まれています。本宮(ほんみや)東側の入り口前のお洒落なカフェ(右)。正月で休みでしたが、八ヶ岳連峰が綺麗に見えるはずです。

本宮は、赤石山脈北端の守屋山北麓に鎮座します。神橋を渡り本宮に入ります(左)。入口御門の木彫は、文政十二年(1829)建立。上社宮大工棟梁である原五左衛門親貞とその弟子藤森廣八(諏訪立川流)が構築し巧微な彫刻が施されている。とあります(中)。ちなみに秋宮は諏訪立川流の立川和四郎富棟で、神楽殿は子の富昌。春宮は大隅流の伊藤長左衛門です。布橋(右)は、古くは大祝のみが渡り、布が敷かれたことからそう呼ぶのだそうです。

本宮摂社 出早社(左)。祭神・建御名方神の御子で、長野市松代の皆神山山頂にある皆神神社の祭神で、出速雄命(いずはやおのみこと)とも書きます。その御子が妻女山の麓にある会津比売神社の祭神・会津比売命(あいづひめのみこと)で、ふたりは科野国(埴科更科)の産土神(うぶすながみ)と呼ばれています。会津比売命の夫は神武天皇の後裔といわれる武五百建命(たけいおたけのみこと)で、崇神天皇の御代に初代信濃國造に任命された人で、森将軍塚古墳に埋葬されているといわれています。関連記事は、右上のブログ内検索でどうぞ。
本宮摂社 大國主社(中)。祭神・建御名方神の父で、大国主命(おおくにぬしのみこと)。出雲大社の祭神です。右は布橋から見た神楽殿。大きな太鼓が目を引きます。

こちらが参拝者が詣でる表参道(左)。もの凄い人です。重要文化財の四脚門(中)。慶長13年(1608年)、徳川家康が大久保長安に命じて建立させたもので、かつては大祝だけが最上段にある硯石へと登るために使ったそうです。拝殿の木彫も入口御門と同じく諏訪立川流の素晴らしい木彫です(右)。

杖突峠の展望台から俯瞰する諏訪の街と諏訪湖。左に高ボッチ山、その右に鉢伏山。右奥には美ヶ原の王ヶ頭。この暖冬では、諏訪湖も結氷しませんね。新年の信濃毎日新聞に、諏訪大社上社の旧神宮寺の本尊が確認されたという記事が載っていたのでスクラップしました。神仏習合の貴重な遺物で、明治の廃仏毀釈の難に遭うも住民が守りつづけたものだそうです。

右を観ると左に蓼科山。右へ八ヶ岳連峰が続きます。真冬だというのに本当に雪が少ない。これからどうなるのか本当に気がかりです。今年は諏訪大社の御柱祭りがあります。大変な賑わいになるでしょう。それにしても、なんだか妙に胸騒ぎのする新年です。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。陣馬平への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
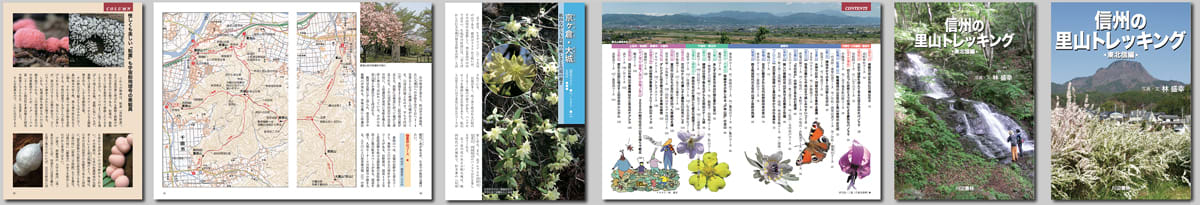
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

























