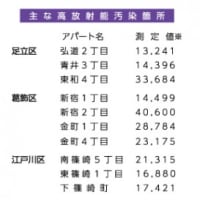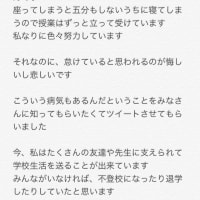*『世界が見た福島原発災害』著者:大沼安史
「第15章 校庭に原発が来た!」を複数回に分け紹介します。3回目の紹介
福島原発災害は、東電、原子力安全・保安院など政府機関、テレビ・新聞による大本営発表、御用学者の楽観論評で、真実を隠され、国民は欺かれている。事実 上の報道管制がしかれているのだ。「いま直ちに影響はない」を信じていたら、自らのいのちと子供たちのいのち、そして未来のいのちまで危険に曝されること になってしまう。
本書は、福島原発災害を伝える海外メディアを追い、政府・マスコミの情報操作を暴き、事故と被曝の全貌と真実に迫る。
----------------
**『世界が見た福島原発災害』著書 「第15章 校庭に原発が来た!」の紹介
前回の話:『世界が見た福島原発災害』校庭に原発が来た! ※2回目の紹介
道徳的な非難から逃れることはできない
今回の「フクシマ」をめぐる日本政府の対応で、周辺住民だけでなく国民一般、さらには世界の人々の間に不信感を広げたのは、もうひとつの「線引き」ともいうべき、被曝基準の嵩上げ問題だった。「フクシマ」の水素爆発は建屋の天井を吹き飛ばしてしまったが、それと同じように、被曝基準の蓋も撤廃されて行った。現場の作業員、そして学童に対する被曝許容基準の緩和は、その代表的な例である。
福島の子どもたちの被曝限度を一気に年間20ミリシーベルトに引き上げる4月19日の日本政府の決定は、国内外に衝撃となって広がった。一般公衆の被曝基準量(年間1ミリシーベルト)の、なんと20倍もの許容量。それほど膨大な被曝を福島の園児、児童生徒に強いる決定だった。
ドイツは「フクシマ」の事故発生後、老朽原発の運転を停止づするなど「脱原発」へ大転換を図りつつあるが、日本政府の今回の学童許容量大幅引上げ問題はドイツ人の「原発廃炉」への動きをさらに加速させたように思える。
ドイツの高級紙、『シュピーゲル』は21日日付の電子版に「日本 子どもたちに高い被曝限度を設定」との生地を掲げ、驚きの声を上げた。
日本の子どもたちに、ドイツの原発作業員と同じ被曝基準値が設定された。
ドイツの人々の受け止め方としては、福島の子どもたちはいま、ドイツの原発の作業員並みの放射線量を浴びながら、日々、学び舎で勉学にいそしむことになったわけだ。福島の教室と校庭は、ドイツの原発並みの学習(作業)環境になったわけだ。
つまり、「フクシマ」ではなんと、「校庭」に「原発」が来ていることになる。
環境団体「グリーンピース」の専門家、ショーンバーニー氏の『シュピーゲル』に対するコメントの最初の一言は、「高い、高すぎる」だった。「子供たちは大人に比べ、放射線に対する感受性が強いのに・・・」。
オットー・フーク放射線研究所のエトムント・レングフェルダー氏は、憤激を隠さなかった。
「癌患者が追加で生まれると完全にわかっていながら我慢しなければならないということだ」
氏はさらに日本政府の決定をこう厳しく非難した。
被曝限度の引上げで司法追訴は免れようと、道徳的な非難から逃れることはできない。
これほど手厳しい言葉はあるだろうか?
ミュンヘンの放射線防護研究所のベーター・ヤコブ所長のコメントも痛烈だった。
「子どもたちの放射線感受性が最も高いという事実に照らせば、20ミリシーベルトがどんな意味を持っているかを、彼らは最大限、勘違いしているに違いない」
※続き「第15章 校庭に原発が来た!」は、6/25(木)22:00に投稿予定です。
 |
![]()