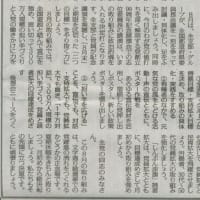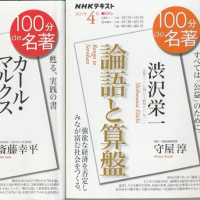27日に「赤旗」2面の下段に、小さな記事で、公明党の山口代表の中国訪問と習近平との会談のことが、以下のように書かれていました。
公明代表が訪中報告
安倍晋三首相は26日、首相公邸で公明党の山口那津男代表と会い、中国訪問の報告を受けました。首相は山口氏と習近平共産党総書記の会談について「戦略的互恵関係を大局的立場で推進することで認識が一致したことは良かった」と評価。「対話の扉を開いていく。今後、政府・与党でその対話を重ねていきたい」と述べ、沖縄県・尖閣諸島をめぐり悪化した日中関係改善に向け、議員外交も含めて対話に努める考えを示しました。 首相は、習総書記が自身との会談に前向きな姿勢を示したことに関しても「対話に向けて努力していく」と語り、早期の会談実現を目指す考えを強調しました。(引用ここまで)
ところが、中国に嫌悪し、日米軍事同盟深化派の「朝日」は社説で、以下のように書きました。上記の記事しか書かなかった「赤旗」とは、アベコベでした。
朝日新聞 習氏との会談/これを雪解けの一歩に /2013/1/26 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit2?
その他の全国紙も、「日経」以外は、「社説」でそれぞれ、以下のように書きました。その特徴的表現と思われる部分を掲載してみます。
「さらに知恵を出し合えば、ことを荒立てず局面を打開するきっかけになるかもしれない…いつまでも対立を続けることは日中両国とも望まないはずだ。尖閣で領土問題は存在しなくても、外交問題は存在する。機会を逃さず改善の糸口をつかむことは2人の首脳にしかできない決断」を迫った「毎日」
「溝が広がった政府間の橋渡しをしようとする意図は理解できる」としながらも「不測の事態を防ぎ、日中関係を改善するには、まず中国が威圧的な行動を控えるべき」とする「読売」
「話し合いの環境整備をすべきは、第一に中国側」とする「産経」
「憲法問題などでタカ派色が批判される面はあるが、安倍政権は対中外交では冷静な対応で対話再開に道筋をつけた…公明党は…日中関係を重視してきた実績も会談実現に弾みとなった。…政凍経冷とでも言えるような難局だけに、大いに政治の力を発揮し、隣国との関係を改善軌道に乗せてほしい。安倍首相は前に政権を担った二〇〇六年、『氷を砕く旅』として訪中し、戦略的互恵関係の構築で合意した実績がある。日中友好議連会長の高村正彦自民党副総裁も近くの訪中を検討している。 政凍経冷とでも言えるような難局だけに、大いに政治の力を発揮し、隣国との関係を改善軌道に乗せてほしい。…何よりも武力紛争が起こらないよう、対話を進めることが肝要である」と期待を寄せる「東京」
など、全体としては前向きな「評価」がなされています。
今回の公明党の訪中は、さらに「対話」という落としどころを模索する動きになって発展していくのでしょうか?公明党山口代表の直後に村山元首相・加藤元自民党幹事長が訪中し、それを受けて安倍首相の訪中が計画されています。
尖閣に言及しなかった首相所信表明、中国が評価(2013年1月29日21時07分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130129-OYT1T01111.htm?from=main1
東京 安倍首相、日中首脳会談に意欲 「関係再構築」とTV番組で 2013年1月29日 21時15分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013012901002205.html
こうした「対話」そのものは憲法の平和主義の具体化でもある訳ですが、一方では「武力」を前提とした「抑止力」論、「脅し」にもとづく外交の推進でもあるわけです。こうした日米軍事同盟深化派の外交が、日本国憲法の否定に連動していくことも、また事実でしょう。
ただ、こうした「対話」による平和外交の推進が積み重ねられていけばいくほど、憲法を改悪して「国防軍」への改悪、集団的自衛権の行使へと一気に進むかと言えば、安倍政権にとっては、厳しい立場に追い込まれることも、また事実と言えます。
ここに戦後平和主義が積み上げてきた歴史の到達点があると思います。日本を憲法改悪・自衛隊の国防軍化、集団的自衛権の行使にまで持っていくためには、安倍自公政権は、当面はハト色を強めなければ国民の支持を得られない、参議院選挙まではタカの爪とクチバシは封印しておく、ゴマカシ路線でいくしかありません。これが薄氷を踏む思いで議席を掠め取った選挙結果の裏返しと言えると思います。
このように、このハト路線とタカ路線を混在させなければならない安倍自公政権の矛盾こそ、新しい時代を予感させているのも事実ではないかと思います。ここでも日米軍事同盟容認・深化派と日米軍事同盟廃棄派・憲法平和主義実践派の綱引き・鍔競り合いがあるというのが愛国者の邪論の見方です。
こうした激しい鍔競り合いは、その言葉が示すように、アッという間に、どちらかが切られる可能性を持っていることも、また事実です。しかし、戦後70年近い歴史の到達点は、安倍自公政権の思うように平和憲法を切れないのも、また事実でしょう。歴史のジグザグは、着実に、戦争による紛争の解決から対話による紛争の解決へと進んできたからです。
アルジェリアの悲劇を悲しむ日本国民の姿は、武力による紛争解決を望んでいないことを示していました。安倍内閣の支持率が上がったのも、紛争の平和的解決を強調して、アルジェリア政府に迫ったからではないでしょうか?
こうした日本の局面を見たとき、共産党が、カヤの外にいるのは、「何をやってんだ!」ということになりますね。本来であれば、習近平氏が就任した段階で直ちに、会談を申し入れ、野党外交の真骨頂を国民の前に示していく必要がありました。ひょっとすると、会談の申し入れはしていたのかもしれません。政権党である中国共産党は、政権与党である公明党と会談することの方を優先したのかもしれません。
それにしても、多くの国民は同じ「共産党」を名乗り、社会主義を目指していると感覚的に思っていることでしょう。その「共産党」が尖閣問題や北朝鮮の核兵器や拉致問題について、どのような解決方法を示すか、非常に興味のあることだと思います。
共同で解決する手立てを示せれば、流石「キョーサントー」、できなければ、ヤッパリキョーサントー」ということになるでしょう。日本共産党は、まさに剣が峰に立っているのだと思います。動いて解決して当然!、やらなければヤッパリ!ということになるのではないでしょうか?
そういう時に、言ってみれば、指を銜えてみているだけ、「赤旗」の記事も申し訳程度!?
日米軍事同盟廃棄を展望すれば、日米軍事同盟容認・深化の口実となっている中国と北朝鮮の「蛮行」に対して、批判するだけではなく、具体的に行動していくことが国民的信頼を獲得し、日米軍事同盟廃棄の条件づくりとなるのだと思います。こうしたやり方は、方針にもあったはずです。しかし・・・・。
以下の「朝日」社説の論理を打ち破るためのお膳立ての用意を、です。オセロの四隅を奪還するために、どんな手を打っていくか、そこにすべてがかかっているのです。それを旺盛にやらないから、嫌中派・日米軍事同盟容認・深化派の「朝日」が繰り返し中国共産党批判を行い、共産党ハブ化させ、共産党嫌悪の感情を国民の腹の中に溜めていくのです。実に上手いやり方です。一石二鳥ですから。
朝日 防衛力見直し―首相の説明が足りない2013年1月28日(月)付
http://www.asahi.com/paper/editorial20130128.html
ここ数年、東アジアの安全保障環境は大きく変わった。とりわけ中国の軍備拡張、海洋進出は著しく、日本との間でも尖閣諸島問題で緊張が続く。ミサイル発射や核実験を繰り返す北朝鮮の脅威も増した。 国際情勢の変化をふまえ、防衛のあり方を不断に点検するのは当然のことだ。米国が「アジア太平洋重視」を打ち出すなか、日米の同盟関係を深化させることも必要だろう。…外交や経済をふくむ総合的な戦略を描く必要がある。防衛力強化だけを突出させるべきではあるまい。 説明を怠らず、無用の緊張をあおらない。これが安全保障政策の要諦である。…一方で、防衛政策をやみくもに変えていると受け止められれば、かえって地域の緊張を高めかねない。安倍政権の前のめりの姿勢を見ると、そんな懸念がぬぐえない。 言うまでもなく、戦後の日本は憲法9条の平和原則のもと、自衛権の行使にみずから厳しい制約を課してきた。自衛隊による海外での武力行使は禁じる、集団的自衛権の行使は認めない、などである。 ところが、安倍首相は集団的自衛権の行使容認に意欲を示している(引用ここまで)
朝日 沖縄@東京―基地問う声が重く響く 2013年1月29日(火)付
http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit1
沖縄県民が求めているのは普天間の閉鎖・撤去そのものだ。経済的な手当てではない。根本的な解決がない限り、沖縄の怒りは消えず、日米同盟を不安定にする要素がいつまでも続く…地域の安定のために、日米同盟を必要だと考える人は多い。だが海兵隊をはじめ、国内の米軍専用施設の74%を沖縄に集中させたままの必要はどこにあるか。安倍政権は説得力のある答えを沖縄に返す必要がある。(引用ここまで)
以上のような論理で日米軍事同盟容認・深化を浸透させていくのです。だからこそ、倍以上の中国共産党との「対話」路線を具体化していく必要があるのです。
ところが、今日の「赤旗」に書かれた志位委員長の発言「共産党ここにあり」は、中国問題でハブにされている!そういう意味で、ピンボケだったかも知れません。「政治の大局」は、憲法の平和主義が着々と進行しているのは事実ですが、そんな「歴史の大局」観よりも大事なことがあるのではないでしょうか?
「共産党ここにあり」の奮闘で参院選勝利の道開く国会に 党議員団総会 志位委員長があいさつ 2013年1月29日(火)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2013-01-29/2013012901_01_1.html
それでは、以下全国紙の社説を掲載しておきます。
朝日 習氏との会談/これを雪解けの一歩に /2013/1/26 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit2?
中国を訪問していた公明党の山口那津男代表がきのう、習近平総書記と会談した。 日本政府による尖閣諸島の国有化で関係が悪化して以来、中国共産党トップが日本の政党党首と会うのは初めてだ。小さな一歩にすぎないが、パイプがつながったことを歓迎する。 山口氏は安倍首相の親書を手渡し、日中の首脳会談を呼びかけた。習氏も「ハイレベルの交流を真剣に検討したい」と応じた。習氏はそのための環境整備も求めており、にわかに実現するかどうかはわからない。 とはいえ、習氏みずから意欲を示したのは前向きのサインと受けとめたい。ぜひ実現につなげてほしい。 もちろん、首脳同士が会ったからといって、尖閣問題で溝を埋めることは望めまい。大切なのは、この問題を経済や文化など両国間の様々な交流に波及させないことだ。 この点でも、習氏は「中日関係は特殊な時期に入っているが、国交正常化の歴史をさらに発展させなければならない」と語った。ならば、尖閣を理由に関係を停滞させないよう、言葉通りの対応を求める。 山口氏は出発前、「将来の世代に解決を委ねることが、当面の不測の事態を避ける方法だ」と発言。中国側の主張に沿った、領有権の「棚上げ」論ではないかとの疑念を招いた。 尖閣が日本の領土であることは間違いない。ただ、「領土問題は存在しない」という、日本政府の棒をのんだような対応ばかりでは、話し合いの糸口さえつかめなかったことも事実だ。 両国のナショナリズムが沸き立つのを避けつつ、互いに知恵を出し合い、粘り強い対話を続けるしかあるまい。 尖閣周辺には、連日のように中国の船舶や航空機が姿を見せている。私たちはこうした挑発行為をやめるよう再三求めてきたが、やむ気配はない。 こんな状態が続けば、いつ偶発的な武力衝突が起きても不思議ではない。 山口氏はやはり出発前、「この島に両国の軍用機が近づきあうことは不測の事態を招きかねない。お互い空に入らないとの合意に至ることも重要だ」と提起した。両政府間で衝突回避の具体策を早急に協議すべきだ。 今回の訪中は、議員外交の意義を再認識させた。 関係改善に向けて、あらゆるパイプを総動員する。そこでつかんだきっかけを逃さず、政府間の話し合いにつなげる。 その積み重ねの中から、雪解けを図るしかあるまい。(引用ここまで)
毎日 山口・習近平会談/対立緩和につなげたい/2013/1/26 4:00
http://mainichi.jp/opinion/news/20130126k0000m070173000c.html
公明党の山口那津男代表が北京で習近平総書記と会談した。習氏は日中関係改善のためハイレベルの対話が重要だとして、安倍晋三首相との首脳会談に意欲を示した。 昨年11月の総書記就任後、習氏が日本の与党幹部と会うのは山口氏が初めてだ。安倍政権にとっても発足後初の与党党首訪中である。山口氏は習氏に安倍首相からの親書を手渡した。事実上の首相特使といっていい。首脳会談の実現は安倍氏の希望とも合致する。トップ同士が早期に対話に乗り出し、尖閣諸島をめぐる対立の緩和につなげたい。 尖閣諸島については、習総書記の前に山口氏と会った王家瑞(おうかずい)中央対外連絡部長が「前の世代が棚上げし、中日友好が保たれた。後々の世代に解決を託すこともある」と問題の棚上げに言及した。棚上げは72年の日中国交正常化や78年の日中平和友好条約交渉の際、周恩来首相やトウ小平氏がとった手法だ。日本政府は明確な棚上げ合意はないとしているが、当時の交渉にかかわった外務省OBは棚上げで首脳間の「暗黙の了解」があったと証言している。 今回、中国側が再び棚上げを持ち出した真意ははっきりしない。そもそも92年の領海法制定で尖閣諸島を一方的に中国領とするなど、「棚上げ」了解を先に崩したのは中国の方である。そうした姿勢に日本が疑念を持つのは当然だ。再び棚上げを言うのなら、中国の対応が信頼できるものでなければなるまい。 ただし、「尖閣は固有の領土」という日本の立場を維持する形であれば、改めて棚上げが可能かどうか、検討してみてもいいのではないか。中国は尖閣周辺への船舶や航空機の接近をやめる。日本も公務員の常駐や船だまりの設置といった措置をとらない。さらに知恵を出し合えば、ことを荒立てず局面を打開するきっかけになるかもしれない。 このところ、アジアをめぐる外交が活発に動いている。クリントン米国務長官は尖閣について「日本の施政権を侵すあらゆる一方的な行動に反対する」と踏み込んだ発言で日本の立場を支持した。安倍氏は東南アジア諸国連合(ASEAN)訪問で、自由で安全な海洋のルール作りを外交の柱に据える考えを強調した。北朝鮮の事実上の長距離弾道ミサイル発射に対する国連安保理決議は、中国も含む全会一致で採択された。 山口氏への中国側の対応も、こうした国際環境と無関係ではないだろう。いつまでも対立を続けることは日中両国とも望まないはずだ。尖閣で領土問題は存在しなくても、外交問題は存在する。機会を逃さず改善の糸口をつかむことは2人の首脳にしかできない決断である。(引用ここまで)
習・山口会談 首脳対話に必要な中国の自制(1月26日付・読売社説)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20130126-OYT1T00136.htm
途絶えている日中首脳会談が再開できる環境を整えるには、日中双方の外交努力が必要だ。
公明党の山口代表が訪中し、中国共産党の習近平総書記と会談した。習総書記が昨年秋の就任後、日本の政治家と会うのは初めてだ。 山口氏は「難局の打開には政治家同士の対話が大事だ」として、安倍首相の親書を手渡した。 習総書記は「ハイレベル対話は重要だ。真剣に検討したい」と明言した。首脳会談の環境を整える必要があるとの認識も示した。 中国は尖閣諸島の領有権問題での日本の譲歩を求めているのだろうが、それは認められない。むしろ中国にこそ自制を求めたい。 昨年9月に日本が尖閣諸島を国有化した後、中国政府による日本の領海侵入は恒常化し、領空への侵犯も起きている。 不測の事態を防ぎ、日中関係を改善するには、まず中国が威圧的な行動を控えるべきだ。 公明党は、1972年の日中国交正常化の際、議員外交で大きな役割を果たした。今回も、溝が広がった政府間の橋渡しをしようとする意図は理解できる。
尖閣諸島は日本固有の領土であり、領土問題は存在しない。日本政府の立場を堅持することが肝要なのに、気がかりな点がある。 山口氏が訪中前、香港のテレビ局に対し「将来の知恵に任せることは一つの賢明な判断だ」と述べ、「棚上げ論」に言及したことだ。日中双方が自衛隊機や軍用機の尖閣諸島上空の飛行を自制することも提案した。 山口氏は習氏らとの会談では触れなかったが、看過できない発言だ。棚上げ論は、中国の長年の主張である。ところが、中国は1992年に尖閣諸島領有を明記した領海法を制定するなど一方的に現状を変更しようとしている。
安倍首相が「自衛隊機が入る、入らないは、私たちが決める」と山口氏の発言に不快感を示したのは当然である。 村山元首相も、近く中国を訪れる。村山氏は、過去の侵略などへの「深い反省」を表明した村山首相談話をまとめた。村山氏から中国寄りの発言を引き出したい中国の意図が見え隠れする。 先に訪中した鳩山元首相は、尖閣諸島を「係争地だ」と述べた。領有権問題の存在を認めたことなどから、中国の主要紙が大きく取り上げた。中国に利用されていることが分からないのだろうか。 国益を忘れた言動は百害あって一利なしである。
(2013年1月26日01時36分 読売新聞)(引用ここまで)
産経 習・山口会談 恫喝の下では対話できぬ 2013.1.27 03:07
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130127/plc13012703080003-n1.htm
中国共産党の習近平総書記が、訪中した公明党の山口那津男代表との会談で尖閣諸島をめぐる日中の対立に言及し、「対話と協議による解決が重要だ」などと語った。 山口氏が安倍晋三首相の親書を手渡し、途絶えている日中首脳会談を提案すると、習氏は「ハイレベルの対話を真剣に検討したい」と応じた。 関係改善の「意欲の表れ」(山口氏)といえなくはないが、習氏が「歴史の直視」との表現で歴史認識への「慎重な対応」を安倍政権に求め、首脳会談の実現に「環境整備が重要だ」と条件をつけたことは順序が違う。 習政権が真摯(しんし)な対話と首脳会談を望んでいるなら、尖閣を海と空から威嚇する恫喝(どうかつ)をただちにやめるべきだろう。そうでなければ、「日中間に領土問題は存在しない」とする安倍政権は一方的に譲歩を迫られ、国益を失うことになりかねない。 今回、習氏が強硬路線の転換をにじませたのは、クリントン米国務長官が「日本の施政権を害そうとする、いかなる一方的行為にも反対する」と警告したことが影響している。 それは日米同盟を強化することが、日本にとって最優先課題であることを意味している。 公明党はかつて日中国交正常化に向けた環境整備に尽力するなど、中国共産党とのパイプ役を務めてきた。その実績をテコに、山口氏は政権与党の党首として日中関係の改善で成果を挙げたかったのだろう。 しかし、訪中前に尖閣問題で中国側が唱える「棚上げ論」に同調する発言をした山口氏は習氏との会談前日、王家瑞中央対外連絡部長からも「棚上げ論」を持ち出された。宣伝戦に利用された印象がぬぐえない。 中国側は今月末、村山富市元首相らを招き、要人との会談を予定している。親中派とされる政治家と接触することによって日本の国内世論の懐柔を狙い、安倍政権を揺さぶる構えだろう。 山口氏の訪中の間も、中国公船は尖閣周辺の接続水域への出入りを続けた。領海侵犯さえ常態化している。領空侵犯も起き、中国機に対する航空自衛隊の緊急発進は昨年4~12月で160回と過去最多となっている。 話し合いの環境整備をすべきは、第一に中国側である。
東京 習総書記が会談 対話の機運を大切に 2013年1月26日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013012602000110.html
中国共産党の習近平総書記が訪中した公明党の山口那津男代表と会談したことは、対話再開に向けた一歩だといえる。粘り強く現実的な外交で、日中関係改善の糸口をぜひにも、つかんでほしい。 日本政府が昨年九月、尖閣諸島を国有化したことに中国が反発し日中関係は国交正常化以降で最悪と言われる状態にあった。 こうした事態になって以降、中国共産党トップが政権与党の党首と会談したのは初めてである。 安倍政権の成立後、中国側は尖閣の国有化について「民主党政権の決定」として新政権との対話は拒まない姿勢を示していた。議員外交によってようやく実現した対話の機運を大切にしてほしい。 安倍晋三首相は新政権スタート直後の会見では、靖国神社参拝を明言せず、選挙中に訴えてきた「尖閣諸島への公務員の常駐検討」の公約にも触れなかった。 憲法問題などでタカ派色が批判される面はあるが、安倍政権は対中外交では冷静な対応で対話再開に道筋をつけたといえる。 公明党は、中国で対日外交に影響力を持つ唐家〓元国務委員や程永華駐日大使らと太いパイプを持つ。日中関係を重視してきた実績も会談実現に弾みとなった。 昨年末、北京に着任した木寺昌人・駐中国大使は「第一の任務は日中の友好関係を深め、広げることだ」と述べた。 民主党政権時代は、与党政治家の対中パイプが細く、外交をバックアップする力に欠けていた。 安倍首相は前に政権を担った二〇〇六年、「氷を砕く旅」として訪中し、戦略的互恵関係の構築で合意した実績がある。日中友好議連会長の高村正彦自民党副総裁も近くの訪中を検討している。 政凍経冷とでも言えるような難局だけに、大いに政治の力を発揮し、隣国との関係を改善軌道に乗せてほしい。 習総書記は尖閣問題で「対話と協議で解決していく努力が重要だ」と述べた。双方が歩みよる努力をすることに異論はない。民主党政権は「(一時棚上げという)約束は存在しない」と閣議決定し、政治の知恵といえる棚上げ論を否定した。 日本に主権があることは疑いもない事実だが、国際社会で外交上の係争地と見られていることはそれも現実として否定できない。 それらを踏まえ、何よりも武力紛争が起こらないよう、対話を進めることが肝要である。 ※〓は王へんに旋(引用ここまで)
朝日 防衛力見直し―首相の説明が足りない2013年1月28日(月)付
http://www.asahi.com/paper/editorial20130128.html
安倍政権による防衛態勢の見直し作業が始まった。 先週末の閣議で、民主党政権下の10年にできた防衛計画の大綱の見直しと中期防衛力整備計画の廃止を決めた。新たな大綱と中期防は年内につくる。 13年度予算では防衛費も11年ぶりに増やす方向だ。 日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定をめぐる日米協議もスタートした。 まさに矢継ぎ早である。 ここ数年、東アジアの安全保障環境は大きく変わった。とりわけ中国の軍備拡張、海洋進出は著しく、日本との間でも尖閣諸島問題で緊張が続く。ミサイル発射や核実験を繰り返す北朝鮮の脅威も増した。 国際情勢の変化をふまえ、防衛のあり方を不断に点検するのは当然のことだ。米国が「アジア太平洋重視」を打ち出すなか、日米の同盟関係を深化させることも必要だろう。 一方で、防衛政策をやみくもに変えていると受け止められれば、かえって地域の緊張を高めかねない。安倍政権の前のめりの姿勢を見ると、そんな懸念がぬぐえない。 言うまでもなく、戦後の日本は憲法9条の平和原則のもと、自衛権の行使にみずから厳しい制約を課してきた。自衛隊による海外での武力行使は禁じる、集団的自衛権の行使は認めない、などである。 ところが、安倍首相は集団的自衛権の行使容認に意欲を示している。一連の見直し作業もそれを前提にしたものだろう。 では、どのような事態のもとで、どんな形の日米協力を想定しているのか。自衛隊の活動を際限なく広げるようなことにならないか。首相は明確に説明する責任がある。 そうでないと、周辺国の警戒感を高め、激しい軍拡競争に陥りかねない。 防衛費の野放図な拡大も許されない。 現大綱は「動的防衛力」という考え方を打ち出した。防衛予算が削減されるなか、自衛隊を効率的に運用する狙いだ。 厳しい財政事情のもと、今後も装備や人員、活動を精査することは欠かせない。尖閣をふくむ南西海域の警備強化には、海上保安庁に予算を重点配分する方が効果的な面もある。 中国との向き合い方は一筋縄ではいかない。外交や経済をふくむ総合的な戦略を描く必要がある。防衛力強化だけを突出させるべきではあるまい。 説明を怠らず、無用の緊張をあおらない。これが安全保障政策の要諦(ようてい)である。 (引用ここまで)
朝日 沖縄@東京―基地問う声が重く響く 2013年1月29日(火)付
http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit1
「オスプレイいらない」「基地ノー」と怒る沖縄県民の叫びが東京で響いた。本土に住む私たちと政府は、この声を誠実に聴かなくてはいけない。 主催者発表で4千人が、霞が関の官庁街に近い日比谷公園に集い、銀座を歩いた。 そのなかに沖縄県内の41市町村すべてからの首長、議長や県議ら約140人がいた。党派の異なる首長、議員らがこれほどまとまって上京するのは他県もふくめ異例だろう。 首長らは、新型輸送機オスプレイの配備撤回と米軍普天間飛行場の県内移設断念を求める建白書を、安倍首相に渡した。 首相は「基地負担軽減に向けて頑張っていきたい」と述べたという。この答え方は民主党政権時代の政府と同じだ。 沖縄県民が求めているのは普天間の閉鎖・撤去そのものだ。経済的な手当てではない。根本的な解決がない限り、沖縄の怒りは消えず、日米同盟を不安定にする要素がいつまでも続く。 どれほど訴えても負担が減らず、逆に安全性に疑問があるオスプレイが新たに配備され、沖縄の人たちは民意が踏みにじられたと受けとめている。 森本敏・前防衛相は退任前の昨年末、普天間移設先について「軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると、沖縄が最適の地域」と話した。 本土に新たな基地を造るのは住民が受け入れないが、すでに米軍基地が多い沖縄ならできるということなのか。沖縄の「戦略的な地理的優位性」を掲げる防衛省とは別の本音を、大臣が明かしたことになる。 日本各地で基地反対の闘争が激化した半世紀前、岐阜と山梨にいた海兵隊が沖縄に移った。 それ以来いまも続く海兵隊の沖縄駐留は、軍事上の必要というより、国内の負担分かちあいをできない日本政府の都合によるものではないか。そう、沖縄県民はみている。 在日米軍の再編見直し計画では、沖縄の海兵隊をオーストラリア、ハワイにも移転し、巡回展開する。地上部隊の主力である歩兵の第4海兵連隊はグアムに。沖縄に残る砲兵の第12海兵連隊は日本本土でも訓練し、およそ半年間は沖縄にいない。 常駐基地が沖縄でないといけない根拠は、ますます薄くなっている。 地域の安定のために、日米同盟を必要だと考える人は多い。だが海兵隊をはじめ、国内の米軍専用施設の74%を沖縄に集中させたままの必要はどこにあるか。安倍政権は説得力のある答えを沖縄に返す必要がある。(引用ここまで)
尖閣に言及しなかった首相所信表明、中国が評価 (2013年1月29日21時07分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130129-OYT1T01111.htm?from=main1
【北京=五十嵐文】北京を訪問中の村山富市元首相、加藤紘一前衆院議員らは29日、人民大会堂で中国共産党の李源潮(リーユエンチャオ)政治局員と会談した。 李氏は3月の全国人民代表大会(国会)で国家主席に就任する習近平(シージンピン)総書記の下で、国家副主席への起用が有力視されている。 加藤氏らによると、李氏は安倍首相が28日の所信表明演説の外交分野で尖閣諸島という具体名に言及しなかったことを指摘。安倍氏の対応を評価していることを示唆したという。また「歴史認識を後退させることがあってはならない」と述べ、過去の植民地支配を謝罪した「村山首相談話」の堅持を求めた。 村山氏らは同日、中国外務省で楊潔チ(ヤンジエチー)(よう・けつち)外相とも会談した。(引用ここまで)
東京 安倍首相、日中首脳会談に意欲 「関係再構築」とTV番組で 2013年1月29日 21時15分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013012901002205.html
安倍首相は29日、日本テレビの番組に出演し、沖縄県・尖閣諸島をめぐり冷え込んだ日中関係に関し「必要があれば首脳会談から再び関係を構築する」と述べ、自ら局面打開に乗り出す意欲を示した。また環太平洋連携協定(TPP)交渉参加をめぐっては参院選前に方向性を打ち出す考えを明らかにした。 尖閣諸島に関し「日本固有の領土であり交渉の余地はない」と重ねて明言した。同時に日中両国が経済面において密接な関係にあるとし「戦略的互恵関係に立ち戻る必要がある」と強調。「常に対話すべきだ。問題があるからこそ首脳会談やハイレベル会談を開くべきだ」と述べた。(共同)(引用ここまで)