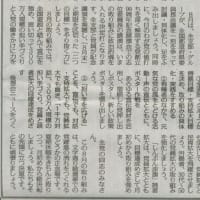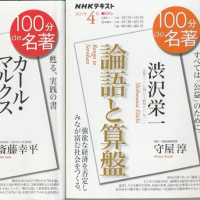熊本県の近くにある稼働中の川内原発だが
熊本には関係なしか?
地震と原発の危険は一応判る!
しかし、しかし、稼働中止は一言もなし?!
何故だ!?
川内原発は熊本県には
関係なし!
大丈夫!安心だ!
ってことなんですね!
川内原子力発電所(鹿児島県)の場所・距離/原発個別地図
http://www.benricho.org/map_energy/sendai.html
活断層地震という「足元の危険」は
いつ起こるか分からないが
しかし必ず潜んでいると考えるべきだろう
原発の位置付け
しっかり検証する必要があろう
原発やダムなどいったん破壊されると
深刻な事態を招く施設は
活断層を絶対に避ける必要がある。
活断層地震 足元の危険、正しく認識を
2016年04月21日
http://kumanichi.com/syasetsu/kiji/20160421001.xhtml
益城町や南阿蘇村、西原村などで多くの建物が倒壊した熊本地震は、内陸部の活断層が動いて起きる直下型地震の恐ろしさをあらためて見せつけた。震源は県内を北東から南西方向に延びる「布田川[ふたがわ]断層帯」と、布田川から折れ曲がるように分かれている「日奈久[ひなぐ]断層帯」とみられている。
地震による地下の圧力変化は周辺の断層にひずみを生み、新たな地震を誘発する。震度1以上が700回を超えているが、誘発を繰り返しながら活動域を拡大させているようだ。19日には八代市でも強い揺れを観測した。引き続き厳重な警戒を心掛けたい。
地震は大きく分けると、地表を覆う厚いプレート(岩板)の境界付近で起きる海溝型と、内陸で起きる活断層型がある。
東日本大震災は太平洋プレートが陸側のプレートの下に沈み込んで起きた巨大海溝型だ。関東大震災やスマトラ沖地震などもこのタイプにあたる。
一方の活断層型は、プレート運動などで地層に圧力が加わり、できた割れ目(断層)が突然ずれ動くことで起きる。阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などが例だ。
活断層による地震は、海溝型に比べると一般にエネルギーは小さい。しかし震源が浅い上に、「直下型」と呼ばれるように足元で起きるため、規模が小さくても局地的に激しい揺れとなり、被害が拡大するのが特徴だ。
阪神大震災以降、過去数十万年以内に繰り返し動き、将来も地震を引き起こす可能性のある活断層について全国的に詳細な調査が行われるようになった。
今回震源となった布田川、日奈久の両断層も主要な活断層とされ、場所によっては「地震の発生可能性が高いグループ」に分類。両断層が動くと最大マグニチュード(M)8・2の地震が起こる可能性も指摘されていた。
これら最新の知見は、地震防災や住民への情報伝達に十分反映されていたのか。南海トラフなど巨大海溝型ばかりに目を奪われていたのではないか。しっかり検証する必要があろう。
一つの活断層が活動するのは数千年に一度ともされる。生活感覚からは懸け離れた長い時間スケールで、毎年のように襲う台風や大雨に比べて関心は遠のきがちだ。
しかし、日本列島には約2千の活断層が走り、まだ見つかっていないものもある。活断層地震という「足元の危険」は、いつ起こるか分からないが、しかし必ず潜んでいると考えるべきだろう。
原発やダムなどいったん破壊されると深刻な事態を招く施設は活断層を絶対に避ける必要がある。病院や学校といった公共施設、通信・交通をはじめとしたインフラも地震による機能低下を極力防ぐシステム構築が課題だ。
私たちとして急ぐべきは建物の耐震化だ。耐震基準を満たせば震度7でも構造が壊れるような被害は避けられるという。天井の落下防止策や家具の固定など室内の安全対策も再点検したい。(引用ここまで)
原発は危険ではない?
危険と思われる建物や道路、橋などには近づかないなど
それぞれが命を守るための冷静な行動を心掛けたい
地震多発 避難長期化に万全の策を
2016年04月17日
阿蘇大橋や阿蘇神社楼門が倒壊し、土砂崩れも相次いだ。宇土市役所は半壊状態。熊本城はやぐらなどが崩落した。目を疑うような光景が次々と飛び込んでくる。
14日夜の震度7以降立て続けに起きている地震は、県内に甚大な被害をもたらしている。これ以上拡大しないよう、一刻も早く沈静化することを願うしかない。
気象庁によると、今回の地震発生回数は、2004年の新潟県中越地震に次いで過去2番目のペースで多発している。被害が広範囲にわたり、土砂崩れで道路が寸断されていることもあり、全容はまだ明らかになっていない。警察と消防、自衛隊は被災者の救出、確認に全力を挙げてほしい。
16日午前1時25分ごろには、熊本市や宇土市、南阿蘇村などで震度6強の地震があった。規模はマグニチュード(M)7・3と一連の地震で最も大きく、震度7を観測した14日夜のM6・5の地震に比べて、エネルギーが16倍も大きい。1995年の阪神大震災と同じ規模だ。気象庁は、この地震を「本震」とし、それ以前の地震は結果的に「前震」と位置付けた。
この本震の後、震度6弱以上の地震が短時間のうちに断続的に発生した。専門家は、九州中央部を北東-南西方向に延びる活断層「日奈久断層帯」がそれまでの地震を起こしたのに対して、M7・3の地震から新たな段階に入り、東北東-西南西方向に延びる「布田川断層帯」に活動が移って広域化したとみている。
本震の後に阿蘇地方や、布田川断層帯の東北東側に位置する大分県でも地震が多発した。気象庁の担当者は、これらは余震ではなく、本震が別の地震を誘発した可能性を指摘する。地震がこれほど広域的に続けて起きるケースは珍しいという。また、16日に阿蘇中岳が小規模噴火したことについては、一連の地震とは直接の関係はないとみている。
震源が浅い内陸直下型は真上で揺れが非常に強くなり、住民の恐怖や不安は募る一方だ。避難所に向かう人たちが増え、避難が長期化する可能性もある。避難所運営が今後の大きな課題となる。
今回と同様に余震が活発だった新潟県中越地震では、自宅倒壊を恐れた多くの住民が長期間、車中で寝泊まりを続けて「エコノミークラス症候群」を発症した。東日本大震災では劣悪な環境の避難所で多くの高齢者らが体調を崩し、震災関連死が相次いだ。
県内で避難している人たちも続発する地震に神経をすり減らし、先の見えない生活を送る。まず優先すべきは身体的な安全の確保。次に生活物資の支援なども求められるが、避難所での生活が長引けば長引くほど、よりきめ細かい対策が必要になることは東日本大震災などの教訓が示す通りだ。
今後1週間は震度6弱程度の余震に注意すべきだという。危険と思われる建物や道路、橋などには近づかないなど、それぞれが命を守るための冷静な行動を心掛けたい。 (引用ここまで)
震災は「万一」のことではあるまい。
災害への備えは常に万全を期す必要がある。
そして、その列島の上に、
原発がひしめいていることも忘れてはなるまい
であるならば原発は停止ではないのか!
震度7「熊本地震」 余震に警戒、今後も備えを
2016年04月16日
http://kumanichi.com/syasetsu/kiji/20160416001.xhtml
地震災害はどんなときも、どんなところでも起こり得ることを、あらためて思い知らされた。
14日夜、益城町で震度7を観測した地震は、同町や熊本市を中心に建物の倒壊などが相次ぎ、死者9人、けが人は約千人に上り、うち53人が重傷を負うという、甚大な被害をもたらした。
国内で震度7を観測したのは、東日本大震災の2011年3月11日以来。九州では初めてという。地震の規模を示すマグニチュード(M)は6・5と推定される。気象庁は15日、今回の地震を「平成28年熊本地震」と命名した。
ライフライン、交通インフラもずたずたにされた。広域で停電、断水が続き、ガスの供給が止まったままのところもある。
九州新幹線は熊本駅近くで回送中の車両が脱線。博多~鹿児島間の新幹線は運転を見合わせ、在来線も運休している。九州自動車道は路面の陥没や隆起が多数発生。復旧の見通しは立っていない。
気象庁によると、震度1以上の余震を140回以上観測。うち震度6強と6弱が各1回、5弱も2回あった。余震多発や揺れの大きさと関連しているとみられるのが震源の深さだ。今回の地震は約11キロと、地表に近い場所が震源だった。地殻は浅い場所ほど強度が弱い傾向にあるため、今後も強い揺れを伴う余震が予想される。
避難を強いられている住民は一時、4万人を超えた。寝食は無論のこと、何をするにも不自由な状況は察して余りあるが、建物だけでなく、場所によっては地震で地盤が緩み、土砂災害が起きやすくなっている可能性がある。16日からは雨の予報。二次災害も含め、まだ十分な警戒が必要だ。
今回の震災について熊本県は政府に対して、災害復旧事業で補助金が上積みされる「激甚災害」の早期指定を求めている。河野太郎防災担当相は15日の会見で「現地の情報収集を受けて、必要なら動きたい」と検討を急ぐ考えを示した。国、県、地元市町は一刻も早く被害の詳しい実態を把握するとともに、被災者へ十分な支援の手を差し伸べなければならない。
熊本県内で大きな地震があったのは、阿蘇市を中心に被害をもたらした1975年1月以来41年ぶりだが、今回の地震は1995年の阪神大震災と同様の、内陸活断層のずれによる直下型との見方が専門家の間で強まっている。
震源付近には「布田川断層帯」「日奈久断層帯」という二つの断層帯が接するように延びている。さらに多くの断層が枝分かれしたり、並走したりして複雑な帯を形成しており、140回超の余震もその帯に沿って起きている。
東日本大震災から5年余り。私たちの国土が“地震列島”であることをもう一度、突き付ける今回の地震だった。震源となる断層帯は、それこそ全国各地に無数にある。震災は「万一」のことではあるまい。災害への備えは常に万全を期す必要がある。そして、その列島の上に、原発がひしめいていることも忘れてはなるまい。 (引用ここまで)
原子力施設が損害を受けた場合の影響の深刻さは
東京電力福島第1原発事故が実証している
のであれば
川内原発の稼働は停止させるべきではないのか!
核安保サミット テロは身近にある脅威だ
2016年04月06日
http://kumanichi.com/syasetsu/kiji/20160406001.xhtml
核テロを防ぐため、各国首脳らが世界に散在する核物質の防護・保全体制の強化を話し合う「核安全保障サミット」の第4回会合がワシントンであった。オバマ米大統領が提唱して2010年に始まり、2年に1度開かれてきたが、来年1月に同大統領が退任するため最後の会合となった。
3月のベルギー同時テロで犯行声明を出した過激派組織「イスラム国」(IS)が核物質入手や原発攻撃を狙っていた可能性が指摘されるなど、核テロは身近にある脅威となっている。
核テロ阻止は「核兵器なき世界」への取り組みの一環でもある。サミットの参加国は、今後もテロ防止へ向けた情報の共有を図り、核物質のさらなる管理強化に努めてもらいたい。
想定される核テロの主な形態は(1)テロ組織が核兵器を入手するか製造して使用(2)原発などに対する破壊活動(3)医療や工業用の放射性物質をまきちらす「汚い爆弾」使用-などだ。これまでサミットでは、核物質の保有の最少化や管理の厳格化が議論されてきた。
米政府は、核安保サミットの成果として、10カ国以上の高濃縮ウランをゼロにした点や大量のプルトニウムを回収したことを誇示。今回のサミットでオバマ大統領は、日本が500キロを超える高濃縮ウランとプルトニウムの撤去計画を進めているとし、「一国からの核物質撤去としては歴史上、最大の規模だ」と称賛してみせた。
しかし、世界には核物質がまだまだ多く存在する。サミットの開催は核テロへの関心を高め、管理強化のきっかけとなった点では評価できようが、その取り組みは緒に就いたばかりだ。
今回、対米関係の悪化で核大国ロシアのプーチン大統領は欠席した。米ロ間の核軍縮交渉の機運もしぼんだままだ。核拡散が懸念されるパキスタンのシャリフ首相もイスラム過激派が犯行声明を出したテロを理由にキャンセルするなど、関係国の足並みがそろっているとは言い難い。
今回のサミットでは、核物質や原子力施設の保安管理は各国の根本的責任であることを再確認。各国が核安全保障を永続的な優先課題に位置付けることを掲げた。国連や国際原子力機関(IAEA)などを通じた五つの行動計画も実施することになった。
各国高官や専門家による「核安全保障連絡グループ」を設立し、協議を定例化することでも合意している。国際機関を主な担い手とすることで、核テロ阻止の機運を失速させず、持続的な取り組みにしていかなければならない。
日本のプルトニウム保有量は14年末時点で47・8トンで、非核保有国では世界最大とされる。単純計算すると核兵器6千発程度の量にもなる。国内対策が十分かどうか、点検を怠ってはならない。
原子力施設が損害を受けた場合の影響の深刻さは東京電力福島第1原発事故が実証している。核物質の管理強化はもちろん、テロ対策に万全を期してほしい。 (引用ここまで)
ベルギー同時テロ 「報復の連鎖」を断ち切れ
2016年03月24日
http://kumanichi.com/syasetsu/kiji/20160324001.xhtml
昨年11月のパリ同時多発テロからわずか4カ月、欧州でまたも多数の市民が犠牲になるテロが起きた。ベルギーの首都ブリュッセルの国際空港と地下鉄の駅で爆発があり、約30人が死亡、日本人2人を含む200人以上が負傷した。一般市民が行き交う場所を狙った卑劣な犯行であり、断じて許すことはできない。
ベルギーでは、パリ同時多発テロ実行犯の1人として国際手配されていた容疑者が拘束されたばかりだった。ミシェル首相が「テロとの戦いにおける成功」と成果をアピールし、安堵[あんど]感が広まったのもつかの間、テロ対策が先の見えないものであることを浮き彫りにした。
パリのテロに続いて今回も、過激派組織「イスラム国」(IS)が犯行声明を出した。ISを攻撃する「十字軍連合」に「暗黒の日々」をもたらすと警告している。パリの事件後、IS拠点への掃討作戦が強化されたが、今回のテロを防ぐことはできなかった。軍事的手段だけでテロを防止するのは限界があろう。
空港の監視カメラには容疑者とされる3人の男が映っており、うち2人は自爆したとみられている。事件を受けて行われたブリュッセル首都圏スカールベーク地区の家宅捜索では、爆弾や化学物質、ISの旗などが発見されている。ほかに事件に関与した人物がいないか徹底した捜査が求められる。
ブリュッセルは、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)の本部がある「欧州の首都」だ。空港とEU本部が近くにある地下鉄駅は、当局が安全確保に腐心してきた最も重要な警備対象だった。そこでなぜ犯行を許したのか、検証する必要がある。
ブリュッセル首都圏のモレンベークやスカールベーク地区には、中東などからの移民街が広がる。パリ同時多発テロでは容疑者の拠点ともなった。失業などで社会への不満を持つ若者に目を付け、過激派が接近してくると指摘されている。過激思想の誘惑を断ちテロを防ぐには、治安対策だけでなく、こうした若者を国民として統合していく努力が必要だ。
パリのテロ以降、欧州では難民の流入を制限しようとする動きが急だ。難民の多くはシリアの戦火を逃れ、命からがら欧州へたどり着いた。今回のテロで保護されるべき難民たちが、さらに窮地に立たされないかが懸念される。
イスラム教徒とテロを引き起こす過激派を混同してはならない。各国でイスラム嫌悪の広がりがみられるが、移民・難民やイスラム教徒への敵意の先鋭化は、新たなテロの口実を与えかねない。「報復の連鎖」は断ち切るべきだ。
今回のテロには日本人が巻き込まれた。日本政府は各国との連携を密にしながら、海外での日本人の安全確保に全力を注いでほしい。もちろん、5月の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)や関連閣僚会合を控え、国内の警戒も怠ってはならない。(引用ここまで)
テロの「脅威」と「危機」は社説で書くが
原発の「危機」と「脅威」は書かない?