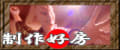応援してくれている方には気まぐれ過ぎる更新で大変申し訳ございません。
これからまた頻繁にやっていこうと思いますので今後とも宜しくお願い致します。
さて、本当に気まぐれですが今回は平成2年の旭町二区さん。
「闘将鳴動 基の猛蹴」

垂仁天皇(すいにんてんのう)の命の下、
野見宿禰(のみのすくね)が当麻蹶速(たいまのけはや)と相撲を取り、
その末に蹴り殺したという紀元前のお話。
※ 当然ググっての情報です・・
うーん、何とも凄い外題ですね。
相撲の起源になってるお話だそうですが蹴り殺すとは何事じゃ。
その後垂仁天皇に仕えましたって、殺人した奴を天皇が雇うのか?
ま、昔はそんなもんか・・
さてさて人形の話です。
右側はさすが蹴り殺すだけあって体格の良い統前人形ですが、左側は誰でしょう?
顔は今年の古川町さんの攻撃の顔だと思いますが・・
体を改造したんでしょうか?そうとも思えませんがね。
それはさておき、ぱっと見面白い配置ですよね!
似たような形の人形を手前に持ってくるなんてあまり他に見ないですね。
まあそれによって統前人形と並べられた左の人形のショボさが際立ってしまってますが・・
そりゃ蹴り殺されるんだべなと。
旭町二区さん、平成17年にも相撲の場面でこの統前人形使ってますが狙ってのことでしょうか?
ちなみにその時も相撲で殺してる場面ですが人形の組み合わせとしてはまさに統前の組み合わせでしたね。
当方HP↓(写真の人形と関係ございません)
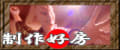
これからまた頻繁にやっていこうと思いますので今後とも宜しくお願い致します。
さて、本当に気まぐれですが今回は平成2年の旭町二区さん。
「闘将鳴動 基の猛蹴」

垂仁天皇(すいにんてんのう)の命の下、
野見宿禰(のみのすくね)が当麻蹶速(たいまのけはや)と相撲を取り、
その末に蹴り殺したという紀元前のお話。
※ 当然ググっての情報です・・
うーん、何とも凄い外題ですね。
相撲の起源になってるお話だそうですが蹴り殺すとは何事じゃ。
その後垂仁天皇に仕えましたって、殺人した奴を天皇が雇うのか?
ま、昔はそんなもんか・・
さてさて人形の話です。
右側はさすが蹴り殺すだけあって体格の良い統前人形ですが、左側は誰でしょう?
顔は今年の古川町さんの攻撃の顔だと思いますが・・
体を改造したんでしょうか?そうとも思えませんがね。
それはさておき、ぱっと見面白い配置ですよね!
似たような形の人形を手前に持ってくるなんてあまり他に見ないですね。
まあそれによって統前人形と並べられた左の人形のショボさが際立ってしまってますが・・
そりゃ蹴り殺されるんだべなと。
旭町二区さん、平成17年にも相撲の場面でこの統前人形使ってますが狙ってのことでしょうか?
ちなみにその時も相撲で殺してる場面ですが人形の組み合わせとしてはまさに統前の組み合わせでしたね。
当方HP↓(写真の人形と関係ございません)