少しまえに「人文書出版と業界再編」(『人文学報(首都大学東京)』514 巻15号、2018年3月)を読んだので、それに関して感想めいたことをかいておこうと思う次第です。
この論考のなかで小林浩さん(月曜社)は、書物の「生」は2つあると言っています。
第一の生は、原稿からそれが編集・校正・印刷・製本を経て書物になるとき。
第二の生は、出来上がった書物が(新刊)書店や図書館で他の書物と一緒にある文脈に沿って並べられるとき。
それに加えて、私は第三の生があると思っています。
新刊書店で読者に買われた本が、やがてその読者から古書店に手渡され、古書店の棚でまた別の読者と出遭うときです。そのとき、古書店の棚は新刊書店とはまた別の哲学によって編集されているでしょう。もっとも、これは私のオリジナルの意見ではなく、古書店・コクテイル書房の狩野俊さんがこのようなことをかつて言っていたなあと思ったもので。
それと同時に、エドワード・サイードが「人文的文化は共存と共有の文化である」と言ったように、書物や知は共有されていかないといけない。
ただし、それはただ誰もが同じものを見られる・読めるだけではダメで、共に読み、共に学び・考えることによって、たとえ小さくてもそこにコミュニティが発生しなければならないのだと思うのです。
でも、コミュニティである以上、そこには面倒な人間関係による制限やしがらみも込み込みであるということ。
「きずな」は「しがらみ」でもあると歴史家の大門正克さんも言っていましたし。
その点、コンピュータ・ネットワークの世界では「しがらみ」「制限」は嫌われるようで、重要なのはコンテナ(本という入れ物)ではなく、コンテキスト(本の内容にリンクする様々な「環境」、BGM・注釈のリンク・関連本や関連説明のサイト・関連動画など)の繋がりの自由度と質なのだそうです。
たしかにインターネットのリンクでは様々な関連コンテキストにすぐ「とぶ」ことができますし、関連するBGMを聞きながら文章を読むという行為は簡単にできる。それは便利だし楽しい。
しかし、そこに最大の価値があるとは私は思わない。テレビもネットも切って、ひたすら紙の本を読みつつ、その形態と内容を深く深く思索し続ける時間。そういうものに最大の価値を私は見出す。
電子書籍が好きな人はどうぞご勝手にというだけで、それが悪いわけではないが、入れ物が窮屈だからそこから出る自由を礼賛するということには共感をおぼえないのです。
なぜなら、私はその狭い箱の中でその隅を何時間でも凝視し続けることに喜びを感じるたちだからです。
でも同時に、箱の隅を見続ける人同士のコミュニティほど楽しいものはないと思うのです。
そういう人間だから、紙の本にこだわり続けるのでしょう。
こういう事をめぐって、小林さんと狩野さんと私で話せたら面白いだろうなあ。
紙の本の偏愛者同士でのコアなコミュニティ、最高だと思うのですが(笑)。
あれ? 結局、これは感想ではないですね。すいません。
この論考のなかで小林浩さん(月曜社)は、書物の「生」は2つあると言っています。
第一の生は、原稿からそれが編集・校正・印刷・製本を経て書物になるとき。
第二の生は、出来上がった書物が(新刊)書店や図書館で他の書物と一緒にある文脈に沿って並べられるとき。
それに加えて、私は第三の生があると思っています。
新刊書店で読者に買われた本が、やがてその読者から古書店に手渡され、古書店の棚でまた別の読者と出遭うときです。そのとき、古書店の棚は新刊書店とはまた別の哲学によって編集されているでしょう。もっとも、これは私のオリジナルの意見ではなく、古書店・コクテイル書房の狩野俊さんがこのようなことをかつて言っていたなあと思ったもので。
それと同時に、エドワード・サイードが「人文的文化は共存と共有の文化である」と言ったように、書物や知は共有されていかないといけない。
ただし、それはただ誰もが同じものを見られる・読めるだけではダメで、共に読み、共に学び・考えることによって、たとえ小さくてもそこにコミュニティが発生しなければならないのだと思うのです。
でも、コミュニティである以上、そこには面倒な人間関係による制限やしがらみも込み込みであるということ。
「きずな」は「しがらみ」でもあると歴史家の大門正克さんも言っていましたし。
その点、コンピュータ・ネットワークの世界では「しがらみ」「制限」は嫌われるようで、重要なのはコンテナ(本という入れ物)ではなく、コンテキスト(本の内容にリンクする様々な「環境」、BGM・注釈のリンク・関連本や関連説明のサイト・関連動画など)の繋がりの自由度と質なのだそうです。
たしかにインターネットのリンクでは様々な関連コンテキストにすぐ「とぶ」ことができますし、関連するBGMを聞きながら文章を読むという行為は簡単にできる。それは便利だし楽しい。
しかし、そこに最大の価値があるとは私は思わない。テレビもネットも切って、ひたすら紙の本を読みつつ、その形態と内容を深く深く思索し続ける時間。そういうものに最大の価値を私は見出す。
電子書籍が好きな人はどうぞご勝手にというだけで、それが悪いわけではないが、入れ物が窮屈だからそこから出る自由を礼賛するということには共感をおぼえないのです。
なぜなら、私はその狭い箱の中でその隅を何時間でも凝視し続けることに喜びを感じるたちだからです。
でも同時に、箱の隅を見続ける人同士のコミュニティほど楽しいものはないと思うのです。
そういう人間だから、紙の本にこだわり続けるのでしょう。
こういう事をめぐって、小林さんと狩野さんと私で話せたら面白いだろうなあ。
紙の本の偏愛者同士でのコアなコミュニティ、最高だと思うのですが(笑)。
あれ? 結局、これは感想ではないですね。すいません。










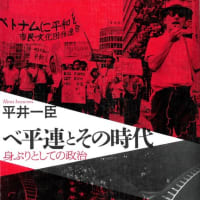
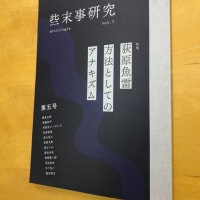



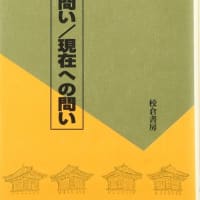
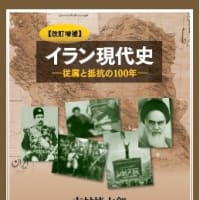

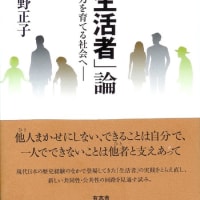

いずれ、ぜひ狩野さんもまじえて3人でお話しできれば有り難いです。