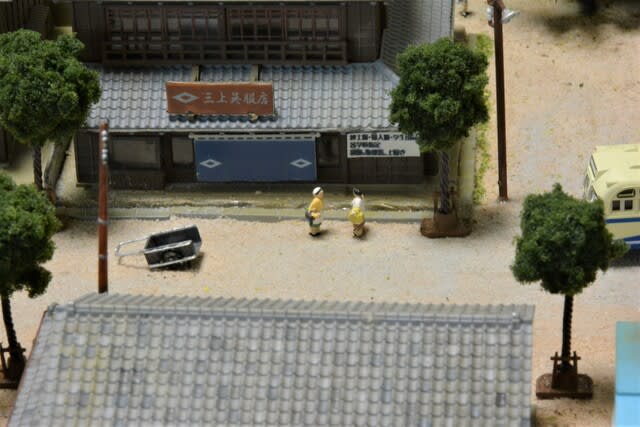レイアウトを夜景でも楽しめるようにしたいというのは早くから構想の中に入っていました。車両の前照灯や赤い尾灯、夜を疾走する車窓の明るさ・・・などは模型メーカーも開発の早い段階から取り入れてきていました。しかしながら夜の風景ということになるとLEDが一般化するまでは方法や配線などなかなか面倒そうでした。

自分も構想段階では秋葉原の小さな店を巡って使えそうな「ムギ球」など探していたものです。
そこへ情景に使える家屋の内部照明を簡便で安価に発売するメーカーが出てきて、構想は一気に実現に近づきました。乾電池を電源に使うという発想やLEDの発達のおかげです。


照明の色も電球色と蛍光灯色があり、内部に付けるだけでなく周辺をライトアップする器具も活用しました。
写真ではわかりにくいかもしれませんが、お寺の本堂は手前の木の陰に仕掛けたLEDから照らし出しています。

建物の中に入れる照明はプラ製品なのでそのまま点けると壁などから光が透けてしまいます。アルミホイルや厚紙を使ってできるだけ透けないようにしましたが、今見てみると透けている部分もけっこうあって、レイアウトがまだあるならすぐにでも修正したい部分です。プラの建物を組み立てる時のすき間も光が漏れてしまっていますね。

それでも部屋の照明を消して、あちこちに明かりが点いたレイアウトの中を夜行列車よろしく窓が明るい客車を走らせると、ふだんの情景とはまったく違った雰囲気を出すことができました。
「ひと粒で二度おいしい」キャラメルみたいでした。

自分も構想段階では秋葉原の小さな店を巡って使えそうな「ムギ球」など探していたものです。
そこへ情景に使える家屋の内部照明を簡便で安価に発売するメーカーが出てきて、構想は一気に実現に近づきました。乾電池を電源に使うという発想やLEDの発達のおかげです。


照明の色も電球色と蛍光灯色があり、内部に付けるだけでなく周辺をライトアップする器具も活用しました。
写真ではわかりにくいかもしれませんが、お寺の本堂は手前の木の陰に仕掛けたLEDから照らし出しています。

建物の中に入れる照明はプラ製品なのでそのまま点けると壁などから光が透けてしまいます。アルミホイルや厚紙を使ってできるだけ透けないようにしましたが、今見てみると透けている部分もけっこうあって、レイアウトがまだあるならすぐにでも修正したい部分です。プラの建物を組み立てる時のすき間も光が漏れてしまっていますね。

それでも部屋の照明を消して、あちこちに明かりが点いたレイアウトの中を夜行列車よろしく窓が明るい客車を走らせると、ふだんの情景とはまったく違った雰囲気を出すことができました。
「ひと粒で二度おいしい」キャラメルみたいでした。