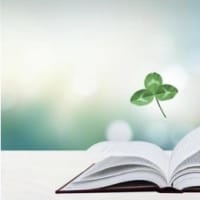この記事は、いささか否定的なニュアンスが含まれています。
閲覧にはご注意ください。
***
以前の記事でお伝えしましたが、二次創作活動には「オン」と「オフ」があります。
「オン」とはオンライン活動で、ネット上でのみ公開するスタイル。温泉やらオン専と名乗るひともいます。いっぽう、「オフ」はオフライン活動で、同人誌を刊行し、イベント会場で頒布する活動。こちらは、一般的に同人者だとか、同人作家とも呼ばれます。
本題に入る前に、すこしお小言を述べます。
私はこの「同人」という言いかたが好きではないので、拙ブログでは常に二次創作活動、二次創作者と呼びならわしています。私のなかで「同人誌」といえば、教養ある紳士淑女がたしなむ詩や俳句などの文芸誌のことで、主宰者の統率のもと、メンバーが節度を保って創作にいそしみ、合評し、切磋琢磨しあうというイメージがあります。同好の志という言葉がありますが、同じ目的のために集まった仲間。ひるがえって、いわゆるヲタク界隈の二次創作同人誌にそういった慎ましいふるまいがあるでしょうか。なお、コミックマーケットなどで販売される同人誌には、評論文や一次創作物もあります。
私は子供のころ、地元開催の同人誌マーケットでしか直接、このオフ活二次創作者に遭遇したことがありません。なにせ、人混みが大の嫌いですから、イベント参加もしたことがありません。ですので、以下の実態は、あくまでネット上の見聞を集めたうえでの私見です。
同人誌を頒布(実際は販売なのだが、営利目的ではないとするのでこうした言いかたをするらしい…)するアグレッシブな二次創作者は、かなりの自己管理能力が求められます。たとえるならば、受験生が年複数回の模試や資格試験にチャレンジしているようなもの。コミックマーケットと呼ばれる日本最大級の歴史あるイベントは、東京マラソン並みにかなりの人気ですので、参加サークルは抽選制となっているようです。参加するのも無料ではない。
いま、サークルと申し上げましたが、これは団体名称です。
個人のペンネームとは別なのですが、おひとり様サークルもあれば、複数名での参加もあります。有名なのが、女性人気の高い作家集団のCLAMPですよね。最近、90年代の話題作だった「東京BABYRONN」のアニメ化も決定しましたけれど。同人誌発行者のなかには、すでにプロデビューして日本を代表するクリエイターになっているひともいます。こうした一般的な作家の登竜門を通さない商業デビューを夢みて、イベント参加する二次創作者もいるわけですね。
さて、めでたくイベントに当選し参加が決まると、二次創作者さんは締切までに原稿を作成せねばなりません。プロの作家ならば企画前の打ち合わせ会議があったり、連載ならばネームという下書き漫画の査定があったりしますが、素人の二次創作者には誰憚ることもなく、創作をすすめられます。誰かに没にされるとか、ネタがお蔵入りすることもありません。ただ、自由なのはいいのですが、ページ数が多すぎると印刷代が高価にもなりやすいでしょう。
そして原稿が完成すると、印刷所へ入稿します。
最近はほとんど版下はデータでしょう。ここで同人誌の紙の素材やデザイン、表紙を選び、指定することができます。印刷された同人誌は、直接持ち込む場合もありますが、たいがい、会場へ郵送する場合がほとんどです。
なお、製本されたものでなくとも、自分でコピーしてホチキスなり、布テープなりで本にしてしまう二次創作者もいます。資本の限られた学生さんならば、よくあることです。
さて、イベント当日。あらかじめ指定された会場ブースに待機し、同人誌を並べてゲストを待ちます。会議机に布を敷いて、本やグッズを陳列する。さしづめ、お祭りの屋台感覚ですね。馴染みのサークルさんがいると、挨拶に出向いたり、同人誌を交換したりもするそうです。読者から感想の手紙をもらったり、差し入れのお菓子をいただいたりもする。
終了時間になると設営を撤去します。
コミケは3日間ぐらい開催されるようですが、だいたいどのサークルも一日だけ参加が多いのかも。そのあと、参加者どうしでオフ会と称して慰労の食事会が催され、親睦を深めたりもするようです。帰宅するとSNS上でお疲れ様報告をするとともに、お付き合いのある二次創作者さんの同人誌の感想を述べたりもする。
以上が基本的な流れ。
このオフ活動の二次創作の醍醐味はなんでしょうか。それは、作家ごっこが疑似体験できて、自分の本という世界で唯一無二のメモリアルがつくれること。執筆者としての自分を他者の前で現前化することによる、アイデンティティの確立とでもいったものでしょうか。また、非日常的な楽しみの場での高揚感を味わいたいというのもあるのかもしれません。おそらく複数年にわたってその趣味活動をつづけ、自腹を切ってまで参加したいという熱意には、それに代わる感動があるのかもしれません。それこそ、一度知ったらやみつきになるような。
ところで、ネット上で散見するこのイベント参加型同人活動家に多い愚痴が、同人誌刊行前よりも、そのあとのこと。小さなイベントの主宰者が逃げたとか、会場で知人に売り子を押しつけられたとか、相性の悪い者で隣り合ったとか。読者に万引きされたとか、本を買わずに傷められたとか。あるいは、同じ二次創作者どうしでも、お義理な差し入れが大変だとか、対応が粗雑で不快だったとか、感想を言い合うのが苦痛だとか。オフ会が楽しくなかったとか。サークル内あるいは合同誌の売上の配分で揉めたとか。
私は経験していないので、ほんとうに他人ごとで申し訳ないのですが。
やはり、こういったヲタク界隈の諍いごとを知りえてしまうと、「同人」という響きはなんなのだろうか、と思うわけですよね。同ジャンルでの二次創作ならば、愛のある原作語りをしたいとか、別ジャンルでも情報交換をしたいとか。親しみのある同調ならばいいけれども…。
オン専の二次創作者は極力すれば、自サイトもしくはSNSアカウントで発表すればいいだけなので、他人に気兼ねをすることが少なくてすみます。
けれども、そこを踏み出して、あえて自分の存在をさらしてまで、二次創作をしていますよ、こんな本を売っていますよと世間さまに顔を売ることには、はたしてどんな意図があるのでしょうか。
そのひとつには、クリエイティブな活動で収益を得たいという野心もあるでしょう。
実際、創作を飯のタネにしているとカッコイイという風潮もあります。他人の編み出した知的財産権のあるキャラや設定などを流用して設けることについてはグレーゾーンではあるのですけども、人気ジャンルのエロ同人誌だと下手すると、その版権物に投資をしなくとも、何となく似せたキャラを描いて絡ませれば売れてしまう。しかし、私はもし、その二次創作者が将来的に本物の創作者を目指すならば、なるべくこうした萌え成分でアドバンテージが得られる二次創作はしないほうがいいかと感じています。
上記の作家性の疑似体験のほかに、同人活動家を惹きつける要素といえば、おそらく共同体への従属ではないでしょうか。日常生活では鬱屈しているけれども、イベント会場では「先生」ヅラして褒めたたえられたり、感謝されもする。そして何よりも、同じものが好きという共通の感性で寄り集まった者どうしの連帯感。もしこれを小賢しく例えるのだとしたら、水滸伝の梁山泊みたいなもの。ならず者だけども豪の戦士が居心地のいいコミュニティをつくりあげる。あるいは、八犬伝のごとく、同じ志を持ったものが集結し、絆で結ばれるといった神話。実際のところ、二次創作で爆発的人気があるのは、数人の美少年グループや美少女軍団が闘いあうといった共同作業めいたストーリーラインです。
自分たちが萌えるキャラの世界観そのままに、同じ美意識=萌えの仲間を求め、自分を認めてもらおうとし、自己のアングラな心情を解放する。それは、なぜか。孤独だからに他ならない。とくに、同人界隈におきまして、女性参加者の声が大きいのは、なにやら世の不満を表現者としてもの申したいからなのかもしれません。
ただ、私は常々思うのですが、オフ活もしくはオン専にかかわらず、二次創作に入れ込んでいる人は、いちど自分を離れたところから眺めてみてもいいのではないかなと思うのです。
世間にはヲタク界隈のねっとりした関係性ではない付き合いもあります。私からすると、ネットで見聞する同人界の闇みたいな人間模様は、それこそひと昔まえの田舎の寄り合いじみていて、絶対に足を踏み入れたくないなあと思わざるを得ないわけです。同人誌そのものを作る作業に否定はしませんが、まあ、生活設計と相談しながらの余暇の道楽ですしね。燃え尽きないように、ほどほどにしましょう。
(2020/11/22)