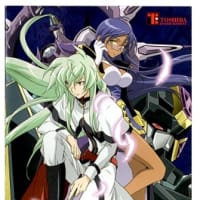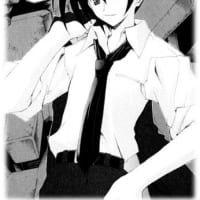米国ではここ数年、大きな新聞社がいくつも倒れている。記憶にあたらしいのは、08年12月に破産申告をしたトリビューン社。ニューヨークタイムズ社とならぶ米国の大手マスメディアの代表格で、名門ロサンゼルスタイムズ紙も傘下にしていた。球団シカゴ・カブスを運営し、新聞10紙、ローカル放送局20局を抱える。それが、破綻したというのだからかなりおおきな話題をさらった。日本でいうなら、読売新聞がつぶれたぐらいの衝撃だろう。もともとジャーナリズム大国で大小各紙が乱立していたであろうから、淘汰の時代を迎えたといえよう。
ふりかえって、我が国。活字の危機なるものはすでに十年近くも叫ばれてきた。だが、去年からの不景気におちいっても、日本のTVも新聞社も倒れる気配はなかった。が、しかし、ここにきて米国のマスメディアの失墜が日本のそれにも押し寄せているのかもしれない。
そう思ったのは、こんなニュースを耳にしてから。
朝日新聞「ボーナス40%減」 業界に衝撃が走る(J-CASTニュース09年5月23日)
朝日新聞社の社員のボーナスを40パーセント削減するというニュースだ。読売新聞社はじめ大手新聞社も軒並み足並みをそろえたかのごとく、人件費削減に乗り出すという。
社長のボーナスゼロをはじめ、役員報酬も減額。こんなこと、あたりまえではないだろうか。
労働組合がわは完全に会社と対立する構えであるという。
ばかばかしいと思ったのは私だけか。
数箇月前に身内がつとめる大手のメーカーでも、新聞誌面では春闘で賃金据え置きが発表されボーナスも出ない、と報じられた。ところが、身内にきけば、労組側が果敢に交渉していて、不利益なことにはならないという。私は呆れてしまった。こうした正社員を優遇するために、おそらく派遣や請負社員をこきつかい、彼らを解雇するか賃金カットしてその余った経費を回しているのだろう。
新聞社は、派遣村が話題になった頃、さかんに派遣労働者の悲惨な実態を書き立てたが、じつはその新聞社こそが契約社員を大量採用しているいっぽう、地方の支局長など管理職には破格の給料を支給しているという。もともと高すぎる業界の給料が減るのはあたりまえだろう。産業構造がかわって、ある流行の業界が衰退していくのは世の常なのだから。
新聞社だけでなくTV業界も同様の苦境を強いられている。
ボーナス2~3割カットに不満 TBS労組が全面スト突入(J-CASTニュース09年3月16日)
この記事は、おどろくことを伝えている。なんと春闘に参加したTBSアナウンサーが、ニュースの看板番組をその日休んだというのだ。もちろん、それまでの高待遇を維持したいのはわかるが、視聴者にニュースを届ける報道の使命を忘れた、ただの守銭奴だと言われてもしかたがない、所業ではないだろうか?
この記事は、前記の新聞社の記事とは違って、業界の衰退原因をワーキングプアを生む下請け労働者の待遇悪化にもとめているのだ。
新聞社もおなじように従業員の格差がはげしい企業だ。とくに新聞の購買というのは、記者ではなく、各販売店の配達人や勧誘員によって支えられている。記者は文士然としているが、こうした末端で雇われているのは低所得者層である。販売店の経営者もやくざ稼業のような傲慢なひとが多く、ちゃんとした給料を従業員に渡していない可能性もある。彼らの生活を救わない限り、購買部数も上がらないだろうし、購読者も減るいっぽうだろう。
さて、この経営難の背景にあるのは、ニュースにもあるように購買部数の落ち込みと、広告収入の激減である。
それだけしか書いてはいないが、それがあきらかにインターネットの普及と関係があることは、誰しもお見通しであろう。
企業はネット上のクチコミ、バズマーケティングを利用することによって、消費者と距離の近いコンタクトがとれる。しかも安い費用で、多くのひとに旬の商品情報をお届けできてしまう。
ニュースだってネットで数秒刻みで読めてしまう。文化教養欄などを読めばまだまだ棄てたものではないなと思うことあるが、ネット上には専門のニュースサイトが発達している。
さらにいっそう侮れないのは、登録すれば自動に配信されるメールマガジンの存在だ。そのタイトルのつけかたはスポーツ新聞のヘッドラインを借りたかのように絶妙。メールを開かずとも、できごとが一文で読めてしまう。
こうしたネットのニュースサイトが普及する影にはブログ文化の反映がある。ブロガーはホットなニュースを記事にしたがるので、リンクしやすいネットのニュースサイトをよく読むだろう。そしてトラックバックによって、各ブログで話題を共有する。
これは、新聞を朝な夕なに各家庭のポストにいれて終わりのニュース配信方法ではとてもマネできない。ブログをさかんに書いている人で、いまだに新聞だけに載せた話題をふりまいているような人は希少価値だろう。たとえばある地方紙だけに載った話題とか、人生相談コーナーなんぞを記事にされたとしても、読んだ側はちっともおもしろくない。なぜなら、その情報元にアクセスできないからだ。(これは、映画や小説のレヴューをそれを知らない人が読んでもつまらない現象に似ているが、新聞が残念なのは一日限りの情報であって、あとになってもそれを追うことがむずかしいことだ)
さて、結論をいうと、私は日本の新聞社が減ろうが、放送局が減ろうがいっこうにかまわない。事実、いま現在の暮らしでは新聞はもう数年間も購読していない。
そしてありていにいうと新聞を読むより、それなりの学識のある個人のブログを読むほうがおもしろいことこのうえない。新聞が売れない理由は単に、広告収入の激減という外部の理由だけだろうか? 記事の質がおそろしく落ちているとはいえないだろうか。記事の質の低下とは、すなわちプロの筆耕がもはや素人レベルに堕落したことを意味する。無料で手に入る文化に慣れ、しかも貧困層の若者ほど、つまらない活字などには見向きもしない。質うんぬんを言うのはおこがましいかもしれないが、世の中にはこんな値段でよくも売りつけたものだと腹立たしくなるような映像や文章もある。(もちろん、無料で読めるもののほうが、そうしたくだらなさは多いが。ブログはくだらなく書いているものだ)
とはいえ、購読者が県民の九割を超えるほどかたく支持されているような地方紙は、地域に密着した情報提供をすることで生き残れるように思われる。むしろ、恐いのは放漫経営をして肥大化し、そのツケを弱者に負わせた巨大メディアだろう。
しかし、ここで危惧するのは、新聞の折り込み広告に頼っていた地域の企業であろう。すでに、企業の側からの広告費削減で折り込みチラシが減っているのかもしれないが。たとえば日替りで日常品のセールスをせねばならないスーパーやショップは、新聞が消えるとしたら、その広報元をべつのメディアに依存することになろう。それがネットなのか、それとも私の郵便ポストに定期的に放り込まれていく、ピザハットのチラシのようなDMなのかはわからない。
もはやメディアのリポーターや新聞記者が言論・表現のオーソリティとしてもてはやされた時代は終わったといえるのだろう。
私が大学受験の際は、朝日新聞の天声人語を欠かさず読み、就職活動時はといえば日経新聞に眼を通すのがあたりまえだったが、もう古くさいのかもしれない。
ちなみに朝日新聞は、かつて新卒のとき就職活動で会社説明会に訪れたことがあった。だが、新入社員はサツ回りといって事件担当にされることが多く、また地方への転勤もあるので入社試験は受けなかった。受けても、自分の力量ではとうていうからなかっただろうとは思うが。