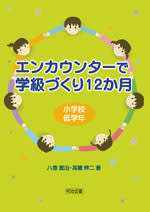
エンカウンターで学級づくり12か月について問い合わせをいただきました。先日お邪魔した大阪でも話題になっていました。低・中・高学年の3冊あります。その時期に合うエクササイズや学級懇談会などで使えるエクササイズが掲載されています。
ぜひご一読ください。
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-872513-3
エンカウンターで学級づくり12か月 小学校高学年
ロングセラー好評14刷
八巻 寛治・平野 修 編著
1年間を見通したワークシート付きのエクササイズが満載。
学級づくりにエンカウンターは絶対に効果的。取り組んだ先生方の声です。本書は、高学年の学級づくりの筋道に生きるエクササイズを選択・網羅、シート付きで手軽に活用できます。特に、若手の先生方の力になること間違いなしです。是非お役立てください。
定価: 1,995円(税込) 送料無料 ISBN:4-18-872513-3
刊行:2006年2月8日 14刷
仕様:B5判 112頁
はじめに
学校現場に活用できるエクササイズの提案
構成的グループエンカウンターは,今や全国どこの学校に行っても実践している人はいる。深く理論を知らなくても,毎年夏の「エンカウンター入門講座」(東京)や,日本教育カウンセラー協会(学会)主催の養成講座などで,全国各地に研修会が開かれるようになった。また,今でも大ベストセラーを記録し続けている「エンカウンターで学級が変わるシリーズ(小・中・高・ショート・総合・事典等)」國分康孝編集・監修(図書文化)をもとに実践することができる。私は同シリーズのショートエクササイズ集(Part1・2)の編集に携わっている。
また最近では,次のように,どちらかというと学校現場で活用しやすいようにアレンジした形のエクササイズ集や,すき間の時間に活用できる簡便法としてのエクササイズを提案し,様々な場面で提供してきている。参考にしていただきたい。
・構成的グループエンカウンターミニエクササイズ56選小学校版八巻寛治著(明治図書)
・小学校学級づくり構成的グループエンカウンターエクササイズ50選小学校版八巻寛治著(明治図書)
・実践構成的グループエンカウンター№1~7(1号は“春”,2号は“夏”)号(明治図書)
・エンカウンター実践テキスト№1~3号,(明治図書)
・保護者会で使えるエンカウンター・エクササイズ八巻寛治他編著(ほんの森出版)
・「小一教育技術」「小二教育技術」〔小一は平成13年度~16年度,小二は平成14年度~16年度まで毎月連載,現在は年数回掲載〕(小学館)
・「月刊特別活動研究」〔平成12年度~平成17年度〕(明治図書)
・「月刊学校教育相談」〔平成12年度~平成16年度〕(ほんの森出版)対話を用いた(シナリオ)ロー
ルプレイングをテーマに連載
本書のねらい
この本を出すに当たり,次の2つのねらいをもった。
①1年間を見通した小学校の学級づくりで活用できるワークシート付き(一部説明のものもあり)のエクササイズを示したい(各学年部月ごとに学級活動・朝の会帰りの会・教科・領域各1事
例ずつ,保護者会4事例,ウォーミングアップ8事例)。
②低・中・高学年と発達段階を考慮して時期にあったものを紹介(実際に実施したもの)し,各学級担任が手軽に学級づくりに活用できるようにしたい。 ことの2つである。
今回掲載した45のエクササイズの多くは,編集に協力してくれた人たちが学級づくりに生かし,教科,学級活動,道徳,朝の会帰りの会など,様々な場面で活用してきたものである。実施するときは追体験するような気持ちでやっていただくことをお勧めしたい。
※本文中の参考・引用文献(主に図書文化刊)は,似ているエクササイズを紹介したいために,意図的に記述させていただいている。
構成的グループエンカウンターを学ぶきっかけは?
私は,小学校の教師になる以前に,民間企業に勤務し,人事研修の1つとして取り組んだ「自己啓発研修」でロールプレイングやエンカウンターなどを学ぶ機会があり,それを学級づくりに取り入れてきた。【参照】平成5年度「月刊特別活動研究」学級活動<低学年>の連載(明治図書)
その後,仙台市教育センターの調査研究事業や長期研修員,グループ奨励研究(小中連携・学級づくり)などを通して,市内や県内の先生方とネットワークをつくり,勉強会を行ってきた。その中でも,國分カウンセリング研究会主催の2泊3日のワークショップ(体験コース・リーダー養成コース)では,元祖國分エンカウンターを肌で感じることができ,目から鱗が落ちるほどの新鮮さを感じたのを今でも覚えている。それ以来,エンカウンターの有効性を確かめながら全国学校教育相談全国大会や日本カウンセリング学会,教育カウンセラー(学会)全国大会,特別活動の研究会などで取り組みの成果を発表してきた。
特に平成8年度,仙台市教育センターの長期研修員として,前年度にいじめが起きたある学級を対象に,その後の予防と再発防止を図ることを目的に,構成的グループエンカウンターのエクササイズをミニエクササイズとしてプログラム化して実践した。
徐々にではあるが,ぎくしゃくしていた人間関係が改善され,その後いじめは起きなかった。また,中学生になってからの追跡調査でも,8割以上の子が構成的グループエンカウンターの体験が,何らかの形で中学校生活に役にたっていると答えた。
こんなことを心がけて実践している
私が今まで担任したクラスには,不登校や場面寡黙,てんかんやLD児,ADHD児,虐待を受けた子,帰国子女など様々な問題や課題を抱えている子がいた。また,前年度に学級崩壊に近い状態になったクラスを受け持ち,涙の卒業式を迎えたという経験も何度かしている。
それらの経験の多くがエンカウンターのお陰であると思っている。國分カウンセリング研究会主催のリーダーコースのスタッフに入れていただいたり,毎年夏に行われている学級づくりのためのエンカウンター体験コースのリーダーを数年に渡り担当させていただいたり,全国の研究会等から要請された研修会で,のべ約5,000人の方とお会いすることができた。
構成的グループエンカウンターは,そんな私の「苦しいときの神頼み」の1つとして有効に活用してきた。「美味しいとこのいいとこどり」的に,自分ができる範囲でやれるように,いわば八巻流にアレンジして取り組んできた。ぜひみなさんも自分流にアレンジして取り組んでいただきたい。
我が師であり,構成的グループエンカウンターの実践を支えてくださっている國分康孝先生久子先生ご夫妻のモットー「分かりやすくてためになる」を心がけ,本誌を編集してきたつもりである。この本の出版にご尽力いただいた多くの方々に「お陰様」の気持ちを伝え,感謝の言葉としたい。
平成18年 初春
編者代表 仙台市立小学校教諭 上級教育カウンセラー /八巻 寛治
《やまかん・こんなことやってます》
明治図書関連↓
http://www.meijitosho.co.jp/eduzine/cskill/?id=20130191
http://www.meijitosho.co.jp/search/?keyword=%94%AA%8A%AA%8A%B0%8E%A1
http://www.meijitosho.co.jp/eduzine/interview/?id=20100296
小学館関連↓
http://www.shogakukan.co.jp/yomi/author/_author_6821
アマゾンさん↓
http://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_pg_1?rh=n%3A465392%2Cp_27%3A%E5%85%AB%E5%B7%BB+%E5%AF%9B%E6%B2%BB&ie=UTF8&qid=1364760796
 授業力&学級統率力 2013年7月号が発刊になりました。
授業力&学級統率力 2013年7月号が発刊になりました。










 やまかん先生のHappy教育コラム♪最終号が掲載になっています。
やまかん先生のHappy教育コラム♪最終号が掲載になっています。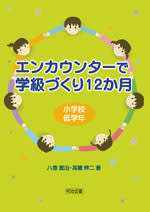 エンカウンターで学級づくり12か月について問い合わせをいただきました。先日お邪魔した大阪でも話題になっていました。低・中・高学年の3冊あります。その時期に合うエクササイズや学級懇談会などで使えるエクササイズが掲載されています。
エンカウンターで学級づくり12か月について問い合わせをいただきました。先日お邪魔した大阪でも話題になっていました。低・中・高学年の3冊あります。その時期に合うエクササイズや学級懇談会などで使えるエクササイズが掲載されています。 やまかん流☆カウンセリングスキル(11)
やまかん流☆カウンセリングスキル(11) 6月の学級づくりパワーアップセミナーの案内です。私もお邪魔させていただきます。Q-Uなどのアセスメントを元にした,いじめ指導の授業提案をします。魅力的な講師,講座内容が満載です。超お勧めのセミナーです。詳細は次の通りで,こくちーずから申込みください。
6月の学級づくりパワーアップセミナーの案内です。私もお邪魔させていただきます。Q-Uなどのアセスメントを元にした,いじめ指導の授業提案をします。魅力的な講師,講座内容が満載です。超お勧めのセミナーです。詳細は次の通りで,こくちーずから申込みください。 やまかん先生のHappy♪教育コラム2013年4月号が発刊になりました。
やまかん先生のHappy♪教育コラム2013年4月号が発刊になりました。 授業力&学級統率力の2013年5月が発刊になっています。
授業力&学級統率力の2013年5月が発刊になっています。