前回、「シカの自然増加率は20%(推定値)で、捕獲しないと4~5年で生息頭数が倍増する」とお話しました。
現在、シカによる農林業被害を抑えるためには、シカを捕獲して、生息頭数を減少させる必要がある・・・ということで、国もシカ捕獲を進めています。
「捕獲しなくても、食べるものがなくなったら、自然に数が減るんじゃないの?」と思われる方もいるかと思います。
北海道や東北など積雪量の多い地域であれば、「数十年に一度の大雪」などの影響で、シカが大量死することもありますが、和歌山県のように温暖な地域では、大量死という現象は起こりにくいとされています。
カモシカの場合、パラポックスウイルスに感染し、大量に死んでしまう場合があるので、一定の個体数が維持できているようですが、シカは、個体数に大きな影響を与える感染症がないようです。
少し、話がズレてしまいましたが、エサが減っても、シカの生息数は大きく減少することはないそうです。
栄養状態が悪いと出産の初産齢が高くなったり、妊娠率が低下したりするので、個体数が大きく増加することはないと思いますが、今まで食べなかった植物を食べたり、落ち葉を食べたり、なんとか生き残ろうとします。
栄養状態が悪いので、一個体あたりの体重は小さくなりますが、シカの個体数は維持するそうです。
エサ資源が少なくなると、栄養状態の悪い貧相なシカが居残り続ける・・・ということに。
そこで、森林を伐採すると、シカのエサ場が出来上がり、シカの栄養状態が改善されると、初産齢の低下と妊娠率の向上という増加の原因につながるというわけです。
皆伐などの生産活動やインフラ整備など開発行為は、シカのエサ場になります。
皆伐の後に生える草木はもちろん、道路法面の緑化工事もシカにとってありがたいエサになります。
広々とした空間に草木が生えれば、そこはシカにとって、最高のエサ場になります。
実は、人間の生産活動や開発行為が、シカの個体数増加を助長しているというわけです。
エサが減少しても個体数は大きく減少しない。
でも、人間が森林や森林に近い場所で、生産活動や開発行為をすれば、シカのエサ場となって、増加を助長させる・・・。
なので、シカの被害対策として、シカ捕獲が重要だと言われているのだと思います。
ちなみに、被害対策として、シカ捕獲を行う場合、「メスの捕獲」が重要となります。
例えば、毎年1頭、オスを捕獲した場合・・・
極端な例ですが、オスを捕獲しても、次位のオスがハーレムを作るので、個体数減少にあまり影響を与えないと考えられます。
また、捕獲したオスが、そのエリアでNo2以下なら、繁殖に関与することもないので、やはり個体数現象にあまり影響を与えないと考えられます。
では、毎年1頭、メスを捕獲した場合・・・
当たり前のことですが、メス1頭を捕獲すれば、子供が産まれないので、個体数現象に影響を与えられると考えられます。
妊娠しているメスを捕獲すれば、2頭分に当たりますし、この先10年以上の繁殖源を断つことができたとも言えます。
そのエリアのメスを全て捕獲すれば、残りはオスなので、増えることはありません。
といっても、これはあくまで机上の空論です。
実際は、捕獲しても捕獲しても、次の群れが入れ替わってくるので、長期間、辛抱強く、捕獲し続けないといけない・・・そういうところが多いのではないかと思います。
明治時代の頃は、絶滅を危惧されたニホンジカ。
個体数回復のために、いくつかある政策の1つとして、メスの捕獲を禁止しました。
それが功を奏し、再び、被害が手に負えなくなるくらいまで、個体数が回復。
前向き(?)に考えると、ニホンジカの保護という政策としては、大成功だったと言えるんじゃないでしょうか。
でも、時代は進み、今は個体数が増加したニホンジカ。
農林業において被害は絶えません。
また、シカを通じてマダニがもつウイルス(SFTS)で、人が亡くなる事例も。
人がシカを捕獲することが少なくなり、シカも人を警戒しない&恐れない個体も生まれています。
人とシカの距離が短くなるほど、ウイルスの感染するリスクも高まると思います。
山に行かなくても、シカがウイルスを保有するマダニを落とすかもしれません。
シカ問題は、農林業被害に限らず、人命にも関わりかねない被害へと発展するおそれもあります。
我が家の周りもシカがウヨウヨしています。
今年はシカを捕獲しようと思います
捕獲方法や解体など、いずれご紹介できれば。
~以下、関連記事です。~
















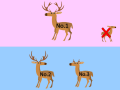
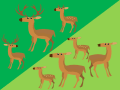









 !?
!? )。
)。



















 )
)









 ものの、1~2回繰り返すと、襲われないと確信するのか、襲われても逃げ切れる自信があるのか、無視
ものの、1~2回繰り返すと、襲われないと確信するのか、襲われても逃げ切れる自信があるのか、無視
