「歴史36戦後/ 祭りじゃ俄じゃ」で使われた俄です。
[番場の忠太郎・小浜(母)・お登世(妹)]
(下手から忠太郎が登場)
忠太郎 母の面影瞼の裏に、描きつづけて旅から旅へ。昨日は東と訊いたけど、今日は西だと風便り。縞の合羽が涙に濡れて、母は俺らをどうして捨てた。恨む心と恋しい想い。宿無し鴉の見る夢は、覚めて悲しい幕切れさ。生れ故郷も遥かに遠い、母恋い番場のこの俺さ。もしやもしやと逢う度毎に、尋ね尋ねてやって来た。此処はお江戸の柳橋、人に知られた水熊よ。ご免めんなすって、おかみさん。
(上手から小浜が登場)
小浜 中へ入って、用があるんならさっさと言っておくれ。わたしゃ忙しいんだから。
忠太郎 ご免こうむります。(敷居を越えて下手に坐り、しばらく何も言えずにいる)
小浜 何とか云わないのかい。用があって来たんだろう。
忠太郎 おかみさん、当って砕けろの心持で、失礼な事をお尋ね申しますでござんすが、おかみさん、もしやあっしぐらいの男の子を持った覚えはござんせんか?
小浜 あっ!
忠太郎 覚えがあるんだ、顔に出たそのおどろきが。ところは江州坂田の郡(こおり)醒ケ井村から南ヘー里、磨針峠の山の宿場で番場という処がござんす。おきなか屋忠兵ヱという、六代続いた旅館へ嫁に行き、男の子をひとり生みなすった。そしてその子が五つの時に家を出た。罪は父親にあったと訊きました。おっ母さん、あっしが伜の忠太郎でござんす。
小浜 私には、おまえのような子はいないよ。確かに番場で忠太郎という子を生んだが、五歳のときに死んじまったよ。どこのどなたか知らないけれど、やけに芝居が上手いじゃないか。ちょっと小金がたまったら、やれ親戚だ倅だとうるさいことだよ。たとえお前が忠太郎だとしても、そんな姿で訪ねて来たんじゃ、誰が喜んで迎えるもんかい。母を探しにきたのなら、なんで気質の姿で訪ねてこないんだよ。
忠太郎 それじゃあおかみさん、どうあっても倅じゃないと・・・。
小浜 うるさいね!
忠太郎 よしやがれ! おい小浜、やい小浜! なんてえ面しやがるんだ! 赤の他人なら小浜で充分だ! おい、おかみさん、なんとか言いなさったねえ。親子の名乗りがしたかったら堅気の姿で訪ねて来いと・・・笑わしちゃあいけねえぜ、親に放れた小僧ッ子が、グレて堕ちたは誰の罪。何んの今更どうなろう。よしや堅気になったとて、喜ぶ人はござんせん。それにもう一つ、おいらのことをゆすりと言いなすったが、春秋数へて二十年。想い焦がれて逢いに来た。たった一人の母だもの。どんなお方であろうかと、寝ても覚めてもその事ばかり、無事でいたならよいけれど暮らしに困っている時は、助けにやならぬと百両を、肌身離さず抱いていた。もしやもしやと逢う度ごとに、尋ね尋ねて目が昏れりや、夕餉(ゆうげ)の煙りが切なくて、窓に灯りがともる頃、人の軒場に佇ずんで、忍び泣きしたこともある。夢に出て来た瞼の母は、こんな冷たい女(ひと)じゃない。逢わぬ昔が懐しいやい! 御免なすって!
(忠太郎は下手に入る)
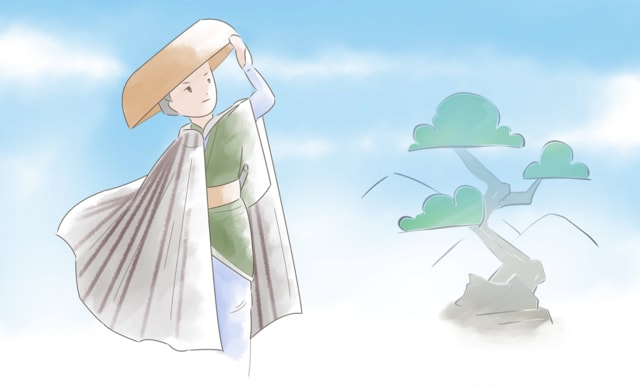
(かわりに下手からお登世が登場)
お登世 おっかさん、
小浜 お帰り、早かったねえ。
お登世 おっかさん、今、出て行ったのは、いつもおっかさんが話していた、番場に残した忠太郎兄さんじゃないの?
小浜 お前、見たのかい。
お登世 ううーん。話は残らず隣の部屋で聞きました。それでもあなたは母ですか。子を持つ親というものは、そんな邪険なものでない。母に捨てられ父には死なれ、広い世間にただ一人、そんな兄さんを一人で返す親はない。たった一人の兄さんとともに涙を流したい。
小浜 お前の心に対してもおッかさんは恥かしい。思いがけない死んだとばかり思っていた忠太郎が名乗って来たので、始めの内は騙かたりだと思って用心し、中頃は家の身代に眼をつけて来たと疑いが起り、終いには――終いにはお前の行く末に邪魔になると思い込んで、突ッぱねて帰してやったんだが――お登世や、あたしゃお前の親だけれど、忠太郎にも親なんだ、二人ともおんなじに可愛い筈なのに何故、何故お前ばかりが可愛いのだろう。
お登世 おんなじおッかさんの子じゃありませんか。
小浜 おっかさんが悪かった。許しておくれ。お前の事や水熊のことを考えて邪険に帰したおっかさんが悪かった。お登世、おまえも一緒にきておくれ。
(二人が外に出ると猛吹雪)
小浜 忠太郎~
お登勢 兄さ~ん
(二人が下手に入る)

(上手から忠太郎が出てくる)
忠太郎 あの声は、おっかさんと妹だ! 何を言ってやんでえ! 何が今更忠太郎だ。ままよ浮世を三度笠、六十余州の空の下、股旅草軽(わらじ)を穿くだけよ。
(奥から 二人が呼ぶ声)
忠太郎 誰が、誰が逢ってやるもんか。それでいい、逢いたくなったら、俺ア瞼をつぶるんだ。
(二人が呼ぶ声が近づいてくる)
忠太郎 あゝまだおっ母さんが、あんなに俺を呼んでいる、妹もあんなに一生懸命呼んでいる。
(忠太郎はいてもたってもおられなくなり)
忠太郎 おっ母さん! 忠太郎は此処だよ、おっ母さん!
(上手から二人が出てくる)
小浜 忠太郎、忠太郎!
お登世 兄さん!
(三人がしっかりと抱き合う)
お登勢 兄さんがお腹をすかしているだろうと、慌てて袂(たもと)に入れた、これで一つになれたのかしら。
(袂から丼ぶり鉢を取り出す)
忠太郎 何や! 空の丼ぶり鉢やないかい!
小浜 これで一つになれたとわ?
お登世 はて!
忠太郎 はて?
お登世 はーて、わかった!
三人 苦労な七坂乗り越えて、末広がりの八(鉢)の中、やっと一つの親子丼になれたわい!


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます