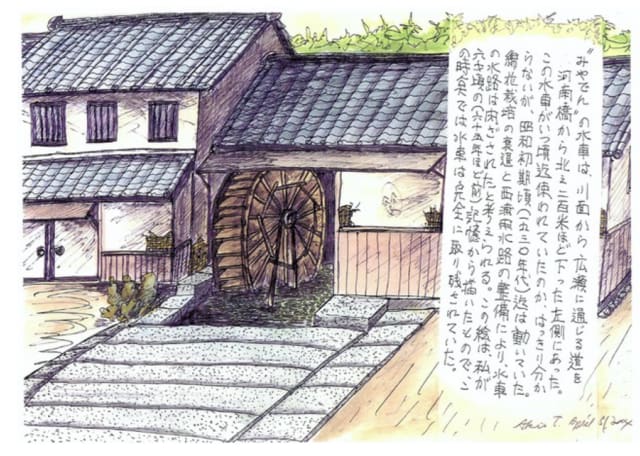冬休みに入ったばかりのある日のことだった。
野球をしようということになって、前の日から人数集めをして、朝の9時に墓の横にある田んぼに集合ということになっていた。
川面には公園はなく、広い遊び場は田んぼしかなかった。墓の横の田んぼは稲の株を短く刈っていたし、真四角で野球するにはもってこいだった。
友達ニ、三人で墓につづく細い道を歩いていると、焼き場の煙突から黄色い煙がうっすらと上がっている。
「誰か死なはったんやな。見に行こか」ということになった。

墓で走って転ぶと死ぬという言い伝えがあったので、ゆっくり歩いて阿弥陀堂に行き、裏の焼き場をのぞくと春やんと二人のオッチャンがいた。
オンボ(隠亡)という一晩中、火の番をする役目で、年寄りが交代でやっていた。
冷ましている途中だったのだろう。釜の火はほぼ消えていた。
喪主からの接待で弁当や茶菓子、酒も置いてあった。
酔っているのか春やんが怪しいロレツで、
「おあおお、や、野球か。ほっとけさんの供養や。好きなお菓子、持ってえ行き!」
「おおきに」と言ってニ、三個ずつポケットに入れると、
「遠慮せんでかまへえん! ほっとけさんの供養や! そこのお供えの岩おこしも持ってき!」
「おおきに」と言って、一つずつポケットに入れた。
隣にいたオッチャンが春やんに、
「ほんで、春やん。先前(さいぜん)のムコがアマにムスメのマゴのヨメがムコに行った、というのは、な、なんのこっちゃねん?」
「ちゃ、ちゃうがな! マゴのムスメがアマのムコのムコにヨメに行ったんやがな!」
「なるほどアマのムコにマゴのムコのヨメが行きよったんやな!」
「ちゃ、ちゃうがな・・・」
こないに酔うて大丈夫かいなと思ったが、骨上げの前に町総代と年行事が来て引き渡しをするとお役目御免ということだった。

ニ、三日後に我が家の餅つきがあった。いつものように春やんも手伝いにきていた。
御鏡用の餅をつき、小餅をつき、かき餅にするエビ、青のり、ヨモギをついた。
私と兄は河原で切てきたネコヤナギの枝に赤、青、緑の餅をひっつけて餅花を作っていた。
春やんが「その餅花はなんのために作るか知とるか?」とたずねてきた。
「飾りやろ!」と兄。
「キリコ(小粒のおかき)つくるためや!」と私。
「まあ、それもあるけど、木綿を作るワタの豊作を祈るためや!」
「ワタみたいどこの家もを作ってないやん!」
「江戸時代には自分らの着物を作るため。それとちょっとした金儲けに作ってたんや」
春やんが湯呑の酒を飲んだのを見て、焼き場のことを思い出してたずねた。
「こないだ焼き場でムコとかマゴとか言うてたけど、なんのこと?」
「ああ、あれかいな・・・」と言って春やんが話し出した。
③につづく