「CDが売れない時代」です。
業界の内外を問わずあちこちで聞く話ですよね。インサイダー情報によれば、オリコンTOPに入るような曲でもディスクの実売数が実は数百枚程度なんてザラだとか。
しかしこれは、業界の裏話をきくまでもなく、実感としてわかります。だってアナタ、先月CDを何枚買いました? いや、そもそもCDショップに行きました?
当方、大学という「18~25歳ぐらいの若者を定点観測できる職場」に身を置いてるので、折にふれ彼らの音楽との接し方をインタビューしているわけなのですが、ここ数年はっきりしているのは、彼らは基本的にCDを買わない。
いやCDどころか、iTunesなどのダウンロード販売で楽曲を買うことすら、ほとんどない。業界は「違法ダウンロードのせいで音楽が売れない」と言いますが、違法合法を問わずダウンロードなんて面倒くさい事は、そもそもしないのです。
もちろん美術大学という特殊な環境なので、これが若者の典型ではないとは思います。けれど逆に言えば、美大生という「どちらかと言えば同世代の中でもアートやクリエイティヴに関心の高い層」ですら、こういう状態なわけです。
とは言え「CDを買わない=音楽を聴かない」ではありません。
それはちょうど、「本が売れない=文字を読まない」ではないのと似ています。本は確かに売れなくなったかもしれない。けれど、メールやインターネット経由で、「文字」そのものを読む時間は、意識するとせざるにかかわらず、昔よりも実は膨大に増えているのではないでしょうか。
本という「編集されたテキスト」ではなく、携帯メールのメッセージのようなプライベートな文章や、twitterに流れてくるアフォリズム(格言、箴言)のような「編集以前のテキストの断片」を、今の僕たちは毎日膨大に読んでいる。
とりわけ、転送に転送を重ねて届いてくるSNS上のテキストに関して言えば、誰がそのテキストを書いたかより、断片としての「強度」の方が重要であったりします。
同じように、CDというパッケージに「編集された音楽」は聞かなくても、友だちがFacebookに貼ったリンクから飛んだYOU TUBEのミュージックビデオは観る。面白ければ、ブックマークや「お気に入り」や「いいね!」ボタンを押す。
YOU TUBEやニコニコ動画のリンクボタン経由で、知らなかった楽曲を次々に聴いて、徹夜してしまったりする。ここでも、誰がその作品を作ったかより、断片としての「強度」の方が重要だったりします。
メーカーが多額の費用をかけてプロモーションし、アーティストやアルバムという形に「編集されたパッケージ」ではなく、たまたま見つけた楽曲という「断片」としてであれば、音楽を聴く時間は、むしろどんどん増えている。そんな気がします。
付け加えれば、AKB48現象や韓流ブームのように、あざといほどパッケージングされた企画に自ら乗って楽しむ行為があれほど盛り上がるのも、日常の音楽行動がこのように極端に「断片化」されていることの、何か反動のように思えてなりません。
さて。しかし、そんな「断片化の時代」に、音楽の作り手はどのように対応すべきか? もっと言えば、どうやって音楽を売っていったら良いのか。そのヒントになりそうな本をいくつか、ご紹介します。
津田大大介&牧村憲一
未来型サバイバル音楽論
―USTREAM、twitterは何を変えたのか
中央公論社, 2010

いわゆるweb2.0時代の音楽ビジネスにいち早く言及した一冊。ネットビジネスに詳しい津田氏と、音楽プロデューサーとして制作現場を熟知した牧村氏の対談。
レーベル経営からコンサートの収支まで、実際の金銭の動きや著作権のシステムなどの「現実的」な話題が盛り沢山。図表も多くて読みやすいので、これまでの音楽ビジネスの仕組みをザックリと概観する入門書としても最適。
永田純
次世代ミュージシャンのためのセルフマネージメント・バイブル
自分を作る・売る・守る!
リットーミュージック, 2011

こちらは徹底的に「音楽家目線」の一冊。もしアナタがミュージシャンなら、自分という「ブランド」をどう構築し、どう販売していくべきか? そんな作戦の立て方をチャート式で簡潔かつ丁寧に教えてくれるテキストブックです。これから世に出たいと願っているミュージシャンは必読。
とりわけ、ミュージシャン本人は「なんとなく"お金まわりの仕事"って感じ?」程度にしか認識していなかったりする「マネージメント」の実体とその重要性について、細かく分類・考察してくれているのが貴重。
高野修平
音楽の明日を鳴らす
~ソーシャルメディアが灯す音楽ビジネスマーケティング新時代~
エムオンエンタテインメント, 2012
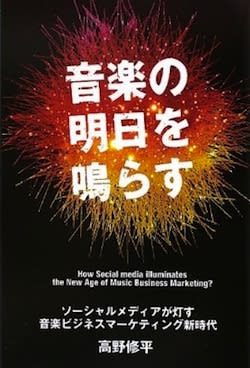
こちらはソーシャルメディアにポイントを絞った一冊。音楽行動の中でSNSが大きな位置を占めるようになった現在の状況は、既に後もどりできない「前提」。ではその中でどう音楽をマネタイズし、ビジネスを展開していく事ができるか?その可能性は?
…というビジネス書と思わせて、実はビジネスを超えた「共有」「共感」「共鳴」こそが重要であり、最終的には音楽への"愛"こそがミュージシャンとリスナーをつなぐ鍵であると訴える、後半の熱い文章が感動的。
デイヴィッド・ミーアマン・スコット&ブライアン・ハリガン
(糸井重里 監修, 渡辺由佳里 訳)
グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ
日経BP社, 2011

ソーシャル時代特有として語られがちな様々なアイディアを、60年代サイケデリック文化の立役者だった伝説のバンド「グレイトフル・デッド」が既に実践していた! という切り口がユニーク。
バンドというブランドの構築、ファンとの双方向的なコミュニケーション、観客というクラスタのコミュニティ化…今でも十分に通用する事例が満載で、音楽ビジネスの一つのケーススタディとして読むこともできる。
とはいえ本書もまた、ビジネスに必要なのは経済効率性ではなく「愛」であり、それが最終的には成功の秘密なのだと教えてくれます。(著者の2人も、もともとグレイトフル・デッドの熱狂的なファン)
他にも関連する書籍はいくつかありますが、とりあえず今日はここまで。
音楽を"売る"戦略とは。(2012年10月18日)
音楽配信と電子出版のマリアージュ(2012年02月07日)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます