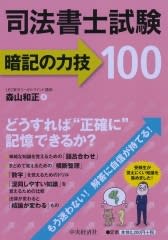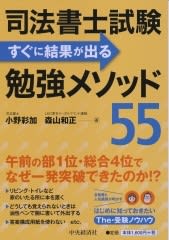今度の土曜日と日曜日の分析会に向けていろいろな角度から本試験問題を分析しています。
誰が見てもわかると思うのですが,
債権法改正を踏まえた出題がされていますね。
錯誤とか,敷金とか。
債権の分野でも,改正により内容変更がある知識が多数問われています。
また,根抵当権の問題(午前14問オ)では,物権の分野でほとんど唯一実質的内容が改正される条文が出題されています。
そこで,今日の午前中は,債権法改正の影響を調べていました。
とはいっても,改正論点は多岐にわたるので,
改正の影響があるのかないのか正直わからないところがあるなと思っていたのですが,
債権法改正後の新法の条文を見ながら作問しているという明らかな痕跡が残っている問題がありました。
午前17問イです。
イ 債権者が被代位権利を行使し,その事実を債務者が了知した場合であっても,当該債務者は,被代位権利について,自ら取り立てその他の処分をすることができる。
「×」となる選択肢です。誤りです。ただ,この選択肢,新法では○になります。
というか,条文そのままです。
その条文がこちら。
第423条の5前段 債権者が被代位権利を行使した場合であっても,債務者は,被代位権利について,自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
どうでしょうか。そのままですよね。
宅建の試験では,すでに,このような出題はされていて,
変更がある新法の条文をそのままコピペして誤りの選択肢としています。
もちろん,「偶然じゃないの」と考える人もいるでしょう。
新法の条文を見なくても,判例を見れば,このような選択肢を作れますから。
ただ,問題文を見てみると,「被代位権利」という言葉が出てますね。
これは,423条の5にも出ている言葉ですが,
実は,これ,新法で新しく作られた言葉なんです。
第423条 1項 債権者は,自己の債権を保全するため必要があるときは,債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし,債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は,この限りでない。
これは,明らかに,新法の条文を参考にして出題している痕跡だと思います。
そうじゃなければ,この言葉は出てきませんから。
実際,債権者代位権の過去問を調べてみましたが,この言葉は僕の探す限り,見つかりませんでした(違ったらごめんなさい)。
ということで,
出題者は,債権法改正後の新法の条文を見ながら問題文を作っていると思います。
なかなか,改正法を理解するのは,難しいですが,
少なくとも,教える側は,改正法でどのように変更されるのかを意識した上で講義にのぞむ必要がありそうです。
誰が見てもわかると思うのですが,
債権法改正を踏まえた出題がされていますね。
錯誤とか,敷金とか。
債権の分野でも,改正により内容変更がある知識が多数問われています。
また,根抵当権の問題(午前14問オ)では,物権の分野でほとんど唯一実質的内容が改正される条文が出題されています。
そこで,今日の午前中は,債権法改正の影響を調べていました。
とはいっても,改正論点は多岐にわたるので,
改正の影響があるのかないのか正直わからないところがあるなと思っていたのですが,
債権法改正後の新法の条文を見ながら作問しているという明らかな痕跡が残っている問題がありました。
午前17問イです。
イ 債権者が被代位権利を行使し,その事実を債務者が了知した場合であっても,当該債務者は,被代位権利について,自ら取り立てその他の処分をすることができる。
「×」となる選択肢です。誤りです。ただ,この選択肢,新法では○になります。
というか,条文そのままです。
その条文がこちら。
第423条の5前段 債権者が被代位権利を行使した場合であっても,債務者は,被代位権利について,自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
どうでしょうか。そのままですよね。
宅建の試験では,すでに,このような出題はされていて,
変更がある新法の条文をそのままコピペして誤りの選択肢としています。
もちろん,「偶然じゃないの」と考える人もいるでしょう。
新法の条文を見なくても,判例を見れば,このような選択肢を作れますから。
ただ,問題文を見てみると,「被代位権利」という言葉が出てますね。
これは,423条の5にも出ている言葉ですが,
実は,これ,新法で新しく作られた言葉なんです。
第423条 1項 債権者は,自己の債権を保全するため必要があるときは,債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし,債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は,この限りでない。
これは,明らかに,新法の条文を参考にして出題している痕跡だと思います。
そうじゃなければ,この言葉は出てきませんから。
実際,債権者代位権の過去問を調べてみましたが,この言葉は僕の探す限り,見つかりませんでした(違ったらごめんなさい)。
ということで,
出題者は,債権法改正後の新法の条文を見ながら問題文を作っていると思います。
なかなか,改正法を理解するのは,難しいですが,
少なくとも,教える側は,改正法でどのように変更されるのかを意識した上で講義にのぞむ必要がありそうです。