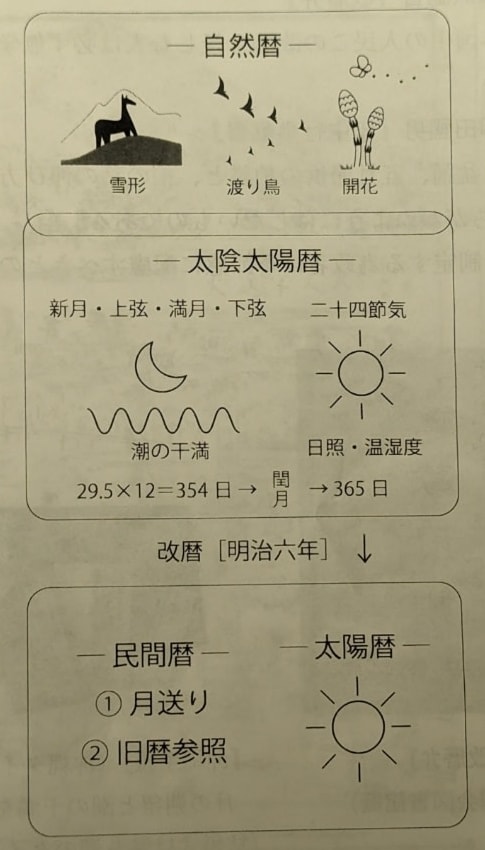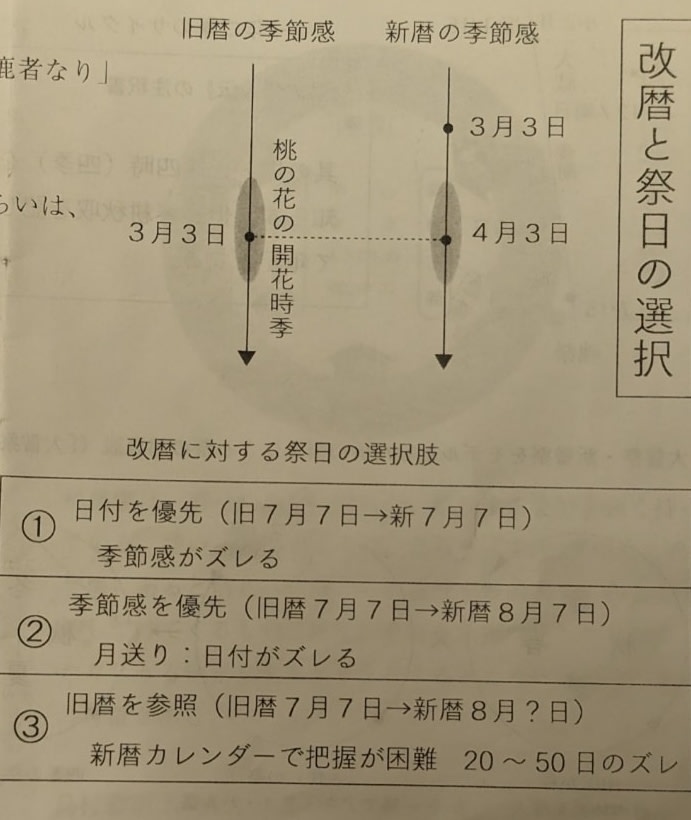😁 愛子さまが大学卒業後、日赤に就職される。と発表された今見ると、この写真の見え方も違ってくる。
愛子さまの日赤での働き方は、常勤なのか、非常勤なのか。
22日 速報は「非常勤」だった。
【速報】愛子さま卒業後は就職…皇室活動を本格化
1/22(月) 17:00配信 テレ東BIZ
天皇皇后両陛下の長女愛子さまが大学を卒業後、日赤=日本赤十字社に就職されることを宮内庁は明らかにしました。
愛子さまは現在学習院大学の4年生で3月に卒業予定です。日赤で非常勤の嘱託職員として働く予定で、具体的な仕事の内容は入社されてから決まります。
愛子さまは福祉活動に興味があり、日赤が、名誉総裁の皇后さまに業務説明をする際にも立ち合われたことがあります。有給の非常勤とされていて、卒業後は皇室活動を本格化させることになります。
同日、速報後に出たNHKの配信には、「非常勤」の文字が無かった。
愛子さま 大学卒業後は日本赤十字社で嘱託職員として勤務
2024年1月22日 19時21分 NHK
天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、大学卒業後のことし4月から日本赤十字社で嘱託職員として勤務されることが内定しました。
愛子さまは、学習院大学文学部日本語日本文学科の4年生で、ことし3月に卒業される見込みです。
その後の進路について、宮内庁は22日、愛子さまが4月1日から東京 港区に本社がある日本赤十字社で、嘱託職員として勤務されることが内定したと発表しました。
日本赤十字社は、全国各地に病院や血液センター、それに看護師などの養成施設を持つ認可法人で、全国に6万人余りの職員がいて、皇后さまが名誉総裁を務められています。
愛子さまは両陛下の活動や大学での授業などを通じて、日頃から福祉活動全般に関心を持っていて、去年10月には、両陛下とともに日本赤十字社を訪ねて、関東大震災での救護活動を振り返る企画展を鑑賞されていました。
こうした中で、日本赤十字社の活動に携わることを希望するようになったということで、皇族としての務めと両立するため嘱託職員として勤務されますが、具体的な仕事内容や勤務条件などは今後決まるということです。
愛子さまは側近を通じて「本年4月より日本赤十字社の嘱託職員として勤務することの内定をいただき、ありがたく思っております。日頃から関心を寄せている日赤の仕事に携われることをうれしく思うと同時に、身の引き締まる思いがいたします。これからもさまざまな学びを続け、一社会人としての自覚を持って仕事に励むことで、微力ではございますが、少しでも人々や社会のお役に立つことができればと考えております」とお気持ちを述べられました。
また両陛下も「愛子が日本赤十字社の嘱託職員として受け入れていただくことになったことを、ありがたく思います。この春から日赤の一員として仕事に従事することにより、多くの人のお役に立てるよう努力を続けるとともに、社会人の1人として成長していってくれることを願っています」と側近を通じてお気持ちを述べられました。
日本赤十字社社長「安心してご勤務いただけるよう 準備進める」
愛子さまがことし4月から嘱託職員として勤務されることが内定したことについて、日本赤十字社の清家篤社長は「愛子内親王殿下が赤十字の活動にご関心を抱かれ、大学ご卒業後の進路として日本赤十字社の活動に携わりたいとお考えいただきましたことは、日本赤十字社にとりましてありがたいことだと考えております。私どもといたしましても、内親王殿下が4月から安心してご勤務いただけるよう、しっかりと準備を進めてまいりたいと思います」というコメントを出しました。
😅 愛子さまも両陛下もNHKも「嘱託職員」を連呼。
😃 当初「愛子さまは非常勤嘱託員」と言い交わしていた報道もネットも次第に「嘱託職員」という言葉を使うようになった。
さて、愛子さまの日赤での働き方は「常勤」「非常勤」のどちらでしょうか。
※もっと詳しく解説してあるサイトもあるのですが、URLが取得できないので、URLが取得できたサイトを参考に上げます。
非常勤とは?一般的な定義からメリット・デメリットまで解説 - スタンバイplus+ (プラス)|仕事探しに新たな視点と選択肢をプラスする
転職活動中の人の中には、非常勤という働き方について具体的なイメージが湧いていない人も多いのではないでしょうか。非常勤の定義やメリット、向いている人を解説します。...
スタンバイplus+ (プラス)|仕事探しに新たな視点と選択肢をプラスする
<抜粋>
職種や企業によって解釈が異なることも
実のところ、労働基準法や労働契約法には、なにをもって常勤・非常勤とするかは規定されていません。基本的には、『1日8時間で週5日のフルタイム勤務』以外を非常勤とする場合が多いものの、企業によっては異なる解釈を取っているところもあります。
例えば、一部の国立大学の中では、定年まで働くことが前提の人を常勤、それ以外を非常勤と定義しています。
求人情報に常勤や非常勤と記載があっても、働き方は企業によって異なる可能性があるので、面接の場でしっかりと確認することが大切です。
正規・非正規は関係ない
常勤・非常勤は、しばしば正規・非正規雇用と同一視されますが、厳密には違います。正規や非正規とは雇用形態を表す言葉であり、就業形態を表す常勤・非常勤とは異なる性質の言葉です。
そのため非正規雇用のアルバイトでも、フルタイムで働いている場合は、常勤とみなされます。逆に正規雇用でも、時短勤務などをしている人は非常勤ということになります。
正規雇用か非正規雇用かを判別する場合は、常勤か非常勤かではなく、求人情報の雇用形態の部分をしっかりと確認しましょう。
😀 もう一つ、嘱託社員 についても見て見ましょう。
参考
<抜粋>
嘱託社員とは、一般的には、一定の期限を定めて雇用される非正規雇用の一つとされています。
つまり、契約形態は有期雇用契約の一つとなります。
ただし、嘱託社員は、法律による明確な定義がある言葉ではありません。そのため、いろいろなケースが考えられます。
- 契約社員
→ フルタイム勤務の契約であるケースが多い - 嘱託社員
→ 短時間勤務や非常勤勤務(週の出勤日が5日未満)であるケースもよくある
😐 つまり・・・
常勤、非常勤、嘱託、、これらには法律による明確な定義はないので、各企業の裁量に任せてある。
ということでしょうか。
愛子さまの「嘱託職員」は、清家氏の言葉など漏れ聞こえて来るところを総合するに、一般的に有期雇用契約とされる嘱託ですが愛子さまは無期雇用?
眞子さんは雇用期限が来ての再契約が宮内庁から発表されていました。
愛子さまの働きかたは週3日程度、一日の勤務時間は短時間。それを一般的にはフルタイム勤務ではない「非常勤」と解するのですが、、、
宮内庁HP >ご略歴>秋篠宮家 より
😊 佳子さまは、全日本ろうあ連盟 非常勤嘱託職員。
両陛下と愛子さまが「嘱託職員」を連呼し、報道に「非常勤」という言葉を使わせないのは、「あちらは非常勤嘱託職員、ウチは嘱託職員!」と格の違いを見せつけたい、、、つまり見栄?
何でも有りの雅子さま愛子さま、常勤非常勤は解釈次第。日赤社長清家氏の言葉は「いかようにもご相談に応じます」と言っている。