「実はお金があったから、科学も哲学も文学も民主主義も生まれたのです」
その2
非常に秀逸な対談。言い回しなどは違えど、ブログでも書いてきているようなことだ。
(ここから引用)
まさにここの部分が今後の肝になってくる。多様性とは、なんでもありの利便性を兼ね備えた都合の良い単語ではない。自由性と公共性という、個と全の在り方の問題だ。個は多様であるべきであるが、全は超個体であるべきなのだ。その方法論こそが、今、世界で問われている問題の本質であろう。
個別に触れたい内容がたくさんあるけど、まぁ気長にキーワードとしてブログに散りばめていこうと思う。
その2
非常に秀逸な対談。言い回しなどは違えど、ブログでも書いてきているようなことだ。
(ここから引用)
(ここまで引用)
2012年1月30日(月)1/6ページ
池上:前回、米国の経済危機の原因の1つに、金融機関の経営者たちの暴走が上げられました。しかも彼らはサラリーマンにして巨額の収入を得ている。なぜ、創業者でもない彼らが、べらぼうな高給を取ることができるようになったのか? そして、なぜ暴走してしまったのか? ここで大きな疑問が浮かびます。米国は、株主による経営のチェック、いわゆるコーポレートガバナンス(企業統治)が厳しいはずです。
岩井:そういうことになっています。
会社と経営者の関係を人形浄瑠璃で例えると・・・
池上:オリンパスの経営陣による損失隠し事件でも、「日本のコーポレートガバナンスはなっていない。もっと米国型の株主主導のガバナンスが必要だ」との声がわき上がりました。ところがその米国で、なぜ金融機関のサラリーマン経営者に対して、株主による経営陣へのチェックが機能しなかったのでしょうか?
岩井:会社と経営者の関係を、人形浄瑠璃における人形と浄瑠璃使いの関係に例えると、問題の構造が見えてきます。
人形浄瑠璃とは、ご存じのように、人形が人間のように、いや人間以上に人間的に演技することによって観客に感動を与えます。当然ですが、その舞台には人形を操る浄瑠璃使いが絶対に必要です。会社とは人形浄瑠璃の人形と同じです。なぜなら、単なる「法人」にすぎないからです。法律の上では人間ですが、実際は契約に署名する手も、従業員を管理する目も、裁判で訴える口もない。会社が経済という舞台でちゃんと演技するためには、それを人間のように動かす浄瑠璃使いが絶対に必要なのです。それが経営者なのです。
では、人形=会社と、浄瑠璃使い=経営者とが、契約を結ぶとしたら、どうなるでしょうか。浄瑠璃使いが人形の手を取って契約書を書くことになりますね。なにせ、浄瑠璃使いがいなければ、人形=法人は動きませんから。すると、悪意のある経営者ならば、自分に有利な契約書を書くに決まっています。
池上:いくら株主によるコーポレートガバナンスが形式的に厳しくても、結局、会社という「人形」を操るのは「経営者」。その経営者の一存で決められることの方がとても大きい、というわけですか。
岩井:ええ。もちろん、この構造自体が悪い、というわけではありません。
大半の経営者は、トップとしての良心にしたがって経営します。最初から悪いことをしようと思っている経営者は滅多にいません。そもそも、金融機関に限らず、会社はみんな社会的公器という側面を持っています。特に公開会社は、株式市場で多くの人からお金を集めており、より強い公共性を持っています。
池上:となると、公共性を持つ会社のトップとして、経営者も必然的に良心が求められるわけですね。でも、必ずしも経営者が常に良心に基づいて倫理的に行動するとは限りません。米国におけるエンロン事件、日本におけるオリンパス事件、いずれも経営者の背任行為が会社と市場に著しい損害を与えました。そんな「例外」的な事件も起き得るのではないですか?
岩井:はい。だからこそ、経営者の倫理的な行動は、なんと「忠実義務」として会社法で規定されています。経営者は、自分の利益は抑えて、会社の利益に忠実に経営するという義務を、法律で課せられているのです。ここが会社と法の関係の不思議な点です。法一般の論理で考えれば、倫理を法律として会社に課すのは実に奇妙な話ですから。そして、この忠実義務に違反すると「特別背任罪」として牢屋に入れられてしまいます。
池上:法律上でも、会社と経営者は「倫理的」であることを求められている――。つまり「倫理的」でなければ、罰せられることがあるわけですね。
なぜ、会社の倫理問題を法律で明記しなければならないのか
岩井:なぜ、会社の倫理問題を法律上で明記しなければいけないのか。これは前回詳しく説明した米国で商業銀行と投資銀行の兼業を禁じたグラス・スティーガル法が、なぜ必要だったのか、ということとも通底します。
池上:どういうことですか?
岩井:会社は人間ではありません。私たち自然人は、生まれながらにして人間として扱われる権利をもっていますが、会社の場合、法律で人間として扱うのは、社会に対して何らかの意味でプラスの貢献をすると期待されているからなのです。その意味で、先ほど述べたように、会社とは社会によって生かされている「公器」なのです。ですから、その経営を任されている経営者も、そもそも公共的な存在なのです。
そして、このように社会に生かされている会社が、実際に社会に貢献するために、経営者が存在しているわけですが、その行動を全面的に自由放任にしてしまうと、池上さんが疑問を提示したように、経営者に自分で自分に関する契約を書く誘惑を与えてしまいます。つまり、アダム・スミスのいうところの「見えざる手」=市場原理にだけ任せておけば万事うまく行くわけではない。
池上:会社と経営者は良心を持つべきであり、倫理的であるべきだが、会社の倫理や良心は法律である程度規制しないと、実現しきれない部分がある、ということですね。
岩井:市場原理だけでは、公共的存在であるべき経営者の暴走や銀行の浮利追求を止めることはできません。だからこそ、会社法やグラス・スティーガル法が必要なんです。会社とは資本主義の中核的な存在ですが、その会社が資本主義の中で活躍するためには、その会社の浄瑠璃使いとしての経営者に倫理性が不可欠だという逆説があるのです。これは、私が心優しいから言うのではありません。純粋に理論からの結論なのです。
ところが80年代以降、フリードマン流の市場万能主義がはびこると、経営者も銀行も自己の利益を徹底的に追求すればいい、見えざる手が最後はうまく調整してくれるから、という論調が支配的になってしまいました。だが、これは、間違えた理論にもとづいている。
池上:米国のサラリーマン経営者の給料高騰や、金融機関の暴走の裏には、極端な市場主義の横行があったわけですね。しかも、市場のメカニズムを利用した経営チェックシステムであるはずのコーポレートガバナンスが機能しなかったのは、なんとも皮肉です。
岩井:ストックオプション制度などの発達で、株主にチェックされるはずの経営者を始め幹部社員たちが、同時に株主にもなりました。株主となったサラリーマン経営者は、自己利益追求の一環として、株主の利益の最大化を目指す。チェックする人間とチェックされる人間が同一人物だったらどうなるか?
池上:たしかに、経営者であると同時に株主でもあるのでは、株主によるコーポレートガバナンスが絵に描いた餅になるのは自明の理ですね。
岩井:かくして自らも株主である経営者たちは、株主価値の最大化、と称しながら、自らの報酬をつり上げていきました。先ほどからお話ししているように、経営者たちの野放図な行動を後押しすることになった背景には、90年代から2000年代にかけて、市場万能論的経済学者が、次々とノーベル経済学賞を受賞したこともあります。理論は誤っているのに、です。
その権威に裏付けられて、経営者たちが、忠実義務という不可欠な倫理性を、すべて自己利益追求という経済論理で置き換えようとする事態が起きてしまいました。
池上:エンロンも、オリンパスも、ですね。
岩井:はい。ただ、オリンパスの経営者の場合は、自己利益というよりは、組織の利益を守るために、会社の公共性を犠牲にしたという面が強いという点で、エンロンとは異なっています。いずれにせよ、どんなところから忠実義務の無視が始まるのか。簡単です。経営者は、ただの株主よりも、はるかに情報を持っているわけです。
池上:当然ですね。内部にいるわけですから。でも、それは突き詰めると一種のインサイダー取引のような危うさが生じるのでは?
経営者が巨額の収入を得る仕組み
岩井:浄瑠璃使いが自分に有利な契約書を人形に書かせるわけですから、まさにインサイダーの構造です。池上さんが指摘したエンロンの経営者やワールドコムの経営者は、まさにこうしたインサイダー取引を実行したわけです。その結果、彼らは巨万の富を得ることになりました。
すると今度は米国中の会社社会で、雪崩を打ったように、経営者の報酬が高騰していきます。そうなると、莫大な報酬を用意しないと、優秀な経営者をスカウトできない。優秀な経営者が来ないと、自分の投資先の会社の経営が危うくなるかもしれない――。こうした悪循環の論理が米国の企業社会にできてしまいました。
池上:かくして米国では、創業者のみならずサラリーマン経営者までがお金持ちになってしまった、というわけですか。
岩井:でも、高収入が必ずしもよい経営成果を上げる訳ではない。エンロン事件、ワールドコム事件、そしてリーマンショックでの当該企業のトップのあり方を見れば一目瞭然です。市場万能主義が、必ずしもよい経営をもたらすとは限らない。それがまさに市場での結果で証明されてしまったのです。
私たちはお金とどうつき合っていけばいいのか
池上:ヨーロッパでは、知性によってお金をコントロールしようとして失敗した。米国では、自由に任せてお金を放っておいたら失敗した。では、今後私たちは、お金とどうやってつきあっていけばいいのか? そもそもお金ってなんなのか? 岩井先生の説をおうかがいしたいと思います。
岩井:お金の未来、の話ですね。その前に、まず、私がなぜお金について考えるようになったのか、それについて多少語ってもよろしいですか?
池上:岩井先生の「お金論」の源流ですね。ぜひお願いします。
岩井:私が経済を学び始めた一つの理由は、お金を儲けるためではなく(笑)、お金を本当に不思議なものだと思ったからでした。お金というのは、本来はタヌキが化かした葉っぱと何の変わりもありません。ただの紙切れや石ころや金属片を、あらゆる人間が「これはお金なんだ」と思ってくれるから、客観的にお金になる。「皆がお金だと思うからお金だ」という循環論法に支えられている存在なんですね。
1万円札は紙切れです。実際の物としての価値と、流通する価値とか完全に乖離している。なぜそういう乖離があるかというと、それは単に人々がお金だと思っているからで、しかもその価値は、ほかの人に渡すときに、実際に使うときに改めて確認されるものです。
池上:持っているだけでは価値は発現しない。銀行預金も似たようなものですね。
岩井:銀行預金というのは、銀行の借金です。貸しているのは我々預金者で、我々の持っている預金通帳は、銀行の借金証文の早見表。ただし、その貸したお金は、流動性が高い。ATMで簡単に現金化ができます。もちろんこれも循環論法に支えられている。すべての人が一斉に現金化しようとしたら、取り付け騒ぎに発展します。
でも、銀行を利用するあらゆる人、あらゆる預金者が、「銀行預金はいつでも現金に換えられる」と思っているから、銀行預金はいつでも現金化できるだけなのです。
近代がお金を産んだのではない、お金が近代を作ったんです
池上:お金とは、いわゆる「共同幻想」、なんでしょうか?
岩井:よく、お金は人々の共同幻想である、という物言いがされます。でも、私はその言い方には多少異論があります。というのは、お金の存在は、「幻想」というレベルではなく、もっともっと人間にとって本質的なものであり、しかも客観的な実体性をもっているからです。だから、お金の存在を前提とした現代社会ができあがっている。世の中にこんなに不思議なものはありません。唯一、お金と比較できるのは「言語」くらいでしょう。私は言語についても考えたかったのですが、その前にまずお金について考え始めたのです。
池上:「お金は、お金だから、お金なんだ」というある種のトートロジーにも聞こえてきます。お金というものは、いつ、どこで、どんなかたちで生まれたんでしょうか?
岩井:3年ほど前のことです。お金についての小さな国際会議がベルリンでありました。非常に学際的で、経済学者の他、社会学や歴史、哲学などの専門家が15人ほど集まって三日間ほど集中的に議論しました。そのなかで私がもっとも刺激を受けたのが、イギリスから招かれたギリシャ古典の大家であるリチャード・シーフォードさんの発表でした。
彼の研究の発端となった疑問は「なぜ我々は、古代ギリシャ人を近い存在に感じるのか。なぜ古代ギリシャは現代なのか」というものでした。具体的に言えば、ギリシャ神話の悲喜劇は、今読んでも、古さを感じさせず、現代の文芸作品と同じような感動を与えてくれる。そしてギリシャが紀元前の世紀に実現した民主主義の仕組みは、現代の民主主義の原型ですし、さらに、ギリシャにおいて、現代につながる哲学や科学が始めて生まれました。
池上:なるほど。古代ギリシャの市民社会文明は、まさに現代社会とそっくりだ。
岩井:ただ、古代ギリシャと現代社会には共通項が多いぞ、という話自体は聞き覚えがあるはずです。私が衝撃を受けた、というよりは歓喜したのは、シーフォードさんが出した解の方にありました。なぜギリシャと現代はそっくりなのか? 彼の結論は「ギリシャは世界史上で最初に、完全な貨幣経済を実現した社会だったから」というものでした。
池上:何と、お金の発明がギリシャ文明の前にまずあった、ということですか!
岩井:ギリシャでは紀元前7世紀ごろから、貨幣が流通するようになりました。ユーロ統合まで使われていたギリシャの通過単位ドラクマが既にこのとき誕生しています。貨幣はコインで、その素材は、金と銀の合金でした。ただし、当時はまだ金と銀の合金を安定して製造する技術はありませんでした。ですから、最初から金と銀が混ざっている合金を掘り出して、それを鋳造してコインにしていたのです。よって、金と銀の比率はコインによってバラバラでした。
つまり素材としての価値はコインごとにバラバラだったのです。金の含有量が多いコインも少ないコインもあった。でも、古代ギリシャでは、金の含有率というコインのものとしての価値を流通させるのではなく、どのコインも1ドラクマという抽象的な「お金」として流通させたのです。
池上:物としての価値ではなく、みんなが認めた貨幣単位をコインのかたちで流通させる。まさに貨幣経済の誕生がすでにこのときのギリシャであったわけですね。でも、それがなぜ現代文明とそっくりな古代ギリシャの文明と結びつくんでしょうか?
岩井:この世の中に、個々のモノや個々の人間を超えた、抽象的な価値や普遍的な法則が存在すること、しかも神様とは独立に存在しうること。これが近代文明の基本です。科学も哲学も政治も文学も、すべて抽象的な価値や普遍的な法則を共有することで、初めて成立する。まず、具体的なモノとしてはバラバラなお金を、抽象的で普遍的な価値として、社会全体が日常的に使い合うという貨幣経済の誕生こそは、まさに近代文明に通じる古代ギリシャ文明の礎なのだ、というのがシーフォードさんの説だったのです。
池上:抽象価値を共有する。それが文明である。そして初めてギリシャ人が共有した抽象価値こそは、「貨幣=お金」だった、というわけですか。目から鱗が落ちる話です。それにしても、ユーロ危機発祥の地ともいえるギリシャが、紀元前6世紀に「お金」を生んだことでと、現代文明の基礎が出来上がった、というのは何とも皮肉な話です。
岩井:まったくですね(笑)。古代ギリシャでは貨幣の流通をきっかけに、抽象思考の実践が行われました。イデア論を唱えたプラトンなどはまさにその申し子です。ギリシャ哲学は、お金から生まれたともいえます。それはまた、この世には個々の事物の雑多さを超えた、普遍的な法則性が存在するはずだという、科学的な世界観の出発点にもなった。
それだけではありません。金の含有率は違っても、1ドラクマコインはすべて1ドラクマの価値を持つ、同じである、平等である、という考え方は、個人の間の平等性を前提とする、まさに民主主義の誕生につながります。さらに、お金の流通が進むと、人間は共同体的な絆から切り離されます。つまり、「個人」となります。これまで共同体的な規制や慣習にもとづいて行動すればよかった個々の人間が、英雄でもないのに、自分で自分の運命を切り開いていかなければならなくなる。それは必然的に、悲劇や喜劇を生み出します。
かくして、お金が日常的に人々の間で流通し始めたことが、今につながる文明社会を生み出したのだ――。こうシーフォードさんは結論づけました。
私も仮説としては前から同様のことを考えていたのですが、経済学者が「お金が文明を産んだ」というとどうしてもポジショントークに聞こえてします。ところが、経済と一見全く縁のない古典学者が指摘した。そこに私は大変嬉しいショックを受けました。
池上:近代がお金を作ったのではなく、お金が近代を作ったのですね。誰かが発明したのか、自然発生的に生じたのかはわかりませんが、私たちの文明は、科学も哲学も文学も民主主義も、まず先にお金ありきである、と。これからも私たちは、お金とは縁を切れそうにありませんね。
電子マネーとは貨幣の究極の形態
岩井:インターネットが発達し、電子マネーが普及し、形をもった紙幣やコインがたとえ姿を消そうとも、単に電子情報が紙や金属に変わるだけです。「お金」は「皆がお金だと思うからお金である」というお金を支える構造は変わりません。電子マネーは、お金の持つ「価値の抽象性」をますます高めるだけで、お金そのものの性質は一切変化しないのです。
池上:インターネット上でデータだけのお金が流通する、ということは、商取引が光速化するわけですね。例えば、電子マネーが完全普及すると、お金そのものが消えてしまうような気がしますが。
岩井:ところが、逆なのです。電子マネーというのは、貨幣の究極の形態です。紙幣やコインというモノではなく、形を持たない抽象的な数字そのものがお金として流通するというのは、お金の究極の形態です。お金とは何かが、もっともはっきり見えて来たのです。
池上:となると、経済はますますグローバル化する。やり取りされるということは、光速に近い商取引が可能になるわけで、市場はグローバル化する。一方で、イタリアやギリシャの田舎住まいの人のように、たとえ職が見つからなくても生まれた土地を離れない、という人たちも依然としてたくさんいる。抽象的なお金の存在と、土地に張り付いて生きる人間の具体的な経済活動と、ますます乖離が進むような気もしますが。
岩井:結果的には、市場はグローバル化するのは間違いありません。それによって恩恵を受ける人は無数にいます。これは強調すべきです。私は反グローバル主義者ではありません。しかし、それはゆっくりやるべきだと思います。ユーロもそうだったわけですが。
地域通貨がお金の代わりになることはない
池上:お金という抽象価値と特定地域を結びつけようという試みとして、地域通貨があります。地域通貨についてはどうお考えですか?
岩井:特定の地域の活性化に、地域通貨が役に立つことはあります。でも地域通貨とは本来的な意味でのお金ではありません。それは、人々が自分の属する共同体全体に対してもつ義務感を共同体の中でやりとりするだけであって、どこでも普遍的な交換価値を持つ「お金」の代わりになることはありません。
さきほど、言語とお金は似ているといいましたが、一度、お金によって自由を知り,平等を知り、普遍的法則の存在を知った人間は、孤独ではありますが、原始共産制のような小さな共同体に戻ることは不可能です。資本主義の善し悪しは別として、私たちはグローバルな価値を持つお金と暮らしていくしかないのです。
池上:一方で、今回のお話では、行き過ぎた資本主義、自由放任主義、新自由経済だけでは、社会を幸福にすることは難しい、という現実があぶり出されました。
岩井:フリードマンの言うような、市場原理による理想社会を追い求めた結果です。市場の見えざる手に任せておけば、経済の効率性と安定性は両立し、最終的には必ず安定すると、フリードマン一派は信じてきました。多くの経営者や経済学者もそれに賛同した。しかし実際には、お金を自由に流通させればさせるほど、つまり、それによって経済の効率性を高めれば高めるほど、必然的にその経済の不安性が増してしまう。効率性を求めると不安定に陥る。私たちが生きている資本主義経済には,本質的にそういう「不都合な真実」がある、ということを再認識せざるを得なくなったのです。
池上:やはり「お金の番人」が必要だ、ということですね。
岩井:はい。基本的には市場経済に任せる。けれども、自由放任にすれば暴走してしまうので、どこかで規制を加え監視する。景気が悪くなったら、政府は財政出動をする。金融に関しては、市場原理を超越した中央銀行の公共性が、やはり欠かせない、と思います。
池上:中央銀行不要論を唱える人もいますね。
岩井:オーストリアの経済学者フリードリッヒ・ハイエクはその最たる存在です。
池上:彼もノーベル経済学賞の受賞者ですね。1974年に受賞しています。中央銀行はいらない、のですか?
岩井:私はハイエクの思想は尊敬してるのですが、その中央銀行不要論は、理論上、100%間違いだと考えています。先ほど述べたように、お金の流通価値は必然的にモノとしての価値を上回りますが、ハイエクはこれをお金を作ることのできる銀行の「独占利潤」とみなし、経済の効率性にとっても安定性にとってもマイナスだと考えたのです。だから、お金の発行も自由化せよと。
しかしながら、これも先ほど述べたように、お金とは本質的に不安定な存在です。その発行を自由放任にすると、安定するどころかますます不安定になる。だからその不安定性をコントロールするために、自己利益の追求をしない超越的な存在がなくてはなりません。それが、中央銀行です。
池上:中央銀行は、どこが発祥の地なのでしょうか。
岩井:スウェーデンです。17世紀の終わりに作られました。有名なのはイギリスの中央銀行、イングランド銀行ですね。これは1688年から89年にかけての名誉革命の際に、国王の資金を補助しようと、当時のロンドン商人が集まって作った、完全な民間銀行だったのです。それが徐々に巨大になって、イングランド銀行が何かをすると、イギリス経済全体が影響を受ける、という体験を通じて、何度も失敗を繰り返しながら、イギリス経済全体のための公共性を自覚した中央銀行として、徐々に変身を遂げたのです。
池上:日本の中央銀行である日本銀行は1800年代の後半にできましたが、米国ではずいぶんと遅れましたね。しかも米国では中央銀行という名前がない。連邦準備制度理事会(FRB)という何とも変な名前です。
岩井:米国の自由放任志向は、中央銀行のあり方にも端的に表れていますね。やはり自由に枷をはめるような行為に抵抗があったんです。建国以来、中央銀行をつくろうという動きはあったのですが、州単位の自治が強い米国では、地方分権論者たちが、中央銀行の成立を嫌ったために、なかなか中央銀行が生まれませんでした。20世紀になってようやく、それも非常に妥協的な形でFRBが、様々な州銀行の寄せ集めとして誕生しました。ウッドロー・ウィルソン大統領が、どさくさに紛れて作ったのです。1913年のことです。
幻に終わったケインズの中央銀行構想
池上:世界全体ではどうでしょう? これだけ市場のグローバル化が進み、お金がインターネットを通じて光速で世界中を飛び交う今こそ、本当の意味での世界中央銀行のような存在が必要な気もするのですが。いまの世界銀行やIMF(国際通貨基金)とも違う、まさに中央銀行的な組織が。
岩井:私もそう思います。実は第二次世界大戦末期、その後の戦勝国が集まり、日本やドイツの敗戦を前提としながら、新しい戦後の金融システムを考えていたことがあるのです。
池上:1944年のブレトン・ウッズ協定ですね。米国のドルを実質的な基軸通貨にするという。IMFもこれをきっかけに生まれました。
岩井:そうです。しかしこの体制が出来上がる前の議論で、ケインズは、バンコールという世界共通通貨を導入し、今のIMFよりも力の強い、それこそ世界の中央銀行としての役割を果たす銀行の設立することを提案していました。ところが米国がケインズの構想を潰してしまいました。
池上:もしこのときに、ケインズの中央銀行構想が潰れていなかったら――。
岩井:世界経済のかたちは大きく変わっていたでしょう。米国はこのとき大きなミスをしたと思います。米国のおかげで英国は戦勝国になったわけですから、英国人であるケインズの案が通らないのは仕方ないにしても、「もし」とは思います。とはいうものの、現実に世界中央銀行ができなかった。つまり、お金のグローバルな公共性を担保する組織が今は存在しません。これからどうやって実現していくかが世界の金融関係者と各国にとって大きな課題です。
池上:新しい世界中央銀行ができる可能性はあるんでしょうか?
岩井:難しいですね。IMFを強化するなど、アドホックな形で進めていくしかないでしょう。実際に、いろいろな動きはあります。しかし、米国はドルが基軸通貨であることの既得権益を守りたいし、中国のような新興国はおいしいどころどりをしたい。各国の利害の対立は避けられないでしょう。
池上:中国を始め新興国がおいしいところどりばかりをせず、世界経済に対して責任を持つようになるまでは、逆にいうと世界単位の中央銀行のようなものをつくるのは難しいでしょうね。
岩井:はい。というと、悲観的な話ばかりのように聞こえてしまいますが、私は、世界が再び社会主義に戻ることはない、と確信を持っていますし、自由とは人間にとってもっとも本質的だとも思っています。だからこそ資本主義が勝ち残ったのです。ただし、市場から公共性までをも排除して自由だけですべてを進めようとして、今日多くの失敗がおきました。社会主義とは別の形で、公共性を何とか担保する仕組みの実現に、世界中の知恵を使うべきだと思います。自由に対する最大の敵は、自由放任主義だと思っています。
池上:資本主義で失敗したから、社会主義にしよう、というのは確かにあり得ませんね。別の選択肢があるわけでもない。
岩井:後戻りもできないし、選択肢もないのです。だからこそ、資本主義を前提としつつ、公共性の担保は絶対に必要だというスタンスをとりながら、いろいろな方法論を寄せ集めていかざるを得ません。気の長い話ですが。でも、ギリシャの話でわかるように、人類はお金を生んだことで現在の文明を手に入れたのです。お金の問題から逃れることは、だからできないのです。
池上:お金の否定は、人類の文明の否定にもなってしまう。ならば逃げずに、最適解を常に探し続けるしかなさそうですね。どうもありがとうございました。
人々が自分の属する共同体全体に対してもつ義務感を共同体の中でやりとりする
一度、お金によって自由を知り,平等を知り、普遍的法則の存在を知った人間は、孤独ではありますが、原始共産制のような小さな共同体に戻ることは不可能
まさにここの部分が今後の肝になってくる。多様性とは、なんでもありの利便性を兼ね備えた都合の良い単語ではない。自由性と公共性という、個と全の在り方の問題だ。個は多様であるべきであるが、全は超個体であるべきなのだ。その方法論こそが、今、世界で問われている問題の本質であろう。
個別に触れたい内容がたくさんあるけど、まぁ気長にキーワードとしてブログに散りばめていこうと思う。










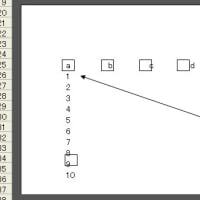
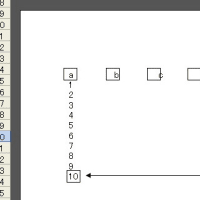
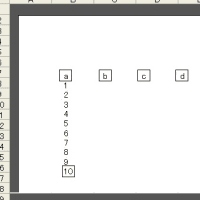





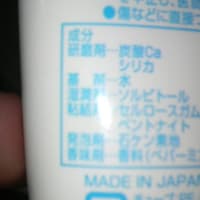
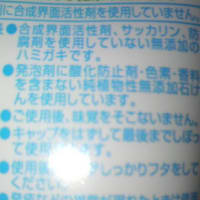
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます