「知性の失敗」のユーロ、「自由の失敗」のアメリカ
池上彰×岩井克人対談 「お金の正体その2」
その1
池上彰×岩井克人対談 「お金の正体その2」
その1
「知性の失敗」のユーロ、「自由の失敗」のアメリカ
池上彰×岩井克人対談 「お金の正体その2」
2012年1月16日(月)
2011年、欧州ではユーロ危機が起きましたが、その前に世界を襲った「お金の危機」、それはなんといっても、米国で2007年のサブプライムショック、2008年のリーマンショックです。
80年代末の東西冷戦の終結と相前後して、アメリカを中心とする金融市場は規制緩和をどんどん行い、実体経済を超える巨大なお金が動く世界ができあがりました。自由放任、新自由主義を標榜し、市場原理ですべてを解決しようというこの流れ、はたして正しかったのでしょうか?
ユーロ危機が「知性の失敗」だとすると、アメリカの金融危機はさしずめ「自由の失敗」である、と看破する岩井克人・東大名誉教授に、引き続き「お金の正体」に迫っていただきましょう。
池上:欧州の人たちが知性を結集して創り上げた共通通貨「ユーロ」。しかし、そのユーロによる経済圏が危機に直面しています。前回は、岩井先生に、なぜユーロ構想がうまくいかなかったのか、なぜ共通通貨ユーロが失敗したのか、その理由を説明いただきました。お金、そして経済という元々管理が難しいものを、「人間の知性」でコントロールしようとしたのが失敗の原因である、というお話でしたね。
岩井:はい。ユーロを通じて平和で安定的な欧州社会を創ろうという意気はよかった。もっと時間をかければ成功したかもしれません。ですが、あまりに拙速でした。
池上:このユーロの失敗を見て、意気軒昂なのが、経済の自由放任主義を標榜してきた英国の経済学者ミルトン・フリードマンを筆頭とする英米の自由主義経済派、リバタリアンの人たちですね。「ほら、今までさんざん我々が主張した通りではないか、お金や経済など、人がコントロールするものじゃない。市場に任せろ」という意見です。
岩井:たしかにユーロの失敗だけを眺めると、新自由主義の相対的勝利に見えます。けれども、私の意見は違います。今回の金融危機はむしろ「市場の見えざる手にすべて任せよう」というフリードマン派の思想の崩壊の始まりです。
ユーロ危機=「知性の失敗」をもたらしたのは新自由主義?
池上:自由放任主義もまた崩壊しようとしている。つまり、今、意気軒昂なフリードマン流の経済政策も間違っているということですか?
岩井:そうです。彼らはユーロ危機における共通通貨ユーロの失敗だけをつついているのですが、ユーロ危機の原因を辿っていくと、通貨統合のみならず、新自由主義経済の失敗が後ろに隠れていることがわかるからです。
池上:え、具体的にはどういうことでしょうか?
岩井:2011年、ユーロ危機の前に起きた世界を襲う「お金の危機」、それは2007年のサブプライムショックであり、2008年のリーマンショックでしたよね。
池上:あ、たしかにそうですね! 2008年9月15日にアメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻し、世界同時不況の引き金を引いたのでした。そのリーマンショックのさらに遠因を辿ると、米国の住宅バブル崩壊とセットとなった2007年のサブプライムローン問題がありました。
岩井:ユーロ危機の前に、まず新自由主義経済の総本山である米国で、自由主義経済の主役でもある金融市場が崩壊した。この事実を見逃してはなりません。その結果、米国に投資していた欧州の金融機関が経営危機に陥り、ユーロ各国も、その救済に乗り出さざるを得ませんでした。その巨大な余波が、ギリシャやイタリアの国家破綻の危機の遠因にもなっているわけです。つまり、ユーロ危機の一部は、アメリカの金融危機によってもたらされたのです。経済における「知性の失敗」が起きる以前に、「自由の失敗」がまずあった。
池上:たしかにおっしゃる通りです。では、新自由主義経済とはそもそも何だったのか。そこから振り返って、岩井先生に「新自由主義の失敗」について、ご説明願いましょう。
岩井:資本のグローバル化が本格的に始まったのは1980年代からですが、既に1970年代のニクソンショックによって、世界中の為替の大半が変動相場制へと移行し、資本の移動をうながしました。70年代末から80年代初頭にかけて登場した、米国のロナルド・レーガン政権、英国のマーガレット・サッチャー政権は、フリードマン思想に影響を受けて、さらなるグローバル化を進めたのです。
池上:レーガノミクスとサッチャリズム、ですね。「小さな政府」路線の走りです。日本では、小泉純一郎政権が明らかにこの路線を踏襲しようとしました。資本のグローバル化について、もう少し解説をしていただけますか?
ケインズはいらない。世界を市場で覆い尽くそう―?:フリードマンの野望
岩井:資本主義のグローバル化というのは、世界経済を「市場」で覆い尽くそうという考え方です。さらに言うと、ミルトン・フリードマンらが考えるグローバル化とは、かつてのアダム・スミスの思想の現実への応用です。
池上:神の見えざる手、ですね。「国富論」でアダム・スミスが唱えた市場の調整機能の比喩でした。
岩井:まさにそうです。市場の見えざる手に任せておければ、経済の効率性も、経済の安定性も共に実現するという考え方です。
さらに言うならば、市場に参加する個人も企業も、全体の公共の利益を考える必要がない。ひたすら自分の利益だけを追求していて良い。それでも、むしろその方が、市場がちゃんと機能すれば結果として全体の利益につながる。公益性も担保される、というわけです。
アダム・スミスは「公共善のためなどと触れ回る人間が善をなしたことなど聞いたことがない」といっています。だからこそ、その市場という仕組みを全世界に広げ、世界を市場で覆い尽くせば覆い尽くすほど、世界経済全体が、より効率的になり、安定性も増す――これがグローバル化の動きの背後にあった経済学の思想です。
池上:そして実際に、金融を筆頭に経済はどんどんグローバル化していった。けれども、岩井先生のおっしゃる通り世界経済が理想的な状態になっているかというと、疑問符がつきますね。
岩井:90年代末にはアジアの通貨危機、90年代末から2000年代初頭にはITバブル景気とその崩壊、そして先ほど池上さんがご指摘されたサブプライムショックが2007年にあって、2008年にはリーマンショックが起きました。
経済のグローバル化が進んできたこの30年というもの、世界全体の生産性は大いに向上しました。ですが、同時にバブルの勃興とその崩壊が繰り返されてきたのです。自由放任一辺倒な経済は、効率性は上がるけれど、ひどく不安定的だぞ、ということが明らかになり始めたのです。
けれども、リーマンショックが起きる直前まで、主流派の経済学者たちは「マクロ経済学は終わりである」という認識を示していました。
池上:それはつまりケインズ流の経済政策の意義が終わったと。
岩井:そうです。見えざる手に任せれば、景気の変動もなくなる。市場が世界を覆い尽くした今、マクロ経済学の出る幕はもはやないのという議論です。
マクロ経済学は、1929年の世界大恐慌を繰り返すまいという意思の下に生まれました。大恐慌は、見えざる手への信頼を失わせました。だからこそ、公共投資や金融政策などで有効需要をつくり、経済を安定させ、失業者が増えるのを防ごうとしたのです。イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズ氏が築いた、マクロ経済学のこの手法は、市場経済を補完するものとして、各国政府がその有効性を認めました。それから現在に至るまで、さまざまな形でケインズ流の経済政策は実行されてきました。
けれども、こうしたケインズ流の政策の役割はもう終ってしまった、というのが主流派の経済学者の論調です。その証拠として彼らが例に挙げるのは、1980年代から2000年初頭まで、日本を除けば先進国で景気循環が消えてしまったことです。
池上:好況と不況の大きな波がなくなった、ということですね。具体的には、誰が発言したのでしょうか?
岩井:「マクロ経済は終わった」と言ったのは、シカゴ大学のロバート・ルーカス教授です。2006年に亡くなったフリードマンの最大の後継者です。米国経済学会の会長に就いた人物で、2003年の米国経済学会の会長講演で、そう高らかに宣言しました。景気変動はコントロールできる。経済学に残された仕事は、ミクロの効率性を向上させて経済を成長させることだけである。すなわちそれは市場を拡大することなのだ――と。それからもう1人、アラン・グリーンスパン氏を忘れてはなりません。
池上:2006年まで、アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)の議長でしたね。
岩井:グリーンスパンは、こう説明しました。バブルが起きても何もするな。バブルを防ぐために行う規制や緊縮的金融政策は、金融市場の見えざる手を縛るだけで弊害が大きい。万一バブルが崩壊した時には、一時的に金利を下げれば良い。そうすれば再び景気が回復する道筋ができる、というものです。さらに、ベン・バーナンキ氏も2004年に「大安定」という題名の演説をしています。
池上:次はバーナンキですか。バーナンキはグリーンスパンの後のFRB議長です。アメリカの「お金の番人」のトップが2代続けて、マクロ経済の終わりと市場の万能性を主張した、というわけですか。
岩井:2004年当時、バーナンキはFRBの理事の一人で、また議長を引き継いでいませんでしたが、今述べたように、日本を除く先進国は「大安定」時代に入ったと自画自賛していました。ところがわずか3年後、その時には彼は議長になっていましたが、2007年夏に米国ではサブプライムショックが起こり、翌2008年9月にはリーマンショックに見舞われました。「大いなる安定」どころか、大恐慌以来の「大いなる不安定」の時代が到来したのです。なぜか? それこそフリードマン派が礼賛した、自由放任主義経済に本質的な矛盾があったからです。
池上:逆に言うと、サブプライムショックまでの間は、大いなる安定が先進国の間では続いていたわけですよね。なぜその安定が崩れ、突如として不安定化したのでしょうか?
岩井:大恐慌以降、米国経済がなぜ一定の安定性を保てたかを語るのに、グラス・スティーガル法を避けては通れないと思います。大恐慌を教訓に1933年に作られた法律です。
商業銀行は「預金」という名のお金をつくる仕事
池上:たしか1999年に事実上廃止されたといわれていますよね。
岩井:グラス・スティーガル法は、米国でいうところの商業銀行と投資銀行の間に垣根を設けました。日本でいうと、銀行と証券会社の事業を区別し、兼業できないようにするための法律だと思ってください。
池上:なぜ、米国は、商業銀行と投資銀行とを厳然と区分けしたんでしょうか?
岩井:「銀行=BANK」という名がどちらもついていますが、「お金」を作れるか作れないかで、両者の役割が根本的に異なるからです。
まず商業銀行は「お金」を作れます。預金者からお金を預かり、お金を借りたい人に融資を行う。それが商業銀行の主な仕事です。でも、単に借りたお金を貸すだけでは、どこからも利益が生まれません。実は、銀行預金とは、本来は銀行の「借金」ですが、同時にそれ自体が「お金」としての役割を果たしているのです。経済学でも「M1」と呼び、貨幣とみなします。だから、貸し出す利子よりも、はるかに安い利子しか払わなくて良く、商売が成り立つわけです。
一方の投資銀行の仕事は、商業銀行とは全く性質が異なります。投資銀行は、顧客のために様々な金融商品の売買を仲介し、手数料を稼ぐのが本来の業務です。
池上:商業銀行における預金が貨幣と同等の役割を果たす、というところをもう少し解説していただけますか?
岩井:何時でも預金者は「銀行預金」を現金化できる。つまり、預金は現金も同然なのです。これを「流動性」といいます。でも、この流動性とは、とても不思議なものです。
私が「預金をいつでも引き出せる」と思っているのは、ほとんどの預金者が引き出さないからです。でも、ほとんどの預金者が引き出さないのは、私と同じように、他のほとんどの預金者も「いつでも引き出せる」と思っていて引き出さないからにすぎません。ここにあるのは、自己循環論法なのです。もし預金者が、「預金には流動性がない」と考え始め、一斉に預金を引き出そうとすれば、取り付け騒ぎが起きてしまう。その時、実際に銀行預金の流動性は消え、預金は貨幣ではなくってしまいます。銀行の単なる借金、しかも銀行が返済できない借金になってしまう。
池上:みんながいつでも引き出せると思っているから、みんなが引き出さない。だから成り立っているのが「預金」というわけですね。なるほど、よく考えてみると不思議な仕組みです。
岩井:本当に不思議です。銀行はお金を貸す時、預金口座に「5000万円」と書き入れれば良いのです。預金者みんなが「銀行預金はお金だ」と思っている限り、私はその口座をお金として使うことができる。これが信用創造とよばれるお金の創造です、商業銀行には、民間企業でありながら、「お金をつくる」力があるのです。
もちろん、無限には作れません。預金者からの引き出しに備えて一定の現金をもつことを法律で定められています。また、預金者を安心させるため、国が預金者1人当たり1000万円までの保障を与えています。その代わりに、商業銀行は預金者の不信を招くような活動、特に投機的な活動に手を染めるのを防ぐために、さまざまな規制を課されているのです。「お金を作ることを許しているのだから、大人しく安定的な商売をしていなさい」ということですね。
リスクをとっていけない銀行と、リスクをとるのが仕事の銀行
池上:一方の投資銀行、日本で言う証券会社には、預金保障のような行政からの保護がない代わりに、業務上、かなりの自由がありますね。有り体にいえば、リスクをとってお金を儲けることができる――。
岩井:そうです。もちろん粉飾決算や利益相反は許されません。ですから、米国では証券取引委員会(SEC)、日本なら金融庁のような組織があって監督をしています。ですが投資銀行は、法に触れさえしなければ、自由な金融市場でリスクをとった投機で利益を上げることが可能です。
池上:さらに、お金持ちや機関投資家向けに、大きな投資を代わりに行うヘッジファンドも登場しました。
岩井:ヘッジファンドは、抜け道的な存在ですね。法人ではないので、さまざまな金融規制の対象外なのです。「仲良しクラブがお金を運用しているのだから自由にさせてあげる」という建前になっています。SECに帳簿を見せる必要もないので、競争相手に手の内をさらさなくて済むという旨みがある。投資銀行以上に高収益だけど、高リスクの投資ができる。
池上:現代の金融市場においては、預金というきわめて信用度の高いお金を扱う商業銀行と、証券投資のようなリスクが生じる投資銀行と、さらに少数の巨額な投資マネーを扱うリスクテイカーであるヘッジファンド、3種類の性格の異なる金融機関が存在する――。「お金を扱う」という意味では、いずれも金融機関ではありますが、リスクのとりかたが全く違いますね。
岩井:そうです。だから、グラス・スティーガル法があったのです。ところが、自由放任主義を推進する人たちは、規制の存在は「見えざる手」の動きを鈍くすると、撤廃を要求しました。特に預金業務が中心だった商業銀行が、収益の高い投資銀行業務をやりたくなったんですね。「そもそも金融とはリスクを売り買いする仕事である。自分のリスクは自分で管理できるので、政府や中央銀行の規制など必要ない」と主張したんです。そして、1999年のグラス・スティーガル法の実質的な廃止へと向かいます。
池上:商業銀行と投資銀行の境がなくなり、商業銀行が証券業務や投資業務に手を出すようになった、ということですね。
グラス・ティーガル法廃止がもたらしたツケ
岩井:すると今度は投資銀行が、収益の高い投資をやっているヘッジファンドをうらやましがって、ヘッジファンドまがいのハイリスクな投資に手を染めるようになりました。そしてついには、商業銀行までがハイリス投資を手掛けるようになりました。
池上:そもそも信用を売りにしていた商業銀行が、ハイリスクなお金の運用をする、というのはきわめて危ういですね。
岩井:ええ。自分で自分の投機のためのお金を作れるなんて、危うすぎます。結果として、本質的に不安定な存在である「お金」は、ますます不安定な存在になります。過剰な投資がバブルを生み、そしてその実態なきバブルが弾ける。90年代後半からの米国経済、そして世界経済はその繰り返しです。
池上:グラス・スティーガル法が骨抜きにされることによって、お金そのもののリスクが増大し、バブルを生んだというわけですか。となると、やはり一定の規制は必要だということになりますね。
岩井:米国では、FRBがその権限を与えられています。しかし、当時の議長であったグリーンスパン氏は、フリードマン以上の自由放任主義者でした。彼は、若い頃は米国の女性哲学者アイン・ランド氏の信奉者でもあった。ランドというのは、徹底的な自由主義者。オカルト的な自由主義者と言ってもいい。その影響下にあるグリーンスパン氏にとって、金融の徹底的な自由化は必然でした。
池上:FRBはバブルが崩壊しても、見えざる手で回復すると考えていたのですか。
岩井:そうです。1998年に、アメリカの有名ヘッジファンド・ロングタームキャピタルマネジメント(LTCM)が破綻したときにも、米国経済は非常に大きなショックを受けました。ですがこのショック時に、米国政府はこれといった財政政策をとらず、FRBによる金融緩和策で乗り切ろうとします。
池上:LTCMには確か、ノーベル経済学賞受賞者が2人、関わっていましたね。
岩井:その通りです。米国で最も信頼されていたヘッジファンドだったのですよ。米国は、その破綻ショックを低金利策でしのぎましたが、これが次のバブルを生んでしまう。それはIT革命による株高で、これは本物の成長だと突き進みました。ところが、結果としてはこちらもバブルだった。2001年にはITバブルが弾け、それも低金利策で何とか抑えるが、次のより大きなバブルが発生するというプロセスを繰り返してきたのです。
とうとう、サブプライムショックが起き、リーマンショックが起きて、今度こそは金融政策だけで乗り越えることができませんでした。つまり、自由放任思想が、米国発の今回の金融危機を作ったといえるのです。
池上:2012年の米国大統領選挙でも、ここは争点の1つになっていますね。再選を狙うバラク・オバマ大統領はリーマンショック以降、言ってみればケインズ型の規制を復活させようと、グリースパンの前にレーガン政権下でFRB議長を務めたポール・ボルカーを引っ張り出して、「ボルカー・ルール」という金融規制法強化案を発表しました。これに対して、共和党の各候補は、依然として徹底したフリードマン流を主張していますね。金融に対する2つの考え方が衝突しています。
岩井:私は今回の金融危機で、経済学の潮目が変わるだろうと思っていました。やはり自由放任主義だけではうまくいかないと、みんな気がつくだろうと思っていたのです。ところが主流派の彼らは、これまでの自由放任主義は「本当の自由放任主義ではない」と言い出しています。
池上:「本当の自由放任主義ではない」、ですか(笑)。つまり、もっともっと自由放任しろ、と主張しているわけですね。
本当の自由市場を―?もはや「教団」化したフリードマン派
岩井:そうです。これはたとえ話ですが、今の自由放任主義派の論の建て方は、新興宗教の教団に似ています。予言者を名乗る教祖が「今夜こそ宇宙が終わる」と予言し、信者を山の上に連れて行き、その瞬間を一緒に待ちます。しかし、一晩が過ぎても宇宙は終わりません。予言が外れたわけですから、その教団は崩壊しそうですが、そうはいきません。信者は「これまでの自分たちの努力が足らなかったのではないか。今まで以上に教祖様の教えに忠実に頑張らなくては」と考えるようになり、教団は一層団結します。
池上:フリードマン派は、もはや「教団」ですか(笑)。
岩井:極端なたとえですが、自由放任主義者の議論を見るとあながち冗談ではないですね。2008年に象徴的な出来事がありました。リーマンショックの後、フリードマンの弟子を自認している当時のブッシュ大統領もさすがに青くになり、明らかにケインズ的な色合いの濃い金融救済法を成立させようとしました。法案を議会に提出し、これはいったんつぶれ、2度目で成立しました。けれども、フリードマン派は、ブッシュ大統領の変節をなじりました。こういう形で金融機関の救済をしたことが「見えざる手」の動きを鈍くしたと。むしろ、つぶれるところはさっさとつぶしたほうがいい、というのが彼らの考えでした。
池上:リーマンショックで破綻しそうになった企業に米国の保険会社AIGがありますね。当初は救済を断っていたFRBが、方針を転換して支援の手を差し伸べたことで倒産は免れました。フリードマン派はAIGも救済すべきではなかったと考えているのでしょうか?
岩井:もちろんです。でも、AIGの救済は正解でした。今から思うと、リーマン・ブラザーズも救済すべきでした。
破綻した金融機関の救済には必ず批判があります。日本では、1995年に住宅金融専門会社(住専)の巨額の損失が明らかになったときがそうでした。大いにマスコミにも責任があると思うのですが、「バブルの後押しをした住専はけしからん、国民の税金で救済するとは何事だ」という世論が巻き起こりました。
でも、あのとき早急に救済措置をとっていれば7千億円近い巨額の公的資金を使う必要はありませんでした。ところが、批判の声が大きいために救済が遅れ、結果として、日本経済は大きなダメージを受け、救済額も膨らんでしまった。
お金を扱う金融機関が破綻しそうになったとき、市場原理に完全に任せてしまうと、後になって悪くなる可能性が非常に高い。だが、金融機関の救済は必ず批判されます。「今までさんざん甘い汁を吸ってきた連中を、なぜ国民の血税を使って救済しなければならないんだ」という声が上がる。こうした世間の批判を受けた上で救済策を実行するのは、本当に勇気がいります。
池上:金融機関の救済には、論理と感情が交錯しますね。金融機関がつぶれてしまうと経済に大きな悪影響を与える、という論理は誰でもわかる。でも、その一方で、「なぜあんな高給取りの連中を税金で助けなければいけないんだ、自業自得じゃないか」、という心情が生まれるのも分かる。
だから、「国は、放漫経営でつぶれかかった金融機関は助けてやるくせに、こつこつやってきたうちの工場の経営危機には手を差し伸べてくれないじゃないか」という声が出てくる。日本だけではなく、今回、ウォール街でデモがあった米国でも似たような話がありますね。
岩井:猛烈にありました。ただ米国に限っては、「金融機関を助けるな」という主張には一理あります。「自分たちこそリスク管理の専門家だから、グラス・スティーガル法をなくしてくれ」言っていたのは、ほかならぬ金融機関自身なのですから。ハーバード大学のマイケル・サンデル教授の白熱教室でもこのテーマは取り上げられていたと記憶していますが、調子が良いときは経営者に巨額なボーナスを支払い、悪くなったときに国家援助を受けるのには、倫理的な問題があります。その意味でもグラス・スティーガル法の実質廃止などの金融の規制緩和は、本当に大きな禍根を遺しました。
池上:オバマ政権は金融の規制を元に戻そうとしています。できるでしょうか。
岩井:完全には戻らないでしょう。1980年代からその骨抜き化が試みられていたグラス・スティーガル法が実質的な廃止になったのは90年代後半の、民主党のビル・クリントン政権のときです。実は、レーガン政権以降で米国の世論全体が最も共和党的なものに傾いたのが、クリントン政権の時代だったのです。
池上:国民の平等を訴える民主主義よりも、勝者劣敗の自由主義を求める声が大きかったんですね。
岩井:はい。そんな時代に民主党が政権を維持するためにはどうすればいいのか。共和党的になることです。クリントンの売りの一つは、「ビジネスマンと話ができる唯一の民主党議員」というものでしたから、金融規制緩和の方向へ進みやすかった。ただ私はクリントン政権は全体的には良かったと思っています。
池上:当時、民主党の中でも反対した人たちもいましたね。
岩井:たくさんいました。お金は人間に自由をあたえると同時に、一種の公共性を持っています。なにせお金は天下の回りものです。人々が、それをお金として受け取ってくれると信じて流通させるから、お金なのです。いわば社会全体の信用に支えられている。お金の自由促進的な面だけを重視して、お金の公共性をないがしろにしたりすると、いざ経済危機になったとき、お金の仕組みを立て直すのがとても難しくなります。
自明の話ではありますが、例えば景気が上向き、バブルのような状態であるときに、お金の公共性を保つために金融引き締めを実施する必要があると人々に理解してもらうのは、とても難しいことなのです。
池上:「お金の公共性」という側面がとても重要ですね。そう考えると、「お金を扱う金融機関も公共的な存在」ということになります。となると、やはり野放図な経営は許されないでしょうし、その意味では公共的な規制が必要ですよね。銀行のような金融機関の公共性については、どうお考えですか?
岩井:預金を扱う商業銀行は、本来は非常に保守的な機関であり、がちがちの規制に縛られたお堅い職業と見なされてきました。お金を作ることのできという公共性を持っているからです。先ほども申し上げたように、お金とは皆がお金だと思わなければお金でなくなるという、本質的にはとても不安定なものです。だから、取り扱う銀行は安定な存在でなければならない――はずだった。
池上:お金という不安定なものを扱っているからこそ、銀行は信用される存在でなければいけない。それなりの給料を得て、それなりの服装をし、それなりの建物で仕事をするのも、信用の裏返しであると。
岩井:そう、給料が高いのには理由があります。ある程度高くしておかないと、意識もまた高くならない。何か間違いを起こすと多額の給料を失うという恐れが、銀行員に規律ある行動させるインセンティブになる、というわけですね。
池上:そういう説明は、子どもの頃からずいぶんと受けてきました。ですが、どうも最近の銀行の不祥事などを見ていると、高給に担保された銀行の倫理感というのも怪しくなってきたようにも思えます。
なぜ、変わってしまったのでしょう?よく、東西冷戦という構造が消えたことが、原因だと言われますね。ロケットやミサイルを研究していた人たちが職を失い、金融工学へと入り込んできたと。あるいは「東=共産主義」という仮想敵がいなくなったことで、資本主義自由経済の中で、油断をして勝手なことをやり出したと。
ニューディール政策と第二次世界大戦が所得格差を縮めた
岩井:自由放任主義を押し進め小さな政府を志向したレーガン政権時代、89年のベルリンの壁崩壊が起き、91年のソ連崩壊で、共産主義の敗北が決定的なものとなりました。これにより、市場の見えざる手を全面的に信奉するフリードマン的な経済思想が完全勝利したとみられていました。
ソ連型の計画経済は、西側の資本主義経済に敗れた。間違いのない事実です。社会主義が再び世界を席巻することもないでしょう。社会主義は、人間の自由を抑圧するシステムであること明らかになったからです。市場は自由を促します。ただし、その結果として、市場主義万能論が短絡的に進みすぎたという側面を見逃してはなりません。
本来、信用をベースに作り上げなければならない金融機関の仕事まで、市場に全部任せてしまおうという流れが90年代に生まれ、米国の株式市場は未曾有の成長を遂げました。株式投資さえしていればお金持ちになれた時代です。しかしその後の市場の動きを見れば、1997年のアジア通貨危機、2001年のITバブル崩壊、2007年のサブプライムショックという具合に、市場の歯車は狂って行き、ついには2008年のリーマンショックへ行き着くわけです。
池上:2011年ウォール街で起きた「Occupy Wall Street」の抗議運動を見る限り、自由放任主義もいよいよ曲がり角に来たのか、という印象を強く持ちます。
岩井:冒頭でも少し述べましたが、こうした自由放任主義の流れを一貫して創ってきたのが、米国と英国の2国です。米国にいるトーマス・ピケッティ氏と、エマニュエル・サエズ氏というフランス系の経済学者、それから日本では一橋大学の森口千晶氏などが、世界中の所得分配の歴史的な推移について優れた研究をしています。
第2次世界大戦前、1929年の大恐慌の頃まで、世界のどこの先進国でも凄まじい所得格差が存在していました。高額所得者トップの1%の所得が、国民全体の所得の約2割を占めていたのです。米国も、フランスも、ドイツも、そして日本もほぼ同じ割合でした。中でも一番格差が大きかったのがスウェーデンです。なんと高額所得者1%の所得が国全体の35%を占めていたのです。
池上:今や、福祉国家として名高いスウェーデンが所得格差の大きい国だったとは。もしかすると当時の反省が、今のスウェーデンを生んだのでしょうか?
岩井:ご明察の通りです。国民の所得格差の酷さを改善すべく、スウェーデンは社会福祉国家の道を歩み、ケインズ以前にケインズ政策を行っていました。
大恐慌時代は、ソ連が急速に台頭して、共産主義に対する憧れや希望が西側諸国にも浸透し始めた時代でもあるのです。ハリウッド俳優にも共産主義信奉者がいたりしました。共産主義に対抗する意味もあり、米国ではニューディール政策を打ち出して社会福祉を厚くし、所得の不平等を抑えようとしたわけです。
池上:大恐慌以降の米国は、行き過ぎた市場主義を反省してケインズ経済学的な財政政策をとったわけですね。その後、第2次世界大戦へ突入しますが、戦争は経済にどんな影響を与えたのですか?
岩井:戦争で国は一丸となります。お金の面で言えば、累進課税が増えます。若者が血を流して戦っている。銃後の人間はお金を出せというわけです。米国の歴史を見ても、所得税はもともと戦争のときにだけ出現する税制でした。
余談ですが、イラク戦争のとき、戦地で米国の若者が血を流しているのに、ブッシュ政権は減税しました。米国の歴史において初めてのことで、大変に不名誉なことです。米国の凋落の一つの原因はここにあると思っています。
池上:第2次世界大戦のときは増税により税収入が増えたわけですね。
岩井:はい。累進課税ですからお金持ちがたくさん税を納め、結果として国民の貧富の差は小さくなりました。第2次世界大戦が終わったとき、米国も日本も、戦前は20%ほどあったトップ1%の占める所得の比率が、8%くらいにまで落ちました。スウェーデンに至っては5~6%です。戦争により不平等度が低くなったわけです。最近日本は多少は上がっていますが、9%止まりです。フランスも同じくらい。ドイツは少し高いく、スウェーデンは7%ほどです。
ところがこのトレンドから、1980年代に2国だけが抜け出します。米国と英国です。両国は自由放任主義を追い求めました。その結果、戦前のように、高額所得者トップ1%が、国全体の所得の2割を保有する不平等な所得構成に戻ってしまいました。
池上:高額所得者トップ1%とは、どういった人たちなんでしょう? やはり株で儲けた人たちですか?
米国の新しい金持ち、実はサラリーマンだった?
岩井:そう思うでしょう? ところが違うんです。戦前の上位1%は、ほとんどが資本家でした。配当所得や利子所得が中心でした。ところが、最近の上位1%に増えているのは、まず自営業者です。その内訳は、スポーツ選手など特殊な技能を持っている人、それからベンチャービジネスを成功させた人。特筆すべきは、昔と違って、給与所得者が多いことです。彼らが上位1%に入ってくるということは、「会社とは何か」という問題に関係します。会社が儲かったとき、株主以上にサラリー所得者が儲けているということが数字で明らかになったのです。
池上:「金融市場で儲けている人たちが米国の金持ち」というイメージがありましたが、むしろ「サラリーマンの一部にお金持ちが増えた」というのが実態なんですね。たしかに、年収数十億や数百億円単位の企業経営者が、米国にはごろごろしています。おそらく彼らがここでいうところの給与所得者ですね。ただのサラリーマンではなく。
岩井:ええ。経営者が、ストックオプションやボーナスなどを使って自身の給与を増やしていったわけです。かつて米国では、経営者と新入社員の平社員の給与比率は1対30から1対40だったのが、どんどん経営者側の給与のみが増えていき、今やその比率は1対500とか1対1000になった。だから高額所得者に占める給与所得が増えている。といっても従業員全体ではなく、一部の経営者が巨額の富を得るようになった。それが今の米国の金持ち事情なのです。
池上:しかし、米国といえば、株主による経営陣へのコーポレートガバナンスが強いはず。創業者やオーナーならばまだしも、サラリーマン経営者が自分の給与を野放図に上げることに、株主の厳しいチェックが入るような気もしますが。なぜ、米国では、経営者の給与が高騰したのでしょうか?
岩井:確かに不思議に思われるかもしれませんね。
池上:次回は、そのからくりと、「お金の未来」について、岩井先生にご説明いただきましょう。










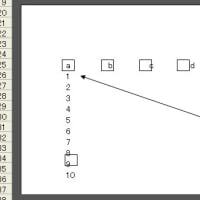
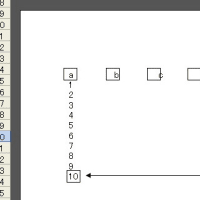
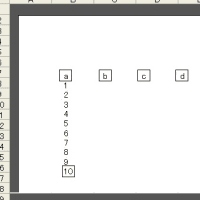





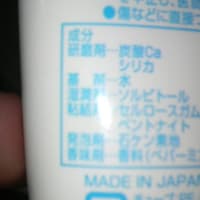
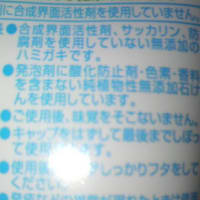
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます