心とはどこにあるのか?ってことはあまり考えたことがない。なので真っ先に思い浮かぶのは、脳細胞じゃないの?っていう当たり障りのない発想。しかし心の在処を解明した人はいないはず(と思う。いたらごめんなさい。)
細胞一つ一つに意思や考える力がある、というと、少しだけ行き過ぎているように感じる。でもそういう考え方も存在するそうだ。少しアレンジというか、俺なりに考えてみようかなと思った。
細胞に、意思や考える力は無い。おっといきなり全否定(笑)全否定の代わりに、細胞は前意識の基を生み出すとする。
どんなときに前意識の基は生まれるか?ある特定のスイッチが押された時だ。(※以下妄言)
いやさ、細胞に意思や思考力があるとすると、60兆もの細胞で競合してしまうと思うのだよね。たったの70億でさえ戦争が起きるというのに。競合しないということは、意思や思考力を持たないのだろう。けど全否定してしまうと文章が続かない(苦笑)「細胞には意思や思考力はない。以上。」で終わってしまう。
なので、意思や思考力の前段階(前意識)に近いものがあると考えてみる。それを前意識の更なる前意識、うーんそうだなぁ、ここでは原意識とでもしておこうか。
妄言なので、間違っても 原意識 - Wikipedia こんな高尚(?笑)なことを言いたいわけではないので悪しからず。似たことを書くかもしれないけどね。
外部からの刺激(無意識)→【何か】(原意識。この記事で解き明かされる。)→原意識の集合(前意識)→更なる集合(意識つまり心)
細胞の一つ一つは、ある特定のスイッチによって原意識を生み出す。細胞の一つ一つは60兆もの異なる原意識のパターンを持っている。この60兆の原意識の組み合わせが前意識を生み出す。そして前意識同士が個々の環境や経験によって有機的に結びつき、心が生み出される。つまり心のパターンは無限に近いが有限だと言える。ん、無限でいいか。
有限か無限かはここでは問題ではないので割愛。
この、原意識を生み出すスイッチは何だろう?外部からの刺激と言っても、その刺激を細胞一つ一つが受信出来ることを仮定しなければならないので、例えば誰かの言葉に刺激を受けて、というような意味での刺激の定義は使えない。もっと細胞一つ一つが受信する事の出来る刺激が必要だ。
ここで俺は、「放射線(広義の意味での放射線ね)」を持ち出す。結論を書くと、心は放射線によって、生み出されるのだ。放射線が無いと心は存在しない。なので低線量の放射線が健康にとってプラスであるという研究は、放射線が心の健全性を保つのに必須であるということがブラックボックスに入っているから、そう見えるのだ。
あ、そうそう。この記事は数十年後の未来にノーベル賞を受賞する研究の原型なので、決して口外しないように。歴史が変わっちゃうので。あと石投げないでね。
なぜLNTにDDREFを付け足す必要があったのか?急に放射線の話になる。
放射線量の、ある任意の閾値以下では、人体に直線的な影響があると言い切れないからだそうだ。ようは苦肉の策。
で、ある任意の閾値以下で人体に直線的な確定的影響があると言い切れない理由(苦肉の策が生まれた理由)が、前述した原意識による影響だ。
細胞は一つだけでは上手く機能を発揮できない。細胞は細胞同士の連携があって最大限の機能性を発揮する。実はこの細胞レベルで連携を欲することが、細胞の集合体である生命が一個体だけで生きていくのを困難にさせていたりする。(原意識の欲求)
細胞同士は原意識のやり取りをしている。やり取りをしている物質があるのかどうかは未解明(単に思い浮かばない。破綻しました。いっそ電子でいいかとか投げやり)。
気を取り直して。
そのやり取りが集合して前意識が生まれる。前意識は主に臓器でより活発に生み出される(なぜかは後述のカリウムの項)。原意識のやり取りをしない細胞は、他の細胞から死んだものと見なされる。孤立した細胞は生きていけず、結果として本当に死んでしまう。(死にやすくなる)高等生物のほとんどが一個体だけで生きていけないのは、この細胞の原意識への欲求の影響であることは書いた。
臓器で前意識がより活発にうみだされる理由。
人体の中には放射性カリウムが常に存在している。太古の昔からそうである。カリウムは人体の中で偏って存在する。特に臓器に多く集まる。臓器は他の細胞よりも多くの放射線を浴び、多くの原意識を生み出す。原意識の細胞同士のやり取りの多さが、臓器の頑丈な理由だ。
また先に述べた、臓器が意思を持ったり思考をするということの説明も、臓器が多くの原意識を生み出し原意識が前意識へと成長しやすいことから、成立する。そして前意識は、情報処理能力の長けた脳細胞によって、意識(心)へと成長する。結果的に心は脳であるとも言える。しかし脳だけが心を作っているわけではない、ということ。
放射線により細胞が原意識を生み出す(心へと成長し、健全な肉体となる)と同時に、放射線により細胞の遺伝子は欠損を被る。なので、ある任意の閾値よりも多い量の放射線を浴びると、直線的な確定的影響がでる。それ以下の場合は、直線的な影響を緩和したり、場合によっては増幅するような動きを見せる。
緩和するのは前述までの仮説で説明がつくはず。増幅する場合はどうだろう?これは個体差である以前に、60兆の組み合わせによる選択であると言えるだろう。放射線がどの細胞を貫くか?によって、生み出される原意識も異なる。細胞同士の原意識の連携も。競合することもある。ようは運次第。
それとも、原意識を一度生み出した細胞は、ある一定期間の休息が必要なのかも知れない。例えば数分間、とか。高線量になると、60兆に対する抽選回数が増えるため、同じ細胞の休息期間内に再度放射線を浴びる可能性が高くなる。しかし低線量であっても抽選はしているので、同様に同じ細胞の休息期間内に再度放射線を浴びる可能性はある。(この辺はこじつけ記事の中の更なるこじつけ)
抽選回数が低い(つまり当選確率が低い)ことによる、確率の収束性の悪さが、閾値以下のブレが大きく見える理由だ。増幅するように見えるのもこのブレのせい。実は高線量でもブレが同じように存在し、ブレ幅も同程度なのだが、人体に対する影響という面からは、高線量でのブレはさほど問題にならない。低線量だと、ブレ幅のほうが人体に対する確定的影響に比較して大きくなる、ということ。
太陽光を浴びると健康に良い(とされる。太陽光がビタミンの働きにryというのは別視点だけど、心の健康のために、ある一定の太陽光(放射線)は重要なのだ。あくまでこの記事的な観点では)。しかし浴びすぎると皮膚ガンになる。これと同じことが放射線の細胞への影響にも言える。
やっぱりこれは除外しよう(笑)。だって他の要素が多すぎて太陽の放射線の影響を測るのは困難だから。ってようなことを、5月の原子放射線の影響に関する国連科学委員会の総会で言ってたような。困難だから、科学としてではなく、社会が望むものとして研究していきます、みたいなことを言ってた気が。別の話だけど。
さて、そろそろ飛んでくる石の量が半端じゃなくなってきてイテテなのでおしまいにしよう。妄言って楽しいなぁ。
放射線を一生浴びずに生きていくことは不可能なはず。だって食べ物には放射性カリウムが。他にも空気中だって水だって。だから、実験室レベルですら実現は困難だ。つまり反証不可能ということで、この記事は疑似科学といわれるようなもの。というか、未来のノーベル賞なので勘弁してね。あ、石が。
でも、もしこの仮説に何か可能性があるとしたら、低線量被曝の問題を人類が解決することは出来ない可能性だろうね。出来るかもしれないけど。
数十年経過しないと影響が確認出来ないかもしれない、ということは、今はまだ考えるには時期尚早、ということかもしれない。
低線量被曝についていがみ合うとか、皮膚ガンを恐れすぎて太陽光を全く浴びないとか、そんな愚かなことはしなさんな、ってことだろうか。
いや議論するのはいいと思うし、研究するのも大事。科学が何を示していくのか、数十年、固唾をのんで見守ろうじゃありませんか、っていうのは無責任だろうか。
結果が残酷であっても、その残酷さがあるからこそ残酷ではない世界を夢見て進歩する。科学が万能ではないからこそ、科学は進歩する。
進歩しなくていい、ということは、逆説的に科学が正しいと言うに等しい。確定的な未来を周囲に押し付けてしまえば、それは科学を批判するよりも低俗な、科学の盲信と同等だろう。
低線量被曝は、高線量被曝よりも危険かもしれないよ?という投げ掛けは、それを裏付ける何らかが見えてきてから語っても遅くはない。何も失わずに未来は生まれない。何も失わないということは、今この瞬間でフリーズするということだ。それのどこが未来のためなのだろう。失うことこそが未来のためである。
暴論乙(笑)
細胞一つ一つに意思や考える力がある、というと、少しだけ行き過ぎているように感じる。でもそういう考え方も存在するそうだ。少しアレンジというか、俺なりに考えてみようかなと思った。
細胞に、意思や考える力は無い。おっといきなり全否定(笑)全否定の代わりに、細胞は前意識の基を生み出すとする。
どんなときに前意識の基は生まれるか?ある特定のスイッチが押された時だ。(※以下妄言)
いやさ、細胞に意思や思考力があるとすると、60兆もの細胞で競合してしまうと思うのだよね。たったの70億でさえ戦争が起きるというのに。競合しないということは、意思や思考力を持たないのだろう。けど全否定してしまうと文章が続かない(苦笑)「細胞には意思や思考力はない。以上。」で終わってしまう。
なので、意思や思考力の前段階(前意識)に近いものがあると考えてみる。それを前意識の更なる前意識、うーんそうだなぁ、ここでは原意識とでもしておこうか。
妄言なので、間違っても 原意識 - Wikipedia こんな高尚(?笑)なことを言いたいわけではないので悪しからず。似たことを書くかもしれないけどね。
外部からの刺激(無意識)→【何か】(原意識。この記事で解き明かされる。)→原意識の集合(前意識)→更なる集合(意識つまり心)
細胞の一つ一つは、ある特定のスイッチによって原意識を生み出す。細胞の一つ一つは60兆もの異なる原意識のパターンを持っている。この60兆の原意識の組み合わせが前意識を生み出す。そして前意識同士が個々の環境や経験によって有機的に結びつき、心が生み出される。つまり心のパターンは無限に近いが有限だと言える。ん、無限でいいか。
有限か無限かはここでは問題ではないので割愛。
この、原意識を生み出すスイッチは何だろう?外部からの刺激と言っても、その刺激を細胞一つ一つが受信出来ることを仮定しなければならないので、例えば誰かの言葉に刺激を受けて、というような意味での刺激の定義は使えない。もっと細胞一つ一つが受信する事の出来る刺激が必要だ。
ここで俺は、「放射線(広義の意味での放射線ね)」を持ち出す。結論を書くと、心は放射線によって、生み出されるのだ。放射線が無いと心は存在しない。なので低線量の放射線が健康にとってプラスであるという研究は、放射線が心の健全性を保つのに必須であるということがブラックボックスに入っているから、そう見えるのだ。
あ、そうそう。この記事は数十年後の未来にノーベル賞を受賞する研究の原型なので、決して口外しないように。歴史が変わっちゃうので。あと石投げないでね。
なぜLNTにDDREFを付け足す必要があったのか?急に放射線の話になる。
放射線量の、ある任意の閾値以下では、人体に直線的な影響があると言い切れないからだそうだ。ようは苦肉の策。
で、ある任意の閾値以下で人体に直線的な確定的影響があると言い切れない理由(苦肉の策が生まれた理由)が、前述した原意識による影響だ。
細胞は一つだけでは上手く機能を発揮できない。細胞は細胞同士の連携があって最大限の機能性を発揮する。実はこの細胞レベルで連携を欲することが、細胞の集合体である生命が一個体だけで生きていくのを困難にさせていたりする。(原意識の欲求)
細胞同士は原意識のやり取りをしている。やり取りをしている物質があるのかどうかは未解明(単に思い浮かばない。破綻しました。いっそ電子でいいかとか投げやり)。
気を取り直して。
そのやり取りが集合して前意識が生まれる。前意識は主に臓器でより活発に生み出される(なぜかは後述のカリウムの項)。原意識のやり取りをしない細胞は、他の細胞から死んだものと見なされる。孤立した細胞は生きていけず、結果として本当に死んでしまう。(死にやすくなる)高等生物のほとんどが一個体だけで生きていけないのは、この細胞の原意識への欲求の影響であることは書いた。
臓器で前意識がより活発にうみだされる理由。
人体の中には放射性カリウムが常に存在している。太古の昔からそうである。カリウムは人体の中で偏って存在する。特に臓器に多く集まる。臓器は他の細胞よりも多くの放射線を浴び、多くの原意識を生み出す。原意識の細胞同士のやり取りの多さが、臓器の頑丈な理由だ。
また先に述べた、臓器が意思を持ったり思考をするということの説明も、臓器が多くの原意識を生み出し原意識が前意識へと成長しやすいことから、成立する。そして前意識は、情報処理能力の長けた脳細胞によって、意識(心)へと成長する。結果的に心は脳であるとも言える。しかし脳だけが心を作っているわけではない、ということ。
放射線により細胞が原意識を生み出す(心へと成長し、健全な肉体となる)と同時に、放射線により細胞の遺伝子は欠損を被る。なので、ある任意の閾値よりも多い量の放射線を浴びると、直線的な確定的影響がでる。それ以下の場合は、直線的な影響を緩和したり、場合によっては増幅するような動きを見せる。
緩和するのは前述までの仮説で説明がつくはず。増幅する場合はどうだろう?これは個体差である以前に、60兆の組み合わせによる選択であると言えるだろう。放射線がどの細胞を貫くか?によって、生み出される原意識も異なる。細胞同士の原意識の連携も。競合することもある。ようは運次第。
それとも、原意識を一度生み出した細胞は、ある一定期間の休息が必要なのかも知れない。例えば数分間、とか。高線量になると、60兆に対する抽選回数が増えるため、同じ細胞の休息期間内に再度放射線を浴びる可能性が高くなる。しかし低線量であっても抽選はしているので、同様に同じ細胞の休息期間内に再度放射線を浴びる可能性はある。(この辺はこじつけ記事の中の更なるこじつけ)
抽選回数が低い(つまり当選確率が低い)ことによる、確率の収束性の悪さが、閾値以下のブレが大きく見える理由だ。増幅するように見えるのもこのブレのせい。実は高線量でもブレが同じように存在し、ブレ幅も同程度なのだが、人体に対する影響という面からは、高線量でのブレはさほど問題にならない。低線量だと、ブレ幅のほうが人体に対する確定的影響に比較して大きくなる、ということ。
太陽光を浴びると健康に良い(とされる。太陽光がビタミンの働きにryというのは別視点だけど、心の健康のために、ある一定の太陽光(放射線)は重要なのだ。あくまでこの記事的な観点では)。しかし浴びすぎると皮膚ガンになる。これと同じことが放射線の細胞への影響にも言える。
やっぱりこれは除外しよう(笑)。だって他の要素が多すぎて太陽の放射線の影響を測るのは困難だから。ってようなことを、5月の原子放射線の影響に関する国連科学委員会の総会で言ってたような。困難だから、科学としてではなく、社会が望むものとして研究していきます、みたいなことを言ってた気が。別の話だけど。
さて、そろそろ飛んでくる石の量が半端じゃなくなってきてイテテなのでおしまいにしよう。妄言って楽しいなぁ。
放射線を一生浴びずに生きていくことは不可能なはず。だって食べ物には放射性カリウムが。他にも空気中だって水だって。だから、実験室レベルですら実現は困難だ。つまり反証不可能ということで、この記事は疑似科学といわれるようなもの。というか、未来のノーベル賞なので勘弁してね。あ、石が。
でも、もしこの仮説に何か可能性があるとしたら、低線量被曝の問題を人類が解決することは出来ない可能性だろうね。出来るかもしれないけど。
数十年経過しないと影響が確認出来ないかもしれない、ということは、今はまだ考えるには時期尚早、ということかもしれない。
低線量被曝についていがみ合うとか、皮膚ガンを恐れすぎて太陽光を全く浴びないとか、そんな愚かなことはしなさんな、ってことだろうか。
いや議論するのはいいと思うし、研究するのも大事。科学が何を示していくのか、数十年、固唾をのんで見守ろうじゃありませんか、っていうのは無責任だろうか。
結果が残酷であっても、その残酷さがあるからこそ残酷ではない世界を夢見て進歩する。科学が万能ではないからこそ、科学は進歩する。
進歩しなくていい、ということは、逆説的に科学が正しいと言うに等しい。確定的な未来を周囲に押し付けてしまえば、それは科学を批判するよりも低俗な、科学の盲信と同等だろう。
低線量被曝は、高線量被曝よりも危険かもしれないよ?という投げ掛けは、それを裏付ける何らかが見えてきてから語っても遅くはない。何も失わずに未来は生まれない。何も失わないということは、今この瞬間でフリーズするということだ。それのどこが未来のためなのだろう。失うことこそが未来のためである。
暴論乙(笑)










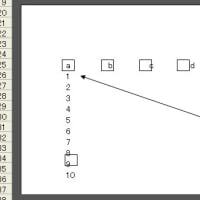
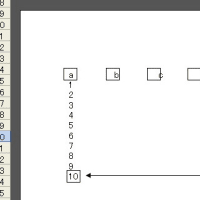
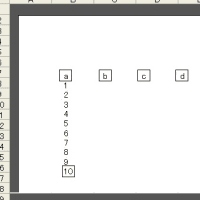





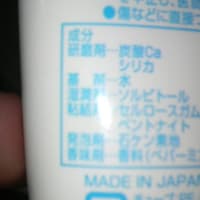
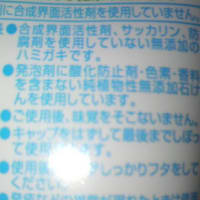
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます