福島の食事、1日4ベクレル 被曝、国基準の40分の1
食事からは検出されなかったとして。
それは「今の」「食事」でしょうに。「食事」を強調したいなら当時の食事、「今」を強調したいなら今現時点での被曝量。切り分け大事。
そして毎度のように、出だしとはあらぬ方向へと記事は進む。(笑)
セシウムが他の物質と結びつくと、除染の研究でも言われているように容易には剥がれなくなる。生体にも取り込まれにくくなるとも言われている。※ただし現時点ではそのように見えるだけ、ということには注意が必要だ。
こうした観点から見るなら、今の状況だと食事よりも吸引してしまうホコリの方が問題ではないかと思う。肺胞は人体のホットスポットとなりえないだろうか。
大人はまぁどうでも良いっちゃ良いのかもしれないけど、とりわけ喫煙者は繊毛が弱っており、肺胞までホコリを吸い込みやすくなっている。喫煙者は放射性物質によるガン率が高まるという研究もある。
もう一点注意したいのは一部で囁かれていることだ。放射線の影響は、生殖器などの再生する細胞よりも再生しない細胞に、より顕著な影響が出てくるのではないかという意見だ。言われてみればごもっとも。長く放射線を浴びるのなら、再生しない(しにくい)細胞のほうがダメージは蓄積されると言える。心筋・脳など。
しかしそれはまた別の機会があったら紹介したい。
要旨は、食事についても注意出来る限りの注意は必要だと思うけど、食事にばかり目を奪われている時にこそ思わぬ落とし穴がありそうな気もする、という事だ。
例えば前記事で書きそびれたんだけど、津波を恐れるあまり高層ビルに人が押し寄せ、圧死するような本末転倒がある可能性などだ。
ここからがあらぬ方向の本線。ころころ話題が変わるのはご容赦ください。
「夫婦の在り方と教育」
食事への注意点を夫婦で共有することでさえ難しい場合もある。少なくとも我が家ではそうだ。ネットでも夫婦の合意が形成されないという意見を目にする事はままある。
我が家でのことだけど、ようやく多少なりとも食事への注意を共有し始めた頃に、今度は空気にも気をつけろと言われれば、意識の低い方にしてみれば「いつまでこんなことを気にしなきゃならないの?」と思うのは無理もない。
意識の高低の問題なだけで、優劣の問題ではない。念のため。
俺のスタンスは、子供は二人の子供であるのだから、どちらかの言い分だけ押し通す形で合意形成を無視してはならない、というものだ。子供は象徴なだけで、本質は、夫婦の合意形成を無視してはならないということだ。もちろん夫婦というのも、本質的には人間と読み替えて差し支えない。
夫婦で出来る限りのことをやり、それで子供に何らかの悪影響が将来に渡って出たとしても、夫婦で出来る限りの事をしたのであれば、それを子供に伝え理解して頂けることを願うしか無い。
逆に、夫婦でガッチリ手を繋げず先に進んでしまったのであれば、どれだけ体裁なり現実なりが想定された悪レベルよりも良い環境に向かったとしても、夫婦は失敗だ。誤解を恐れずに言えば、合意形成に失敗した関係の先に、本質的な成功があるようには、俺は思えないのだ。
もちろん夫婦が成功した先では必ず子供が成功する、とも思ってはいないが。
教育に焦点を当てた場合のもっと本質な部分では、夫婦がどうだとかよりも、きちんと子供を向いているかどうかがより重要だろう。親(大人)がきちんと子供の方を向いていれば、子供は身体が病気になろうと心健やかに育つと信じたい。見た目健康だけど心が病むような時代に生きる親の一人としては、そちらのほうが魅力的に感じてしまう。
子供の方を向いている側の意見を重視したいのが本音だ。しかし、どちらがより子供の方を向いているかなんて誰にも分からない。「子供の方を向く」と一言で言っても、その方法は様々あり、それこそ価値観の数だけあるのだから比較のしようがない。
世間一般的な、標準的価値観はもちろんあるのだろうけど、世間とか標準とかがあまり好きではない俺には、オーソドックスな子供との接し方とやらに意味を見出しにくい。子供の核となる部分がどこにあるのか注意して見ていれば、表層的な接し方の問題はあまり重要ではないと考えている。
少し型破りな俺の教育論。それを指して「お前は子供の事を考えていない」と評されるのは悲しいものだ。自分への評価が悲しいのではなく、俺自身も当てはまることではあるが、人間は自分が正しいと思う生き物なんだな、という部分がひどく悲しいのだ。
そんな思い込みの塊が子供を育て、人類は歴史を積み上げていく。子供を、親や大人のエゴに巻き込むな。教育と、エゴの境目は難しい。
「教育と国益」
子供を思う教育と、子供が願う教育。今の教育界を取り巻く問題は、ちょっとずれている気がする。国益を担う子供の将来を考え教育することも大事だけど、前にも書いたように、グローバル化が進む以上競争率は10倍20倍になるのだ。
そこを勝ち上がる事が出来た日本の子供は、国のために働くだろうか。それはないような気がする。企業のために働くのではなかろうか。
企業は多国籍化・ひいては無国籍化すると思われる。少なくとも今の方向性はそうと言える。国よりも企業が今より更に強くなることだろう。企業をどのように誘致するかが国の大問題となる。
企業は国に尽くすのではなく、自社が生き延びる事が出来る環境に尽くす。日本で優れた教育を受けた子供が、必ずしも日本に利益をもたらすとは限らない。それをどのようにもたらしてくれるようにするかが教育の要でもある。
仮にだが、愛国的な教育を是とする子供が勝ち残っていくことはあるだろうか。ちょっと考え難いんだよね。今の日本の企業を取り巻く環境は、国益よりも自社の利益ではないのかな。
その環境の上で国益に結びつけるためには、ソフトを読み込むハード作りが肝要だろうと思われる。ハードよりもソフトの時代なのだが、ソフトはより優れたハードを求めるのだ。
小さな社益を求める日本国の教育が、国民一人一人が国のために戦える国に勝てるのか。真の国益とは何か、ということから考えなければならないのではないだろうか。
そこはちょっと棚上げ。
要するに、わざわざ教育を施すよりも、優れた教育を施された人材が来てくれた方が遥かにコストは低くて済むと思うのだ。経済的国益を考えるのであれば、ソフトを開発するよりも、ソフトを買って自社ブランド化する方が早いし安い。ソフトを作ることに満足感を見出すか、ソフトを誘致出来るハードを作ることに満足感を見出すかで、かなり違うのだと思う。
世界に開けた教育環境で、優れたソフトをどんどん誘致する外国との戦いを、日本の子供だけに押し付ける議論は如何なものだろう。日本という檻に閉じ込めたまま、野生の中で生き抜いてきた大量の敵に立ち向かえるとは到底思えない。
当然だがそれと教員制度等々改革は別の話だとは思っている。
世界で戦える人材の育成が出来る教育だけを進めてもならないのだ。たった一人のジョブズを育てるために、数百万人の子供を犠牲にすることは、経済的な観点の教育としては正しくても、子供にとっては過酷だ。秀才は教育で生まれるが、天才は教育では生まれない。天才は数から生まれる。子供の数の多い国が圧倒的有利である。
日本は逆に、圧倒的不利な状況にあえて挑もうとしている。日本は別の方法で戦わなければならない。圧倒的に天才発生率が違うということを認識しなければならない。
もう一度書くけど、それと教員制度等々の改革問題は別なんだけどね。
「そんな教育論、どうでもいいってね!」
俺はどちらかと言うと、食事に気をつけよう、とか、将来に備えよう、とか考えてしまう方なんだけど、その考えが現実に即しているかどうかという部分では非常に弱い。紆余曲折を経て今の考え方にひとまず落ち着いているものの、どこかに非現実的な夢物語を描いてもいる。
ただ、それよりも何よりも、俺たち夫婦の歴史の中では、夫婦になるということの意味を最重要課題として掲げざるを得なかった。1年先5年先10年先の俺予測が当たったとする。それが現段階において理解されなかったとして、その上で行動が遅れ自滅したとしても、俺は父親として責任を持ちたい。
昔、水と油は常にかき混ぜていないと混ざらない、と言われた。価値観の違う人間同士とはそういうものなのだと思う。世の多くの問題は、「お前が混ぜろよ」「いやお前こそ混ぜろよ」という醜い争いから生まれている。
挙句に、「俺が混ぜるよ」って言う人が現れると、「いやお前じゃダメだ」とか言い出す。自分でやらないくせに足も引っ張る。まるで俺のようだ。あふん。
何にしても、意識の高い方が一生懸命かき混ぜるしか無い。
そしてもっと言えば、相手の方がより意識は高いのだと認識し、相手のかき混ぜ方・懐に飛び込むことだ。相手にかき混ぜて頂き、相手と混ざらせて頂き、相手の内側から、千年の計すらも持ち問いかけ続けるしかない。
親が出来うる子への教育は、子の中で生き、問いかけ続けることだ。しかし、国が出来うる子への教育は全く異質なのだ。一本筋を通さなければならないケースは多いのだけど、今の世界の状況は、我々が経済に甘んじ、企業が利益重視となり、国が企業を助け、国が破綻しようとしている状況である。我々が経済に甘んじたことが、全ての事の始まりなのだ。
それに対して、俺は知らねーよ、と白を切っているのが、人として正しいのか考える必要があるのだと思うのでありました。ちゃんちゃん。
食事からは検出されなかったとして。
それは「今の」「食事」でしょうに。「食事」を強調したいなら当時の食事、「今」を強調したいなら今現時点での被曝量。切り分け大事。
そして毎度のように、出だしとはあらぬ方向へと記事は進む。(笑)
セシウムが他の物質と結びつくと、除染の研究でも言われているように容易には剥がれなくなる。生体にも取り込まれにくくなるとも言われている。※ただし現時点ではそのように見えるだけ、ということには注意が必要だ。
こうした観点から見るなら、今の状況だと食事よりも吸引してしまうホコリの方が問題ではないかと思う。肺胞は人体のホットスポットとなりえないだろうか。
大人はまぁどうでも良いっちゃ良いのかもしれないけど、とりわけ喫煙者は繊毛が弱っており、肺胞までホコリを吸い込みやすくなっている。喫煙者は放射性物質によるガン率が高まるという研究もある。
もう一点注意したいのは一部で囁かれていることだ。放射線の影響は、生殖器などの再生する細胞よりも再生しない細胞に、より顕著な影響が出てくるのではないかという意見だ。言われてみればごもっとも。長く放射線を浴びるのなら、再生しない(しにくい)細胞のほうがダメージは蓄積されると言える。心筋・脳など。
しかしそれはまた別の機会があったら紹介したい。
要旨は、食事についても注意出来る限りの注意は必要だと思うけど、食事にばかり目を奪われている時にこそ思わぬ落とし穴がありそうな気もする、という事だ。
例えば前記事で書きそびれたんだけど、津波を恐れるあまり高層ビルに人が押し寄せ、圧死するような本末転倒がある可能性などだ。
ここからがあらぬ方向の本線。ころころ話題が変わるのはご容赦ください。
「夫婦の在り方と教育」
食事への注意点を夫婦で共有することでさえ難しい場合もある。少なくとも我が家ではそうだ。ネットでも夫婦の合意が形成されないという意見を目にする事はままある。
我が家でのことだけど、ようやく多少なりとも食事への注意を共有し始めた頃に、今度は空気にも気をつけろと言われれば、意識の低い方にしてみれば「いつまでこんなことを気にしなきゃならないの?」と思うのは無理もない。
意識の高低の問題なだけで、優劣の問題ではない。念のため。
俺のスタンスは、子供は二人の子供であるのだから、どちらかの言い分だけ押し通す形で合意形成を無視してはならない、というものだ。子供は象徴なだけで、本質は、夫婦の合意形成を無視してはならないということだ。もちろん夫婦というのも、本質的には人間と読み替えて差し支えない。
夫婦で出来る限りのことをやり、それで子供に何らかの悪影響が将来に渡って出たとしても、夫婦で出来る限りの事をしたのであれば、それを子供に伝え理解して頂けることを願うしか無い。
逆に、夫婦でガッチリ手を繋げず先に進んでしまったのであれば、どれだけ体裁なり現実なりが想定された悪レベルよりも良い環境に向かったとしても、夫婦は失敗だ。誤解を恐れずに言えば、合意形成に失敗した関係の先に、本質的な成功があるようには、俺は思えないのだ。
もちろん夫婦が成功した先では必ず子供が成功する、とも思ってはいないが。
教育に焦点を当てた場合のもっと本質な部分では、夫婦がどうだとかよりも、きちんと子供を向いているかどうかがより重要だろう。親(大人)がきちんと子供の方を向いていれば、子供は身体が病気になろうと心健やかに育つと信じたい。見た目健康だけど心が病むような時代に生きる親の一人としては、そちらのほうが魅力的に感じてしまう。
子供の方を向いている側の意見を重視したいのが本音だ。しかし、どちらがより子供の方を向いているかなんて誰にも分からない。「子供の方を向く」と一言で言っても、その方法は様々あり、それこそ価値観の数だけあるのだから比較のしようがない。
世間一般的な、標準的価値観はもちろんあるのだろうけど、世間とか標準とかがあまり好きではない俺には、オーソドックスな子供との接し方とやらに意味を見出しにくい。子供の核となる部分がどこにあるのか注意して見ていれば、表層的な接し方の問題はあまり重要ではないと考えている。
少し型破りな俺の教育論。それを指して「お前は子供の事を考えていない」と評されるのは悲しいものだ。自分への評価が悲しいのではなく、俺自身も当てはまることではあるが、人間は自分が正しいと思う生き物なんだな、という部分がひどく悲しいのだ。
そんな思い込みの塊が子供を育て、人類は歴史を積み上げていく。子供を、親や大人のエゴに巻き込むな。教育と、エゴの境目は難しい。
「教育と国益」
子供を思う教育と、子供が願う教育。今の教育界を取り巻く問題は、ちょっとずれている気がする。国益を担う子供の将来を考え教育することも大事だけど、前にも書いたように、グローバル化が進む以上競争率は10倍20倍になるのだ。
そこを勝ち上がる事が出来た日本の子供は、国のために働くだろうか。それはないような気がする。企業のために働くのではなかろうか。
企業は多国籍化・ひいては無国籍化すると思われる。少なくとも今の方向性はそうと言える。国よりも企業が今より更に強くなることだろう。企業をどのように誘致するかが国の大問題となる。
企業は国に尽くすのではなく、自社が生き延びる事が出来る環境に尽くす。日本で優れた教育を受けた子供が、必ずしも日本に利益をもたらすとは限らない。それをどのようにもたらしてくれるようにするかが教育の要でもある。
仮にだが、愛国的な教育を是とする子供が勝ち残っていくことはあるだろうか。ちょっと考え難いんだよね。今の日本の企業を取り巻く環境は、国益よりも自社の利益ではないのかな。
その環境の上で国益に結びつけるためには、ソフトを読み込むハード作りが肝要だろうと思われる。ハードよりもソフトの時代なのだが、ソフトはより優れたハードを求めるのだ。
小さな社益を求める日本国の教育が、国民一人一人が国のために戦える国に勝てるのか。真の国益とは何か、ということから考えなければならないのではないだろうか。
そこはちょっと棚上げ。
要するに、わざわざ教育を施すよりも、優れた教育を施された人材が来てくれた方が遥かにコストは低くて済むと思うのだ。経済的国益を考えるのであれば、ソフトを開発するよりも、ソフトを買って自社ブランド化する方が早いし安い。ソフトを作ることに満足感を見出すか、ソフトを誘致出来るハードを作ることに満足感を見出すかで、かなり違うのだと思う。
世界に開けた教育環境で、優れたソフトをどんどん誘致する外国との戦いを、日本の子供だけに押し付ける議論は如何なものだろう。日本という檻に閉じ込めたまま、野生の中で生き抜いてきた大量の敵に立ち向かえるとは到底思えない。
当然だがそれと教員制度等々改革は別の話だとは思っている。
世界で戦える人材の育成が出来る教育だけを進めてもならないのだ。たった一人のジョブズを育てるために、数百万人の子供を犠牲にすることは、経済的な観点の教育としては正しくても、子供にとっては過酷だ。秀才は教育で生まれるが、天才は教育では生まれない。天才は数から生まれる。子供の数の多い国が圧倒的有利である。
日本は逆に、圧倒的不利な状況にあえて挑もうとしている。日本は別の方法で戦わなければならない。圧倒的に天才発生率が違うということを認識しなければならない。
もう一度書くけど、それと教員制度等々の改革問題は別なんだけどね。
「そんな教育論、どうでもいいってね!」
俺はどちらかと言うと、食事に気をつけよう、とか、将来に備えよう、とか考えてしまう方なんだけど、その考えが現実に即しているかどうかという部分では非常に弱い。紆余曲折を経て今の考え方にひとまず落ち着いているものの、どこかに非現実的な夢物語を描いてもいる。
ただ、それよりも何よりも、俺たち夫婦の歴史の中では、夫婦になるということの意味を最重要課題として掲げざるを得なかった。1年先5年先10年先の俺予測が当たったとする。それが現段階において理解されなかったとして、その上で行動が遅れ自滅したとしても、俺は父親として責任を持ちたい。
昔、水と油は常にかき混ぜていないと混ざらない、と言われた。価値観の違う人間同士とはそういうものなのだと思う。世の多くの問題は、「お前が混ぜろよ」「いやお前こそ混ぜろよ」という醜い争いから生まれている。
挙句に、「俺が混ぜるよ」って言う人が現れると、「いやお前じゃダメだ」とか言い出す。自分でやらないくせに足も引っ張る。まるで俺のようだ。あふん。
何にしても、意識の高い方が一生懸命かき混ぜるしか無い。
そしてもっと言えば、相手の方がより意識は高いのだと認識し、相手のかき混ぜ方・懐に飛び込むことだ。相手にかき混ぜて頂き、相手と混ざらせて頂き、相手の内側から、千年の計すらも持ち問いかけ続けるしかない。
親が出来うる子への教育は、子の中で生き、問いかけ続けることだ。しかし、国が出来うる子への教育は全く異質なのだ。一本筋を通さなければならないケースは多いのだけど、今の世界の状況は、我々が経済に甘んじ、企業が利益重視となり、国が企業を助け、国が破綻しようとしている状況である。我々が経済に甘んじたことが、全ての事の始まりなのだ。
それに対して、俺は知らねーよ、と白を切っているのが、人として正しいのか考える必要があるのだと思うのでありました。ちゃんちゃん。










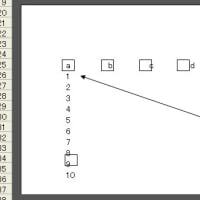
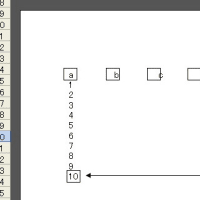
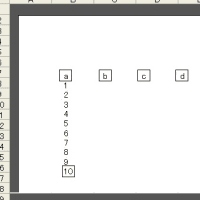





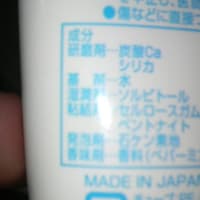
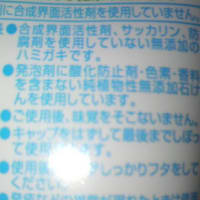
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます