少し荒れてきましたぞ。想定していない形だけど。
想定していない、というより、所長が先手を打ったことによって歴史が変わった、と言った方がいいかもしれない。歴史が変わったという表現は思惑と違った場合に使われる都合の良いフレーズ(笑)
会社の話は後述。
俺は連続的に物事を捉える傾向が強いので物事を断片的に見るように努力しているのだけど、どこを断片的にするかがとても難しい。だいたいの場合(多くの人の場合)、主張には自分の思惑が含まれる。思惑とは感情に近いものではなかろうか。感情を出来るだけ意識的に排除しようとして、ようやく主張に正当性が生まれてくるように思える。
しかし多くの人の感情が蠢く集団において、感情を排除していくと残るものは「いろいろあるよね、人間だもの」ではないかと思える。正当性を、俯瞰し客体化すること、と言い換えるとして、さらに別の言い方をするなら、全てを包括的に許容することだろう。
ところが正当性というものは、それ自体が相対的な意味合いを持っている。もし全てに対して相対的であることを仮定するなら、「全てに対して許容すること」に加えて「全てに対して相対(あいたい)すること」のどちらも意味しそうである。究極的な正当性は、全体が包まれることか、個が全体に属さないことかのどちらかであるのかもしれない。自分はそう思う(感じる)から、というのは、それだけで全と個の相対関係では正当性を持つ。
そうだとすると、全体に適用されることは、全体が一様であることと同時に、その一様が個の多様性を脅かさない範囲であることが示唆される。全体は多様性を保持するためにおいてのみ一様的であり、それ故に個の多様性が全体の一様性を侵食してはならない。
まぁ別段崇高なことを書いているわけでもなく、他人の権利を脅かして良い権利は許されない、ということなんだけどね。
なので俺は、個と全は本質的に同じものだと解釈した。全体が包まれて「何でも良い」は個の多様性を意味するもので、個が全に相対して「何でも良い」も個の多様性を意味する。どっちも全体の存続(つまり多様性の保持)にとって大差はない。しかしこの論理は全体の一様的価値観としてとても大事なものである。だからこそ全体主義と個人主義のせめぎ合いに多様性の本質がある。
例示として全体と個人を理解しやすい国家を挙げてみる。国家の自由を求める姿勢(国家が自由である、とは、近代思想の意味においては、古い封建社会の権力者を暗示するものだろう)と、個人の自由を求める姿勢(個人が自由である、とは、閉鎖的な空間における抑圧に対する解放を暗示するものだろう)は、自由の意味合いが違うだけであってその意味においてこそ対立的であるものの、たった一つの一様性を見失う場合に、本質的には多様性を失わせる姿勢だと思える。
つまり広義の意味におけるバランス(広義では、偏りもバランスの一側面)が重要だと言うことだ。個人の自由が、その集合である意味において国家をも打ち砕くことが可能になったのだから、自由の定義にこそ近代から次世代へのブレイクスルーが求められつつあるように思える(これは狭義におけるバランス)。他人の権利(例えば自由)を奪って良い権利が無いのであれば、自由の定義をどう解釈するかが重要で、近代の意味における自由が国家(権力者)に対する脅かされない権利であったことを、今後、変化させていく可能性に人類の進化を予感する。全が個の自由を脅かしてはならないのと同時に、個も全の自由を脅かしてはならない。自由とは何ぞや?昨今のネットを介在した揺らめきは、おそらくこの意味における過渡期なのだろう。
会社のことを書こうと思ったけど、何となく間延びしてしまった感覚に襲われまたの機会に順延します。で、記事自体はまとめ切れていないように感じるので、書き掛けの記事扱いという逃げ口上を格好悪く置き土産として付記するのであります。だははは。
想定していない、というより、所長が先手を打ったことによって歴史が変わった、と言った方がいいかもしれない。歴史が変わったという表現は思惑と違った場合に使われる都合の良いフレーズ(笑)
会社の話は後述。
俺は連続的に物事を捉える傾向が強いので物事を断片的に見るように努力しているのだけど、どこを断片的にするかがとても難しい。だいたいの場合(多くの人の場合)、主張には自分の思惑が含まれる。思惑とは感情に近いものではなかろうか。感情を出来るだけ意識的に排除しようとして、ようやく主張に正当性が生まれてくるように思える。
しかし多くの人の感情が蠢く集団において、感情を排除していくと残るものは「いろいろあるよね、人間だもの」ではないかと思える。正当性を、俯瞰し客体化すること、と言い換えるとして、さらに別の言い方をするなら、全てを包括的に許容することだろう。
ところが正当性というものは、それ自体が相対的な意味合いを持っている。もし全てに対して相対的であることを仮定するなら、「全てに対して許容すること」に加えて「全てに対して相対(あいたい)すること」のどちらも意味しそうである。究極的な正当性は、全体が包まれることか、個が全体に属さないことかのどちらかであるのかもしれない。自分はそう思う(感じる)から、というのは、それだけで全と個の相対関係では正当性を持つ。
そうだとすると、全体に適用されることは、全体が一様であることと同時に、その一様が個の多様性を脅かさない範囲であることが示唆される。全体は多様性を保持するためにおいてのみ一様的であり、それ故に個の多様性が全体の一様性を侵食してはならない。
まぁ別段崇高なことを書いているわけでもなく、他人の権利を脅かして良い権利は許されない、ということなんだけどね。
なので俺は、個と全は本質的に同じものだと解釈した。全体が包まれて「何でも良い」は個の多様性を意味するもので、個が全に相対して「何でも良い」も個の多様性を意味する。どっちも全体の存続(つまり多様性の保持)にとって大差はない。しかしこの論理は全体の一様的価値観としてとても大事なものである。だからこそ全体主義と個人主義のせめぎ合いに多様性の本質がある。
例示として全体と個人を理解しやすい国家を挙げてみる。国家の自由を求める姿勢(国家が自由である、とは、近代思想の意味においては、古い封建社会の権力者を暗示するものだろう)と、個人の自由を求める姿勢(個人が自由である、とは、閉鎖的な空間における抑圧に対する解放を暗示するものだろう)は、自由の意味合いが違うだけであってその意味においてこそ対立的であるものの、たった一つの一様性を見失う場合に、本質的には多様性を失わせる姿勢だと思える。
つまり広義の意味におけるバランス(広義では、偏りもバランスの一側面)が重要だと言うことだ。個人の自由が、その集合である意味において国家をも打ち砕くことが可能になったのだから、自由の定義にこそ近代から次世代へのブレイクスルーが求められつつあるように思える(これは狭義におけるバランス)。他人の権利(例えば自由)を奪って良い権利が無いのであれば、自由の定義をどう解釈するかが重要で、近代の意味における自由が国家(権力者)に対する脅かされない権利であったことを、今後、変化させていく可能性に人類の進化を予感する。全が個の自由を脅かしてはならないのと同時に、個も全の自由を脅かしてはならない。自由とは何ぞや?昨今のネットを介在した揺らめきは、おそらくこの意味における過渡期なのだろう。
会社のことを書こうと思ったけど、何となく間延びしてしまった感覚に襲われまたの機会に順延します。で、記事自体はまとめ切れていないように感じるので、書き掛けの記事扱いという逃げ口上を格好悪く置き土産として付記するのであります。だははは。










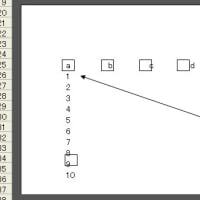
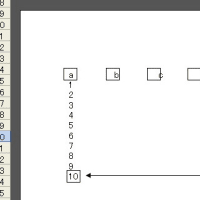
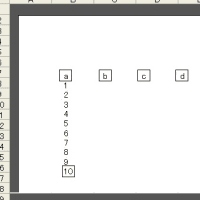





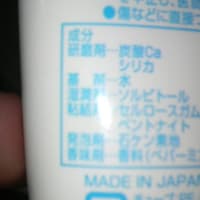
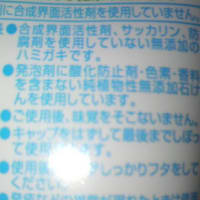
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます