ある地域で見た光景である。わたしの思い込みかもしれないが、そう思わせるのは緑の濃い水路際の草が、気になるほど伸びているわけではないためだ。あえてこの写真を撮影したのは、この道を通った際に、やけに土手の草に比べて水路際の草が目立ったためである。ちょっと写真では分かりづらいのだが、車を運転していて見た最初の印象は、「土手の草が刈られているのに、水路際の草は刈られていない」ということだった。何を言いたいか、といえば、土手の上は転作された畑であるが、その所有者は、自らの土手の草は刈ったものの、その下の水路際はもちろん水路を越えた道端の草は刈らなかったことだ。もしかしたらそれほど伸びていなかったから、あえて刈り残した、のかもしれない。定かではないが、ふつうなら土手の草とともに、公共的空間に当たる水路際も刈るのではないか、とはわたしの勝手な受け止め方、ではある。
わたしの日記の中でも、初夏からこれまでの間で最も閲覧数が安定している記事に「草刈をする範囲」があることは、以前にも述べた。常にわたしの日記の中ではトップ5内に入るほど閲覧数は多い。先ごろも触れたとおり、わたしの日ごろの草刈の意識では、自分の土地に隣接する公共空間は、当たり前に「刈るもの」という意識だ。かつては当たり前にあった意識であるが、では「どこまで刈るか」というあたりは個人差があるもの。もともと家畜を飼っていた時代は、刈った草は有用なものだった。餌となったからだ。さらに時代をさかのぼれば、草は肥料にされた。ただただ「余計なもの」として捉えられる今とは、ずいぶん違ったのだ。その記憶が少なからずあるからだろう、逆に他人の土地の草は「刈らない」という意識もあった。勝手に刈れば「泥棒」と捉えられかねない。他人の領域には足を延ばさない、も当たり前にあった意識だ。とはいえ、過去と今とは様子が異なる。公共空間の草が「伸び放題」という姿は、あちこちで目にする。やはり隣接地はその関係者が草刈をする、が今の世の基本姿勢だとはおもうのだが、なかなかそうとはいかない。
今年も何度となく記してきたが、我が家は隣接空間に公共空間が多い。自ずと自分の土地ではない場所の草刈をすることは多くなる。先日の「山の日」から盆にかけてもそうだが、出勤日や休日に特別な用事がなければ「草刈」三昧となる。とはいえ、妻の実家まで足を延ばしての作業なので、フルに1日中ではない。この炎天下だから、年老いたわたしには、日中ずっと草刈だとしたら、とてもその疲労は容易に抜けない。半日レベルであっても、週末の草刈の疲労が抜けきらずに翌週を迎えて、そのまま週末まで疲労が続くことも珍しくない。それでも草刈範囲を一通りクリアーできていない。当たり前にそうした日々を過ごしているが、「わたしが草刈ができなくなったら」その後どうなるのか、などとは考えないようにしている。











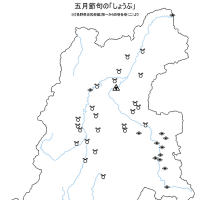















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます