
旧開田村末川左岸の橋のたもとに村唯一といわれる双体の道祖神が建つ。向かって右側が男神、左が女神となる。どちらも相手の肩に手を掛けて抱き合っているのだが、肩に掛けた手はお互いの身体の離れからすると少し違和感は残る。温和な表情はどちらも同じような面持ちで、軽く微笑みかけている。地蔵峠を越えた黒川谷には双体道祖神がたくさん建てられているが、黒川谷の道祖神を見た後にここ末川の道祖神を拝すると、同じ作者の手によるものとすぐにわかる。
この末川の道祖神とともにいくつもの石碑が並んでいるが、その中に「稗田の碑」といわれる縦長の碑が立つ。前面に小さな文字が刻みこまれているが、彫りが浅く容易には読み取れない。この碑の拓本が、開田郷土館に飾られている。そもそも旧開田村は、木曾御嶽山の東北山麓に展開する標高2000㍍前後の高原の村。把之沢川・末川・冷川が村の南部で西野川に合流し、三岳村をへて木曽川に注ぐ。河川に沿って、西野と末川の集落があり、水田や耕地が散在する。江戸時代のはじめは末川村一村であったが、享保9年(1724)の検地以後西野村が分村独立した。明治になって両村が合併し、「この村、水田の開けること木曽第一なるに因って」開田村と名づけられたという。『長野県土地改良史』によれば、「高冷地で、年平均気温は八度と低いため、江戸時代の中期まで村内では稲作はおこなわれなかった。享保の検地には、末川村・西野村には一坪の水田も書き上げられてはいない。一八世紀中期の延享年間(一七四四~四八)にはじめて水田を開いて稗を栽培し、ついで稲を作った」と言われる。この開田の歴史を物語る碑が「稗田の碑」で、開田には末川のほかに西野と把之沢に合わせて3基存在する。末川の碑について「末川村の庄屋中村彦三郎は、寛延元年(1748)に尾張藩から金五〇両の資金を得て二二町歩余の水田を開いた。開田事業による心労のため彦三郎は事業半ばで耳が聞こえなくなり、子の弥惣兵衛が庄屋として事業を継続した。碑文には「ここにおいて、民大食を得、ようやく凍えや飢えを免る」と記されている。この碑は安永五年(一七七六)彦三郎七三歳のときに、村民が建立したもの」という(前掲書より)。ようは開拓記念碑にあたるわけである。

末川の稗田の碑










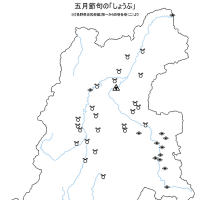
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます