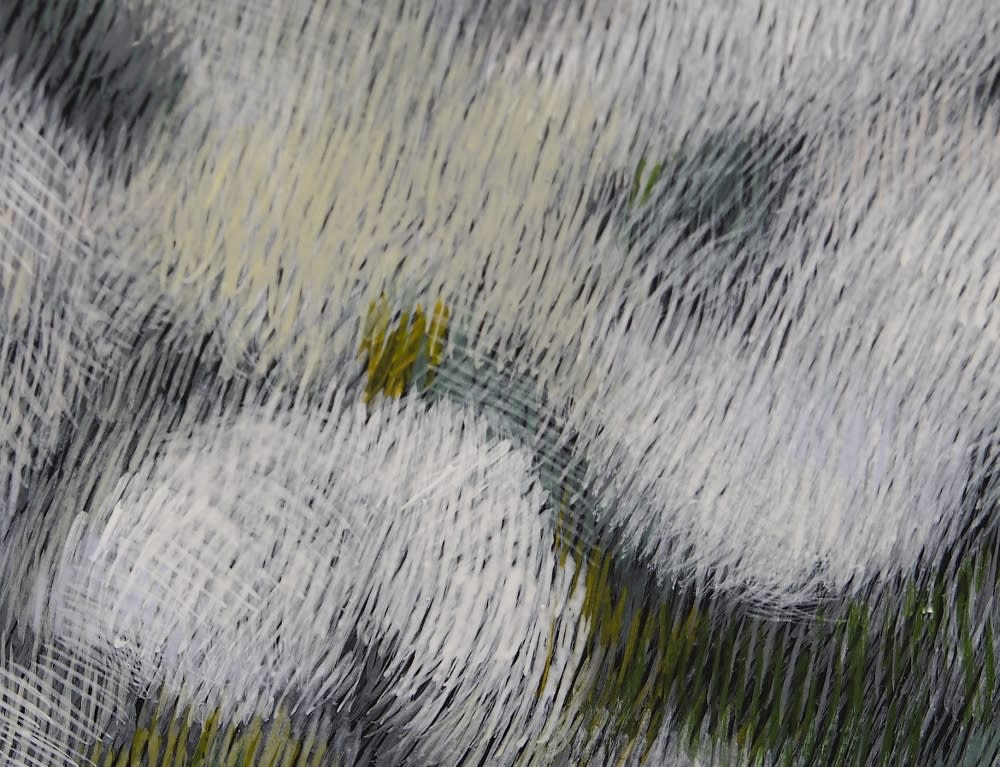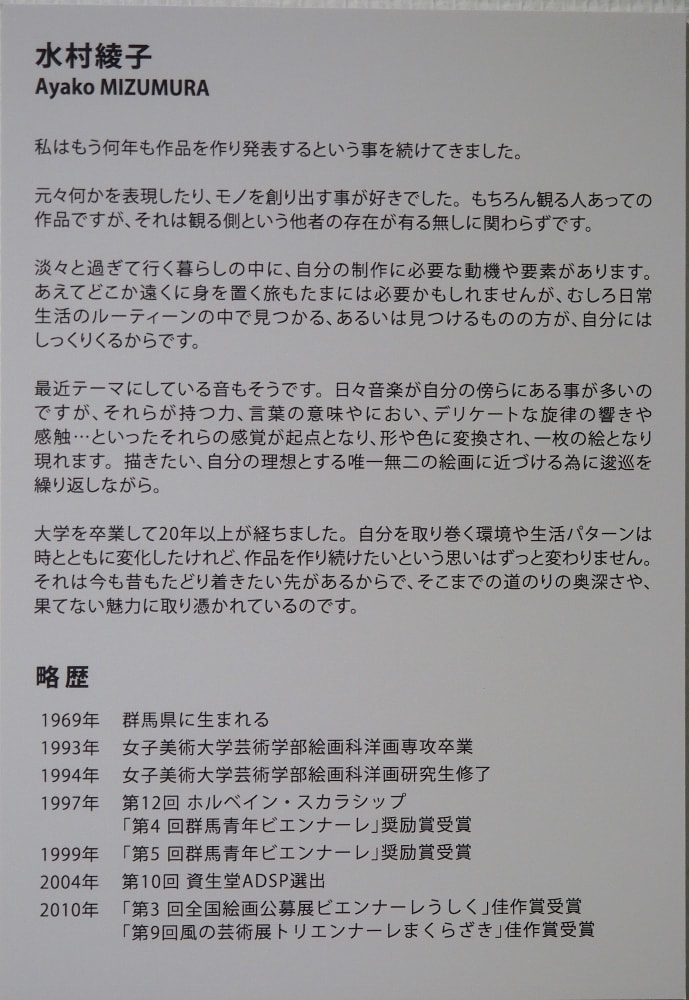7月25日(土)に横浜美術館で開催されている蔡国強展”帰去来”に行ってきました。

入口にこの巨大な作品。 2階から撮影

《夜桜》2015年、火薬・和紙、800×2400cm、作家蔵
1階で 素材は和紙!

左側は篝火かな?

2階でこの作品の裏面を撮影。 和紙の裏面まで爆発の力が及んでいます。
《春夏秋冬》 白い磁器パネルに草花などが浮彫されています。 これも大きな作品です。

《 春夏秋冬》より (部分) 2014年、火薬・磁器、作家蔵
その表面を爆破処理して、あえて汚濁をつくり、清濁混合の美をつくっている。

そして驚いたのは、《人生四季》と題された、江戸時代の浮世絵師:月岡雪鼎の春画をモチーフにした絵画(火薬絵画と称している)
蔡のカタログテキストから、この作品と関連する考え方が明瞭に述べられていました。
”今回、私は日本絵画の構図や情感、東洋の文化思想や生き方について考え、現代絵画の言語や表現手法に置き換えることを模索した。
・・・
横山大観などの先人が描いた日本画はすでに形式化しており、自分なりの表現を加える余地はあまりない。一方、日本の春画の
自由さには興味をおぼえた。春画を描いた絵師は、いわゆる正統派ではなく、「古代中国の多くの著名な絵師も春宮画を描いた」
ことを根拠に、自らの絵も芸術であると主張した。伝統的な“日本画”はもちろん主流ではあるが、その画面は窓から見る景色の
ようで、単なる観賞の対象になっているものが多い。だが、春画の中にはいのちが流れており、自然の変化もとり入れられてい
る。さらには、東洋文化における時空一体の概念が含まれ、現代アートとも通じるものがあり、その意味で対話の余地が残され
ていた。
《人生四季》
春画のうち、私が最も多くのインスピレーションを受けたのは、月岡雪鼎が一組の男女のいのちの営みの変化を描いた《四季画
巻》である。中でも女性の描写が特に印象深かった。春、娘にはまだ陰毛が見えず、はにかんで潤んでいる。夏になるとよろこ
びを覚え、秋には朗らかで開放的となり、子を宿している。冬が来て、情けが深まり、男性の上に覆い被さってさえいる……。
女性の表情にそれほど大きな変化はないが、局部の色はピンクから紫へと徐々に変化しており、歳を重ねていることを感じさせ
る。それぞれの春画と対になった花卉図も、いのちの盛衰に沿ったものとなっている。
カンヴァスの上に火薬を使って描いた《人生四季》では、まず人物を中性化し、服装や時代的な特徴をなくした。肌の刺青は、
花札の図柄からとり、四季の動植物と対応させ、人が情欲を深めていく段階を示した。柔らかくぼんやりとした「春」の光の中
で、燕が鳴き交わし、欲望は子鹿のように無邪気にぶつかり合う。色鮮やかな「夏」では、百合や牡丹が花開き、カッコウが鳴
く中で、ひとしきりのおたのしみ。清々しい「秋」には、すっかり知り尽くし、菊や朝顔が咲き誇り、南へ飛ぶ雁や芒が秋風を
示す。「冬」はあたり一面の雪で、ゆったりとした深い情にあふれ、松の上に鶴が舞い飛び、梅の梢には小鳥が寄り添う……。
春画や刺青の表現などの試みのほかに、最も予想外だったのは、色がもたらす興奮だった。昼用花火の材料の爆発によって出し
た赤などの色は、フランシス・ベーコンの油絵のような制御不能の狂気とサディズムを感じさせる。局部の濃厚で強烈な色合は、
画面の大部分を占める、永久に安らかな灰色を挑発しているかのようで、そこには野獣を放ったような痛快さがあり、もう一人
の自分が解放された気分だった。黒い火薬の原始的エネルギーと昼用花火の色彩によって情欲を表現し、生きる上での喪失や渇
望を伝えていくことの今後の可能性は、少なくないようだ。”
長文でしたが、現代絵画に翻訳した春画が見事でしたので、引用させていただきました。
9月13日追加:本日、図書館で蔡国強さんがインスピレーションを受けた月岡雪鼎の《四季画巻》を見てきました。
芸術新潮1月号の月岡雪鼎特集にありました。 雪鼎の原画もさすがです。 江戸の浮世絵師とはちょっと違い、上方の細や
かなリアリティが感じられます。
《人生四季 春》

《人生四季 夏》

《人生四季 秋》

《人生四季 冬》

蔡は美術を目指した頃、キャンバス作品を制作していたが、その後、火薬ドローイングやインスタレーションで国際的に有名になった。
今回は、火薬を用いて絵画に回帰してみたかったとのこと。 帰去来にはそうした意味もある。
そして《壁撞き》


《壁撞き》 2006、99 体のオオカミ[鉄芯、 藁、石膏、着色された羊の毛皮、合成素材]のレプリカ、ガラス壁[合わせガラス、鉄骨ベニヤ貼り、塗装仕上げ台座] 400×800×3200(ガラス壁:290×350×340)cm ドイツ銀行蔵
このオオカミの毛、羊の毛を着色して植え付けたものとか。 ベルリンの壁、崩壊後の目に見えない壁をモチーフにしてつくられた巨大インスタレーションの
ダイナミックさと、細かいディテールまで手を抜かない緻密さ、・・・世界で活躍するのも当然でしょう。
こちらは、芸術新潮9月号の蔡国強展の紹介ページです。 オオカミ、爆破、春画・・・わかりやすい
コンセプトです。

その土地々々の文化や、伝統などを織り込みながら制作する蔡国強さん、頭の良い人という印象も受けました。







































 赤丸は売約済の印だそうです。
赤丸は売約済の印だそうです。