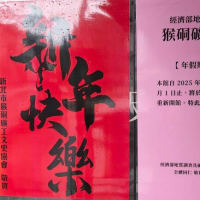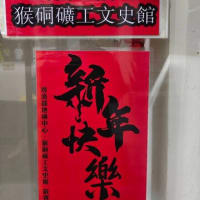今日は「大寒」・・・1年で寒さが最も厳しくなる頃です
毎年大寒が近づくと思い出すことがあります。
それは「寒糊炊き」の行事です。
文化財の修理には、小麦澱粉を水で炊いて作る新糊と古糊が主に使われます。
新糊は毎朝その日使う分を炊くのですが、古糊は名前の通り、糊を甕に入れて10年以上暗所に保管し、
微生物の働きでゆっくりと熟成させたもののことを言います
この古糊は「装こう」と呼ばれる日本画の表装作業の際に用いられ、主に掛け軸などの裏打ち紙を貼り合わせる際に使われています。
古糊の特徴は、柔らかく、接着力が弱く、そして接着後も水を与えると容易に剥がれる。
また使用後にカビが生えにくいことなどが挙げられます。
「古糊」は1年に一度、大寒の頃に作ります。
この古糊作りは、毎年雑菌の少ない寒い時期に作られるため「寒糊炊き」と呼ばれています。
古糊は各修理工房で独自に作られるもので、その配合も工房ごとに微妙に異なるようです。
(同じ工房で作られたものでも、甕によって異なることが多い)
最初は液体だった糊が、混ぜ続けることによって徐々に固まり始めると、
「撹拌する棒が重くなり、腕が痛くなる 」手を休めると糊は直ぐに焦げてしまうため、
」手を休めると糊は直ぐに焦げてしまうため、
焦がさないように皆で協力し掻き混ぜ続けなければ糊は炊きあがりません。
炊きあがった糊を甕に移し、甕が一杯になるまで炊く作業は続きます。
全ての甕(工房によって個数は異なる)が一杯になったら、蓋をして封をします。
甕の表面に作った日(年月日)と共に、糊を炊いた一人ひとりの名前を書き記します
保管期間中には、表面にカビが生え、毎年そのカビを取り除く作業も行われます。
カビも最初の数年は酷いようですが、次第に生成しなくなるそうです。
初めは甕いっぱいに作った糊も、10年経つと使用できる量は3分の1程度になるようです。
以前寒糊炊きに参加する際にこの行事について調べたのですが、
この古糊が出来上がる10年という期間は、ちょうど表具師が一人前 になる期間とも言われており、
になる期間とも言われており、
糊炊きは弟子入りした最初の仕事で、10年後、暖簾分けする時に自分がかつて作った古糊を分けてもらい独立していたようです
我が身を振り返ると、最初に寒糊炊きに参加させていただいた頃から、早くも5度目の大寒を迎えました。
職人さんと比べても意味のないことですが、毎年この季節になると襟を正し、また1年精進しようという気持ちになります。
これから2月上旬まで暦の上では寒さの厳しい日が続きますが、皆さま健康第一にお過ごしください

毎年大寒が近づくと思い出すことがあります。
それは「寒糊炊き」の行事です。
文化財の修理には、小麦澱粉を水で炊いて作る新糊と古糊が主に使われます。
新糊は毎朝その日使う分を炊くのですが、古糊は名前の通り、糊を甕に入れて10年以上暗所に保管し、
微生物の働きでゆっくりと熟成させたもののことを言います

この古糊は「装こう」と呼ばれる日本画の表装作業の際に用いられ、主に掛け軸などの裏打ち紙を貼り合わせる際に使われています。
古糊の特徴は、柔らかく、接着力が弱く、そして接着後も水を与えると容易に剥がれる。
また使用後にカビが生えにくいことなどが挙げられます。
「古糊」は1年に一度、大寒の頃に作ります。
この古糊作りは、毎年雑菌の少ない寒い時期に作られるため「寒糊炊き」と呼ばれています。
古糊は各修理工房で独自に作られるもので、その配合も工房ごとに微妙に異なるようです。
(同じ工房で作られたものでも、甕によって異なることが多い)
最初は液体だった糊が、混ぜ続けることによって徐々に固まり始めると、
「撹拌する棒が重くなり、腕が痛くなる
 」手を休めると糊は直ぐに焦げてしまうため、
」手を休めると糊は直ぐに焦げてしまうため、焦がさないように皆で協力し掻き混ぜ続けなければ糊は炊きあがりません。
炊きあがった糊を甕に移し、甕が一杯になるまで炊く作業は続きます。
全ての甕(工房によって個数は異なる)が一杯になったら、蓋をして封をします。
甕の表面に作った日(年月日)と共に、糊を炊いた一人ひとりの名前を書き記します

保管期間中には、表面にカビが生え、毎年そのカビを取り除く作業も行われます。
カビも最初の数年は酷いようですが、次第に生成しなくなるそうです。
初めは甕いっぱいに作った糊も、10年経つと使用できる量は3分の1程度になるようです。
以前寒糊炊きに参加する際にこの行事について調べたのですが、
この古糊が出来上がる10年という期間は、ちょうど表具師が一人前
 になる期間とも言われており、
になる期間とも言われており、糊炊きは弟子入りした最初の仕事で、10年後、暖簾分けする時に自分がかつて作った古糊を分けてもらい独立していたようです

我が身を振り返ると、最初に寒糊炊きに参加させていただいた頃から、早くも5度目の大寒を迎えました。
職人さんと比べても意味のないことですが、毎年この季節になると襟を正し、また1年精進しようという気持ちになります。
これから2月上旬まで暦の上では寒さの厳しい日が続きますが、皆さま健康第一にお過ごしください