
世界の架け橋、Bridge Over the Worldは、略称がBOWである。
世界へ架ける虹🌈rainbowのBOW🌈🏹でもある。
🌈虹が、ある意味では、弓となるスタッフや保護者の方々であり、
放たれる矢🏹が未来の子どもたちと想像してみたい!
社会、世界へと飛び行く矢、がっしりと支える揺るぎない弓から
放たれれ、また支える喜びが世界の架け橋になり、自由への彼方🏹へ
・・・射る者の手によって
身をしなわせられるのをよろこびなさい。
射る者はとび行く矢を愛するのと同じように
じっとしている弓をも愛しているのだから。
Kahlil Gibranの詩集「預言者」より
「子どもについて」というハリール・ジブラーンの詩を
神谷美恵子さんの訳で🔻一緒に感じてみましょう!
赤ん坊を抱いたひとりの女が言った。
どうぞ子どもたちの話をしてください。
それで彼は言った。
あなたがたの子どもたちは
あなたがたのものではない。
彼らはいのちそのものの
あこがれの息子や娘である。
彼らはあなたがたを通して生まれてくるけれども
あなたがたから生じたものではない、
彼らはあなたがたと共にあるけれども
あなたがたの所有物ではない。
あなたがたは彼らに愛情を与えうるが、
あなたがたの考えを与えることはできない、
なぜなら彼らは自分自身の考えを持っているから。
あなたがたは彼らのからだを宿すことはできるが、
彼らの魂を宿すことはできない、
なぜなら彼らの魂は明日の家に住んでおり、
あなたがたはその家を夢にさえ訪れられないから。
あなたがたは彼らのようになろうと務めうるが、
彼らに自分のようにならせようとしてはならない。
なぜなら命はうしろへ退くことはなく
いつまでも昨日のところに
うろうろ ぐずぐず してはいないのだ。
あなたがたは弓のようなもの、
その弓からあなたがたの子どもたちは
生きた矢のように射られて、前へ放たれる。
射る者は永遠の道の上に的をみさだめて
力いっぱいあなたがたの身をしなわせ
その矢が速く遠くとび行くように力をつくす。
射る者の手によって
身をしなわせられるのをよろこびなさい。
射る者はとび行く矢を愛するのと同じように
じっとしている弓をも愛しているのだから。
Kahlil Gibran
(1883-1931)
On Children
From The Prophet (1923)
And a woman who held a babe against her bosom said, Speak to us of Children.
And he said:
Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow,
which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.
カリール・ジブラン(KAHLIL GIBRAN)
1883年 レバノンの山間部、Bcharret村にて生まれる。 1894年 父親だけをレバノンに残し、母親と兄弟たちとともに渡米、ボストンに住む。 1898年 アラビア語の高等教育を受けるために単身帰国。 15歳で「THE PROPHET(預言者)」の草稿をアラビア語で書く。 その後、散文詩を発表したり、詩人たちの肖像画をかいたりする。 1903年 再び渡米。絵や文を発表。 1908年 パリへ。ロダン、ドビュッシー等と親しく交わる。 1910年 ボストンにもどり、「THE PROPHET」英語に書きなおす。 その後も何回も推敲を重ねる。 1923年 ついに英語でALFRED A KNOPF社より「THE PROPHET」を出版。 1931年 ニューヨークにて死す。 遺体は生れ故郷のBcharret村の修道院に葬られ、その同じ修道院には ジブラン記念博物館が建てられ、数多くの絵画作品や遺品などが展示 されている。 詩人・哲学者・画家であったジブランの「THE PROPHET」は30数か国 に訳され、現在もなお世界の人びとに愛読されている。 このほかThe Madman(1918)、Jesus the Son of Man(1928)をはじめ 12冊の著書がある。
与えられた時間の中、何を命(いのち)の器(うつわ)入れるのか?
種まく人から人々へ、の『命いのちの器うつわ』は、
実は、神谷美恵子さんの下記の詩から名付けられている!
うつわの歌
神谷美恵子
私はうつわ
愛をうけるための。
うつわはまるで腐れ木よ、
いつこわれるかわからない。
でも愛はいのちの水よ、
みくにの泉なのだから。
あとからあとから湧き出て、
つきることもない。
うつわはじっとしてるの、
うごいたら逸れちゃうもの。
ただ口を天に向けていれば、
流れ込まないはずはない。
愛は降り続けるのよ、
時には春雨のように、
時には夕立のように。
どの日もやむことはない。
(中略)
うつわはじきに溢れるのよ、
そしてまわりにこぼれるの。
こぼれてどこに行くのでしょう、
そんなこと、私知らない。
私はうつわよ、
愛をうけるための。
私はただのうつわ、
いつもうけるだけ。
*神谷美恵子さんは、精神科医であり、すばらしい翻訳家でもあった方です。
2020年は、生誕106年になります。
臨床心理・人間科学や介護・看護医療や教育関係に係わる方々を初めとして、多くの方々に「神谷美恵子」さんの著作を読んでいただきたいと存じます。
すでに読まれた方々も、これを機会に再度、繙かれてはいかがでしょうか。
私たちの齢(よわい)とともに、きっと新たな「気づき」があるのだと思います。
いったい何を、命(いのち)の器(うつわ)に入れるのか?
「命いのちの器うつわ」種まく人から人々へ
*神谷美恵子
大正3年(1914)1月12日岡山県に、前田多門・房子の長女として生まれる。ジュネーブのジャンジャック・ルソー教育研究所付属小学校、ジュネーブ国際学校、自由学園、成城高等女学校に学び、昭和10年(1935)に津田英学塾を卒業する。学生時代に多摩全生園聖書研究会にオルガン奏者として関わり、ハンセン病患者のために働くことを志す。その後、コロンビア大学の医学進学課程に進み昭和19年(1944)東京女子医学専門学校を卒業し、インターン時代に長島愛生園で実習を経験する。東京帝国大学医学部精神科医局で研究した後、昭和27年(1952)大阪大学医学部精神科に入局し、昭和35年(1960)「らいに関する精神医学的研究」により医学博士となる。昭和32年(1957)から長島愛生園精神科医師(非常勤)となる。昭和35年(1960)神戸女学院大学教授、昭和38年(1963)津田塾大学教授を務める。昭和47年(1972)、長島愛生園精神科医師を辞め、昭和51年(1976)津田塾大学も退職する。昭和54年(1979)10月22日65歳で逝去した。含蓄に富んだ人生論的エッセイを数多く残し、マルクス・アウレリウス『自省録』をはじめ、ヴァージニア・ウルフ、ミッシェル・フーコーなどの翻訳も手がけた。










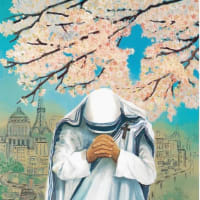




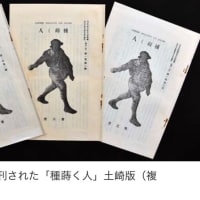
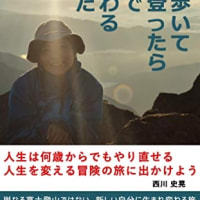


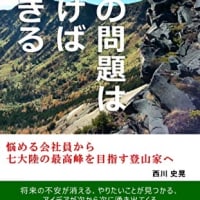
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます