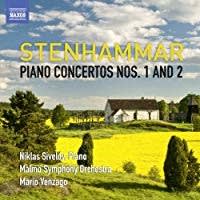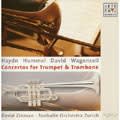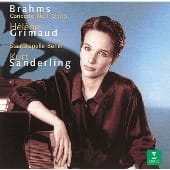バラキレフ、ステンハンマルに引き続きナクソスのマイナー作曲家シリーズ第3弾です。本日ご紹介するのはポーランドのイグナツィ・ヤン・パデレフスキです。日本ではあまり知られていませんが、本国ポーランドでは国民誰もが知る有名人です。と言うのもパデレフスキは作曲家であると同時に国際的に活躍したピアニストであり、何より第一次大戦後に独立したポーランド共和国の初代首相だからです。音楽と政治の道はかけ離れているように思えますが、長らく外国の支配に苦しんだポーランド人にとって祖国の独立は民族全体の悲願であり、パデレフスキも演奏活動のかたわら独立運動に奔走していたようです。ただ、パデレフスキの役割はあくまで独立の‟顔”としてだったようで、首相の座からは1年足らずで降り、その後は再び音楽活動に復帰します。

今回ブログで取り上げるのは彼の代表作であるピアノ協奏曲です。他にも交響曲とオペラを1曲ずつ残しているようですがそれらの演奏機会はほとんどありません。いかにもピアニストが書いたコンチェルトらしくピアノが活躍する場面がふんだんに盛り込まれています。特に第1楽章は16分を超えるボリュームでそれだけで1つの楽曲と呼べるほどの威容を備えています。曲はややベタな旋律の第1主題で幕を明け、続けてロマンチックな第2主題が現れます。後はそれを交互に繰り返すだけですが、華やかなピアノ独奏と終盤に向けてのオーケストラの盛り上がりで聴き応えのある内容に仕上がっています。続く第2楽章は静謐なアンダンテ。CD解説にはラフマニノフの有名なピアノ協奏曲第2番第2楽章に匹敵すると書かれていますがさすがにそれは大袈裟すぎますね。ただ、美しいメロディであることは間違いないです。第三楽章は躍動感あふれるアレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ。ピアノとオーケストラが一体となってフィナーレに向けて突き進んでいきます。
CDには他に「ポーランド幻想曲」と「序曲」が収録されています。うち序曲は特筆すべき内容ではないので割愛しますが、「幻想曲」の方はピアノを大きくフィーチャーした管弦楽曲で、ボリュームも20分強あり、ミニピアノ協奏曲のような趣です。前半はやや重々しいですが、後半は一転して快活なメロディが主体でなかなか魅力的な一品です。演奏はナクソスではお馴染みのアントニ・ヴィト指揮ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団、ピアノはヤニーナ・フィアルコヴスカです。作品、オケ、指揮者、ソリストと全てポーランドで固めて、ポーランド愛に満ちあふれた1枚となっています。

今回ブログで取り上げるのは彼の代表作であるピアノ協奏曲です。他にも交響曲とオペラを1曲ずつ残しているようですがそれらの演奏機会はほとんどありません。いかにもピアニストが書いたコンチェルトらしくピアノが活躍する場面がふんだんに盛り込まれています。特に第1楽章は16分を超えるボリュームでそれだけで1つの楽曲と呼べるほどの威容を備えています。曲はややベタな旋律の第1主題で幕を明け、続けてロマンチックな第2主題が現れます。後はそれを交互に繰り返すだけですが、華やかなピアノ独奏と終盤に向けてのオーケストラの盛り上がりで聴き応えのある内容に仕上がっています。続く第2楽章は静謐なアンダンテ。CD解説にはラフマニノフの有名なピアノ協奏曲第2番第2楽章に匹敵すると書かれていますがさすがにそれは大袈裟すぎますね。ただ、美しいメロディであることは間違いないです。第三楽章は躍動感あふれるアレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ。ピアノとオーケストラが一体となってフィナーレに向けて突き進んでいきます。
CDには他に「ポーランド幻想曲」と「序曲」が収録されています。うち序曲は特筆すべき内容ではないので割愛しますが、「幻想曲」の方はピアノを大きくフィーチャーした管弦楽曲で、ボリュームも20分強あり、ミニピアノ協奏曲のような趣です。前半はやや重々しいですが、後半は一転して快活なメロディが主体でなかなか魅力的な一品です。演奏はナクソスではお馴染みのアントニ・ヴィト指揮ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団、ピアノはヤニーナ・フィアルコヴスカです。作品、オケ、指揮者、ソリストと全てポーランドで固めて、ポーランド愛に満ちあふれた1枚となっています。