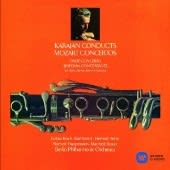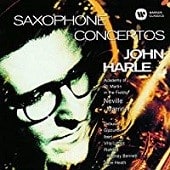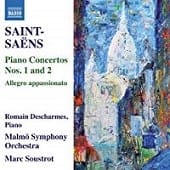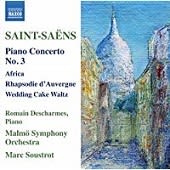前回に引き続き、本日はモーツァルトのもう一つの協奏交響曲である「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」をご紹介します。管楽器のための協奏交響曲については真偽の論争が未だに続いているようですが、こちらの作品については履歴がはっきりしており、1779年モーツァルトが23歳の時に書かれた作品だそうです。モーツァルトは自身が人気ピアニストだったこともあり、生涯を通じてピアノ協奏曲を書き続けていますが、ヴァイオリン協奏曲については5曲とも全て10代の時に書いています。本作は協奏交響曲と名前が付いていますが、実際はヴァイオリンとヴィオラによる二重協奏曲と言ってよく、モーツァルトが書いた最後のヴァイオリン協奏曲と言ってもよいかもしれません。また、この作品はソリストとして脚光を浴びることの少ないヴィオラ奏者にとっても大変貴重な作品で、今でもヴィオラ奏者の最重要レパートリーとして人気の高い作品となっています。内容についてですが、何せ天才モーツァルトなのでクオリティの高さについてはあらためて述べるまでもありませんね。あえて特徴をあげるなら第2楽章がこの時期のモーツァルトにしては珍しく短調で書かれており、哀しみを感じさせる旋律になっていることでしょうか?第1楽章と第3楽章はいかにもモーツァルトらしい天国的な美しさと明るさに満ち溢れています。特に第1楽章のハーモニーの美しさは絶品ですね。
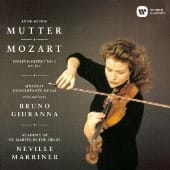
CDはネヴィル・マリナー指揮アカデミー・オヴ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズのものを買いました。ヴァイオリンはアンネ=ゾフィ・ムッター、ヴィオラはブルーノ・ジュランナです。このCDには協奏交響曲の他にモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第1番とヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョが収録されています。ヴァイオリン協奏曲第1番の方はモーツァルト17歳の時に書かれた作品で、その後に書かれた第3番や第5番に比べると目立たない存在ですが、なかなか溌溂とした佳曲だと思います。「アダージョ」の方は7分弱の小品ですが、非常にメロディの美しい作品です。
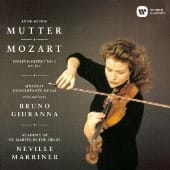
CDはネヴィル・マリナー指揮アカデミー・オヴ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズのものを買いました。ヴァイオリンはアンネ=ゾフィ・ムッター、ヴィオラはブルーノ・ジュランナです。このCDには協奏交響曲の他にモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第1番とヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョが収録されています。ヴァイオリン協奏曲第1番の方はモーツァルト17歳の時に書かれた作品で、その後に書かれた第3番や第5番に比べると目立たない存在ですが、なかなか溌溂とした佳曲だと思います。「アダージョ」の方は7分弱の小品ですが、非常にメロディの美しい作品です。