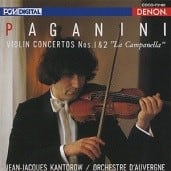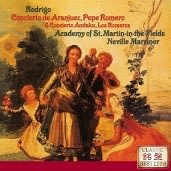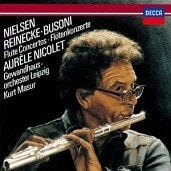本日はアレクサンドル・スクリャービンをご紹介します。19世紀から20世紀初頭にかけて活躍したロシアの作曲家で、作品自体は決して多くはないですが今日取り上げる「法悦の詩」やピアノ協奏曲は演奏機会も多いです。スクリャービンは音楽史的には「神秘和音」と呼ばれる独特のコードを生み出したことで知られており、現代音楽の先駆者の1人ともされています。とは言え、現代の我々からするとそこまでアヴァンギャルドな感じはありません。後期の代表作である「プロメテウス」なんかは調性もだいぶ崩れつつありますが、それより前に書かれた「法悦の詩」は普通に幻想的なクラシック音楽として楽しめます。ただ、当時としてはいろいろ異例の作品だったようです。まず、この曲は交響曲第4番として書かれたものですが、単一楽章で20分弱しかなく、伝統的な交響曲の形式を一切とどめていません。題名も刺激的で、日本語名は「法悦」などという固くるしい訳がされていますが、英語にするとエクスタシー、つまり性的な絶頂のことです。曲はけだるい中にも幻想的な美しさを帯びた独特の旋律が繰り返され、序盤は静かだったのが徐々に盛り上がり、金管楽器も加えながら最後はフルオーケストラで感動的なエンディングを迎えます。何度も聴くうちにクセになる名曲と言っていいでしょう。

ピアノ協奏曲の方は「法悦の詩」より10年前の1898年、スクリャービンが26歳の時に書かれた曲で、こちらの方は例の神秘和音もまだ登場せず、構成も伝統的な3楽章形式です。旋律も後期ロマン派の王道を行くもので、ややベタなぐらい抒情的な旋律の第1楽章、素朴な緩徐楽章の第2楽章、最後は情熱的なフィナーレの第3楽章で幕を閉じます。同時代のラフマニノフにも通じるものがあり、彼のピアノ協奏曲が好きな人はかなりの確率で本曲も気に入るでしょう。CDはデンオンの廉価版シリーズでリボル・ペシェク指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、ピアノ独奏はギャリック・オールソンのものです。この2曲がセットになったCDは意外と少なく、スクリャービン初心者には最適の1枚と言えるでしょう。

ピアノ協奏曲の方は「法悦の詩」より10年前の1898年、スクリャービンが26歳の時に書かれた曲で、こちらの方は例の神秘和音もまだ登場せず、構成も伝統的な3楽章形式です。旋律も後期ロマン派の王道を行くもので、ややベタなぐらい抒情的な旋律の第1楽章、素朴な緩徐楽章の第2楽章、最後は情熱的なフィナーレの第3楽章で幕を閉じます。同時代のラフマニノフにも通じるものがあり、彼のピアノ協奏曲が好きな人はかなりの確率で本曲も気に入るでしょう。CDはデンオンの廉価版シリーズでリボル・ペシェク指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、ピアノ独奏はギャリック・オールソンのものです。この2曲がセットになったCDは意外と少なく、スクリャービン初心者には最適の1枚と言えるでしょう。