
より
*****
アメリカ政府は、なぜ遺族への補償を拒否するのか
日米地位協定の「軍属」をめぐる「ボタンの掛け違い」 ジャーナリスト 布施祐仁氏
4月17、18両日(現地時間)、アメリカのフロリダ州にあるトランプ大統領の「マール・ア・ラーゴ」で日米首脳会談が行われた。会談後の共同記者会見で「トランプ大統領との友情と信頼関係を更に深めることができた2日間であった」と強調したように、安倍晋三首相にとって今回の会談の最大の目的はトランプ氏との蜜月関係の演出だった。
安倍首相が「100%共にある」と繰り返しアピールする日米関係だが、日米地位協定の運用をめぐって現在、両国の主張が対立し協議が難航している問題がある。
 補償金の支払いを巡って対立する日米政府
補償金の支払いを巡って対立する日米政府
2年前の2016年4月28日夜、沖縄県うるま市で20歳の女性がウオーキング中に米軍属のアメリカ人男性に襲われ、殺害される事件があった。この事件で、アメリカ政府が日米地位協定に基づく遺族への補償金支払いを拒否しているのだ。
日米地位協定は、米軍の兵士や軍属が公務と関係なく起こした事件でも、加害者に支払い能力がない場合は、アメリカ政府が被害者に「慰謝料」を支払うと定めている(第18条6項)。今回の事件では、那覇地方裁判所が今年(2018年)1月、ケネス・フランクリン・シンザト被告(刑事裁判の一審では無期懲役の判決。現在控訴中)に対して、「損害賠償命令制度」に基づく被害者遺族への賠償命令を出した。遺族の代理人によると、請求額のほぼ全額が認められたという(「琉球新報」2018年2月2日)。裁判所の命令が出ているにもかかわらずアメリカ側が支払いを拒んでいるとあって、沖縄では新たな怒りを生んでいる。
シンザト被告は事件当時、米軍嘉手納基地内のインターネット関連会社に勤めていた。日本政府関係者によると、アメリカ側は日本政府に対し、「被用者と軍属とは異なる概念。被告は事件当時、軍属だったが、米軍が雇用していたわけではなく米軍と契約していた民間会社に雇用されていた。アメリカ政府が補償金を支払う義務はない」と主張しているという(「朝日新聞」2018年3月16日)。
他方、日本政府は、日米地位協定に基づいてアメリカ側に補償金の支払い義務があると主張している。
日米地位協定第18条6項は、「合衆国軍隊の構成員又は被用者(members or employees of the United States armed forces)」が公務外で起こした事件について、アメリカ政府が慰謝料を支払うと規定している。日本政府は、この「被用者」にはシンザト被告のように直接米軍に雇用されていない軍属も含まれるという見解を示しているが、アメリカ側は含まれないと180度違う主張をしている。いったいなぜ、こんなことになっているのか。
請負業者まで軍属に含めているのは日本だけ!?
結論から言うと、世界中に米軍基地を置くアメリカの「国際基準(グローバルスタンダード)」では、シンザト被告のように米軍と雇用関係のない者は賠償の対象外となっている。とはいえ、沖縄の人々が今回のアメリカ側の対応に反発するのも理解できる。なぜなら、シンザト被告には事件当時、軍属として日米地位協定上のさまざまな特権が与えられていたのである。実際、シンザト被告が逮捕された際、在沖米軍トップのローレンス・ニコルソン中将は「米軍や米政府が雇用しているわけではないが、日米地位協定が適用される人物だ。事件は全て私の責任だ」(「琉球新報」2016年5月20日)と言って謝罪している。日米地位協定が適用され、さまざまな特権が与えられているのに、賠償は「米軍が雇用していないから対象外」というのでは、到底納得できないのも当然である。
実は、この問題はそもそも、米軍が雇用していない請負業者の従業員まで地位協定上の軍属に含めてしまっているところに「ボタンの掛け違い」がある。
NATO(北大西洋条約機構)地位協定を始め、日米地位協定以外のほとんどの地位協定では、軍属とは原則として米軍に雇用されている文民(軍人ではない者)と明確に規定されている。アメリカとアフガニスタンが2014年に結んだ地位協定でも「アフガニスタンはアメリカの契約業者およびその従業員に対する裁判権を有する」と明記し、刑事免責特権を与えていない。米軍と雇用関係のない請負業者の従業員は、あくまでその業者の指揮命令下で仕事をしており、米軍には直接の監督権はない。そのような存在に対して、国内法の適用免除などの特権を与えるというのは理に合わない。
しかし、日米地位協定では、米軍に雇用されている者だけでなく在日米軍基地で「勤務する者」も軍属の定義に含めてしまっている。だから、シンザト被告のように基地内のインターネット関連会社で働く従業員まで軍属になっていたのである。これは、日本以外の国ではありえないことである。
日米地位協定の曖昧な規定が軍属の拡大解釈を許した
なぜ、日米地位協定だけがこんなおかしな軍属の定義になっているのか。その理由を知るためには、66年前の1952年までさかのぼらなければならない。まだ日本が連合国の占領下にあった1951年9月、日本政府はアメリカのサンフランシスコで二つの国際条約に署名した。一つはサンフランシスコ講和条約で、もう一つは日米安保条約である。前者は連合国との戦争状態を正式に終わらせる条約で、後者は前者が発効し、日本が主権を回復した後も米軍の駐留を認める条約である。これに基づき、日米両政府は1952年の1月から2月にかけて駐留米軍の地位について定める「行政協定」の交渉を行った。
この中で、アメリカ側は請負業者の従業員も軍属に含めるよう求めたが、日本側は「請負業者は日本社会で不人気者である」「請負業者を軍属とすることは、労働組合の反対なども予想され同意できない」として、NATO地位協定と同じように米軍に雇用された者のみを軍属とするよう要求した。交渉の結果、当初のアメリカ側協定案の軍属の定義に明記されていた「合衆国軍隊の請負業者に雇用され、又はこれと契約関係にある者」というセンテンスは削除され、新たに「特殊契約者」という条項(14条)を設けて、与える特権を軍人や軍属と区別して課税免除などに限定し、日本の国内法適用も明記した。「特殊契約者」とは、「特殊」と付いていることからも、請負業者全般を指すのではなく、一部の専門的技術者に限るというのが当初の日米双方の共通認識であった。
この行政協定の軍属に関する規定は、1960年に制定された日米地位協定にもそのまま引き継がれた。日米地位協定は一度も改定されていないので、現在もこのままである。それなのに、なぜ、シンザト被告のような請負業者の従業員が「軍属」の地位を与えられていたのだろうか。
それは、先ほど述べた通り、日米地位協定の軍属の定義の「曖昧さ」に由来する。日米地位協定は、軍属を「合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの」と定義しており、解釈次第では「勤務」「随伴」する者の中に請負業者の従業員も含めることのできる規定となっているのだ。
つまり、1952年の交渉で日本側担当者の奮闘でせっかく軍属の定義から請負業者を外すことに成功したのに、その後、規定が曖昧なのをいいことに拡大解釈され、64年後の2016年にはシンザト被告のようなインターネット関連会社の従業員まで軍属に含めて、さまざまな特権を認めていたのである。
地位協定前身の交渉官・西村熊雄の気概
行政協定の交渉に臨んだ当時の政治家や外交官には、日本の主権回復後も占領時代に獲得した米軍の絶対的な権限を維持しようとするアメリカに対し、少しでも独立国にふさわしい協定に近づけようとする気概があった。1952年1月、最初の公式会議で、日本側の代表を務めた岡崎勝男官房長官(吉田茂内閣)は「平等な主権国家としての日米間の関係は、占領時代とは異なることを明らかにしなければならない」と強調した。
結果的には、「在日合衆国軍隊の地位が平和条約の発効により一夜に激変を受けることを回避するよう」(外務省の交渉記録)求めるアメリカ側の強い態度に押し切られ、全体的にはNATO地位協定に比べて不平等な内容となってしまった。
これについて、実務者レベルで日本側の責任者を務めた外務省の西村熊雄氏は、交渉の一連の経過をまとめた文書の結語に次のように記している。
「こうして協定を通読すると、日本ばかりがgive and give することになる印象をつよめることも見逃してはならない。(中略)国会および世論の期待するところを達成すべく根気よく努力を重ねたところであった。が、ついに目的を貫徹しえず(中略)交渉当事者自身はなはだ不満で早晩できるかぎり早めにその改善をはからねばならないと心ひそかに期するところがあった」(外務省日本外交文書「平和条約の締結に関する調書」)
もし、西村氏が今の日米地位協定の現状を見たら、どう思うだろうか。協定の条文がほとんど変わっていないことにも驚くだろうが、自分たちが努力して勝ち取った成果(軍属の定義から請負業者の従業員を削除)まで実質的に失われてしまっている現実に愕然とするのではないか。
事件後の日米合意は国際標準にすら届かなかった
沖縄で発生した米軍属による女性暴行殺人事件を契機として、日米両政府は軍属の範囲を明確にする協議に入った。私はてっきり、これでようやく日米地位協定も、軍属は原則として米軍に雇用される者に限るという「国際標準」に合わせられるのだろうと思っていた。だから、最終的に日米が合意した内容を目にしたときは、それこそ愕然とした。
事件の翌年の2017年1月、日米両政府は「日米地位協定の軍属に関する補足協定」に署名した。日本政府は「これまでの運用改善とは一線を画する画期的なものだ」(岸田文雄外務大臣=当時)と自慢してみせたが、地位協定上の軍属の定義を変えないばかりか、何と、米軍の任務遂行に不可欠な専門的技術者など一部の請負業者の従業員を引き続き軍属に含めるという合意だったのである。私は、行政協定締結から65年が経ってもなお、「国際標準」にすらしてもらえないのかと暗澹たる気持ちになった。
元防衛大臣で、現在は小野寺五典防衛大臣の政策参与を務めている森本敏氏が共著本の中で、この交渉について「アメリカ国防総省を相手にした強烈な交渉であったようです」と記している。森本氏によれば、外務省の森健良北米局長らがペンタゴン(国防総省)で交渉している最中、アメリカ側は「君らとこれ以上話したくない」などともの凄い剣幕だったという(森本敏・田原総一朗共著『徹底討論 どうする!? どうなる!?「北朝鮮」問題』海竜社)。
この交渉で日本側がどういう要求をしたのかは不明だが、おそらく、「国際標準」を超えるような無理な要求はしていないだろう。それでも、もの凄い剣幕で怒鳴る(?)のだから、ペンタゴンが日本をどう見ているのかが透けて見えるエピソードである。
しかも、米軍から日本政府に報告された軍属の数は2017年10月時点で7048人と、補足協定締結前(2016年末)の約7300人からほとんど減っていないのである。いったい、何のための補足協定だったのかと思わざるを得ない。
この軍属の問題は、日米地位協定における日本の主権放棄ぶりを象徴している。
日米両政府の長年にわたる不作為が招いた混乱
安倍首相は今回の日米首脳会談で、トランプ大統領に対し、日米地位協定に基づき遺族への補償金を支払うよう求めるべきであった。だが、トランプ氏との蜜月関係を演出することに腐心する安倍首相は、沖縄県が反対する普天間基地の辺野古移設を「唯一の解決策」と再確認することはしても、日米で意見が対立しているこの問題は議題に上げようともしなかった。
繰り返しになるが、事件当時はシンザト被告は軍属としての特権を享受していたのだから、アメリカ政府は日米地位協定に基づいて慰謝料を支払うべきだ、という主張には正当性がある。
そもそも、アメリカの国内法では公務と関係のない事件の賠償は、米兵だろうが軍属だろうが加害者の責任で行うべきものとされている。それでも地位協定でアメリカ政府による慰謝料支払いの規定があるのは、軍の性格上、加害者が外国に移動してしまったり、加害者に日本国内で支払い能力がない場合、被害者が救済されない可能性が高いからである。
慰謝料支払いのアメリカ国内法上の根拠は、「外国人請求法(Foreign Claims Act)」である。これは、米軍関係者が公務と関係なく外国で起こした事件でも、加害者による被害者への賠償がなされないまま放置した場合、住民感情が悪化し、米軍の安定的な駐留が困難になりかねないことから制定された法律である。この法律では、慰謝料を支払う対象の要件に、米軍との雇用関係の有無は入っていない。
おそらく、世界的には、軍属ではない請負業者の従業員による事件の場合、アメリカ政府が慰謝料を支払うことは原則として行っていないのだろう。その原則を崩して日本で支払えば、米軍が駐留する他国でも支払いを求める声が上がることを懸念しているのかもしれない。
しかし、シンザト被告は事件当時、まぎれもなく軍属の地位を与えられていたのであり、この「ボタンの掛け違い」は日米両政府の長年にわたる不作為の結果である。であれば、日米両政府の責任で、被害者遺族への補償を行うべきだろう。
そして、今後このような混乱が生じないよう、日米地位協定を改定し、軍属の定義を「国際標準」に合わせて、原則として米軍に雇用されている者に限定すべきだ。
*****
 より
より











 より
より


 より
より


 より
より

 世の中が右傾化しているといわれる。安倍政権を支持する勢力には、排外主義をあらわにする極右的な思想の持ち主も少なくない。政権側も右翼的な政策を推し進めてきた。安倍政権の5年間で日本はどう変わったのか。今後、どうなるのか。民族派右翼の重鎮、「一水会」元最高顧問の鈴木邦男氏に話を聞いた。
世の中が右傾化しているといわれる。安倍政権を支持する勢力には、排外主義をあらわにする極右的な思想の持ち主も少なくない。政権側も右翼的な政策を推し進めてきた。安倍政権の5年間で日本はどう変わったのか。今後、どうなるのか。民族派右翼の重鎮、「一水会」元最高顧問の鈴木邦男氏に話を聞いた。 僕は、安倍首相の憲法改正には反対です。本来、憲法には夢や理想が必要なはずなのに、思想性もなく、ただ戦前に戻ろうとしているように見える。戦争であれだけの犠牲を払ったのに、教訓を生かせず、軍備を増強して国民の人権を抑圧するなんて愚かすぎます。僕は現行憲法は米国による「押し付け憲法」だと思っていて、自主憲法の制定には賛成だけど、自由のない自主憲法より、自由のある押し付け憲法の方がずっとマシだ。
僕は、安倍首相の憲法改正には反対です。本来、憲法には夢や理想が必要なはずなのに、思想性もなく、ただ戦前に戻ろうとしているように見える。戦争であれだけの犠牲を払ったのに、教訓を生かせず、軍備を増強して国民の人権を抑圧するなんて愚かすぎます。僕は現行憲法は米国による「押し付け憲法」だと思っていて、自主憲法の制定には賛成だけど、自由のない自主憲法より、自由のある押し付け憲法の方がずっとマシだ。 より
より
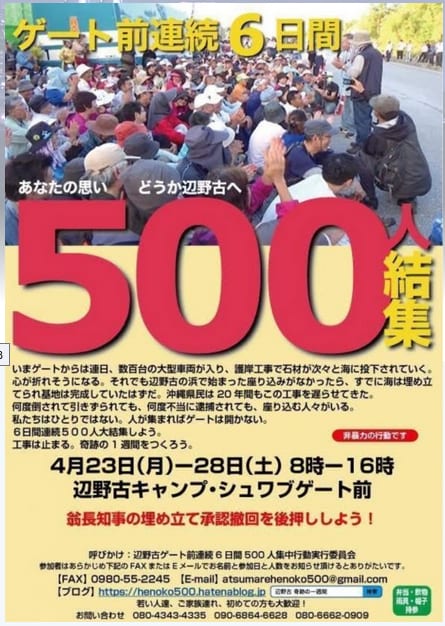






 森友・加計問題、自衛隊の日報隠蔽に続き、財務次官“セクハラ”辞任で安倍政権が末期状態だ。
森友・加計問題、自衛隊の日報隠蔽に続き、財務次官“セクハラ”辞任で安倍政権が末期状態だ。

 より
より
 米国のトランプ大統領が、4月に安倍首相と会談した際、在韓米軍の削減や撤退の可能性に言及していたことが分かった。これに対し、東アジアの軍事バランスが崩れることを懸念した安倍は、その場で反対の意向を伝えた――。5日の読売新聞が1面で報じた“スクープ”だ。安倍の危険な正体を端的に伝えている。
米国のトランプ大統領が、4月に安倍首相と会談した際、在韓米軍の削減や撤退の可能性に言及していたことが分かった。これに対し、東アジアの軍事バランスが崩れることを懸念した安倍は、その場で反対の意向を伝えた――。5日の読売新聞が1面で報じた“スクープ”だ。安倍の危険な正体を端的に伝えている。 9日には日中韓3カ国の首脳会談が東京で開かれるが、安倍はここでも韓国の文在寅大統領や中国の李克強首相に対して、圧力継続の必要性を説く方針とみられる。
9日には日中韓3カ国の首脳会談が東京で開かれるが、安倍はここでも韓国の文在寅大統領や中国の李克強首相に対して、圧力継続の必要性を説く方針とみられる。