キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
第7章
白い水仙と赤いチューリップ
白い水仙と赤いチューリップ
その朝、ポニーの家の住人たちはキャンディとテリィの帰還を温かく迎えた。前日二人が出発してから数分後にレイン先生がラジオで吹雪注意報を聞いたのだ。先生たちは二人の安否を心配したが、吹雪が起こり始めたのが10時30分頃で、それまでには二人は山小屋に着いて安全にしているだろうと判断していた。
その後レイン先生は、キャンディがまだ結婚していない男性と一晩を二人きりで過ごさねばならないことに気が付いて、夜のお祈りを二倍の長さにしなければならなくなった。ポニー先生が何度も繰り返しグランチェスターさんは紳士だからと安心させようとしても、レイン先生は一晩中一瞬たりとも落ち着いた気持ちになれなかった。もちろんレイン先生はテリィの育ちの良さについて疑問を抱いてはいなかったが、ポニー先生よりも心配性な性格が、紳士は必ずしも聖者ではないということを忘れさせなかったのだ。
しかし二人がポニーの家に戻ってきたときにキャンディの目を見て、レイン先生は胸を撫で下ろした。キャンディを赤ちゃんの時から知っている鋭い目を持つレイン先生には、その娘の動作を見れば何か間違ったことが起きたかどうかわかるのだった。そのような状況を把握しているテリィは、何の隠し事もなくキャンディの先生たちの目を見られることに安堵し誇らしさを感じた。
大人たちの問題や心配ごとをよそに、ステアはおもちゃの車とぬり絵の本が一度に手元に戻ってきたことに大喜びだった。テリィのレンタカーはまだ山小屋に停めてあったので、ステアには単純に《魔法》が車を元の大きさに戻したとしか思えなかったのだ。大きくなってしまった車は大人しか運転できず、小さい車で遊ぶ方がよほど楽しかったので、ステアは車が元の大きさに戻ってもがっかりしなかった。
その日は日曜日だったので、教会に行くために続きの会話は後回しとなった。毎週日曜の正午になると、地元の神父さんがポニーの家の住人のための特別な礼拝に来てくれていた。セントポール学院以来ミサに出席したことがなかったテリィには、これはやっかいな問題だった。国教忌避者(訳者注*英国国教会に服従せずカトリックの信仰を守った者)の家の出身として、テリィはローマンカトリックとして育てられたが、父の家を出てからは宗教的な儀礼から遠ざかって生きてきたのだ。テリィは無神論者でも不可知論者でもなかったが、伝統的な形式での精神活動は彼の得意分野ではなかった。人生に関する個人的な物の見方があるにせよ、もしキャンディと結婚するとなれば伝統的な宗教儀礼に対する寛容が必要になることもテリィにはわかっていた。長年の間礼拝を怠ってきたにもかかわらず、ポニーの家でのミサへの初参加をテリィはかなり上手くこなした。
ミサの後の昼食の席でキャンディとテリィが二人の婚約の報告をすると、先生たちはもちろん喜んで祝福した。特に二人の復縁を応援し仲介役をしてきたポニー先生は、自分の果たした役割に満足して大いに喜んだ。レイン先生はより控えめな表現で喜びを示したが、ポニー先生と同じくらい二人の幸せを祝っていた。ステアには結婚が何を意味するのかわからなかったので、大人たちが説明しなければならなかった。結婚の祝宴が終わったらテリィは家族の一員になるのだとキャンディが言うと、その子はキャンディとテリィを何度か代わる代わる見て口を開いた――
「ぼくのおにいちゃんになるの?」 テリィを見てステアは聞いた。
「ちがうわ、ステア。テリィはあなたのおじさんになるのよ」 キャンディが説明した。
「G(ジー)おじちゃん!」 ステアはトレードマークの笑顔を見せてやにわに言った。
「きみときみの青い車がおれたち二人にもたらしてくれた幸福を考えれば、おれのことを何とでも呼んでくれて構わないよ、小さな発明家さん」 その子をひざの上に乗せながらテリィは返事をした。
キャンディはテリィとステアの間に奇妙な絆が生まれているのを見ながら、アーチーがこのことをどう思うだろうかと考えていた。しかし物事をあまり深刻にとらえない気性から、キャンディはため息をついてただ最善を願うことにした。
その夜アルバートさんから電話があり、翌日に到着すると知らせてきた。昨日の悪天候にもかかわらず列車は通常通りに運行していて、22日にはポニーの家に着けると予測したのだ。ポニー先生は、今回は電話の最中にテリィがまったくたじろがなかったことに気が付いた。キャンディから結婚の約束を得たことで、彼女の愛情を確信できたのだろうとポニー先生は考えたが、それでもテリィの落ち着いた表情にごまかされてはいなかった。年寄りの知恵で、男性の嫉妬心が一晩では消えないことくらい十分承知していたのだ。しかもポニー先生はキャンディの気性もわかっていたので、キャンディの独立性とテリィの独占欲の衝突を乗り越えるために、二人はこれから大変な努力をしなければならないだろうと見通した。それでも、長い時間と別離の試練を乗り越えた二人の愛が、この弱点を同じように乗り越えさせてくれることを願っていた。

アルバートさんは約束に忠実に翌日の11時にポニーの家に到着し、そこにテリィがいたことに嬉しい驚きを得た。久しぶりの再会にお互いを確認し合いお決まりの挨拶を交わすと、テリィとアルバートさんは昔のように自然に会話を弾ませていた。最愛の男性二人が仲良くしている姿を見て、キャンディはこれ以上ない喜びを感じていた。
しかし子どもたちが起きていて新しい冒険を飽くことなく探している間は、ポニーの家では大人たちの会話は長く続かなかった。アルバートさんは子どもたちの大のお気に入りで、午後から夕方の間中ずっと、事実上子どもたちに拉致されていた。アルバートさんが子どもたちを構ってくれている間、他の大人たちは自分等の仕事に取りかかれるのがありがたかった。そのためテリィがアルバートさんと真剣な話をする静かな時間が持てたのは夜遅くなってからだった。
薄暗い居間でアルバートさんがコーヒーを飲みながら静かな時を楽しんでいると、テリィが来て横に座った。
「今日は大活躍でしたね」 テリィが口火を切った。
「からかうもんじゃないよ、テリィ。今日でぼくはもう若くないことを痛感したよ」 アルバートさんはコーヒーカップを持ちながらクックッと笑った。
「ぼくには昔と変わらないように見えますよ」
「でもきみには同じことは言えないなぁ。最後にぼくがきみに会ったのは、きみがまだ16才の少年の頃だった。背も今よりずっと低かったし痩せていたからね。きみの変化を見て、それでもぼくがまだ自分のことを若いと感じられると思うかい?」
「それじゃあこれからぼくが言おうとしていることも、あまり助けにはならないですよ」 テリィは眉を持ち上げながら予告した。
遅かれ早かれ真剣な話になるだろうと予想していたアルバートさんはテーブルにコーヒーカップを置いて言った。
「何なりと聞こうじゃないか」
「あなたは今朝ぼくがここにいることにあまり驚いていないように見えました」 アルバートさんの訳知り顔を見て、テリィは自分の洞察が間違っていなかったことを理解した。「ぼくたちは長い間会っていなかったけれど、あなたにはぼくのことが手に取るようにわかるみたいだ。だから、もしぼくがキャンディとの結婚を許可してほしいと願い出ても、あなたを気絶させるようなことにはならないだろうと思いました」
「きみはぼくに許可を求めているのかい?」 アルバートさんは頭を傾けて聞いた。
「はい」
「きみが結婚したいというその女性は、すでにきみの申し込みを承諾したと思うが……」
「はい、承諾してくれました」 嬉しさを隠しきれずにテリィは答えた。
「もし二人がそうすると決めたのなら、ぼくだけじゃなく世界中の誰にも邪魔することはできないよ。きみたちは婚約したんだ」
「でも、あなたは賛成してくれますよね?」 テリィは心配そうに聞いた。
「もちろん賛成だよ、大ばか者!」 アルバートさんは笑った。「実際のところ、ぼくはキャンディの相手が他の男じゃなくきみでよかったと思っているんだ。きみ以外の人間に、あの勇ましいキャンディを操縦できるとは思えないからね。それに正直に言えば、きみを操縦できるのもキャンディしかいないと思っているよ、テリィ。おめでとう!」 アルバートさんは愛情を込めてテリィの背中を軽く叩きながら付け加えた。
「で、結婚式はいつ頃を予定しているんだい?」 アルバートさんはまだ中身の入ったコーヒーカップを再び手に取って聞いた。
「2、3週間以内には」 テリィが簡潔に答えた。
アルバートさんはカップから目を上げて、テリィを意味ありげにじっと見た。
「なぜそんな急に?」
「心配しないでください! 誓って間違ったことは何も起きていませんから」 アルバートさんが疑念を抱いたのを理解してテリィは言った。「ニューヨークとここは長い婚約期間を設けるには距離が離れすぎているし、ぼくたちは以前同じことを経験しているからもう二度と繰り返したくはない。ぼくは自立した自由な立場の男で、キャンディも十分大人で、そしてあなたの承諾もある。待つ必要はどこにもない」
アルバートさんの肩に入っていた力が抜けた。
「そんなに急な挙式では多くの人に知らせることもできないし、立派な式を準備することもできないことはきみも理解していると思うが」 アルバートさんが警告した。
「ええ、実はぼくたちはこじんまりした静かな式を挙げたいと思っています。最低限必要なものとして、母がぼくの出生証明書を郵送の代わりに持参して来てくれると電話で約束してくれました。ぼくが式に出席してほしいのは母だけです。キャンディはあなたとコーンウェル夫妻とマーチン先生がいてくれればいいと言っています。他の友人たちにも式に出席してもらうには時間が足りないことはわかっていますから。式はここの教会で挙げることを考えています。だから、準備といってもそんなところなんですよ」
「それじゃあきみたち二人は世界中に衝撃を与えるつもりなんだね」 アルバートさんはいたずらっぽい光をその青い瞳に浮かべて言った。「世間は噂でもちきりになるだろうし、ぼくのいとこたちは愕然とするだろうし、新聞にはあることないこと書かれるだろうし……ぼくの叔母がこの話を聞いてどんな顔をするか想像がつく……こりゃいいな!」
二人の男性はこの考えに笑った。
それから二人はしばらく話を続け、結婚式の前にキャンディとテリィが二人でシカゴへ赴き、いくつか事務的な手続きをすることで合意した。アルバートさんは二人がそのまま大晦日をシカゴの邸宅で過ごせば、一族の長老たちにテリィを紹介するまたとない機会になるだろうと提案した。テリィはその提案にはあまり心躍らなかったが、キャンディの親せきたちから永久に逃げているわけにはいかないこともわかっていた。アルバートさんがシカゴに戻る前にキャンディにこの計画について話をすることになった。
あと数分で深夜の鐘が鳴るころに、アルバートさんはそろそろ休息が必要だと気づいた。翌日にはアリステアを連れてシカゴに戻ることになっていたので、その子のとめどないおしゃべりに付き合うために英気を養っておかねばならなかったのだ。
「アルバートさん」 寝室に戻ろうと行きかけたアルバートさんをテリィが呼び止めた。
「なんだい?」
「お父さんと呼んでも構いませんか?」 唇を曲げて半笑いを作ってテリィが尋ねた。
「お父さんなんて呼んでみろ、きみをコテンパンに叩きのめすぞ」 アルバートさんは冗談を言い返したが、子どもたちの相手をしていて痛めた背中を感じて付け加えた。「でもそうするとぼくの背中が大変なことになる」
「わかりました。じゃあこれからもアルバートさんと呼ばせてもらいます」 テリィはクックっと笑いながら話を締めくくった。

テリィのクリスマスの思い出は、ほとんどがどんよりとしたものだった。子どもの頃は、父が貴族の親族のために大きなディナーパーティを開いていたのをぼんやりと覚えている。子どもたちは祝宴に参加できず、テリィは夜遅くにこっそり部屋を抜け出して、階段の上から優雅な招待客たちを眺めていたかすかな記憶がある。そして部屋に戻ると、クリスマスプレゼントは何かと想像したり、父が一緒に遊んでくれるのを期待したりしながら一晩中目を覚ましていた。なぜならクリスマスの日の朝は、父が注意を向けてくれる数少ない機会だったのだ。しかしそれから公爵夫人に子どもができると、彼女は家族の輪からテリィを事実上締め出すためにあらゆる手を尽くした。そのため少年テリィは、幾度ものクリスマスイブをセントポール学院の寮に閉じ込められたままで過ごした。
その後俳優になってからというものクリスマスは仕事を意味した。マーロウ母娘と暮らしていた時も、テリィはクリスマスに普通の人が感じるような気持ちを得られなかった。3人は同じ屋根の下に暮らしていたがテリィにとってそこは自分の家ではなく、家のない男がどうしたらクリスマス休暇を誇らしく迎えられるというのだ。母親にしてもその時期は冬のシーズンで自分と同じようにずっと仕事をしていた。だからテリィはクリスマスを本来の意味で経験したことがなかったのだ。
そして今、人生で初めてテリィはこれまで物語の中でしか読んだことがなかったクリスマスのお祝いを目撃していた。詰め物をしたおいしい七面鳥の丸焼きや、居間のあちこちにぶら下げられた靴下や、昔ながらのポップコーンのクリスマスツリー飾りは確かにあった。けれど、祝いの中心にあるのはそれらの飾りや食事やプレゼントではなく、この家に満ちている深い真の愛情だった。
ポニーの家の子どもたちが一人一人愛情に満ちた扱いを受けているのを見て、テリィはキャンディがどのように思いやり深い心を育んだのかが理解できる気がした。自分の孤独な心が花に引き寄せられる蜂のようにキャンディに魅かれたのも当然のことのように思えた。こうしたことを考えながら、テリィはこのような温かさが自分の人生にもたらされたことと、そしてこれからやってくる毎年のクリスマスへの新たな期待に胸が高鳴った。
クリスマスイブの従来の夕食の後には全員がクリスマスツリーの周りに集まって一つ二つお話を聞き、その夜はお開きとなった。クリスマスイブには早い時間に寝床に入り、翌朝クリスマスプレゼントをみんなで開ける行事のために休息をとるのがポニーの家の慣習だったのだ。子どもたちがそれぞれの部屋に戻される時にテリィがキャンディに視線を投げかけるとキャンディも無言でそれに応えた。数時間後みんなが就寝の床についてから、キャンディとテリィは寝る前に二人きりの時間を過ごすために居間で再び落ち合った。
キャンディが居間に入ると、テリィは木製のマントルピースに寄りかかりながらその上に飾られた写真を見ていた。ポニーの家出身の子どもたちや若者たち、そして大人たちまでの笑顔の写真がいろいろな大きさの写真立てに収められ暖炉を飾っていた。その写真の中に明るい緑の目をした長い金髪の髪の美しい少女の顔を見て、テリィの心臓は一瞬止まった。
「この写真はセントポール学院の時に撮ったものだろ?」 テリィは背中にキャンディの気配を感じて聞いた。
「すぐにわかるでしょ。制服を着ているから」 キャンディは12年前のアニー・コーンウェル――当時はアニー・ブライトンだったが――とパトリシア・オブライエンと自分の写った写真を愛おしそうに見ながら言った。
「このふとったのはどうなった?」
「パティのことね?」 誰彼かまわずあだ名をつけるテリィの習癖にあきれた表情でキャンディは言い直した。「パティは戦争中には何年かシカゴに住んで先生になる勉強をしていたの。卒業後は市内の学校で働いていたのだけど、3年前にもう一度勉強を再開することに決めてオックスフォード大学に入学申請をして受け入れられたのよ。今はオックスフォードで文学の博士課程の勉強をしているわ」
「確かに彼女は本好きなタイプだったっけ。付き合っている男はまだいないのかい?」 テリィは興味を持って聞いた。
「いないわ……」 キャンディは辛そうに返事をした。「パティの心はきっとまだ喪に服しているのよ」
「すべての希望が無くなっても死ぬまで失われない愛もある」 テリィはキャンディの手に口づけをすると、「それで思い出したけど……」と言ってキャンディをクリスマスツリーの隣に置かれたポニー先生の肘掛け椅子に座らせてから言い足した。「おれからのクリスマスプレゼントを今きみに渡そうと思うんだ」
「でもまだクリスマスじゃないわ」 キャンディは弱々しく反論したが、自分だけに向けられるテリィの楽しげな笑顔で見つめられると、彼には逆らえないこともわかっていた。
「もう数分でクリスマスだよ」 テリィは時計を指さしながら言うと、キャンディの足元の寄せ木細工の床に座った。
「わかったわ。あなたのお望み通りにするわよ」 キャンディは結局テリィに従うと、体を曲げて長方形の箱を拾いあげテリィに手渡しながら言った。「それじゃあ、メリークリスマス、テリィ」
キャンディが自分のためにプレゼントを用意していたことに若干驚いて、テリィは黙ってその箱を受け取った。
「開けないの?」 キャンディは瞳を輝かせながら聞いた。
「これを開けても爆発しないだろうね?」 テリィは箱を怪しそうに見るふりをしながらからかった。
「危険を冒さなければ一生中身を見られないわよ、弱虫さん」
キャンディの言葉にけしかけられてテリィはやっと包みを開き、プレゼントが出てくるとしばらくそれを見つめた。それは本物の古い重厚な革表紙の本だった。
「『トーマス・ハンマー編集シェークスピア史劇』!」 テリィは驚きと共に声に出してタイトルを読んだ。
「それしか手に入らなかったの」 キャンディはまるで本当は別のものを贈りたかったのにというように肩をすぼめて言った。
「これしか手に入らなかっただって? この本は170年以上も前のものだ!」
「正確には180年前よ」 キャンディは本を開いて最初のページに刻まれている1744年という日付を指して言った。「でもシカゴのお店の店員さんは、あなたがいるストラスフォードのようなプロの劇団では『ファースト・フォリオ』(訳者注*1623年に出版されたシェークスピア戯曲の最初の作品集)のテキストしか使わないと言ったわ。この本は編集されたものだから読書室の飾りにしかならないわね。本当は『ファースト・フォリオ』のオリジナルが手に入れられたらよかったのに」 キャンディは少しがっかりした調子で言った。
テリィはキャンディの素人の意見をおもしろがった。
「きみが英国図書館に泥棒に入る時はぜひ事前に教えてくれよ。おれはきみを刑務所から逃がす方法を考えておくからさ……もちろんきみが捕まったらの話だけどね」 テリィは笑った。
「それじゃあこれは気に入らなかったのね?」 キャンディは口をとがらせて聞いた。
「冗談だろ? 物凄く気に入ったよ」 テリィはその古い本をじっと見ながら心から言った。「これと同じような古い編集のコレクションを始めたいと前からずっと思っていた。ただこういった希少な本を探す時間がなかなか見つけられずにいたんだ。これはファースト・フォリオじゃないかもしれないが、それでもかなり高価だったはずだ。この本はまさに宝だよ。ここまでしてくれる必要はなかったのに」
「わたしは滅多に買い物を楽しまない家督相続人なのよ。たまにちょっと贅沢するくらいで誰にも文句は言われないわ……気に入ってもらえてよかった!」 テリィがプレゼントを喜んでくれたことがわかってキャンディは笑顔になった。
「ありがとう、ラヴ(愛しい人)」 テリィからそのような愛情のこもった表現で呼ばれることに慣れていないキャンディは、顔を真っ赤にした。その頬の色はドレスの薄いピンク色でより一層引き立った。
「もしよかったら、これと同じ編集版の全集をこれから集めましょうよ」 テリィに優しく手を撫でられて興奮してきた自分を鎮めようとキャンディは提案した。
「それはいい考えだ! ただ……」 頭の中に疑問が生じてテリィは一旦話を止めた。「これは急に思い立って買えるようなプレゼントじゃあない。クリスマスを一緒に過ごすことはわかっていなかったのに、どうしてこんなものを用意してくれていたんだい?」 テリィは理由を知りたくて聞いた。
「先月シカゴに行った時にあなたに何か特別なものを用意しようと決めたの。クリスマス休暇の間にあなたに会えるかどうかはわからなかったけど、遅かれ早かれまた会えるとは思っていたから」
テリィはしばらく黙っていた。自分がキャンディのことをいつも考えているのと同じように、彼女も自分のことを考えていてくれたのだという思いが心を溶かした。奥深い感情を言葉で表すことが苦手だったテリィは、キャンディがその感触から自分の思いを理解してくれることを願いながら彼女の手を握り続けた。
その瞬間時計が午前12時の鐘を鳴らした。
「きみのプレゼントも開けてみるかい?」 テリィが促した。
「何かしら?」
「見てのお楽しみだよ」 クリスマスツリーの下に他のプレゼントに紛れて隠しておいた質素な赤い包みをキャンディに手渡しながらテリィは言った。
その大きさと形を見てこれも本だと予想して、キャンディは笑顔を浮かべた。そして、これがテリィからもらう最初のプレゼントだと思った――もちろんピッツバーグで贈られた花束を別にすれば、だが。
包みを開けてバーガンディ色のハードカバーの本が出てくると、キャンディは感激した。――Poems in two volumes by William Wordsworth(ウィリアム・ワーズワース『二巻組詩集』)――と金色のエンボス文字でタイトルが書かれていた。
キャンディは本に栞が挟んであるのに気が付くと、意図的にそこに挟まれているのだろうと考えそのページを開いて声に出して読み始めた。
谷また丘のうえ高く漂う雲のごと、
われひとりさ迷い行けば、
テリィもキャンディに加わり、その詩を最後まで一緒に暗唱した。
折りしも見出でたる一群の
黄金(こがね)色に輝く水仙の花、
湖のほとり、木立の下に、
微風に翻りつつ、はた、踊りつつ。
天の河(あまのがわ)に輝やきまたたく
星のごとくに打ちつづき、
彼らは入江の岸に沿うて、
はてしなき一列となりてのびぬ。
一目にはいる百千(ももち)の花は、
たのしげなる踊りを頭にふる。
ほとりなる波は踊れど、
嬉しさは花こそまされ。
かくも快よき仲間の間には、
詩人(うたびと)の心も自ら浮き立つ。
あれ飽かず見入りぬ――されど、
そはわれに富をもたらせしことには気付かざりし。
心うつろに、或いは物思いに沈みて、
われ長椅子に横たわるとき、
独り居(ひとりい)の喜びなる胸の内に、
水仙の花、しばしば、ひらめく。
わが心は喜びに満ちあふれ、
水仙とともに踊る。
(訳者注*ウィリアム・ワーズワース『水仙』田部重治訳/岩波文庫/ワーズワース詩集より)
二人が最後の詩句を朗読し終えると、あたりは神秘的な静けさに包まれた。キャンディの耳にはまだその詩の言葉が残っていた。
「覚えているかい、キャンディ?」 テリィが柔らかな囁き声で聞いた。「3月も近くなった昼休みに、きみはおれがいることに気づかずに学院の草原を駆けていて、おれにつまずいたんだ」
「覚えてるわよ!」 キャンディはテリィが口にしている出来事を思い出して大きな声で言った。「地面に寝ているあなたが水仙のつぼみの間に隠れていて見えなかったの。わたしはものすごくみっともない転び方をしたんだわ」 キャンディは自分のことを笑った。
「おれも水仙の香りに心を奪われていてきみがやって来るのが見えなかった……おれは……おれはきみのことを考えていたんだ」 テリィはその当時の本当の気持ちを思いきって告白した。「そうしたらきみがまるでおれの思考に呼び起されたように現れた。おれはきみに会えて嬉しかった……特におれの腕の中に飛び込んで来た時にはね」
「あなたがわたしに会えて嬉しかったなんて知りようがなかったわ。だってあなたが最初にしたことと言えばわたしのぶかっこうをあざ笑うことだったわ……わたしに言わせればとっても生意気にね。それに、ケガをしたあなたがわたしの部屋に倒れ込んで来てから一月も姿を見ていなかったから心配していたのに、そのことを言うとあなたはわたしを冷たくあしらったのよ」 キャンディはふくれた。
「それできみは怒っておれに反撃したわけだ」
「わたしが?」
「そうさ、きみはこう言ったよ『親切の押し売りなんかする気はありませんからね! 売ってくれって言われても、こちらこそ、ごめんです!』」
「あなたも腹が立った?」
「いいや、その反対さ、キャンディ。おれには世界が輝いたようだったよ。その日、きみはおれのことをテリュースではなくて初めてテリィと呼んでくれたんだ。おれは嬉しかった。それ以来、水仙を見る度に、あの時のことやきみがおれをテリィと呼ぶ声を思い出して胸の鼓動が早まるよ」
キャンディは、テリィの瞳が晴天の朝の海波のように濃青色に変わっていくのを見た。感情の高まりで喉が渇き、一瞬催眠術をかけられたようになった。テリィはその時は自分に触れてもいなかったのに、言葉を口にするだけで自分をこんなに落ち着かない気持ちにさせてしまう力を持っているのだ。――これは注意が必要だわ……! キャンディは思った。
「水仙は復活の花といわれているのよね」 キャンディは本を閉じながらかすれた声で言った。「……毎年イースターの時期になると花を咲かせるから。……あなたがピッツバーグで水仙の花を届けてくれた時……わたしは……もしかしたらこれは……わたしたちの愛が再び花開く証ではないかと思ったの」
「そのつもりだったさ!」 テリィはそう言うとポケットに手を入れて小さな箱を取り出し、それをキャンディの手の平に乗せた。「これはきみのだ」
リボンがかけられた見覚えのある明るい青い箱を見て、キャンディにはその中身が何かの予想はついた。ただ、その箱の角が少しよれて丸くなっているのに気付いて興味をそそられた。
ぎこちない手つきでリボンを外して箱を開けると、そこにはティファニーのクラシックな立て爪のリングに乗った1カラットの丸いダイアモンドが光り輝いていた。
「おれに金があればもっと上等なものを買えたんだけど、おれはまだ俳優の仕事を始めたばかりだったから」 感情が高ぶり、テリィははっきりしない声で述べた。
「俳優の仕事を……始めたばかり?」 キャンディはその意味を理解しようとしてテリィの言葉を繰り返した。それからもう一度箱をよく見てみると、リボンは本来の白さではなくなっていて、ティファニーブルーのターコイズも若干色あせていることに気が付いた。「それって……この指輪は……」
「きみが『ロミオとジュリエット』の初演を見にニューヨークに来る前に買ったものだ」 テリィは説明した。「初演の日の夜におれはきみを帰さないつもりで……結婚を申し込むつもりでいた。でもすべてが狂ってしまった。それでもおれはこの指輪を返品することができなかった。おれがストラスフォードを辞めてウィスキーを買う金が必要だった時にもこれだけはどうしても売る気になれなかった。おれはこの指輪を手元にずっと持っていた。ただ、今この指輪をきみに贈るべきか、あるいは新しい指輪を買おうかどうか迷ったんだ。サイドストーンのついたものとかダイアモンドバンドの指輪とか……おれの心のただ一人の女性に相応しいものを贈りたかった……これではシンプルすぎるから……」
「この指輪は完ぺきよ、テリィ!」 キャンディは目に涙をいっぱいためながらテリィの言葉を遮った。「これ以上のものは望めないわ」
そしてキャンディがその指輪を嵌めようとして箱から取り出すと、何かに気づいて動きが止まった。リングの内側のティファニーのトレードマークの横に刻まれた文字が目に留まったのだ。そこにはシンプルにこう刻まれていた――
an ever-fixed mark
(訳者注*シェークスピアのソネット集116番の有名な一節からの引用 日本語では「盤石不動の航路漂」(平井正穂)などの訳がある)
キャンディはその引用が何かを認識すると涙の中に笑顔を見せた。 キャンディが動けなくなっているのを見て、テリィが手をとって彼女の指にその指輪を嵌めた。
「11月にきみと再会して一緒に踊った時……おれは……それまではきみにゆっくりと時間をかけて結婚を申し込もうと思っていんだが、おれにはもうそんなに長く待てるだけの忍耐がないということがわかった。それで家政婦に連絡を入れて、この箱を送ってもらっておいたんだ。おれは、できるだけ早くきみに妻になってくれと言おうと決めていた。……だからおれはここに来たんだ……メリークリスマス、キャンディ」
「これ以上に素敵なクリスマスはないわ」 キャンディはそう言うとテリィが座っている床にひざまづき、彼の唇に深い口づけをした。
真心と真心との交わりに、よけいな異議を
挟むのは慎んでもらいたい。相手の心が変わるにつれて
変わるような、相手の心が離れてゆくに従って
離れてゆくような、――そんな愛は愛ではない。
言語道断な話だ! 愛は、嵐にあってもびくともしない
まさに盤石不動の航路漂なのだ。
愛は、大海をさすらう小舟にとってはまさに北極星、
高さは測りえても真価は測りしれないものなのだ。
愛は、「時間」に弄ばれる道化ではない――たとえ、
その曲がった鎌で薔薇色の唇や頬が台無しにされてもだ。
慌ただしく月日がたっても聊(いささ)かも変わらず、世界の終焉の
間際まで毅然として堪えてゆくもの、それが愛なのだ。
もしこれが誤りで、私の考えが嘘だとしたら、――私は詩を
書かなかったも同然、この世に愛した者がいなかったも同然なのだ。
――ウィリアム・シェークスピア
(訳者注*ウィリアム・シェークスピア『ソネット集第116番――真心と真心との交わりに』平井正穂編/岩波文庫/イギリス名詩選より)
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when alteration finds,
Or bends with the remover to remove :―
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests, and is never shaken ;
It is the star to every wondering bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come ;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out ev’n the edge of doom :―
If this be error, and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.
――William Shakespeare

*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします















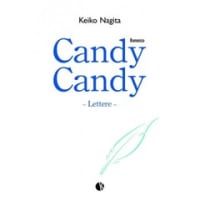









大好きな花です。
次の頁も ワクワクして待ってます。
いつもお返事ありがとうございます。
キャンディとテリィの幸せ秒読みって感じで、ついムフフと笑ってしまいます。幸せのおすそ分けをもらってる気分です(^ω^)
キャンディ良かったね、より今の章がテリィ主観のせいもありますが、テリィ良かったね!おめでとう!って言ってあげたいです(^ω^)
更新楽しみにしすぎて、最近一日一回クリックしておりました!
続きもまってます♪がんばってください!!
今1頁目の後半を更新しましたので、どうぞ楽しんでください
そうですね……テリィ……このファンフィクのテリィには子供っぽさや男っぽさや大人の部分やいろんな要素が込められていて、翻訳していてもほんとに愛おしくなってしまいます
やんちゃな感じはマンガのテリィよりアニメのテリィのイメージが作者さんの中で濃く影響しているように思うので、前にもコメント欄に書きましたがテリィの台詞はできるだけ一度テリィのアニメの声(富山敬さん)に変換してみてます。
第7章もどうぞお楽しみください
良かったです(^ω^) このまま幸せになるんでしょうか!?キャンディのことだから、もう一波乱とかあったりするんでしょうか!?どきどきです。
二人の今後……どうでしょうか。この頁のシェークスピアのソネット116番をじっくりお読みください
子どもの時はポニー先生やレイン先生の気持ちなどはスルーしてしまっていたように思いますが、自分が親になった今は先生方の場面にも心に響く時があり、あらためて奥が深い物語なんだなって感動しています。これからも翻訳、よろしくお願いします
ファイナルストーリーの中でもキャンディが顔も知らない本当の両親にポニーの家に捨ててもらったことを感謝しているのが泣けました
先日妹から言われるまでまったく忘れていたのですが、子どものころ親が構ってくれなくて「こんな家ならポニーの家に捨てられた方がいい」と小学生のブログ主は妹に愚痴をこぼしていたそうです
ポニー先生やレイン先生に共感できるShiho様のお子さんはきっとそんなことは思う必要がないでしょうね。
続きをお楽しみに。
(きっと)外は、夜空の星の囁きさえ聞こえてきそうな静かな夜、日付を越えたクリスマスに(T_T)プロポーズだなんて…(号泣)
今まで読んだ、どのキャンディのその後の物語よりも優しくて愛溢れている様です。
アチコチ宝石みたいな少女時代のエピソードを、散らばせて(*^o^*)
トロけますぅ~トーストの上のチーズみたいに~
こんなに幸せな気持ちで床に入れるなんて♪
ブログ主さま☆ありがとう!
また次の翻訳…楽しみにしてます(o^∀^o)
みなさんいろいろ好みはあるかと思いますが、眼鏡越しのそら様の琴線に触れるファンフィクションをご紹介できてよかったです