キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
食事の後、テリィはアルバートさんのささやかな本棚から本を一冊選び、暖炉の横に座って朗読した。キャンディは寝室から持ってきたシェニール織のブランケットを足にかけ、テリィの肩に頭をもたれかけていた。
このように何の気兼ねもなく共に過ごす時間は、二人にとってまったく新鮮な経験だった。授業の合間にこっそり学院の森へ脱け出して会っていたのが昨日のことのように思えた。突如として二人は自由で自立した大人になり、世界の片隅に押し留められていた。二人の親密な時間に押し入ってくる人はどこにもいなかったし、誰にも二人を無理やり引き離すことはできなかった――二人を邪魔できるものは何もなかったのだ。キャンディにはこのことがまだ信じられずにいた。顔が赤くなるほどに暖炉の火に暖められながらテリィに寄り添っていると、かつて共に過ごした別の時間を思い出さずにはいられなかった。
「こうしているとスコットランドを思い出さない?」 キャンディはテリィの朗読をさえぎって聞いた。
テリィは本を置き、黙ってキャンディを見た。暖炉のぼんやりした明りの下で、キャンディの瞳は緑の海の中に黄金色が揺れて玉虫色になっていた。
「もちろん」 テリィは同意した。「でもあの頃と今では大違いだ。おれは愚かで未熟な若蔵で、きみをひどく恐れていたのを認めることすらできない高慢ちきだったのさ」
テリィの言葉にキャンディは声を出して笑った。
「あなたがわたしを恐れていたの? そんなこと思いも寄らなかった」 信じられないというようにキャンディは言った。
「おれは真面目に言っているんだよ、キャンディ……きみに対して感じる思いをおれは恐れていた」 本を脇に置きながらテリィは言った。「きみへの思いが大きすぎて自分でもコントロールできなかったから、きみがおれの気持ちを知ってしまったら何が起きるか怖かった。もしきみに拒絶されたら、それまで以上に傷ついてしまうだろうと思っていた。だからおれは冗談を言ってきみをからかったり、時には厳しい言葉できみを突き放したりしていたんだ。でも本当のところは、あの日今みたいに暖炉の火をぼんやりと見ながら、おれはこんなふうにきみを腕に抱きしめたくて仕方がなかった」 テリィはキャンディの頭を優しく胸に抱き、髪に口づけをしながら言った。「おれはそれから何年も、あの日の自分の勇気のなさを後悔したよ」
「でも、そうしたらその時わたしはどう反応していたかわからないわ」 キャンディが言った。
「きみはおれを叱りつけてひっぱたいたさ」 テリィは心から笑った。「今はその悪い癖がなくなったみたいでおれは嬉しいよ、キャンディ」
「お願いだからそれは言わないで! あの時わたしがあんなに厳しい態度をとっていなければ……」
キャンディは途中で言葉を止めた。テリィの表情が急に真剣になり、キャンディはその目に浮かぶ疑問の色を直観的に読み取った。
「今更こんなことを言っても遅いかもしれないけど、あの日のわたしがしたことを謝らせて、テリィ。あなたを傷つけるつもりなんてなかったの……ただあまりにも」 キャンディは言葉を探して目を上げた。「あまりにも突然だったから……それに、わたしもまだ若くて経験がなかったし」
「でもただのキスだよ」 非難じみた声でテリィは言葉を差し挟んだ。
自分が言いたかったことを理解してくれていない様子に少し苛立って、キャンディはテリィを見た。
「テリィ……あれは……あれはわたしのファーストキスだったの。あの時そう言ったのを覚えていないの?」 キャンディは目を伏せながら言った。
テリィの瞳は複雑な感情を宿していた。テリィはキャンディのファーストキスを奪ったのは自分だという密かな優越感を感じてきた。しかし、あの時キャンディに自分とアンソニーを比べられた傷が、本来ならば青春時代の最も甘い思い出になるはずの経験をみじめなものにしていた。あの出来事に正当な理由づけをいくら試みたところで、大人になってからでさえ傷ついた心を完全には癒せずにいた。
「おれには……」 テリィはまだ自分自身の気持ちをどう説明すればいいのかわからなかった。「おれにはかなりな痛手だったよ……おれも衝動的に行動してしまったけど、それはおれの心が言葉にできない気持ちを表現したことだったんだ……でもそれなのに」 テリィは話を一旦止めて空間の一点を見つめた。「それなのにきみはアイツのことを言った……きみはアイツならこんな野蛮なことはしないと言ったんだ」
渦のような感情がテリィの顔に浮かんでいるのを見て、平手打ちよりもあの時に自分が発した言葉が彼を傷つけたのだとキャンディは気が付いた。
「テリィ」 キャンディはテリィの顔を両手で挟んで自分の方を真っ直ぐ向かせた。「テリィ、すまなかったわ。あの時はショックで混乱していて、わたしの言葉があなたを傷つけていることがわからなかったの。わたしはまだ若い女の子で、ファーストキスはもっと後になって、もっと違った状況で経験することを想像していたんだもの。わたし自身の気持ちが不安定で、混乱していて、よくわからなくて……あなたの突然の行動にあまりにも驚いてしまったの。あなたがわたしの中に引き起こしていた感情は、それまで一度も感じたことがなかったものだったから。でもね、テリィ、今のわたしはあの頃のような怖がりで純情な女の子じゃないの。あなたを比べられる人なんてどこにもいないってことをちゃんとわかっているわ。だから許してくれる?」
キャンディの言葉がテリィの耳に優しい夏の風のように染み込んだ。拒絶されたという感情を抱いてきたテリィにとって、自分がほかのどの男性よりも大切だという彼女の言葉は心の傷を癒す薬だった。心の中に自信のようなものが芽生えてくると同時に、テリィは徐々に自分の側の過ちにも気づき始めた。
「きみにもおれの不作法を許してほしい」 返事がないのをキャンディが心配し始めた頃、テリィはやっと答えた。「……おれがもっと優しくキスしていればよかったんだ。でもおれも誰かを好きになるのは初めてのことだったし、きみと同じように無知で混乱していた……それからもちろん、おれがお返しにきみをひっぱたいたのは許し難い行為だった」 テリィはあの時の自分の反応を悔やみながら非を認めた。
「すべてを許したら、そしたら……」 笑顔で答えたキャンディの言葉は新たな口づけでふさがれた。その口づけは、ぎこちなかった二人のファーストキスよりも心地よかった。
「若いって凄まじく最悪なことだよな?」 互いの唇が離れるとテリィは言った。「それでもきみのファーストキスを奪うためならおれは同じことをもう一度するけどね」 テリィは唇を曲げて、彼独特の悪戯っぽい笑顔を見せて言った。
二人は何も言わずにしばらく抱き合っていた。テリィはキャンディの告白によって肥大した自尊心をなだめる時間が必要だったし、キャンディも今の会話で引き起こされた感情を落ち着かせることができた。
しかしながら、テリィの独占欲の強い傾向はこの状況で長く満足していなかった。心がまた別の方向に彷徨うと、体はその考えに緊張した。テリィの胸に頭を預けていたキャンディは、彼の心臓のリズムが変化したのを感じた。
「キャンディ……」 テリィはこれから言おうとしていることに不安を感じながら言葉を発した。
「なぁに?」
「こんなことを聞いていいのかわからないが……」
キャンディはテリィの腕の中から少し起き上がり、いぶかしげな目で彼を見た。
「わからないが……なに?」 キャンディはテリィを促した。
「いや……忘れてくれ。大したことじゃない」 テリィは気を変えた。
「テリィ、だめよそんなの。何か聞きたいことがあるのなら聞いてよ」 キャンディは主張した。
テリィはまだ迷って口を結んでいたが、しばらく考えてやはり聞いてみることにした。
「きみはずっとおれのことを愛していたと言ってくれた……おれにとっては期待すらしていないことだったが……それでもおれにはまだ知りたいことが……」 テリィは再び言葉を止めた。「おれたちが別れていた間……きみは誰か他の人と……もしそうだったとしてもおれには何も言う資格はないけれど……ただおれは……」
「テリィが聞きたいのは、別れた後にわたしにボーイフレンドがいたかってこと?」 キャンディはテリィの言葉を正確に言い直した。
「まぁ……そういうことだ」 返ってくる答えに緊張しながらテリィは顔をそむけて相槌を打った。
普段は深刻そうなテリィの目にこのような子供っぽい表情をかつて見たことがなく、キャンディはこの会話を楽しんでいた。
「決まったボーイフレンドはいなかったわね」 キャンディは一つ一つの言葉を慎重に吟味しながらゆっくり話し始めた。「アニーが紹介してくれた男性にエスコートされて舞踏会に何回か行ったし……それから確か……デートもしたわよ」 キャンディはテリィの反応を見るために言葉を止めた。テリィは一言も発することなく目をそむけていた。「でもどの男性とも真剣な交際には発展しなかったわ。アニーはそのことでとても苛立っていたけど、わたしには居心地がよくなかったのよ。その人たちがわたしに興味があるのか、それともわたしが相続する遺産の方に興味があるのかもわからなかったし、それに……わたしにはどうすることもできなかった……出会う人すべてをあなたと比べてしまうのよ……あなたと比べてしまうと、誰もかれも色あせて見えたわ」 キャンディは手を伸ばしてテリィの手を優しく撫でた。
胸の緊張が緩むと、テリィはキャンディの愛撫をもっと感じられるように手のひらを開いた。
テリィは言葉を発することができなかった。互いの指と指を絡ませながら、キャンディは落ち着かない様子でまばたきをするテリィを黙って見つめた。テリィの目には喜びの光が輝いていたけれど、唇は、次に言うべき言葉を探すように何かに躊躇している様子を表していた。
「おれはずっと」 テリィがやっと話し出した。「おれはずっと、きみを永久に失ってしまったと思っていた。一年が過ぎるごとに、おれは……きみがおれのことを忘れて、いつか誰かが……誰かがきみの心を勝ち取るだろうとあきらめかけていた。……理性のレベルでは、それが最も自然なことで、望ましいことなのだと……少なくともおれたち二人のうち一人は幸せになれることに満足するべきだとわかっていた。でも……きみが誰か別の男といることを想像する度に……おれの心は限界に達して逆上していた。おれはそんな時の自分を憎んでいた。他の女性と婚約しているこのおれがそんなことを思うのは利己的で一方的すぎると思っていた。……それでも、おれには嫉妬に駆られる感情をどうにもできなかった」 テリィは、熱望に満ちた深い感情を目に浮かべて言った。
キャンディはテリィのそばに行き、両手をその首に回して右頬と右頬をくっつけた。キャンディは何も言わなかったが、その抱擁の温かさでテリィは自分の恐れが無意味だったということを理解し、心臓の鼓動が速度を緩めた。しかししばらく経つと、テリィはその清廉高潔な精神で、二人の過去の話題をまだ終わらせるべきではないと感じ始めていた。
「今度はおれの方がきみに説明すべきことがある」 テリィは長椅子に背中をもたれ、キャンディを腕に引き寄せながら続けた。
「説明すべきこと?」 キャンディにはテリィが何を言おうとしているのかわからなかった。
「おれはきみに過去のことを聞いた。だからおれも正直になる必要があると思う。おれは……おれは何年も別の女性と同じ家に暮らしていたから……説明が必要だと思う」
「必要ないわ」 キャンディはその話題に触れることに気が進まずに、小柄な体をテリィにすり寄せながら言った。
「たぶん、おれの方が胸のつかえを吐き出してしまいたいんだ。不快な話だったとしても聞いてくれるか?」 テリィは二人の間の障壁を完全に失くすためには、これからする説明が不可欠なことを内心では確信しながら強く言った。
キャンディは一瞬迷ったが、テリィの決意が固いのを見てあきらめた。
「どうしてもというなら、いいわ」 キャンディは頭をテリィの肩にもたれながら承諾した。
「おれは……ロックスタウンでの出来事の後、旅費がたまるとすぐにニューヨークへ戻った。ショービジネスでの仕事を探しながら、生活費を稼ぐためにいくつかつまらない仕事をした。おれには先例があったから、ショービジネスの世界への復帰はたやすいことじゃなかった。ほとんどの舞台監督は、大した理由もなく舞台を放棄したという評判を持つ若い役者と仕事をするリスクを負いたがらなかった。小さな役にありつくまでに1年かかったよ。まるで一から出直すようなものだったけど、おれには自分の本来の道に戻ったということだけが大切だったんだ。その時に仕事をした劇団はストラスフォードの半分の評価もなかったけど、それでもちゃんとしたプロフェッショナルな劇団だったし、何よりもロックスタウンのどさまわりの芝居小屋とは全く違っていた。そしておれはニューヨークへ戻ってから初めてスザナの元を訪れた。彼女は二人の関係をもう一度取り戻すことに以前にも増して積極的だった。彼女に普通の女性では考えられないような寛大さや物わかりのよさを示されて、おれは正直ひどく罪の意識を感じた。しかも、おれは彼女に一度も愛していると言ったことがなかった。おれが彼女に示すことができたのは、愛のない関係の中で約束を果たすという決意だけだった。そして結婚の話をする前に、経済的な基盤が取り戻せるまで時間がほしいとおれは彼女に頼んで、彼女もそれを承諾した」
「俳優として仕事を再開してから10か月が過ぎた頃にロバート・ハサウェイから話がしたいというメッセージが送られてきた。おれがどれだけ嬉しかったかはきみにも想像がつくだろう。会いに行くと、団長は以前のように全面的に受け入れてはくれなかったし優しくも協力的でもなかった。団長はまだおれに対して疑念を抱いているのがわかったが、それでも次のシーズンに役を与えてくれた。おれは喜んでその役を受け、今回は団長をがっかりさせないと自分に誓った」
「もちろん団長がくれた役は主役ではなかったけれど、そんなことは関係なかった。おれは再びブロードウェイで第一級の劇団で仕事をしていたんだ。もしそのことが、スザナとの約束を果たす時が来たということを意味していなければ、おれは完全に満足だったよ。おれは不本意ながらも今回は約束を守ってスザナに結婚の申し込みをした。驚いたことに、その時は彼女の母親が出てきておれが娘により良い待遇を与えられるようになるまでもう少し長い婚約期間を置くべきだと言って反対した。スザナは母親の考えに賛成はしていないようだったが、それでも最終的にはその意見を受け入れたんだ。それで結婚の日取りを翌年1918年の冬に決めて、その間スザナは治療を受けて義足を試すことで合意した。もちろんおれが全面的に経済的な援助をした」
「その時からおれの生活は仕事とスザナを中心に回った。おれは毎日ブルックリンまでスザナと彼女の母親を迎えに行き、マンハッタンのセントビンセント医療センターまで送り届けてから仕事に向かった。そして仕事が終わるとまた彼女たちを家まで送り届けた。時には彼女たちと食事をしてから深夜の稽古に戻ることもあった。それなりに疲れる日課だったが何とかこなしていたよ。きみとおれが別れてから3年が経ったころ、遂にロミオとジュリエット以来の初の主役がこれ以上は望めないという役で決まった」
「その芝居は大当たりで、最初の週にシーズンのチケットが完売したんだ。劇評もよかったから、団長はアメリカ国内だけでなくイギリスでの公演を思いついた。戦争が終結したばかりでイギリス人も過去を忘れるための娯楽を必要としていたから、おれのような新たなスターは大歓迎されるだろうと団長は言っていた。団長にはロンドンに何人かの知り合いがいて、ストラスフォード版のハムレットに興味を示していたから物事はとても簡単に進んだんだ」
「長い公演旅行になることがわかっていたから、マーロウ夫人はおれが居ない間のことを考えて、彼女たちにマンハッタン市内に部屋を借りることと、病院まで送迎する運転手を手配するようにと言ってきた。それでおれは公演旅行に出発する直前におれの部屋と同じビルに彼女たちの部屋を借りたんだ。結婚はまた延期となった。長期の公演旅行もあったし、スザナは治療のためにニューヨークに留まらなければならなかったから、この時はおれから日程の変更を提案した。マーロウ夫人は当初結婚の延期に乗り気ではなかったけれど、市内のアパートと、運転手と、それに加えて車を手配しておれが夫人の望みをかなえたことで、最終的には同意したよ」
「おれが留守にしていた6ヶ月の間にスザナは戯曲を書き始めた。そんなに素晴らしい作品ではなかったが、一般のエンターテイメント作品としてはそれなりに通用するものだった。テリュース・グレアムの婚約者が書いた作品を演りたがる劇団を探してくることなどマーロウ夫人には簡単なことだった。ある意味おれの名前でスザナの新しい可能性が開けたが、それでもおれは満足だった。婚約してから2年半の間、スザナは絶えずおれに依存して所有欲を示していたから、イギリスから戻って彼女が新しいキャリアにわくわくしているのを見て安心したんだ」
「イギリスでもハムレットが成功してかなりな収入が入ったことで、マーロウ夫人がまた欲を見せ始めた。おれがアメリカに戻るや否や、マーロウ夫人は今の部屋では小さすぎると言い始めたんだ。スザナは劇作家としての評判を得始めていて、打ち合わせに顧客や監督や俳優たちを招待する必要が出てきたからというのがその理由だった。おれはマーロウ夫人にこの部屋に住み続けてスザナが望んでいるような盛大な挙式を行うか、家を買う代わりに結婚をさらに6ヶ月延期するかどちらか一方を選ぶように言った。マーロウ夫人はその時は即答を避けて考える時間をくれと言った。おそらくは、おれが俳優として成功してそれなりの収入を得たことでスザナから離れてしまうのではないかという恐れと、とめどない欲求の狭間で悩んでいたんだろう。最終的には、おれが自分と彼女たちのために借りていた2部屋を解約して家を購入し、おれは結婚するまではスザナの付添人として同居するということで双方が妥協した。結婚の日取りは1920年の春ということになった。」
「マンハッタン市内のタウンハウスに住み、娘がおれと同居しているという公然の事実を得たことで、ある意味すべてがマーロウ夫人の思惑通りになったんだよ。結婚はしていないものの二人が同居しているという事実に、業界内でおれはすでに《誰かのもの》となったわけだ。おれに好意を持つ女性がいたとしても、婚約者と同じ屋根の下に暮らしている男であればアプローチするのに二の足を踏むだろう。マーロウ夫人は実にかしこい人だったということだ」
テリィはキャンディの物問いたげな目に気づいて一旦話を止めた。
「おれはきみを不愉快にさせているかな?」 テリィは聞いた。
「そうじゃないの……わたしはあなたがスザナと同居していたことは知っていたから。ただ、母親がそのような取り決めを提案することがわたしには理解できなくて。なんだかそれって……」
「正しいことに思えない?」 テリィはキャンディの言葉を引き取って言った。「キャンディ、マーロウ夫人はきみが慣れ親しんだ高い道徳基準に従って行動するような人じゃないんだよ。それに、おれが住む世界では誰も世間の常識になどとらわれていないから、マーロウ夫人もスザナも、業界からつまはじきにされる心配などせずに自分たちの計画を推し進められたのさ。スザナはおれと同居したことで、ニューヨークの社交界のもっと保守的な階層ではレディーとして通用しなくなってしまったが、真実を言ってしまえばマーロウ夫人はあらゆることを損得勘定で決めていたんだ。ご主人が一銭も残さずに亡くなってから、マーロウ夫人はスザナの容姿を収入の糧にした。おれがスザナに出会った頃には、彼女は母親の生活費から何からを自分の稼ぎから支払っていた。マーロウ夫人はおれの母親と同じ年代で決して働けないわけじゃなかったにも関わらず、スザナの収入をあてにして生活する道を選んでいた。だからぜいたくなタウンハウスや快適な生活と引き換えに娘の評判に少し傷をつけるくらい平気だったとしても、おれはまったく驚かない」
「可哀そうなスザナ」 キャンディはぞっとしてポツリとつぶやいた。
「スザナを憐れむ必要はないんだ、キャンディ。スザナも罪のない被害者だったわけじゃない。彼女は意志が弱かったし時には子供っぽいこともあったけれど、母親のやっていることはちゃんと見えていた。スザナは自分の母親がおれの金を好きなように使う方法を探していることがわかっていても、それを止めようともしなかった。母親の計画に従うたびに、スザナには何かしら得るものがあったんだ。結婚の延期の話が出ると、スザナは必ずおれの前でひと騒動を起こして、彼女が払った犠牲とおれが失踪していた間の苦しみを再度思い起こさせてから承諾した。スザナはおれの罪悪感を操作することで、結婚の約束がしっかり守られるという安心感を得ていた。おれはそんな毎度のやりとりが嫌でたまらなかったが、スザナのそばにいるというきみとの約束があったから、いつも最後にはマーロウ夫人の計画に従い、スザナの脅しにも耐えたんだ。おれは一度ならず何度も背を向けその場から永久に立ち去りたいという衝動にかられた。今ではなぜ本当にそうしなかったのかが悔やまれるよ」
キャンディは言葉を失っていた。テリィの話の中で明かされるスザナのような複雑な人格を持った人間にはこれまでの人生で出会ったことがなかったのだ。テリィはキャンディの沈黙に気づき、その暗い話を一旦止めた。これから明らかにしていく部分は、話を進めるのが一層難しかった。
「キャンディ、おれがきみにこの話をしているのは、きみに知ってもらいたいからなんだ……たとえおれとスザナが同じ屋根の下に暮らしていたとしても……」
「テリィ、それを言う必要はないわ。ほんとうに……わたしには……知る必要がないから」 キャンディは胃が締め付けられるのを感じながら話を遮った。
キャンディはテリィの胸に預けていた体を起こし、硬直した様子で彼の横に座った。テリィはキャンディが抵抗しているのを見ると近づいて、手で彼女のあごを持ち上げ自分の方を向かせた。
「キャンディ、おれとスザナの関係は疑われてもしょうがない状況だったことはわかっている。おれとスザナが恋人同士でそういう関係だと多くの人が思っていたのも確かだ。でも実際はそうじゃなかった。おれたちは同じ屋根の下に暮らしていたけど、そういう親密な関係じゃなかったんだ。おれが言いたいことわかるだろ?」 テリィは落ち着かない様子でキャンディを見て聞いた。「そのようなことはおれたちの合意の中には入っていなかった。そんなことをしてしまったら、スザナとマーロウ夫人に家を提供する行為そのものが欲得ずくで紳士的でないものになってしまうと思った。その後結婚が予定されていた翌年の春にスザナが病気になってしまった。彼女の病状はその年から翌年にかけてどんどん悪くなった。そしてその病気は不治の病だと宣告され、おれたちが同居してから3年目の12月に彼女は亡くなった」 テリィは話を締めくくった。
テリィの話が終わったことがわかると、キャンディは肩から重荷が取れたように感じた。キャンディは、結婚を前提にテリィとスザナが同居していた事実をこれまで見ないようにしてきたのだ。判断をしないよう極力努めてはいたけれど、いくらスザナと婚約していたとは言え、そのような行為はテリィの清廉高潔さにそぐわないと心の奥底では感じていた。それは自分の知っているテリィではなかった。外から見える状況とは裏腹に、テリィがスザナに対して立派な態度で接していたことを知ってキャンディはほっとしていた。
「正直に話してくれてありがとう、テリィ」 キャンディは恥ずかしそうに言った。緊張が和らいだ様子を見て、テリィはもう一度キャンディを腕に抱いた。
「キャンディ……酒浸りの時期におれがしたことは決して自慢できるようなことじゃない」 テリィはキャンディの目をじっと見ながらひどくまじめな調子で続けた。「できることなら時間を戻して、きみと別れた時の汚れのない17歳の少年のおれをきみに差し出すことができたらと思うが残念ながらそれはできない。ここにいるのは深い苦悩を経験して人生に汚点を残してきた一人の男だ。それでもこれだけはきみに言える。ニューヨークに戻ってから、おれは正しく生きるために最善の努力をした。持ち物はすべてまっとうに働いて得たものだ。スザナに関して言えば、結婚の申し込みをしてからは彼女を尊重し、病気の間も貞節を守った。おれがそうしたのは、それがきみへの貞節を守ることだと思ったからだ。これが今のおれがきみに与えられる精一杯だ……きみをニューヨークに招待した10年前の半分にも満たない。それでもいいか?」 テリィは躊躇した。「それでも……」 次の言葉を口にする勇気を探してテリィの顔は青ざめた。「おれの過去の過ちを許して……おれの……おれの妻になってくれないか?」
この会話の中で初めてえくぼを見せてキャンディは笑顔になった。その表情からは答えを聞かなくても返事がわかった。
「この人生と、そしてこの魂の続く限り何度でも、テリィ、わたしはあなたの妻になります」 キャンディは優しくテリィを抱きしめて返事をした。そしてしばらくそのまま静かで完璧な時を過ごした。

翌朝テリィが目を覚ますと部屋の中は暗く、周りをよく見ることができなかった。暖炉の薪は燃え尽きていて、窓のシャッターは閉まっていた。外は凍えるような寒さだったが部屋の中はまだ少し暖かかった。すると、覚えのある特有の香りが鼻についた。その香りがどこから来ているものなのかわからなかったが、香水の香りでも体にかけている洗いたてのシーツのものでもなかった。テリィは目を閉じてもう一度深く息を吸い込むと、しばらく考えるのを止めて、そのうっとりするような甘い香りの魅力にひたっていた。その甘い香りに身を委ねていると、いつしか肉体の高ぶりのきざしを感じた。
筋肉が緊張してくると、テリィは自分の右手がキャンディの腰を抱いていることに気が付いた。甘い香りはキャンディから来ているものだったのだ。それは香水の香りではなく、彼女の肌から醸し出されていた。キャンディを腕の中に抱いたことはこれまでにもあったが、これほどの刺激的な香りを感じたことはなかった。テリィは静かに眠るキャンディを後ろから抱きしめていて、胸に押し付けられた背中から、彼女の規則正しい寝息を感じた。キャンディの香りや温かみをこんなに近くで感じられることは、テリィにとって純粋な至福だった。こんな夢から目覚めたい人間がいるだろうか?
それでもテリィはもう一度目をあけて暗さに目を慣らすことにした。しばらくして周囲のものが認識できるようになってくると、前日の出来事が思い出されてきた――これは夢なんかじゃない……。信じられないような最高に幸福な現実だった。薄暗い部屋の中にキャンディのクセのある金髪の髪が浮かび上がった。テリィは手を伸ばし、そのクルクル乱れた髪を優しく撫でると脈がどんどん早くなっていった。テリィにはその原因がよくわかっていたが、しばらくそのままじっとしていた。
その時テリィは二人が別れたあの運命の夜に吹いていた吹雪を思い出していた。今回その同じ吹雪によって二人がようやく互いへの気持ちを伝え合う機会がもたらされたことに、テリィは奇妙な偶然を感じていた。そして今朝、あの夜キャンディが去って行く時と同じように彼女を後ろから抱きしめていたが、状況はまったく違っていた。
キャンディが暗闇の中に消えてしまわないのを確かめるように、テリィは彼女をきつく抱きしめて顔をその髪にうずめた。鼻がキャンディのうなじに触れると、彼女の肌の香りがより濃厚に感じられた。荒れ狂うような感覚が体を走っていたが、それでもテリィはまだ離れたくなかった。
人生で初めてキャンディと一夜を明かしたという事実の喜びの中で、テリィはそのままじっとしていた。キャンディの気持ちがはっきりわかった今となっては、アルバートさんに嫉妬した自分が馬鹿らしく思えた。昨日の午後キャンディは、アルバートさんとのことについてシカゴの小さなアパートでの同居生活から、本当の正体がわかった時のこと、ニールとのことで果たしてくれた役割、そして長い年月をかけて兄と妹のような近しい関係になったことなどを包み隠さず話してくれた。
(おれは愚か者だったな) テリィは思った。(でも今大事なのはキャンディがここにいる……おれとここで眠っていることだ!)
テリィは新たな笑みを浮かべ、二人をこの山小屋に押し留めてくれた悪天候と降り積もった雪に感謝した。もし話をする前に時間をかけていたら、物事はこれほど上手く運ばなかっただろう。
昨夜夕食後にテリィが暖炉に火をくべていると、キャンディは長椅子で眠ってしまったのだった。テリィはキャンディが心地よく眠れるように寝室に運んで、自分はソファで一夜を明かすつもりだった。しかしテリィがベッドに寝かせた時に、半分眠ったままのキャンディが目を開けて両手で優しく彼を引き寄せたのだ。
「一人にしないで」 キャンディが懇願した。「寒いから」
正直なところテリィにはそれ以上の求めは必要なかった。キャンディの懇願をすんなりと受け入れて、靴を脱ぐと彼女の隣に横になり後ろから抱きしめた。
「このくらいまでならいいだろう」 テリィが耳に囁くと、キャンディは再び眠りに落ちた。
テリィは深い満足のため息をついた。洋服を着たまま眠って何も起こらなかったとして構わなかった。他のどんな男もキャンディとこのような時間を共にしたことがないことを知っていて、テリィには今はその事実だけで十分だった。何よりもキャンディは自分の妻になると言ってくれたのだから、間もなくもっと親密な交わりが可能になるのだ。
そんな未来の明るい展望はあったけれど、今朝のテリィがひたすら望んだのは、自分との結婚指輪をはめたキャンディを体の欲求に従って自由にできるようになることだった。しかし10年も待った男であれば、必要に応じてあと数日我慢することができないはずはない――そうだろ……?
昨日テリィは春先に結婚式を挙げようと提案した。キャンディにもいろいろと計画したりポニーの家で代わりになる人を見つけたりする時間が必要だろうと思ったのだ。驚いたことに、キャンディはそんなに長く待つべきではないという考えを示した。
「もう離れ離れになりたくないの、テリィ。もしあなたがニューヨークへ戻ってわたしが春までここに残っていたら、また何か起きるかもしれないと怖いのよ。だからできるだけ早く結婚しましょう。記者の人たちやブロードウェイのお友達を招待した盛大な結婚式ができなくてもかまわない?」
「お友達?」 テリィは顔をしかめた。「おれにはロバート・ハサウェイ以外に友達なんていないし、別に団長を結婚式に呼ぶ必要があるとも思わない。記者に関しては絶対に来てほしくないね。おれは今夜結婚したっていいんだ。春先と言ったのは、たいてい女性にとって結婚式は人生の一大事だし、準備する時間も必要だろうと思ったからだけど……きみはシンプルな式でいいのか?」
「わたしがしきたりを気にするような女性じゃないってこと、そろそろわかっておいた方がいいわよ。わたしには結婚式よりもあなたと結婚することが大切なの」 キャンディはまさしく光輝いて言った。
テリィは昨日のことを思い出して再び笑顔になった。確かにキャンディは他のどんな女性とも違っていた。そして、他のどんな女性とも違うキャンディの魅惑的な香りにこれ以上自分を抑えることができなくなりそうだった。テリィはしぶしぶキャンディから離れ、冷たい水が頭と体を冷やしてくれることを願いながらバスルームへと向かった。

キャンディはやっと目を覚ました。洋服を着たまま眠ってしまったので、きっと洋服はしわくちゃになっているだろうと思った。キャンディは大きく伸びをして、ベッドの反対側に寝返りを打った。隣の枕に顔をうずめるとテリィの香りがした。キャンディは昨日のことを思い出して笑顔になった。
二人が共有した親密な時間を思い出し、キャンディの笑顔がさらに大きくなった。
「わたしったらすごくいけない娘だったかも!」 キャンディは思った。「わたしの奔放な振る舞いにエルロイ大おばさまは何と言うかしら?」 大おばさまの険しい表情を想像してキャンディはクスクス笑った。「でも全く後悔してないわ」
「なんだか嬉しそうだね、アードレーのお嬢さま」 その時ちょうどバスルームから出てきたテリィが言った。テリィの髪は少し濡れた状態でしっかりとかされていた。ズボンに少ししわが寄っていたが、それ以外はきちんとした身なりだった。
「幸せだからよ、テリィ」 キャンディはそう答えてからテリィを見て付け加えた。「それとちょっとうらやましいわ。洋服を着たままで寝て、どうやったらそんなにきちんとしていられるの? わたしを見てよ。こんな有様よ! 髪だってひどいわ!」
「髪は別に変じゃないよ」
「とっても礼儀正しいのね……でもわたしには鏡を見なくてもこの凄まじい髪がどうなっているのかくらいわかるわ。この髪とずっと付き合ってきたんだもの」
キャンディの言葉と口をとがらせた表情にテリィは笑った。
「きみはそばかすと同じくらいそのクルクルした髪が嫌いなんだね」 ベッドのキャンディの横に腰を下ろしながらテリィは言った。
「あまり好きじゃないわ。無秩序で手に負えないところがわたしとそっくりでしょ。アニーのきれいなストーレートの髪がいつもうらやましかったわ」 おでこにかかっている邪魔な髪をはねのけながらキャンディは答えた。
テリィは右手を伸ばしてキャンディのクルクルした髪を撫でた。その目には、催眠的であると同時に怖くも感じられるあの特殊な光が輝いていた。
「きみはきれいだよ、キャンディ」 テリィはキャンディのあごを持ち上げて、真っ直ぐ目をみるようにしてから言った。「なんできみがそのことに気づかないようにしているのかおれには理解できないよ。でもこのことについてはおれの言葉を信じるんだ……コーンウェル夫人の髪などきみのまばゆいクルクルの髪の比べものにもならないね」 そして一旦言葉を止めてから、意味ありげな口調で付け加えた。「客観的に見たきみの美しさの話に加えて、おれはもっと深い主観的なレベルできみがなぜおれにとってそんなに魅力的なのかについて広範囲にわたって話すことができるけど、でもその話題はきみがおれの奥さんになってからにするよ」
自制心がまだ危うい状態にあったので、テリィはおでこにキスをするだけに留め、支度を整えられるようにキャンディを一人部屋に残して出た。そして外に出て窓のシャッターを開け、吹雪の後の状況を確かめた。

雪が問題なのは明白だった。車は1メートル近く雪に埋もれ、道路もかき消されていた。キャンディも外に出てテリィに加わると、二人は今後の行動について検討した。山小屋にもう一日留まるという選択肢はなかった。ポニー先生とレイン先生が二人のことをとても心配していることがキャンディにはわかっていたし、先生たちにこれ以上の不安を与えたくはなかった。テリィにしても、まだ紳士のままでいるためには、できるだけ早くポニーの家に戻らなければならないと考えていた。問題は、車なしでどのように帰り着けるかだった。
幸い山小屋から4キロほど離れたところに知り合いの農場があることをキャンディが思い出した。オーナーのキンケイド夫妻がこれまでに何度かキャンディの患者だったことがあったのだ。もしその農場まで辿り着ければ、キンケイド氏にポニーの家に帰るためのそりと馬を貸してもらえる。
「この雪の中をその農場まで歩いていくなんて言わないよな、キャンディ?」 テリィはその計画に賛同できない様子で聞いた。
キャンディはテリィに微笑みかけてから小屋の中に走っていくと、数分後に手にスキー板を持って出てきた。
「スキーだったらどう?」 キャンディは楽しそうな表情で聞いた。
「おれたち二人いることを忘れてないか?」 テリィは胸の前に腕を組んで異議を唱えた。
「何を寝ぼけたこと言ってるの?」 キャンディはテリィに小言を言った。「もちろんスキー板はまだあるわよ。アルバートさんがいくつか保管しているんだから。行ってあなたも選んできたら?」
「わかったよ、きみの言う通りにしようじゃないか、ターザンそばかす。でも森の道案内は大丈夫なんだろうね? この寒さの中で道に迷いたくはないからね」
「あなたが話している相手が誰かを忘れてない? わたしは人生の大半をこの森の中で暮らしてきたのよ。行くわよ。急げばキンケイドさんのお宅の朝食に間に合うわよ!」
山小屋の戸締りをしてアリステアのおもちゃの車とぬり絵の本を持つと、二人はキャンディの道案内で森の中をスキーで移動した。キャンディの予測通り、二人は朝食の時間にキンケイド夫妻の農場に辿り着いた。中年の農夫婦は二人を温かく迎え、キャンディと一緒にいる男性が彼女の婚約者だと紹介されるととても興奮した。結婚も近いと聞いて、夫妻は二人を祝うために朝食に招待したが、これもキャンディの予測通りだった。食事の後で、キンケイド氏は二人が尋ねる前にそりの提供を申し出た。
キャンディは自分の計画の成功に得意になってテリィにウィンクした。テリィはキャンディに笑顔を返すと、声を低くして言った――
「おれが吹雪に足止めされそうな時には次からはきみを一緒に連れて行くことにするよ。きみは最も役に立つ連れだからね」
*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします















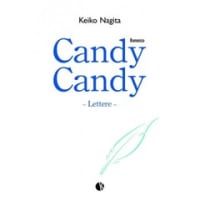









小学生の時に漫画が終了した時、この先テリィ絶対には幸せになれないと落ち込み、ファイナルを読んでもテリィの幸せを確信出来なくて複雑な思いを抱き続けていた私にとって、本当に待ちこがれた場面でした。もう嬉しくって。職場でトラブルがあっても、家事が忙しくても、しばらくはハッピー気分で過ごせそうなほど、幸せ気分です
すばらしい翻訳に感謝いたします。
テリィ、やっと言えましたね!本当にこの二人ってちゃんと言葉にした愛の告白ってなかったですよね。頭の中に金髪巻き毛のキャンディの大きな目が更に大きくなって潤んでるのが浮かんでいます。
ああ、そして二人はどうなるの?
ヤコブ病院での絶望は払拭されるのね!?
多くの皆様が感じていらしたように、二人の別れは子供の頃信じられませんでした。ショックで食のすすみが遅くなった記憶があります。
大変な翻訳、尚且つ語彙も選択されての作業はとても労力の必要なことだと拝察致します。
こんな素敵な話を拝読させて下さった主さまに感謝です!
ありがとうございます!!これからも楽しみにしております!!
ブログ主も個人的にはスザナという人間といてテリィが幸せになれるはずがないと思っていたので、ファイナルストーリーで彼女が死んで、このようなファンフィクが書ける土壌ができてよかったと思ってます。
ナオ様の幸せな時間はまだ続きますから、楽しみにしていてください。
>ショックで食のすすみが遅くなった記憶があります。
ほんとうに悲しかったんですね~
温かいお言葉ありがとうございます。
自分のことのように感激しています。
どんなに待ち望んだことか
でも・・次の章ですんなりと結婚まで行きつくのかとても心配だったりして・・・このまま2人の幸せが続きますように。
ブログ主さんいつもありがとうございます。
翻訳作業大変でしょうけど 頑張ってくださいね。いつも楽しみに待っています。
次章はまた内容が盛りだくさんですよ~どうぞ楽しみにおまちくださいませ
次の章も 楽しみにしていますね
くれぐれも、ご無理なさらずに
実は英語での原作も読みましたが、とても繊細な文章で私の英語力では理解しきれぬところがありました。わからなかった所を補いながら読んでいます。
私の頭の中では、英語を話しているテリィの声はワントーン低くまろやかなんです・・・それがまたかっこよくて。次章の話になってしまいますが・・・テリィが「Touch me!」と言うシーンがありますよね。その声が頭の中で響いて思わず「おお~っ!」と叫んでしまいました・・もちろん心の中でですが。一番ぞくっとしたセリフでした。「Touch me」たかが2語ですが、訳すには微妙にやっかいですよね・・。
翻訳作業、大変な労力と時間がかかることと思います。頑張ってください。どうしても感謝の気持ちを伝えたかったので・・応援しています。 最後に・・くだらない話ですが、先週竹内まりやの曲を聞きたくなり数年ぶりに聞いてみました。「真夜中のナイチンゲール」という曲があるのですがこの曲の間中ずっとキャンディとテリィの顔がぐるぐると・・
たしかドラマの主題歌だったと思いますが、キャンディとテリィの為に書いた曲なんではないかと思える程でした。キャンディワールドにどっぷり浸かっている最中に聞いてしまったので思わず泣いてしまいそうになりました・・よかったら聞いてみてくださいね。 次回更新楽しみにまっております。長文におつき合いいただきありがとうございました。
次章のことに触れられていたので、次章が更新されるまでいただいたコメントを保留にさせてください(すみません)。コメントで触れられていた部分が更新された時にいただいたコメントもこちらに公開しますので、お待ちくださいませ