キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
第4章
家族の肖像
家族の肖像
キャンディは無意識の状態で車両間を移動した。足は確かに床を踏みしめているのだが、それでも宙に浮いているように感じた。周囲の状況もぼんやりとしか知覚できず、腹を立てた乗客にぶつかりながらやっと自分の客室へと辿り着いた。それでもしばらく中には入らず、テリィの口づけが自分の唇に残した甘い疼きを感じていた。突如として、キャンディには空が曇っていても今日が寒い日でも構わなかった。太陽は高く、全世界が信じられないほどの奇跡だった。
すべてはあっという間の出来事だった。テリィが近づいてくるのを見た時心臓が止まり、テリィの唇が自分の唇に触れた時に周りの景色が消えた。その口づけはこれまで夢見てきたことではあったが、実際は夢以上だった。テリィが優しく、しかし断固として自分に触れたあの短い瞬間に血管を駆け巡ったぞくぞくとした感覚は、これまでに経験したことのないものだった。やっと座席に座ると、間の抜けた、にやけた笑顔が顔いっぱいに広がった。幸運なことにその客室にいるのはキャンディ一人だけだった。
腕を伸ばし両手を首の後ろに置いて深くため息をついた。吐き出す息が肺から出ていくと、長年に渡り人生に重くのしかかっていた雲がゆっくりと消えていくのをはっきりと感じた。キャンディはある一つの考えで頭がいっぱいになっていた。
(これは偶然の出来事なんかじゃない。テリィはそうしようと決めて振り向いたもの。わたしたちの関係が変わっていくのね!)
キャンディは昨晩の出来事を思い出しながら楽しげに目を上げた。新聞の写真ではいつも深刻そうなテリィの顔が、二人で踊っている時に輝くような表情になっていたのを思い浮かべた。再会した時からテリィが自分に触れたがっていた様子や、自分が見ていないと思った時に浮かべていた独特の目の光を思い出していた。
(テリィは学生時代の古い友人と再会して喜んでいるだけだったと思う?)
(古い友人を、あんなに激しく燃えるような目で見つめたりしないわ) キャンディは喜びの中で自分に答えた。(古い友人に、あんな口づけはしないわ!) 指で唇に触れると、今でもテリィの決意の動かしがたい証拠を感じた。
キャンディには自分の幸運が信じられなかった。昨夜から起きたすべてのことが不思議なほどに完璧だったので、もう一度自分をつねってみた。ちくっとした歓迎すべき痛みを感じた。今度のことは夢ではないと、単純に認めなければならなかった。テリィは自分に友情以上のものを求めていて、自分は喜んでそれを受け入れる。
(これからどうなるの?) キャンディは急に考えた。(何を期待したらいいの?どう対応したらいいの?)
疑問はどんどん膨らんだが、今ではその不確実性が、ぞくぞくする感覚をより刺激的にしていた。テリィの口づけで奔放になっていたキャンディは、車内が暑くなってきたのを感じると列車の窓を両手で持ち上げ、外に顔を出した。黄金色の景色が雪景色に変わっていくところだった。骨まで沁みる身を切るような冷たい風が顔に当たったが、キャンディは寒さを感じなかった。頭がくらくらしながら大声で叫んだ。
「あなたが好き! テリィ! ほかの誰よりも!」
線路の上を走り続ける列車はテリィからどんどん遠ざかっていたが、今のキャンディには、二人の間の距離は取るに足らないことだった。

絶え間ない列車の振動もその優雅な食堂車ではほとんど感じられず、代わりに銀食器やグラスのぶつかる音が空間を満たしていた。ロバート・ハサウェイは、手に持ったブランデーの琥珀の液体の中で光が作り出す効果を鑑賞していた。そのグラスの向こうには、煙草を吸いながらぼんやりと紅茶を飲んでいる連れの、うつろな表情が見えた。ハサウェイは、もう百回も聞こうとして聞けなかった質問を、どう切り出せばいいのか思案した。
「ピッツバーグでの公演は大成功だったな」 ハサウェイは質問のとっかかりとして聞いた。
「ぼくも同感ですよ、団長」 テーブルの向こう側からテリュースが答えた。
「ゲイティーはいい劇場だ。楽屋が少し汚いから、その部分は改装した方がいいな」
「そうかな? 何も悪い所には気づきませんでしたよ」 テリュースは口から煙を吐き出しながら見解を述べた。
「ここ最近、きみはあまり多くのことに気づいてないようだがね。それでも不満は言えないな。きみの芝居は今が過去最高だよ」 空になったグラスをテーブルに置きながらハサウェイは言った。
「褒め言葉として受け取っておきます」
「飾りのない真実だ。きみのこの2日間は見事だった」 ハサウェイは言葉に意図を込めた。「実際のところ、わたしはきみがなぜ最良の形のマクベスを初演の段階ではなく、ピッツバーグまで披露しなかったのか不思議に思っているんだよ」
テリュースは灰皿に煙草の吸殻を落とすと、独特のしぐさで眉を持ち上げてハサウェイを見た。
「わざとそうしたのではありません」 テリュースは簡潔に答えた。
「冗談だろう」 ハサウェイは含み笑いをした。「計算がなかったなんて信じないよ。きみはいつだってインスピレーションや直観よりも技術やメソッドの支持者だったじゃないか。それについては何度も議論したはずだ。芝居に関しては偶然の幸運など信じないと、きみは言っていたのではなかったかね?」
ハサウェイは珍しいものでも見るようにテリュースを見た。目の前で移り変わる窓の景色を見ているテリュースには、続く沈黙に苛立つ様子もなかった。
「ピッツバーグでのきみの芝居はその……インスピレーションによる偶然のものだったと思えと?」 ハサウェイはたまらず懐疑的に聞いた。
「わかりません、団長。ただそうなったとしか言いようがありません」 テリュースは煙草を置いて、椅子から立ち上がりながら返答した。「おそらくインスパイアーされたんです……たぶん、天使が触れたんだ」 そして付け加えた。「ばくはちょっと眠ります、団長。楽しかったですよ」
「わたしもだ」 テリュースが今言ったことに思いを巡らしながら、ハサウェイは言った。
テリィは両手をポケットに入れ、自分の客室へとけだるそうに歩いた。表情はいつも通り厳めしかったが、内心密かに生きている感覚を楽しんでいた。長い年月の後、初めて明るい兆しの波に浸され、気分が晴れたように感じていた。
客室に入り上着を脱ぐと満足げに椅子に座った。今でも時々起きたことが信じられずにいた。愛に関してこれまで不幸な経験ばかりをしてきたテリィには、あの瞬間以上に幸運で満足な瞬間を思い出せなかった。もちろん、スコットランドのあの穏やかな日々の、純粋で穢れのない喜びの思い出は忘れていない。しかし、長い間失われていたものを取り戻したこの新しい感覚には比べようもなかった。
ぼんやりと指で椅子張りを優しく撫でながら、テリィはその腕にキャンディの体を抱いた時に呼び覚まされた感覚について考えていた。昔にも同じようなことはあったが、その時感じたものとは強さも深みも違っていた。踊りながら、歳月がキャンディの体に起こした変化に、驚きと喜びを感じずにはいられなかった。最後に会った表情豊かな可愛らしい少女が、魅惑的で優美な体つきの女性に変わっていた。表情豊かな目はそのままだったが、感情を表現する時の口調やその唇は昔よりも甘かった。
――キスの仕方がわかるようになったな、キャンディ……。 自分の口づけを受け止めたキャンディの唇の感触に満足しながら、テリィは思った。――ひっぱたかれないことがわかっていたら、もっと前にしてたのに……。
テリィは、始めは友好的に再会を締めくくろうと、握手をして別れるつもりだったことを思い出していた。しかしキャンディに背を向けた時に突然、過去の瞬間のさまざまな記憶に激しく襲われたのだった。スコットランドの暖炉の前でキャンディに触れたいという衝動を抑えた自分の姿が見え、ニューヨークの駅で抱きしめたくてもどうしてもできなかった苛立ちを感じ、そして何よりも、その翌日に病院でキャンディが立ち去るのを見送った時の絶望をありありと再体験した。その時だった。もう慎重さを捨て去る時だと心に決めたのは。結果はすばらしかった。キャンディの熟れた唇の感触がまだ残っていた。
――おれは欲張りな男だぜ、キャンディ……。 テリィは思索を続けた。――しかも、大人になるにつれ忍耐強くなるどころか、むしろ逆だってことに最近気づいたよ。再会したその日にキスをしたのはおれの期待以上だった。でもその唇を奪った今では、きみのすべての口づけとそれ以上のものが欲しい。男が女に求められるすべてをきみから手に入れるまで、おれは止まらないからな、キャンディ。きみはおれのものだ。最初からそうだった。今度は友達にも誰にも、おれたちの邪魔はさせない……。

完璧な朝だった。その青年は砂色の髪を軽くなで、その髪を注意深く顔から払った。青年は朝食の席で静かに新聞を読んでいた。フランス製のカフスシャツとダブルブレストのテーラードジャケットに身を包み、うるさい好みを満足させるように服装の細部に至るまで細心の注意が払われていた。青年の妻が食事の間中なにくれとなく世話を焼き、青年は昼間の仕事の準備をするために目覚めのコーヒーを飲んでいた。
その日の朝は特に重大なニュースは何もなかった。経済欄に注意深く目を通してから時事欄を見渡し、新聞を横に置こうとした時にエンターテイメント欄が目に入った。すると、その口元に冷笑的な笑みが浮かんだ。
「ほら、あいつが本性を現わしたよ」 静かにお茶を飲んでいた妻に新聞を渡しながらアーチーは声に出して言った。「スザナ・マーロウが死んで、とうとう下品な女たらしの本性を見せ始めたよ。ぼくは昔からそうじゃないかと思ってたんだ。この記事のあいつを見てごらんよ!」
男女のカップルが口づけを交わしている写真を見て、アニーの目は飛び出しそうになった。
「明るいうちから見せつけるなんて悪趣味だよ。あいつがこの家に入り込まなくて良かったと思わないかい? キャンディも、危ういところで逃れられたことを喜ぶべきだね」 朝食の席を後にしながらアーチーは付け加えた。
アニーは夫の質問には答えずに、新聞をじっと見ながら、いってらっしゃいのおざなりな挨拶をした。見出しにはこう書いてあった――
『ロミオに新たなジュリエット――ブロードウェイの人気スターに新しい恋人か?』
それはテリュース・グレアムが女性に口づけをしている写真だったが、女性の顔は黒いクロッシェ帽と、その女性の頬を持つ俳優の手で隠されていた。記事にはこの女性の身元はまだ不明とあったが、写真は一週間前にピッツバーグの地元の駅で撮影されたものだという。アニーはいぶかしげに目を細めて写真をじっと見ていたが、突然、謎の笑みを顔に浮かべた。

それから数日後の夜、キャンディはボストンのホテルの部屋にいた。後援者への挨拶周りは大きな成功を収め、新しい年にポニーの家の子どもたちが持てる可能性にわくわくしていた。ポニー先生とレイン先生には長い手紙を書いて報告してある。後は荷造りをして、翌朝にはいよいよシカゴへ出発する。
洋服をたたんでスーツケースにしまい始めると、キャンディはナイトテーブルから自分の古い祈祷書を手に取り、真ん中から開いた。そしてそこに、1914年のテリィの最初の新聞記事のぼろぼろになった切り抜きを見て目を輝かせた。祈りの中でいつもテリィの名を呟いていたので、祈祷書に挟んでずっと持ち歩いていたのだ。今ではその次のページに、テリィから贈られたアイリスと水仙の押し花が挟んであった。
電話が鳴り、キャンディは夢想から覚めた。
「アードレー様、シカゴからお電話でございます。アーチーボルド・コーンウェル様の奥様からでございますが、お受けになりますか?」 オペレーターが聞いた。
「ええ、お願いします。ありがとう」 キャンディが急いで言うと、特有のクリック音の後に回線がつながった。「アニーなの?」
「そうよ、キャンディ。元気?」
「元気よ、アニー。もう荷造りを始めているわよ。会えるのが待ちきれないわ」
「わたしもよ」 アニーも興奮気味に言った。「今年は歴史的なサンクスギビングパーティーになるわ。アーチーのご両親は二日前にこちらにいらしたし、わたしのパパとママも出席するのよ」
「それは素晴らしいニュースじゃない! あとはニールとイライザが風邪をこじらせでもしてくれたら完璧ね」
「いじわるなこと言わないで。最近では二人とも親切になってきたじゃない」 アニーが叱った。
「この14年間いじわるをしてきたのはわたしだって言うの、アニー? それに、わたしは二人の皮肉を親切とは受け取らないわよ。とにかく、そんなことどうでもいいことだわ。アルバートさんはもう戻っているの?」
「ええ。今日の午後に着いたのよ。昼食をご一緒したわ。前よりも日に焼けて、少し体重が増えたみたいよ」
「それは魅力的ね! 前回ブラジルから戻った時には痩せすぎだったもの。早く会いたくて仕方ないわ。アルバートさんに代われる?」
「ごめんなさい、キャンディ。アルバートさんとアーチーは提携先との遅い時間の会議に出かけているの。明日はアルバートさんが駅までキャンディを迎えにいくわ。わたしが電話したのは、実は頼みがあるからなの」
「そうだったの? 何かしら?」 興味をそそられてキャンディは聞いた。
「ばかみたいなことなのよ。でもわたしの言うことを聞いてほしいの」 アニーははっきりしない口調で言った。「明日着る服を準備しているわよね?」
「してるわよ」
「明日は、赤いブローチをつけないで来てくれる?」 やっとの思いでアニーは伝えた。
「赤いブローチ? どうして?」
「理由はこっちに来た時に話すわ。でも赤いブローチだけはつけて来ないでね。わたしを信頼してくれるわよね?」 アニーは頼み込んだ。
「心配しないで、アニー。あなたの言うとおりにするわ」
それから二人はもう少し話をした後で電話を切った。受話器を置くと、キャンディはアニーの奇妙なリクエストに従って荷造りを続けた。アニーがあんなに興奮した声を聞いたのは久しぶりだった。

シカゴのダウンタウンにある中央駅では、大勢の人波が終わることなく行ったり来たりしていた。キャンディはその光景を始めて目にした時のことを思い出していた。メリー・ジェーン看護学校から、4人の同級生たちとこの街に派遣されてきたのだ。看護生たちがこんな大きな街を見たのはそれが初めてのことで、みんな感激したのと同時に、人の群れがまるで舗道を這うモンスターのように一つに動く様子を見て、少し恐ろしくもあった。それ以前にニューヨークやロンドンを訪れたことがあったキャンディさえも、シカゴの街には感銘を受けた。あの日からたくさんのことがあった。人混みの中を探しながら、11年前にシカゴのあの病院の部屋でアルバートさんを見つけられたことを、神様にもう一度感謝した。アルバートさんは常に飛び回っていたし、いくつもの仕事上の責務があったけれど、あれ以来二人は最も親密な友人になっていた。
アルバートさんが世界のどこに行こうとも、二人は本当に血がつながっているようにしっかりと、見えない糸で結ばれていることがキャンディには分かっていた。アルバートさんはキャンディにとって悲しい時にしがみつける強固な岩のような存在であり、キャンディはアルバートさんにとって闇夜を照らす灯台だった。二人は、本当に血のつながった兄弟が羨ましがるほどに、互いに慰めと癒しを与えあった。
キャンディは不安になって辺りを見回した。時間に遅れるなどジョルジュらしくないことだった。アルバートさんを約束の場所に連れ回すのは実質的にジョルジュの役目だったので、列車の到着の時刻を過ぎても二人の姿が見えないのは奇妙だった。プラットフォームを見渡すこと三回目でキャンディはようやく、ずっと会いたかった濃いブロンドの髪の背の高い人物を見つけた。
「キャンディ! キャンディ!」 熱心に手を振りながらアルバートさんが叫んだ。
キャンディは、その年齢の女性に求められている落ち着きなどすっかり忘れて、ダブルブレストのオーバーコートをきれいに着こなしたアルバートさんの方へと全速力で駈けて行った。アルバートさんが大きくて頑丈な男性でなかったら、キャンディが駆け込んできて抱きしめた時の衝撃で、押し倒されてしまったことだろう。
「ああっ! アルバートさんがここに居るなんて信じられない!」 その広い胸に顔をうずめながらキャンディが言った。「すごく幸せ!」
「ぼくもだ、キャンディ」 アルバートさんが笑顔で応えた。「会えなくてとても寂しかった。お願いだ。顔を見せておくれ」 そう言うと、キャンディの顔をよく見るために、自分から優しく引き離した。
アルバートさんは誇らしげな目で、明るいコバルトブルーのコートと、キャンディの金色の髪に乗っている青い羽根のついた黒いつば広の帽子を眺めた。黒いシルクメッシュのベールの向こうには、愛して止まない快活な緑の瞳と可愛らしいえくぼが見えた。アルバートさんの笑顔が大きくなった。
「この可愛いレディの顔の下に、まだ小さな女の子が見えるよ」 アルバートさんは愛情深くキャンディに言った。
「わたしには、日焼けしたハンサムな男性に変装した、大好きなウィリアム大おじさまが見えるけど」 アルバートさんをからかう機会を決して見逃さないキャンディが言い返した。「大おじさまは、そのご年齢にしては大層若返ったみたいですけど、それは旅先の太陽が魔法をかけたからですか?」
「もう止めてくれよ、キャンディ。いつになったらぼくをからかうのを止めてくれるのかな?」 クスクス笑いながら、アルバートさんは愛情を込めてキャンディの肩に手を回した。「ジョルジュにも挨拶をするかい?」
アルバートさんに促されキャンディが振り返ると、側頭部を覆う白髪以外は子供の時から覚えているのと全く変わらない、細身で完璧な姿のジョルジュ・ヴィレルがいた。
「ご機嫌いかがですか、ジョルジュ?」 キャンディは手を差し出して温かく挨拶をした。
「大変結構です、キャンディスさま」 ジョルジュはキャンディの手の甲にキスをしながらお辞儀をして答えた。「お元気そうで何よりです」
「この父上を、たいへん良くお世話していただいたようですね」 キャンディは、いたずらっぽく目を丸めながら言った。
「最善を尽くしました、キャンディスさま」 ジョルジュは笑顔を抑えながら返答したが、一族の当主がムスッとした顔をしているのを見ると真面目になった。「よろしければお荷物をお運びいたします、キャンディスさま」
「ありがとう、ジョルジュ。どうぞ先に行って、父上のことは心配しなくていいわ。父上なら大丈夫ですから。ところでお父上さま、杖はどこ?」
「もういいだろう、泣き虫キャンディ」 アルバートさんは、頼りがいのある腕をキャンディの肩に回したまま陽気に言い返した。「みんなの前でお仕置きをしなければならなくなる前に家に戻ろう」
「泣き虫なんて呼ばないで。わたしは立派なレディよ。ちっちゃなバート」
車に乗り込んでからも二人の楽しげなやりとりは続いた。会えばいつものことではあったが、二人とも互いに一緒にいることで心が温まるのをはっきりと感じた。助手席に座っていたジョルジュは、やっと心置きなく笑顔になることができた。ジョルジュは、アードレー家にキャンディが存在してくれていることに感謝していた。アードレー一族は、これまで絶え間ない悲劇に襲われてきた。その悲劇は時に苛酷なものであったが、キャンディの快活な性格はそのような中にあって一服の清涼剤だった。キャンディが養女になる前は、ローズマリーがアードレー家にとっての唯一の晴れやかな存在だった。しかし残念なことに、ローズマリーが逝ってしまってからもう20年以上が過ぎていた。ジョルジュは、キャンディ以上にローズマリーの代わりが務まる人間はどこにもいないだろうと確信していた。長い年月を通して、この小さなブロンド髪の娘が、はかなくか弱そうな外見とは裏腹に、ローズマリーには欠けていた強靭な肉体と精神を持ち合わせていることを学んでいた。キャンディが《アルバートさん》のそばにいてくれることは、ジョルジュにとって喜ばしいことだった。

*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします















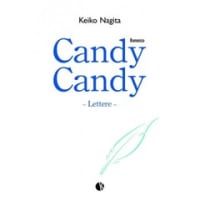









この小説も、その翻訳も、考察も、FinalStoryがなければ書かれることはなかったと思うと、やはり小説の出版は大きかったですね。