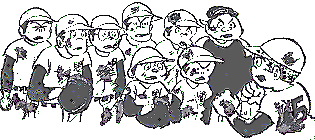黒川紀章の、『共生の思想』という本を読みました。
この本のタイトルにもある、『共生(きょうせい)』という言葉は、浄土宗の僧である、(ご存知!笑)椎尾辨匡(しいおべんきょう)先生が設立した『共生(ともいき)仏教会』に基づいています。著書では、この概念をさらに地球環境にまで及ぶ建築論、都市論にまで発展させているわけですが、もはやこれは、建築に関わらず他のどの分野でも通じる哲学でした。
西洋 . . . 本文を読む
○広辞苑に「イケ面」が追加されたそうで。
TVでコメンテータが「イケメンのメンはメンズのメンじゃないんですね」
と言っておりましたが、確かに言われてみるとそうですね。
○そうですね、といえば『いいとも』です。
私は増刊号を毎週録画してるわけですが、タモリが2ヶ月位前、こう言ってました。
「最近、イケメン増えたねぇ」
これも確かに言われてみればそんな気がします。
タモリが何気なく口にしたこの一言。 . . . 本文を読む
というわけでいきなりですが、売れそうな本のタイトルを勝手に考えてみることにします。
[1]「そういわれば何でだっけ」をタイトルにする
やはり、最近の流行と言ったら、疑問を投げかけるタイトルです。
『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』
この本は随分前のものですけど、やはりこれが一番いい例ですね。
この本から似たようなタイトルが増えたような気がしますし。
疑問を問いかけて、本を手にしてしまった . . . 本文を読む
というわけでいきなりですけど、漫画のタイトルのつけ方を勝手に考えて見ます。
今回は、タイトルによって主人公をどう捉えてるかが解る、って視点で言ってみますよ~。
かといって次回はないですよ~。
[1]主人公をそのまんまタイトルにする
これは解りやすいですよ。主人公が誰ってすぐにわかりますから。
『おぼっちゃまくん』
『ちびまるこちゃん』
『まじかる!たるルートくん』
どうも、こういうのは子供 . . . 本文を読む
広告業界の人たちは必ず読んでる、とか言われてる
ヴィレバンでは必ず平積みされてお勧め!とか書かれてる
とかで有名な本を2冊まとめて読んでみました。
『アイデアのつくり方』(ジェームス W.ヤング)
『アイデアのヒント』(ジャック フォスター)
個人的には、原典の『アイデアのつくり方』よりも、『アイデアのヒント』(写真)の方がピンと来たみたいです。
アイデアを思いつく為に必要なポイントがそこに . . . 本文を読む
経営者の条件
たまには、ということで『経営者の条件』(P.F.ドラッカー )を読みまして。
いや~ガツンときたましたねえ。目の前が開けました。開けましておめでとうです。
あとがきによりますと、
本書は、経営学を創始し確立した経営学者ドラッガーの名著集の第1巻で、
『経営学者の条件』(1964)に、ハーバードビジネスレビュー誌の寄稿論文を序章につけ加えて刊行されたもの。
だそうです。
随分と古 . . . 本文を読む
朝、歯を磨こうとすると、つい手を左側に出してしまう。
実家の洗面台では歯ブラシが左側に置いてあったからだ。
しかし現在住んでる所は右側にある。
習慣とは恐ろしいものである。
自転車から降りると、つい手をハンドルのところにやってしまう。
学生時代乗ってた原付にはちょうどその辺に鍵がついてたからだ。
しかし今乗ってるのは自転車で、当然そんな所に鍵はついていない。
習慣とは恐ろしいものである。
. . . 本文を読む
言葉遊びをシリーズでやってみることにします。
【理不尽なこと】
小学教師に「ダメでしょ」と言われてシャーペンを取りあげられた挙句、怒られること。
【理にかなったこと】
高校教師に漫画『墨攻』を読んでるのがバレて取り上げられるも、「歴史モノです」と言ったら許されること。
【うっかり】
朝起きたら隣の家の奥さんが横に寝てたときに発する言葉。
【めっきり】
隣の家から年賀状が届かなくなる様。 . . . 本文を読む
初詣しておもったんだけどね。
神社でさ、歩き煙草してたら、なんかバチ当たりな感じするじゃんね。
何か、新年早々、そういうのもヤダしさ、一応、そんなんは控えるわけ。俺も。
何だか、新年になると急に、宗教じみたり、いい人になっちゃったりする感じ。
行った先の神社さ、そんな大きいわけじゃないんだけど、けっこう面白くてさ。
そこの神社さ、まだ、地域性的な何かが残ってるとこで。
そこら辺に住んでる人達 . . . 本文を読む
私は常にギリギリ出社でございます。
もう5分さえ早く家を出てれば余裕なハズなのにそれをしないため、電車を乗り換える度に走る必要がありまして、会社に着くころにはもう汗がぐちょぐちょになっているしまい、仕事どころの騒ぎではなくなってしまうわけでございます。
しかも、ただ走るだけではございません。
走りながら、人ごみをかき分けなくてはならないのです。大阪という町は、とにかく人が多いのです。特に大阪駅 . . . 本文を読む
飲食業の品質
飲食には、料理の味の問題以前に、品質的な絶対条件が幾らかあると考える。今回は個人的なそれを紹介する。だからしてどうする。
マック
●生産方式
7年間バイトした子によると、その間だけでも生産方法は2回変更したらしい。肉は焼き溜め、パンは注文を受けてから焼く。包装紙上で作る。トヨタで言うところのパンはJIT、肉は中間在庫。
●セット
高校時分に単品に対して最もお買い得なバリューセッ . . . 本文を読む
飲食店の環境
飲食店には、料理の味の問題以前に、環境的な絶対条件が幾らかあると考える。今回は個人的なそれを紹介する。してどうする。
パスタ屋
●チーズは各テーブルに
飲み会を除いて外食イコールパスタの私。たまにチーズをかけてくれる店があるが、なんでわしが「はいストップ」言わないかんねん!て話である。無類のチーズ好きな私は、サラダに、パスタに大量にチーズをかけるので、削ったチーズを置いといてく . . . 本文を読む
監督インタビュー
今まで、映画監督のインタビューや講演会に、機会があれば参加してきた。
原作よしもとよしとも『青い車』の奥原浩志監督。横で主演のARATAがスチール撮影、チラ見しつつ監督のお話を聞いた。
『まぶだち』『ロボコン』古厩智之監督インタビュー、長澤まさみをチラ見。
『空の穴』熊切和嘉監督インタビュー、
原作つげ義春『蒸発旅日記』の山田勇男監督インタビュー、
など(もう思い出せない・・・) . . . 本文を読む
非日常は日常の中にあった
長い旅行へ行く。
旅先での宿泊も何日か経つとだいぶ慣れてくる。楽しい毎日を過ごす。
そして楽しい日々はあっという間に過ぎ。気づけば久しぶりの帰還だ。
不思議なことに、久しぶりの我が家にたどり着く、その間に、
いつもの(旅行に出る前の普段の)感覚が段々と戻ってくる。
「やっぱりここが一番落ち着くな」
「あー明日から学校だー」
「現実が待ってるなぁ」
誰もがそんな感覚を持った . . . 本文を読む
我が家(社員寮,世帯員数1人)では、勝負パンツならぬ「デッド・パンツ」というルールみたいなものがある。
「デッド・パンツ」。
その聞きなれない言葉にどう反応していいのかわからない人も多いだろう。
だがこの「デッド・パンツ」という概念は、誰にでもすぐに実践することができる、非常に単純で明快なコンセプトを持つ。
生活のちょっとした知恵から生まれた、便利で、粋なアイデアである。
そのデッド・パン . . . 本文を読む