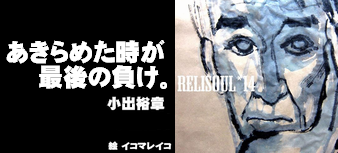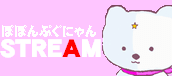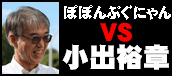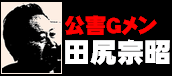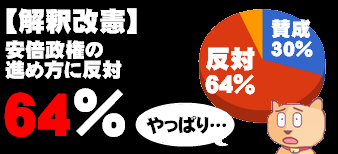小出裕章さんにきく。(13) - 「自立した個人」について。- 2014.04.28
■水戸巌さんの著書より引用。
緑風出版│原発は滅びゆく恐竜である(ISBN978-4-8461-1403-9)
「原発の危険性を理解するのに必要なものは知識ではない。必要なのは論理である。極端な言い方をするならば、論理をもたない余計な知識は、正しい理解を妨げることさえある。」
「とり返しのつかな巨大な潜在的危険性に対しては明確な論理をもたねばならない。それは判断の基準を最悪の事故がおきたときの結果におくということなのである。交通事故といっしょにしてはいけない。この論理をぬきにした余計な知識は健全な判断をくもらせるだけである。」

いま、小出裕章さんが「数少ない恩師の一人」と呼ぶ、故・水戸巌さんの著書「原発は滅びゆく恐竜である」を読んでいます。
いや、原発の話ではないのですが、「問題は知識ではなく論理である」という事に、本当にそうだなぁと思ってしまいました。
知識ばかりの人は多いのですが、「なぜそうなのか?」「なぜダメなのか?」「なぜいいのか?」それを説明できる人って意外に少なかったりする。
いや、わかっていても言葉にできないだけなのかもしれませんが、そういう「論理を言葉にする」訓練というのも必要でしょう。
時々、ツイッターなどで反論らしきものがくる事がありますが、「なぜダメなのか?」「なぜ違うのか?」という論理的な反論がくる事は滅多にありませんね。
一方的な決めうち、レッテル貼りで終わってそれで満足してるような人が多いような・・・。
あと、この本にはほんの少し伊方原発裁判の原告側証人として立った、小出裕章さんと槌田劭(たかし)さんの話が載っているのですが、国側の証人の東大の御用学者・三島良績は弁護士の質問に答えられず、住民側の証人は答弁に窮する事もなかったもそうで、小出さんに言わせれば「裁判は全体的に圧勝」だったそうですが、その裁判の直後に裁判官が入れ替えられて結局、敗訴してしまったとか。
しかし、入れ替えなければならないほど、住民や小出さんたちが追い詰めたという事で、やはり「論理」が大きな武器となっているわけですね。
原発問題だけでなく、いろいろな社会問題にしても、それを追及しようと思えばやはり「論理」がどうしても必要です。
「なぜダメなのか?」という事を誰にでもわかるように説明しなければなりませんからね。
まあ、追及だけでなく、ちゃんとコミュニケーションを取るためにも「論理的」に説明できる事は必要だと思いますね。
知識だけ並べても「ああ、そうですか」で終わってしまいますからね。
そして、きちんとした「論理」を身につけることができれば、人の意見に流されたり同調圧力に屈する事なく、小出さんの言う「自立した個人」に近づけるのではないでしょうか。
気をつけたいと思いました。
■水戸巌さんを知るには、この記事がよくわかると思います。
評者◆水戸喜世子(聞き手・小嵐九八郎)|図書新聞
■水戸巌さん、凄い人です。
Twitter / poponpgunyan: 水戸巌さん。失礼かもしれないが、非常に面白い。反原発運動だけ ...
(Podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ 2013年4月29日(火)
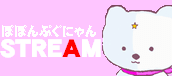
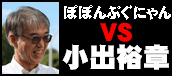
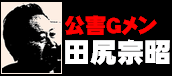
■ぽぽんぷぐにゃん対談
■ぽぽんぷぐにゃん通信
■web拍手-おみくじ
■ぽぽんぷぐにゃんSTREAM(twicas)
■ぽぽんぷぐにゃんカレンダー+マップ