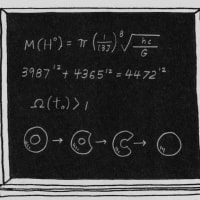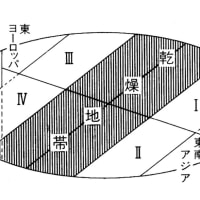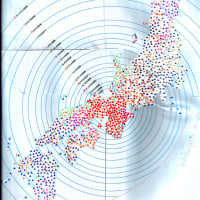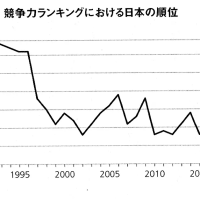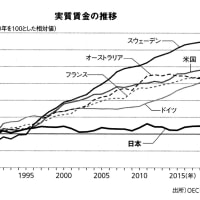虚無と格闘した作家・ヘミングウェイ

野洲図書館でヘミングウェイが目にとまった。大学時代にドストエフスキーについで好きだった作家である。すでに読んでいた『武器よさらば』『老人と海』はさけて、『ヘミングウェイ短編集』(西崎憲編訳、ちくま文庫、2010年)を借りてきた。

本の初めから読む。「清潔で明るい場所」はカフェで毎日閉店までねばる老人と、二人いるウェイターの話である。老人に早く帰ってほしいウェイターと、老人にも事情があるだろうとかばうウェイターが会話をしている。老人を含めた3人が俯瞰されている印象。その関係は「老人が上客である一方、飲みすぎると金を払うのを忘れて帰ってしまうことも知っていた。だからふたりは老人から目を離さなかった」と至ってシンプルだ。その上、老人は耳が聞こえない。
老人が主人公かというと、そんな風でもない。早く帰りたがっている若いウェイターは老人を邪険に追い出す(その光景の描写がいい。ヘミングウェイの世界に浸れる)が、年長のウェイターはしぶしぶという感じで店のシャッターをおろす。彼は不眠症で暗い場所が苦手なのだ。帰りに彼はバーに寄るが落ち着けない。「清潔で明るい場所」でないと、彼は眠れない。それはとりもなおさず、彼が閉めてきたカフェなのだ。不眠のウェイターと老人とが重なる。老人は先週自殺を図ったらしい。しかし、この短編の印象は何故か「清潔で明るい」。
二番目の「白い象のような山並み」は男女の会話で成り立っている。何気ない会話だが、一触即発の気配が充満している。会話のテーマは明示されないが、読者には堕胎の話だと察しがつく。男が言うには「簡単な手術」で「僕たちの関係も元通り」になる。しかし、それを口にしたとたん、彼は地雷を踏んでしまったのだ。会話は爆発寸前の衣をまとっている。鉄の棘が見え隠れしている。女が山並みを見て何気なくいった一言「白い象が並んでいるようにみえる」には何の問題もない。それが新たな摩擦を生む。
「きみが望まないことはしてほしくない」。男はなだめるが、もう遅い。会話は不毛となり、気持はもう届かない。最後の会話はこうだ。
「気分はよくなったか」
「いい気分。すっきりしてるわ。いい気分」
騙されてはいけない。女は「気分は最悪」といっている。読み返すと、表の会話に裏の会話がぴったり張り付いて、延々と続くのがわかる。綱渡りより疲れる。私なら地雷を踏んだと分かったら、即座に謝るところなのに。主人公のように、地雷を踏み続ける意味がわからない。この短編は別名「鈍感な青年」である。彼はどこまで、鈍感なのか?…という疑問が生じる。破局に面した二人は列車を待っている。駅の周囲は「白い象のような山並み」で明るく、一点の曇りもない。明るい景色の中の、スリリングな会話。ヘミングウェイらしい。会話の芸が冴える逸品である。
大学生のころ、ヘミングウェイに惹かれたのは、彼のペシミズムだ。涙とは無縁のペシミズム。あやうくニヒリズム(虚無主義)に転落しようとするペシミズムである。「清潔で明るい場所」で不眠症のウェイターがつぶやく場面がある。「ナダ(無)にまします我らのナダ(無)よ」と。言うまでもなく「天にまします我らの父よ」のもじりである。キリスト教の信仰をなくす、という意味を、異教徒の者が体験することは難しいだろう。私の中では、ニヒリズムへの接近という眺望において、ドストエフスキーとヘミングウェイはつながっている。
最晩年の作品『老人と海』は、老いた漁師が誰も漕ぎだしたことのない沖合まで漁に出掛け、そこで大物のカジキマグロを釣り上げるが、港に帰ってくるまでにサメに襲われ、獲物はすっかり食い尽くされて影も形もない、という徒労の物語だ。誰も行ったことのない沖合は、ナダ(無)の海の光景であろう。彼は何を見たか、直接には書いていない。が、ナダ(無)を見た者がこの世を見ると、生きる意味はほとんどなくなるはずである。事実として、ヘミングウェイは猟銃自殺を遂げた。信仰を失うということは恐ろしいことである。今更のように、言うことではないが…。
彼の作品は端正で無駄がない、とよくいわれる。ヘミングウェーの真骨頂は、ナダ(無)というスクリーンを通して、ベルエッポック(古き良き時代)の生活を丹念に描きだしたこと。信仰を失いながらも、19世紀末の生活様式を守り、あるは破たんさせたのが、彼の作品なのであろう。ヘミングウェイには乾いたリリシズムがあって、不思議なことに、暴力を描く際にもそれが生きる。文学の手法は新しいが、基本的にノスタルジーの文学…というのが私のヘミングウェイ観である。

短編を読んでヘミングウェイの世界が懐かしくなった私は、まだ読んでいない『日はまた昇る』(高見浩訳、新潮文庫、2004年)を借りてきた。ロストジェネレーション(失われた世代)を描いた、といわれるヘミングウェイの出世作。たしかに名作である。第1次世界大戦後の新興階級であるアメリカの若者が描かれている…という意味でも新しいし、アルコールを浴びるように飲み、いつも陽気な、そして騒がしいアメリカ人気質がよく描かれている。しかし、読む方としては、あのアルコール摂取量に(読書で)つき合うだけでも大変だ。
ブレットという女性を中心に何となく集まっているグループが、パリからスペインのパンプローナへ出かけ、闘牛を見るというあらすじだが、主人公が通信社の記者であることを除けば、登場人物の職業はよくわからない。何故、金に不自由しないのかもわからない。第1次大戦後にヨーロッパは没落し、代わりにドルの地位が上がって、いってみれば新興成金の御一行様なのだろう。
一行は始終のんだくれていて喧嘩もするが、不思議な連帯感があってお互いにカバーし品位は落とさない。この辺が「古き良き時代」のモラルなのであろう。一行の中には「空気の読めない」ユダヤ人もいて、ブレットに横恋慕し、何かと違和感を醸し出す。皆は辟易としながらも彼を追放したりはしない。結局、ブレットの婚約者が酔っ払って彼を罵倒し、そのブレットは19歳の闘牛士と駆け落ちする、という波乱の展開。ブレットは誰とでも寝てしまう身持ちの悪い女だが、恋に真剣で、気品があって美しく、一行の誰もが一目を置かざるを得ない。
正直なところを言うと、ブレットのイメージが湧かない。今東光の短編で、河内の「こつまなんきん」(小柄で男好きのする女性の総称)を描いた作品で、誰とでも簡単に寝てしまうにもかかわらず、「寝る」だの「寝ない」だのといった次元を超えていて、天衣無縫な魅力にあふれ、少し聖性も感じさせる作品に出合った記憶がある。ブレットはそういう女なんだろう、と類推するほかはない。
『日はまた昇る』は、青年たちの飲酒と祭好き、乱痴気騒ぎを描いたものである。それがベルエポックの残影として描かれ、過剰と無意味に彩られている有様が手に取るように分かる。主人公のジェイクは戦争で男性の機能を失っている。欲望は正常に働くが、欲望を満たす機能が働かない…という過酷な条件を背負っている。彼とブレットは愛し合っているが、それは不毛の愛でもある。小説の最後は、闘牛士と別れたブレットがジェイクをマドリードに呼ぶ場面。二人は市街見物のため、タクシーに乗っている。
「ああ、ジェイク」ブレットが言った。「二人で暮らしていたら、すごく楽しい人生が遅れたかもしれないのに」
前方で、カーキ色の制服を着た騎馬警官が交通整理をしていた。彼は警棒をかかげた。タクシーは急にスピードを落として、ブレットの体がぼくに押しつけられた。
「ああ」ぼくは言った。「面白いじゃないか、そう想像するだけで」
ジェイクは達観しているのか? 恐らくそうではあるまい。欲望を超越しなければならない、という意味で、ヘミングウェイは仏教的である。彼がどこまで仏教に興味を覚えたかはともかく。仏教は超越することに価値を見出すが、ヘミングウェイは小説の描写力で、猥雑な現実を超越してみせた。しかし、現実の方が復讐した。それが彼の猟銃自殺であろう。しかし、虚無との闘いの跡がわれわれを粛然とさせ、喝采を送らせるのである。