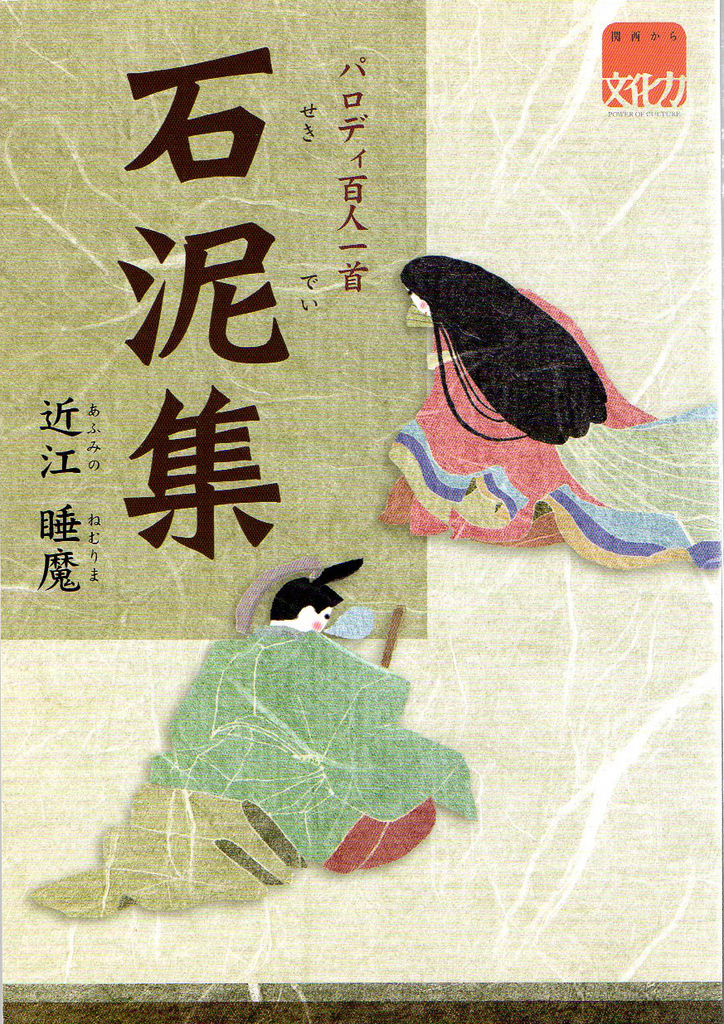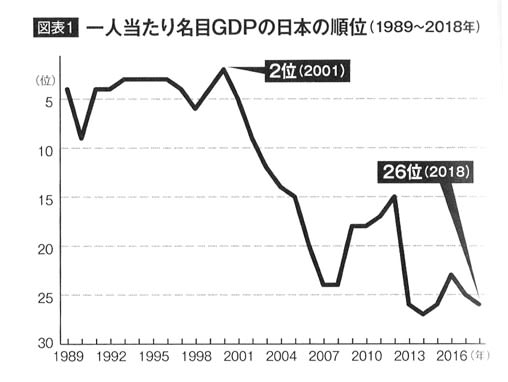面白半分から半覚醒まで
ブログを始めて23年になる。この間、ブログの記事を抜粋して、『パロディ百人一首・石泥集』(2005年)『イミテーション・エッセイ』(2013年)『パロディ短歌・新石泥集』(2016年)『エッセイ対談集・虎を描いて猫』(2020年)と4冊の本も作り続けてきた。その動機を記そう。
『パロディ百人一首・石泥集』について
当初は森図房(地図制作)のホームページの一部「おまけ」で、百人一首の替え歌をつくることから始めている。単に面白いから、という理由である。もっとも、本業の地図制作のかたわらなので、パロディの創作にはムラがあった。2,3日で10首作れることもあり、半年間、何も作らなかった時期もあった。しかし4年後、替え歌が50首を越えはじめたころから欲が出てきた。100首すべての替え歌がつくれるのじゃないか、という思いである。さらに3年くらいかけて残りを整備。
替え歌だけでは意をつくせないものもあったので、詞書に情景描写を加え、すべての替え歌に「蛇足」という寸評を加えた。こうしてできたのが、92ページの小冊子にまとめた初代『石泥集』である。知人に1,000部近くを配ったところ、110通にのぼる反響の手紙を頂戴した。型通りのお礼はわずかで、お気に入りの歌を選んで感想を述べて下さったり、読んでいて電車を乗り過ごしたとか、退屈な教授会が(本を盗み読みして)充実したとか、著者冥利に尽きる文言もあった。
『イミテーション・エッセイ』について
「蛇足」の批評部分を拡大して1冊の本にしたのが、次の『イミテーション・エッセイ』である。『石泥集』が百人一首の本家どりであるのと同様に、名だたる小説家・評論家の文体模写(つまり本家どり)を行なったことで、形式としては一貫しているつもりである。単に事象を茶化すのではなく、もう一歩先へ進んで事象の本質を探りたいという気持ちもあった。文体模写は思ったより楽しい出来事であった。
ある種の自伝を試みていたことは、本が出来上がってから気づいた。幼年時代、少年時代、青年時代のエピソードに加え、大学時代に思想の骨格を作ってもらったフロイトやサルトルについて書き、大好きな映画やクラシック音楽の記述を続けたのは、自分が人生にどのような意味づけをしたのか、を確認する回顧的要素が強い。この本にも100通あまり、心のこもった返事をいただいた。
『パロディ短歌・新石泥集』について
もう一度、パロディ短歌に戻ったのが、次の『新石泥集』であった。替え歌の対象に近現代の短歌を加えたのと、題材の多くを時事問題に求めたのが特徴である。時事問題と言っても、パロディの対象であるから、とりあげるのはゴシップやスキャンダルが多くなる。ただ、マスメディアのように一過性の騒ぎにするのは避けようと思った。
たまたま、この時期にチャイナの反日デモがあり、毒入りギョーザ事件があった。私は父の仕事の関係で、1歳から8歳まで北京で育っている。北京が故郷の感じで、毛沢東や周恩来にも身びいきのような感情を抱いていたが、江沢民が近代国家の自由・平等・人権などをパスし「現代化」に邁進する姿をみて、チャイナへの幻想を断った。
たまたま、民主党政権が成立したものの、幼稚な運営をしたことで、野党(左翼)への幻影もなくなった。どんどん貧相になっていったピエロ鳩山とイラ菅の、反面教師としての存在が大きい。私は革新色の強い京都で育っていて、チャイナも左翼も身近な存在だった。ただし、自分自身もあまり信じないような懐疑派であったから、チャイナと左翼の結果にも驚いたりはしなかった。
『虎を描いて猫』について
この本では「大東亜~太平洋戦争」について、かなりのページを割いている。本の中にも記したが、戦後、マッカーサーと毛沢東が「日本国民は軍部に騙されていた」と懐柔を図った。大多数の国民は悪くないよ、と言ったのである。私に言わせれば、騙される方が屈辱だと思うが、この言に乗っかり「自分は無実」と言い張って始まったのが戦後体制である。ここから堕落が始まって、独立心なき国民が闊歩するようになった、と私は見ている。
二度と騙される立場に立ちたくない、と思ったのは20歳のころ。誰にもごまかされたくはない。そう思って少しづつ勉強した。まだ、成果といえるほどのものは上がっていないが、現在の段階で中間報告したいと考えた。これが『虎を描いて猫』を発刊した理由である。サヨクと復古右翼、そして一部のフェミニズムに厳しい評価をしたこの本は、私の本音である。彼らの言動は、昔の狂信的な陸軍参謀を彷彿とさせるからである。
難しい問題を語るとき、わが国では渋面を作りながら行うのが伝統になっている。戦後の論壇をリードした知識人が、勿体ぶった伝統をつくってきた。いまでも国会審議では、硬直した議論に切り口上と金切り声が飛び交う。つくづく生産性が低いなあ、と思う。酒でも飲んでいるような調子で、愉快に議論したいのが私の性(さが)である。昔からの願望を実現し、関西弁を交え、喋っているような文体を心がけた。
サヨクと復古右翼、双方から何か抗議があるかなと思ったが、サヨクと思われる知人から、否定の根拠を訊ねてきただけだった。それなら自信がある。共産党の強い京都で私は育っているし、父は投票の度に共産党を支持していた。妹は共産党の傘下にある民主主義青年同盟(民青)に参加していた(あまりの非民主的運営に愛想を尽かしたが)。左翼の生態については詳しいのだ。復古右翼が抗議してきたら、「強きを挫き、弱きを助ける」―人の道として、これを実践するよう勧めるだけである。