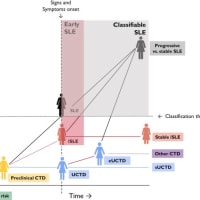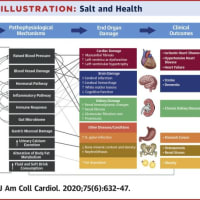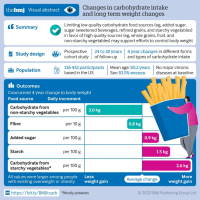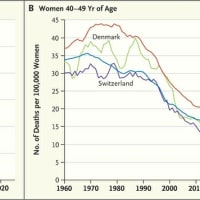高リスク一過性脳虚血発作と脳梗塞に対するクロピドグレルとアスピリンによる DAPT の効果
N Engl J Med 2018;379:215-225
背景
軽度の脳梗塞または一過性脳虚血発作(transient ischemic attack: TIA)後 90 日間に脳梗塞を再発するリスクは 3〜15%である。
いくつかの臨床試験において、アスピリン (aspirin) は脳卒中の再発リスクを約 20%減少させることが示されている。クロピドグレル (clopidogrel) は P2Y12 受容体経路を介して血小板凝集を阻害するが、この機序はアスピリンと相乗的である。この 2 剤の併用は、急性冠症候群患者における虚血性イベントのリスクを減少させる上で、アスピリン単独よりも有効である。
我々は、軽度の脳梗塞または TIA を発症した国際的な患者集団において、クロピドグレルとアスピリンの併用療法をアスピリン単独療法と比較評価するために、Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke(POINT 試験)を実施した。
方法
無作為化試験において、軽症の虚血性脳卒中または高リスクのTIA患者を、クロピドグレルを 1 日目に600 mg (ローディングドーズ)、その後は 75 mg/日を投与し、さらにアスピリン(50~325 mg/日) を併用する群、または同用量のアスピリンを単独投与する群に割り付けた。各群のアスピリンの用量は治験責任医師が選択した。Time-to-event 解析における有効性の主要アウトカムは、脳梗塞、心筋梗塞、虚血性血管イベントによる死亡からなる 90 日後の複合虚血性イベントとした。
結果
269 の国際施設で合計 4,881 例の患者が登録された。
図 1. 対象患者
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6193486/#F1
表 1. 患者背景
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6193486/#T1
データ・安全性モニタリング委員会が、クロピドグレルとアスピリンの併用は 90 日目においてアスピリン単独よりも複合虚血イベントのリスクが低く、出血のリスクが高いと判断したため、試験は予定症例数の 84%が登録された時点で中止された。
複合虚血イベントは、クロピドグレル+アスピリン投与群では 2,432 例中 121 例(5.0%)、アスピリン+プラセボ投与群では 2,449 例中 160 例(6.5%)に発生し(ハザード比、0.75;95%信頼区間 [confidence interval: CI]、0.59~0.95;P = 0.02)、ほとんどのイベントは初回イベント後 1 週間に発生した。大出血はクロピドグレル+アスピリン投与群 23 例(0.9%)およびアスピリン+プラセボ投与群 10 例(0.4%)に発生した(ハザード比、2.32;95%CI, 1.10~4.87;P = 0.02)。
図 2. 複合虚血イベントと出血の経時的なイベント発生率
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6193486/#F2
表 2. アウトカムと安全性プロフィール
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6193486/#T2
議論
この国際多施設無作為化試験において、軽症の脳梗塞または高リスクの TIA 患者において、クロピドグレルとアスピリンの併用療法を受けた患者は、アスピリン単独療法を受けた患者に比べて、重大な虚血性イベントのリスクは低かったが、大出血および小出血のリスクは高かった。
脳梗塞は有効性の主要評価項目の複合イベントのほとんどを占めており、抗血小板薬 2 剤併用療法の効果はこれらの脳卒中の発生率の減少に起因していた。それぞれの転帰による障害を確認することができないため、臨床的転帰と安全性転帰を直接比較することはできないが、90 日間にクロピドグレル+アスピリン治療を受けた患者 1,000 人あたり、この治療により約 15 件の虚血性イベントが予防され、5 件の大出血が発生すると推定される。
本試験の結果は、中国人患者を対象とした CHANCE 試験の結果を、より多様な集団や医療環境に拡大したものである。CHANCE 試験では、中等度から重度の出血の発生率は、抗血小板薬併用群、アスピリン群ともに 0.3%であった。この 2 つの試験の結果は、非心原性脳梗塞を対象としており、心塞栓症が原因と推定される脳卒中患者や、脳卒中が軽症であるために静脈内血栓溶解療法や血管内血栓除去術の適応とならない脳卒中患者は除外されている。CHANCE 試験では、我々の試験で用いられたものとは異なるクロピドグレルとアスピリンの併用が試験された(最初の 21 日間は 2 種類の薬剤を併用し、その後クロピドグレル単独で初回負荷量 300 mg を投与したのに対し、我々の試験ではクロピドグレル 600 mg を投与し、その後 1 日 75 mg を投与した)。
CHANCE 試験では、クロピドグレル+アスピリン併用療法の負荷用量が少量であったこと、あるいは投与期間が短かったことから、出血のリスクが少なかった可能性がある。この仮説は、クロピドグレル+アスピリン併用療法の有益性が試験の最初の 1 ヵ月間に集中していたのに対し、出血のリスクは試験期間を通じて比較的一定であったという我々の所見と一致している。さらに、クロピドグレルの活性化の機能低下に関連する CYP2C19 をコードする遺伝子の多型は、アジア系に多い。
国際的な SOCRATES(Acute Stroke or Transient Ischemic Attack Treated with Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes)試験では、国際的な集団において P2Y12 阻害薬であるチカグレロル (ticagrelor) とアスピリンが比較され、主要血管イベントのリスクに群間差は認められなかった。
チカグレロルとアスピリンの併用は THALES(Acute Stroke or Transient Ischemic Attack Treated with Ticagrelor and ASA [acetylsalicylic acid] for Prevention of Stroke and Death)試験(ClinicalTrials .gov number, NCT03354429)で試験されている。クロピドグレルとアスピリンによって達成される以上の血小板活性の遮断は過剰出血を引き起こす可能性がある。TARDIS(Triple Antiplatelets for Reducing Dependency after Ischemic Stroke)試験では、脳梗塞または TIA 発症後 48 時間以内にクロピドグレル、アスピリン、ジピリダモール (dipyridamole) の 3 剤併用療法をクロピドグレル単独またはアスピリン+ジピリダモール併用療法と比較した。その結果、3 剤併用療法を受けた患者では、脳卒中再発の発生率や重症度に関する有益性は認められなかったが、出血率が高かった。
この試験には限界がある。中等度から重度の脳卒中患者、心原性脳梗塞患者、血栓溶解療法や血栓除去術の適応となる患者はこの試験には含まれていなかったので、結果をこれらの群に一般化することはできない。試験参加基準から、血小板阻害が有効である可能性のある症候性頸動脈アテローム性動脈硬化症の患者数は限られていた。しかし、中止率は 2 つの治療群で同程度であり、中止の理由も同様であった。さらに、ほとんどのアウトカムイベントは早期、つまり中止の大半が起こる前に起こっており、as-treated 解析の結果は intention-to-treat 解析の結果と同様であった。
われわれの試験では、全体的なイベント発生率は予想より低かったが、特に ABCD2 スコアの低い TIA 患者において、その傾向は顕著であった。このことは、一部の患者は TIA を発症しておらず (つまり誤診)、治療効果はもともと期待できないことを示唆している。アスピリンの用量は 2 つの治療群で異なっており、これは治験に参加した医師の臨床プラクティスを反映したものであった。しかし、検出力は十分でない可能性はあるが、アスピリンの用量による治療効果の差は示されなかった。
結論として、さまざまな国の軽症脳梗塞または高リスク TIA 患者において、クロピドグレルとアスピリンの併用投与を受けた患者は、90 日間の試験期間中、脳梗塞、心筋梗塞、虚血性血管死などの複合リスクは低かったが、大出血のリスクはアスピリン単独投与を受けた患者より高かった。
元論文
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6193486/