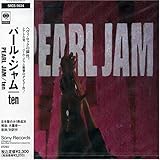|
グレース
価格:¥ 2,345(税込)
発売日:1994-09-08 |
<グランジ・オルタナティブ Vol.3>
「Grace」 (グレース) 1994年US
1.モジョ・ピン
2.グレース
3.ラスト・グッドバイ
4.ライラック・ワイン
5.ソー・リアル
6.ハレルヤ
7.恋人よ、今すぐ彼のもとへ
8.コーパス・クライスティ・キャロル
9.エターナル・ライフ
10.ドリーム・ブラザー
ジェフ・バックリィの声は日常に流され麻痺しスポイルされている者に痛々しく突き刺さる。美しい、という形容で聞き流せる類ではない。
1966年生まれ。5オクターブの父親のティムからうけついだ3.5オクターブの恵まれた声帯。高校時代はジャズバンドを組み、フュージョンを聴き、LAの音楽短大でバンドを組み、と同時代のアメリカのグランジ・オルタナ系のガレージ・パンク的とは一線を画すバックグラウンドがこの人のユニークネスの素になっているのだろう。
精神性は間違いなく、Xジェネレーションのそれだ。CMJでソニックユースやREMがあけた風穴が
見せたものは、80年代までのロックが見せた夢や享楽とは正反対の、極めてパーソナルな、ちいさな、繊細な苦しみと葛藤とストレスの発露であり、そのリアルな戦いこそが圧倒的な共感を呼び、
今に至るまで、殆ど全てのアーティストの音楽性に共通的に影響している時代的気分と言えるだろう。
NY系パンクからソニックユースまでガレージパンクの表現の中でそれらは表現され、90年代初め、カートコバーンという突出した個の輝きを得て爆発した。ジェフ・バックリィはカートと並び立つほどのもう一方の突出した個として、同じ気分を発露した人といえるだろう。
ジェフ・バックリィの声にはまず諦念のようなものが感じれる。
しかし諦めきるにはなんといっても若すぎるし、あまりに繊細でナイーブだ。
声の先にまで通っている末梢神経が、撫でるような風にも痛みを感じているような繊細さ。
よどみのない澄んだ声がロックの文脈を超えたバランス感覚、センスで自由に空間をさまよう。
まるで飛べない鳥が、声だけ飛翔してゆくような切なさ。
そして何よりその音を痛く、切なくさせているのは、彼の声に希望を見いだそうとする祈りのようなものが感じられるからだ。傷つき諦め痛みながらも祈りの悲鳴をあげているような、そんな声に聞こえるのだ。”美しい”という言葉ではとても形容できるとは思わない。。
革命的な音楽は突出した個によってもたらされるというが、ガレージパンク系、グランジの荒々しさとは全く異なる天分という方法で傑出してしまったジェフ・バックリィには、グランジ系のパンク的ムーブメントのようなフォロワーはありえず、その資格を相当選ぶことになり、派手な流れにはなりようもなかったが、それだけに、もし彼自信が生きていたら、どんなことになっていたのかと、どれだけの人が思ったことだろうか。時代の気分を歌い上げる21世紀のNo.1シンガーソングライターになっていただろうか。あるいは彼の才能に張り合えるほどのバンドを得て、新しいグルーブを手に入れたりしただろうか。U2かREMか、それを超える存在にだってなり得たのではないか。90年代で最も将来を嘱望されたアーティストは、その才能を開花させた矢先にいなくなってしまった。
ほとんどの曲がそのような彼の個性をうつしているが、レナード・コーエンのカバー 6. ハレルヤ がほっとするような癒しの空気をもち異色だ。ライブアルバムなどでも、自作以外のカバー曲でみせる違う顔が、彼のもう一つの魅力ともいえるだろう。
彼亡き後、そのフォロワーとしての資格を得ているのはレディオヘッドかジャズピアノのブラッド・メルドーくらいだろうか。しかしその真摯な精神性と音楽性は現代のロックの一つの確信として、意識的なロックバンドのバックボーンとして在り、伝説のような、夢のように消えてしまったジェフ・バックリィという鮮烈な記憶として今という時代の墓銘碑としてのこりつづけることだろう。