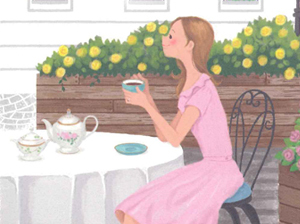7月のラボ便り
7月のラボ便り
皆様、こんにちは。
ジメジメと暑い日が続きますね。
今回のラボ便りでは、
精子の構造についてお話します。
精子は、おたまじゃくしの様な形をしており、
頭部・中片部・尾部の3カ所に、大きく分けられます。
それぞれの機能は以下の通りです。
・頭部(頭の丸い部分)
…中には男性の遺伝情報が含まれています。
・尾部(しっぽの部分)
…尾部の動きによって、精子は泳いで前へ進み、卵子に向かう事が出来ます。
・中片部(頭部と尾部の間の部分)
…精子が動く為に必要なエネルギーを作る、ミトコンドリアが含まれています。
精子は、
初めからおたまじゃくしの様な形をしているわけではありません。
最初は、丸い細胞です。
精巣内で作られていく過程で、
頭部・中片部・尾部に分かれていきます。
また、細胞の形が変わっていくだけでなく、
卵子と受精する事が出来る様に、染色体の数を減らす変化をします。
何故、染色体を減らす必要があるのでしょうか。
それは、受精をし、新しい染色体の組み合わせを作る為です。
元々、人の体の細胞には、46本の染色体が入っています。
同じ長さ同士の2本の染色体が組み合わさった状態で、23組あります。
精子の元になる細胞も、元々は46本の染色体を持っています。
卵子と精子、
異なった染色体を持つもの同士が合わさる事で、
新しい組み合わせを持った細胞、新しい生命が誕生します。
しかし、ここで精子の染色体が46本ある状態のままだと、
新しい組み合わせを作る為には多いのです。
同じ長さ同士の染色体を半分に分け、
ひとつの細胞に23本ある状態にする必要があるのです。
精子が卵子と受精する為に染色体の数を減らすように、
卵子も染色体の数を減らし、受精が出来る状態に変化をします。
 とくおかLCラボスタッフより
とくおかLCラボスタッフより
ーby事務長ー

 スタッフが綴るアメブロもご覧になって下さい
スタッフが綴るアメブロもご覧になって下さい
 とくおかレディースクリニックHPはこちら
とくおかレディースクリニックHPはこちら
コマーシャルの下(一番下)にございます
「人気ランキングブログ」




 のクリック、是非お願い致します
のクリック、是非お願い致します