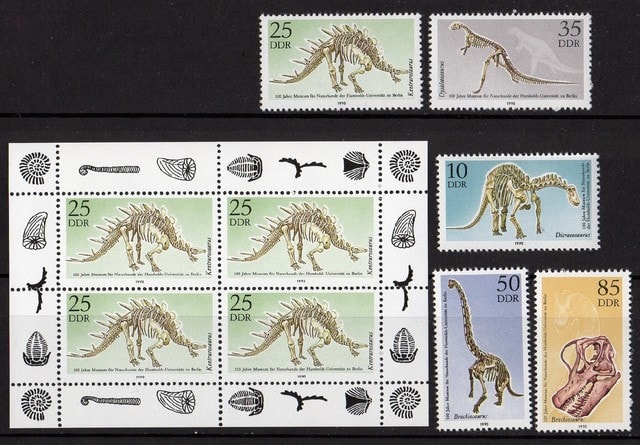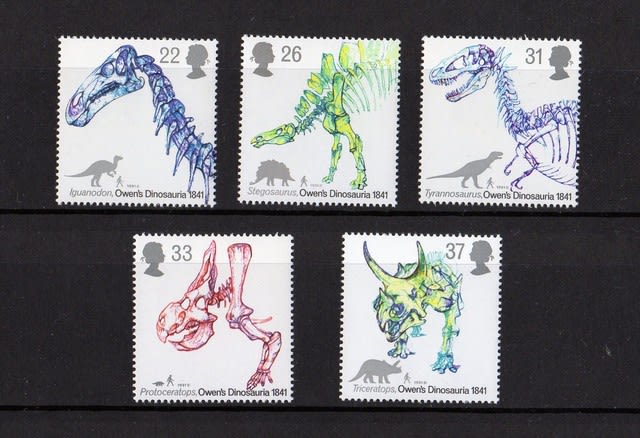大規模な噴火をしている火山の麓。
2匹のデイノニクスがテノントサウルスに襲いかかっている。鋭いかぎ爪がテノントサウルスの体に突き刺さり、流血している。生きながらエサとなっているのだ。
手前の草陰でコリトサウルスが身を潜めている。ストゥルティオミムスは別の獲物を探しに出たのだろうか。全てをトロオドンが冷徹に見つめている。
彼らのこうした日常を打ち破るように、空から脅威が迫っている。隕石が長い光の尾を引いて落下しているのだ。
1997年にマダガスカルで発行された、恐竜たちの生き生きとした姿を描いた小型切手シートである。
マダガスカルの通貨は「アリアリ(Ariary)」。額面は2500アリアリである。2004年12月31日までマダガスカルフランとの併用であったため、アリアリの上に12500FMG(マダガスカルフラン)も記載されている。
こちらは「スタンプショウ2018」の、ロータスフィラテリックセンターさんのブースで発掘した。
それでは、マダガスカル共和国(Repoblikan'i Madagasikara)について。
マダガスカル共和国(Madagascar)、通称マダガスカルは、アフリカ大陸の南東海岸部から沖へ約400キロメートル離れた西インド洋にあるマダガスカル島及び周辺の島々からなる島国である。
・・・
先史時代に存在した超大陸ゴンドワナは今からおよそ1億3500万年前に分裂し、「マダガスカル=南極=インド」陸塊と「アフリカ=南アメリカ」陸塊とに分かれた。その後マダガスカルは、およそ8800万年前ごろにインド亜大陸や南極大陸と分裂し、島に残された動植物は比較的孤立した状態で進化した。(ウィキペディア)
ワオキツネザルとバオバブで有名な島国である。ワオキツネザルも原始的なタイプのサルだ。8800万年前に大陸と切り離されたこの島の現生固有種の動物たちも、大変興味深い存在だ。実は私の「いつか行ってみたい国ランキング」1位の国である。
1枚のシートに5種類もの恐竜が描かれている。豪華海鮮丼のような切手である。それでは、それぞれの具材、じゃなかった、恐竜たちに注目していこう。

「植物食恐竜を肉食恐竜が襲う」という図は、昔からよく描かれてきた想像図である。恐竜と言えば、こんな風に戦っていたんだ、というむしろ当たり前の姿かもしれない。
この切手の図案も、そんな当たり前の想像図かというと、そうでもなかったのだ!
デイノニクス(Deinonychus)の歯が、大型の鳥脚類であるテノントサウルス(Tenontosaurus)と共に見つかったことから、前者が後者を食べていたことが示されていた。しかし、両者の大きさの違いを考えると、デイノニクスが集団で狩りでもしていない限り、大きな獲物を仕留めるのは到底無理な話である。これを受けて、恐竜が集団で狩りをしていたという説が、映画『ジュラシック・パーク』シリーズによって猛烈に広められていった。(『恐竜学入門』p.188)
実際に発見された化石の情報を元にした図案だったのだ。案外、恐竜同士が戦っていた証拠って少ないのかもしれない。化石に残された歯形だとか、化石に刺さってる歯だとか。プロトケラトプスとヴェロキラプトルの格闘している姿のままの化石なんていうのは、奇跡に近い発見だったのだろう。
ちなみに、デイノニクスは「恐竜内温説」(恐竜温血動物説)のきっかけとなった恐竜である。
1969年、イエール大学の古生物学者・J. H. オストロムがデイノニクスの学名記載をした。その彼の論文が、その後の恐竜学を一変することとなったのである。
彼は、デイノニクスの骨格を調べるうちに、「その骨格デザインは高い運動性能以外の機能があるとは思い当たらない」(『恐竜学入門』p.298)、と結論づけた。それまで恐竜はワニのように外温性(いわゆる冷血動物)であると思われており、それが一般常識だったのだから、オストロムの論文は画期的、革命的なものだったのである。
テノントサウルスはイグアノドンティア類というグループに属する。
彼らは、植物の多様化と関係が深いと言われている。
鳥脚類の多様性の進化は裸子植物と被子植物の多様性と平行しているように見えるのだが、おそらくこれは偶然ではなく、恐竜と植物が(あたかも二人舞踊の“パ・パ・ドゥ”のように)ある種のパートナー関係を結んでいたせいかもしれない。すなわち、裸子植物は捕食から逃れる方向に発達し、そして鳥脚類はますます効率的に栄養素を抽出する方向に発達した、ということだ。(『恐竜学入門』p.138)
というわけで、まだまだ具材、じゃなかった、注目すべき恐竜たちが残っているので、次回へと続く。
【参考サイト・文献】
・ウィキペディア「マダガスカル」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%80%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB
・『恐竜学入門』 Fastovsky, Weishampel 著、真鍋真 監訳、藤原慎一・松本涼子 訳 (東京化学同人、2015年1月30日)