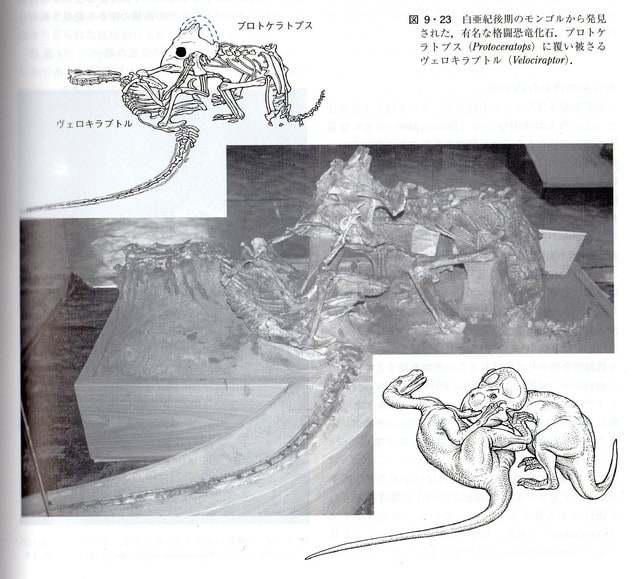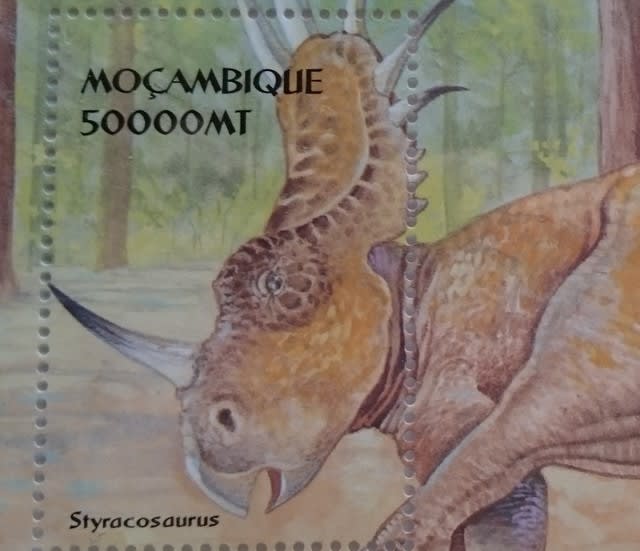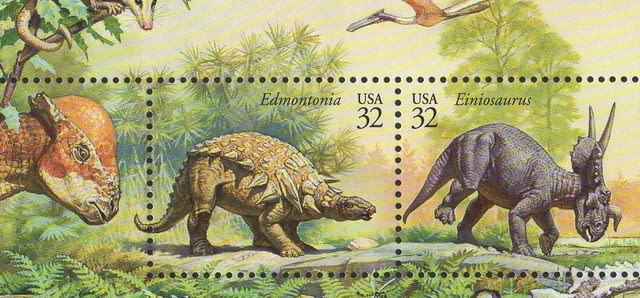大切な方にお手紙を出そうと、町の小さな郵便局へ出かけた。
便せんに合わせたデザインの切手を探すためだ。
切手は収集するけど筆無精な私が、珍しく切手本来の使い方をするために購入するのだ。
「確かあんなのが出てるはず」「あれもいいけどこっちも良かったよね」と思いつつ窓口へ。
「すみません、82円切手のきれいなのありますか?」と私。
「はい、こちらの2種類でしたら1枚ずつお売りできます」と局員さん。
勧められたのは「日露友好」のきれいな花束切手と、「切手趣味週間」の風神・雷神切手。どちらも魅力的である。
ふと記念切手の掛かったラックを見上げると、なんと!あのおにぎり切手が!
「おにぎり切手、まだあったんですか?!」と急に鼻息の上がる私。
「はい、ございますよ」と微笑みを浮かべる局員さん。
「1シート下さい!!!」

「おにぎり切手」と言えば、今年の『さくら日本切手カタログ2019』の表紙を飾るかわいい系切手である。普段私は「かわいい系切手」を購入することがほとんどない。「そういうのは切手女子が集めるものさ」とクールにスルーしていたのである。私は「恐竜切手収集家」であるから。ふっ。

ところがどっこい、である。『さくら日本切手カタログ2019』を参照する度に、どうも刷り込みが起きていたようだ。表紙を見る度にものすごく魅力を感じてしまったのである。とくに「おいなりさん」を図案化する辺り、渋くてかわいい!と思うようになったのだ。
日本郵便のHPで購入しようとしたら・・・売り切れだったのである。
そりゃそうだ。これ、去年2017年の10月24日に発行された切手なのだ。大分前に発行された上、めちゃくちゃかわいいときたら、複数シート購入する方々がいて当然で、とっくの昔に完売していてもちっともおかしくないのである。
だから、ちょっぴりがっかりしていたのだ。
それが、こんな片田舎の小さな町の郵便局に堂々と陳列されているなんて「奇跡である!」と思ったのだ。というわけで、遠慮深く1シート購入。
日本郵便のHPにこの「おにぎり切手」ならぬ、「おむすび切手」の紹介が載っている。
「人と人をむすぶ」お手紙にちなんで「おむすび」という意味が込められているとか。
日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男)は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」について、その社会性、機能性、地域性などを題材としたシリーズの第3弾として、特殊切手「和の食文化シリーズ 第3集」を発行します。
第3集では「生活に根ざした米料理」をテーマとしています。
ちょっと長いのだけど、図案化された各おむすびについて事細かに説明がなされているので、せっかくだから一気に引用しよう!
握り飯については、おにぎりやおむすび等、様々な呼び名がありますが、当シリーズでは、人と人をむすぶお手紙にちなみ、「おむすび」という意匠名を採用しています。
(1)太巻き
巻き寿司の誕生は江戸時代とされ、18世紀に出版された江戸料理書の中に、その製法が確認できます。また巻き寿司といなり寿司のお弁当といえば、歌舞伎の十八番「助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」の幕間に提供された「助六弁当」が挙げられます。その名称は、主人公・助六と恋仲になる吉原の花魁・揚巻(揚=いなり寿司・巻=巻き寿司)の名前に由来するといわれています。
(2)おむすび(おぼろ昆布)
北陸で定番のおぼろ昆布のおむすび。北海道や東北の一部でしか収穫できない昆布が、北陸の食文化として根付いた理由は、北前船の西回り航路(別名 昆布ロード)の重要な中継地として栄えた歴史的背景が要因でした。ちなみに昆布を幾重にも重ねて削るとろろ昆布に対し、おぼろ昆布とは、一枚の昆布の表面を薄く削ったもの。まさに職人技を味わえる伝統食品です。
(3)おむすび(うめぼし)
お弁当界の救世主、うめぼし。うめぼしのもつ殺菌・防腐効果は、鎌倉時代より兵糧食にいかされるなど、時代の目的に沿った形で重宝されてきた歴史があります。
また明治時代に出版された料理書には、安全面を考慮し、子供の夏のお弁当に、うめぼしおむすびをすすめる著者のあたたかなアドバイスがみえます。さらに昭和初期の児童書には、士気を高めるために「日の丸おむすび」を分け合う兵隊たちのお話も登場。うめぼしおむすびは、日本人の心遣いの歴史をそっと物語ってくれるのです。
(4)おむすび(鮭)
日本人と鮭の関係は古く、その関わり合いの歴史は縄文時代にまでさかのぼるとも伝えられます。奈良時代には都への献上品に重用され、中世以降も多くの武士たちに賞玩されました。
江戸時代の教訓集「雨窓閑話」には、3代将軍・徳川家光に仕えていた毛利秀元の鮭の逸話が紹介されています。それによれば、秀元がお弁当のおかずに干鮭を持参したところ、同席していた仲間たちに「珍しい」と注目され、仲良く分け合って食べたとあります。
現在もお弁当のおむすびの定番として、広く親しまれている鮭。昔も今もその人気ぶりは変わらないようです。
(5)おむすび(しらす)
俵型のおむすびをデザインしました。おむすびの形にも地域差はあり、関東では三角形、関西では黒ゴマをまぶした俵型が定着し、さらに北海道・東北では太鼓型、東海・北陸では球型を主流とする見方もあります。
また昨今の「おにぎらず」の流行で、サンドイッチ型という新たな形も登場。しかし今日ではコンビニのおむすびの影響で、地域差が薄れ、全国で三角形が定番となりつつある状況も否めません。
(6)いなり寿司
江戸時代に生まれ、屋台の人気者として愛されてきたいなり寿司。
初午の稲荷神への奉納品としても、古くから日本人の生活に根づいてきました。いなり寿司の形は、関東では俵型、関西では三角形が定番とされ、俵型は五穀豊穣を象徴する稲荷神にちなんだ米俵を意味し、三角形は稲荷神の使いである狐の耳を模していると伝えられます。また信太寿司、こんこん寿司、きつね寿司、おいなりさんなど、地域によって、その呼び名もさまざまです。
(7)おむすび(赤飯)
お食い初め、七五三、成人式、結婚式、還暦といった人生儀礼にかかせない赤飯。その歴史は古く、弥生時代にまでさかのぼると伝えられます。しかし当時は、赤色に邪気を払う魔力があると信じられ、赤米を神にそなえ、祭礼を行っていました。もち米と小豆を組み合わせるようになったのは江戸時代以降とされ、庶民の世界でも、五節句をはじめ、お祝いごとに用いられるようになりました。
(8)天むす
ナゴヤめしの定番として認知されている天むすですが、実はその発祥は三重県津市。昭和30年代初め、天ぷら定食屋を切り盛りしていた女性がまかない料理として、車エビの天ぷらで作ったおむすびを考案したのが始まりとされています。「せめて夫には栄養があるものを」という女性のあたたかな心遣いが生んだ一品として、今に伝えられます。
(9)おむすび(ごま塩)
1987(昭和62)年、石川県・杉谷「チャノバタケ」遺跡で、弥生時代中~後期のものとみられるチマキ型炭化米が発見されました。この三角形に握られた炭化米は、日本最古のおむすびの化石としても評価されています。
携帯食としてのおむすびの歴史は、平安時代にさかのぼることが出来ます。その起源は宮中や貴族社会でふるまわれた「屯食(とんじき)」(蒸したもち米を握り固めたもの)とされ、『源氏物語』にもその名称は登場します。やがて江戸時代には浅草海苔の養殖が開始されたのを機に、おむすびに海苔が使用されるようになります。
ちなみに海苔の嗜好にも東西の違いはあり、関東では焼きのり、関西では味付け海苔の人気が高い模様。ちなみに「パリパリ」の海苔が好まれるようになったのは、コンビニおむすびが誕生する1970年代後半以降とされています。
(10)おむすび(豆ご飯)
米といろいろな食材を組み合わせて味わう楽しみもまた米食文化の醍醐味です。実際江戸時代の料理書にも、米に野菜や芋、雑穀、海藻などを混ぜる多彩な製法が記されています。しかし当時の混ぜご飯は、米の増量剤として具材を加えた「かてめし」が主流とされ、米の収穫の少ない地域や飢饉対策に対応して考案されたものがほとんどでした。ちなみに豆ご飯といえば、関西では「うすいえんどう」が定番。優しい香りと甘さが、春の訪れを教えてくれます。
切手の図案についてこんなに詳細に説明がなされるというのも珍しいのではないだろうか。
こうした変形切手が貼ってあったらちょっと嬉しい。

よく見ると、カラーマークが米粒の形をしている!

裏側にはたこさんウィンナーとたくわんが添えられている!
この切手、どうやら「隠し文字」が仕込まれているらしいのだが、私はまだ「しらす」しか発見できていない。
ちなみに、肝心の大切な方へのお手紙に貼る切手であるが、こちらも素敵な変形切手にしてみた。

「夏のグリーティング切手 2018」である。涼しげで、うちわと浴衣の形の切手がかわいい。砂浜のパラソルの下に蟹が歩いているのも素敵。便せんが貝殻の模様であるから、このシートが一番合うのではないかと思い、購入した。
お手紙を出すって、なんかいいなあ。送る相手の顔を思い浮かべながら便せんを選び、切手を選ぶまで。その過程がなんとも楽しい。
しかし私、切手1枚買うつもりがなんと20枚も購入している・・・。
これって日本郵便の策略なのか!!
【参考サイト】
・日本郵便
https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2017/h291024_t.html