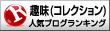このブログは「ベル麻痺」に罹患した経験から病院等で教えてくれない事を、伝えたいとの思いがあり始めたものです。
ベル麻痺は、痛感などは無いように思われますが、顔が歪んでしまうので、若い人達は精神的に苦しまれると想像できます。
私は、初期のリハビリを怠って(ほったらかしに近い)失敗しています。
癌の手術で学んだことは術後のリハビリの重要性でした。
麻酔から目覚めると、ICU内でリハビリが始まります。
頭を上げるだけで痛いのですが、痛みは薬で抑えてリハビリをするのだそうです。
この経験からベル麻痺も治療中から「自分で出来るリハビリ」は行う方が賢明なように思います。
具体的には、
- 舌を動かす
- 鏡を見ながら口を動かす発声練習「ア エ イ ウ エ オ ア オ」を行います。
- 私の場合は、ウとオが出来ませんでした。
- それから首のマッサージを丹念に行います。
- 「広顎筋・胸鎖乳突筋」のマッサージが重要に思われます。
さて、タイトルの「愚痴なしブログ」は、子供の頃に「男の子(おのこ)は、泣くな、グチるな」と、バァーちゃんに言われたことと、成人してからの故相田みつお氏の「のにがつくと 愚痴になる」に由来しています。
途中で、検索しやすいように、頭に「ベル麻痺」つけまして現在に至っています。
カテゴリー一覧を見ますと「電験3種」136件あり、件数からしますと「電験3種」ブログに見えますが、あくまでも主役はベル麻痺です。
ベル麻痺の更新は行っていませんが、必要なことは網羅されています。
カテゴリーに「電験3種」を設けのは電験関係のブログを読んで、一般のテキスト等に載っていない事を、織り込みながら書いてはと考えました。
当初、ブログ機能に不慣れなため回路図や模式図の載せる方法が分かりませんでした。
そこで回路図をスキャナで読み込み写真化すればブログにのせられることを発見し、今日に至っています。(回路図はエクセル化したファイルで多数ありますので楽をしています)
<現在、市販中の書籍に殆んど書かれていない主な項目の抜粋>
- 「SCRのターンオン」⇒ゲートバイアスゼロでのターンオン動作
- 「hパラメータ等価回路」⇒偏微分表記を電気屋流で簡単な一次式に変換
- 「共振回路の性質」⇒L性・C性の考え方と応用
- 「PN接合」⇒全ての半導体動作の理解に通じます動作原理
- 「オペアンプ」⇒内部等価回路から新しい等価素子の導入
- 「差動増幅回路」⇒最も優れた増幅器で真空管時代から注目していました。
- 「PWM」⇒Mは変調なのに変調の説明が少ないと感じています。
1.の「SCRのターンオン」は1970年7月に出版された加野洋吉/鈴木彰著「小電流サイリスタ」日刊工業新聞社、初版および専門雑誌を参考文献として学んだもんですが、今は絶版と考えられます。
ショックレーの接合理論に基づく、接合型半導体の基本は「PN接合」にあります。
接合型半導体は、接合面が1つ増す毎に動作が1つ加算されることの理解が必要です。
- ダイオーは、接合面が1つであり、注入⇒引き寄せの2行程です。
- TRは、接合面が2つであり、注入⇒拡散⇒引き寄せの3行程です。
- SCRは、接合面が3つあり、注入⇒拡散⇒蓄積⇒引き寄せの4行程です。
7.PWM(パルス幅変調)は、一般書籍の多くが、変調については一部分について数式で示されています。
- 変調を波形動作でなく数式を見て理解できる方は、電験を例にしますと3種および2種を受ける必要がなく、最初から1種を受験する方になります。
- 最近は別にしましてパワー制御・半導体関連では変調理論が得意でないことが著書から推察できます。
- また、数式で理解できても波形を作成できる保証は無いと考えられます。
- 数式で示すのは著者は楽なのです。工学は積み重ねの学問と言われますので自分で考えて作りすものでは無く学んだもので済ませることが可能です。
- しかし、波形は個々について自ら動作を理解し作図する必要があります。
- 便法も含めて波形は入門者が理解するのに最適な武器と思っていますので、波形を多用しています。