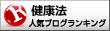TR回路で接地方式を見分け方が難しと感じる場合が有ります。
〇〇電極が設置されているから〇〇接地としても当たる確率は高いのですが、技術屋らしくないので正確な見分け方を示しておきます。
☟ベース接地回路です。この回路は全ての基本であるので、接合TRの模式図で示します。
信号電流と出力電流がベースを共通する回路をベース接地回路と言い、ベースコモンともいう。

市販本ではいきなりβから入るケースを見かけますが、よく理解していない方ですね。
α→βの順ですからαの解説が先になるのが正しいと考えられます。
- TR動作は、B-E間に順バイアス、B-C間に逆バイアスを掛けることで動作する。
- 順バイアスによりE電極からB電極へのキャリアの注入が起こる。
- B領域に注入されたキャリアはN形とP形のキャリアの濃度差により拡散現象が働き、B領域を拡散により移動する。
- B領域を拡散で移動する際にB領域のキャリアと再結合が起ります。
- 即ち、注入されたキャリアの一部が再結合で失われることになります。
- この失われたキャリアを外部から補充する必要があり、この補充動作がベース電流となるのです。
- 一方、EからB注入されたキャリアは拡散現象により移動し、Cとの接合面に達すると、B-C間に掛かっている逆バイアスがCに到達したキャリアに対しては加速電圧となり、コレクタ電極に引き寄せられる。
- 即ち、キャリアは注入→拡散→引き寄せの3工程で移動し動作することになります。
- さて、例え話で、E電極から100個のリンゴを送ったらC電極に98個が届いたとすればリンゴの輸送効率は98%となります。
- この輸送効率に相当するのが「α」なのです。従って、αは1以下になります。
- 動作を検討すると、βはαから数式的に誘導されたものであり、原理的ではないのです。
ベースはその名の様に基本ですね。
TRの動作は、ベース接地から学ぶと、惑わされことなく理解できます。
- この接地方式は、αが1以下なので電流増幅は出来ない。
- rLを大きくできるので電圧増幅と電力増幅は可能である。
- ただし、入力インピーダンスが低く一般的に使い勝手が悪い。
☟E接地回路です。信号電流と出力電流が共にエミッタを共通する回路をエミッタ接地という。
エミッタコモンとも呼ばれる。

- 電流増幅、電圧増幅、電力増幅が行えるので最も広く使用される接地方式である。
- エミッタに抵抗を入れることで電流負帰還を掛けることが出来のでバイアスの安定化が可能である。
- エミッタ抵抗を入れると、交流信号に対しても電流負帰還が掛かるのでバイパスコンデンサを並列に入れて使用する。
☟コレクタ接地回路またはエミッタホロワ回路です。
信号電流と出力電流が共に負荷RLを流れる接地回路をコレクタ接地回路という。
また、別名でエミッタホロワ回路、ボルテージホロワ回路と呼ばれる。
- 電圧増幅度が1以下なの電圧増幅は出来ないと考える。
- 入力インピーダンスが高く、出力インピーダンスが低い特徴があり、インピーダンス変換器としての用途がある。
- また、回路間に挿入することで前段と後段の緩衝増幅器(バッファー回路)として用いられる。

- コレクタ接地回路は、テブナンの定理を応用すればコレクタは定電流源に接続されているので
- コレクタとアース間は同電位とることから推測してコレクタ接地回路と見ることも可能です。
<追記>前回の解答例
iout=(1+β)ib
vout=iout×RE=(1+β)ib×RE------①
vin=rbib+(re+RE)iout------②
電圧利得vout/vin=②/①=(1+β)REib/re(1+β)(re+RE)
数値を代入し求めると≒0.97