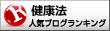昭和40年代にはじめて電験3種講座を受けた際に「法規は理論である」と法規担当の講師が教えてくれました。
例えば、IV電線の許容電流は理論的に決まり、60℃で流せる電流はゼロになることは理論の問題と理解できました。
なお、電験1種の法規(過去問)に理論と同等の内容が出題された事が有ります。
さて、この問題は消防設備士の実技(製図)の過去問ですが、法規を知らないと解けない問題です。
(何となく昭和40年代の電験3種問題を連想します)


問(3)このポンプの電力を求めよ。ただし、機械効率は65%とする。
この消防設備士の製図問題は、法規を勉強しないと正解が得られないのです。
①の揚程を求める問題は、4階の倉庫であることから1号消火栓になり、1号消火栓の17mの固定損失を忘れると全滅です。(2号栓の場合は25m)
答え H=h1+h2+h3+17 (m)
②全揚程は、値られた損失ヘッドと落差を加算して求めます。
③の問は、法規を知らないと解けないので、消火栓は同時に放水するのは2箇所と考えて答えを求めます。
1個の消火栓の送水量は150L/min、2個では300L/minとなり、ポンプの吐出量=300L/min
(2)の問題は少し難しいと感じましたが、法規と意味を理解すれば解けます。
法規には、吐出量の150%増での全揚程を定格全揚程揚程で除した値が65%以上であることが判定条件になります。
320×1.5=480L/min
QH曲線上にこの値を取ると、全揚程は10mとなり、10÷40=0.25となり、0.65未満であることから不適当と判断される。
(3)は付け足しですが、問題範囲に無くとも何時も計算するようにしています。
電験3種の発電の問題と類似します。