(1)第63代 冷泉天皇
62代村上天皇と、藤原師輔の娘「安子」の子。
村上天皇の第一皇子には、藤原菅根の孫「広平親王」がいたにも関わらず、
第二皇子の冷泉天皇が、生後2ヶ月で立太子されている。
また、数々の奇行から、即位に反対する者もいたが、押し切って即位した。
これは、当時の藤原一族の中でも、「藤原忠平一族」が際立って権力が強かったことを
示していると、考えられる。
【冷泉天皇の奇行】
皇太子時代より、精神に問題があるといわれていた。
・足が傷つくこともかまわず、一日中鞠を蹴っていた。
・父帝村上天皇の手紙に対して、男根の図を描いて送った。
・番小屋の屋根の上に、座り込んでいた。
・場をわきまえず、大声で歌う。
【摂政】
冷泉天皇自身が政治を執ることが出来ず、病気として、藤原忠平の子「藤原実頼」が
摂政として、政治の実権を握る。
関白・左大臣:藤原実頼
右大臣:源高明
(2)安和の変
[安和の変]は、969年に起きた藤原氏による「源高明」をターゲットとする他氏排斥事件。
冷泉天皇の次期皇太子の候補は、冷泉天皇の弟である「為平親王」と
その下の弟「安平親王」の2人が候補にあった。
だが、年長者であり、次期皇太子の有力候補であった「為平親王」は、
その妻の父が右大臣「源高明」であり、為平親王が天皇になれば、
源高平が外戚となるため、藤原氏としては、源高平を失脚させる必要があった。
969年、源高明が冷泉天皇の謀反を計画している密告があり、源高明は流刑となった。
この事が、藤原北家の摂関常置のきっかけ、
藤原家による、国政の完全支配体制の完成であった。


「藤原実頼」と「藤原伊尹(ふじわらのこれただ)」がたくらんだ説が有力。
62代村上天皇と、藤原師輔の娘「安子」の子。
村上天皇の第一皇子には、藤原菅根の孫「広平親王」がいたにも関わらず、
第二皇子の冷泉天皇が、生後2ヶ月で立太子されている。
また、数々の奇行から、即位に反対する者もいたが、押し切って即位した。
これは、当時の藤原一族の中でも、「藤原忠平一族」が際立って権力が強かったことを
示していると、考えられる。
【冷泉天皇の奇行】
皇太子時代より、精神に問題があるといわれていた。
・足が傷つくこともかまわず、一日中鞠を蹴っていた。
・父帝村上天皇の手紙に対して、男根の図を描いて送った。
・番小屋の屋根の上に、座り込んでいた。
・場をわきまえず、大声で歌う。
【摂政】
冷泉天皇自身が政治を執ることが出来ず、病気として、藤原忠平の子「藤原実頼」が
摂政として、政治の実権を握る。
関白・左大臣:藤原実頼
右大臣:源高明
(2)安和の変
[安和の変]は、969年に起きた藤原氏による「源高明」をターゲットとする他氏排斥事件。
冷泉天皇の次期皇太子の候補は、冷泉天皇の弟である「為平親王」と
その下の弟「安平親王」の2人が候補にあった。
だが、年長者であり、次期皇太子の有力候補であった「為平親王」は、
その妻の父が右大臣「源高明」であり、為平親王が天皇になれば、
源高平が外戚となるため、藤原氏としては、源高平を失脚させる必要があった。
969年、源高明が冷泉天皇の謀反を計画している密告があり、源高明は流刑となった。
この事が、藤原北家の摂関常置のきっかけ、
藤原家による、国政の完全支配体制の完成であった。


「藤原実頼」と「藤原伊尹(ふじわらのこれただ)」がたくらんだ説が有力。










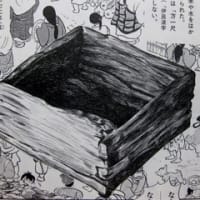









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます