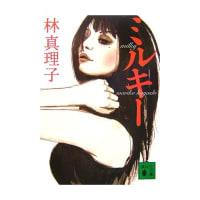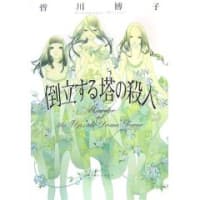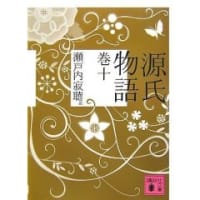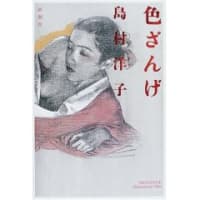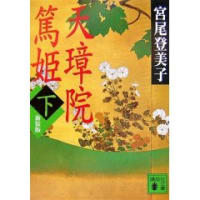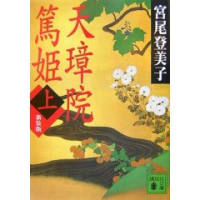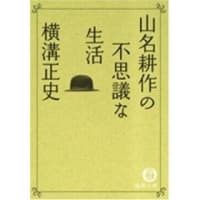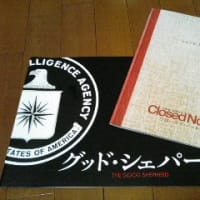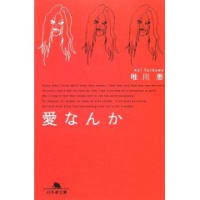横溝正史『山名耕作の不思議な生活』
2007年8月15日初刷
徳間文庫
(1977年3月 角川書店より刊行の復刻)
【裏表紙より】
なぜ彼はあんな妙な所に住まうのか。新聞記者の秘密とは?(表題作)夫がいつの間にか双子の弟と入れ替わっている!妄想に囚われた夫人の恐怖(双生児)……横溝正史は短篇の名手でもあった。当初江戸川乱歩名で発表された作品を含む傑作集!
***************************************************************
徳間文庫による横溝正史作品の復刻シリーズ。
この復刻シリーズでは、『夜光虫』(2007.4.5発行)を購入・読んでいる。
横溝正史作品といってすぐに思い出すのは、やはり金田一耕助のミステリで、私もそこから入って、『夜光虫』などの“耽美物”や、同作『山名耕作…』のような“ナンセンス”時代の作品に遡っているわけだが、ここまでガラリと何度も作風を変えてしまえるのも凄いことだ(そういう作家で、そういう時代だった)。
この柔軟性と(いい意味での)こだわりの無さはデヴィッド・ボウイに通ずるものがあるように思うがどうだろうか。
本書は、昭和5年前後、著者が20代後半の頃に書かれた短編集である。
一口に「ナンセンス」といっても、作品のテイストはバラバラで、復刻に際して寄せ集めてきた感がなきにしもあらずだ(読了まで時間がかかったのは、統一性のなさのせいにしていいだろうか……)。
正直、今は死滅してしまった“ユーモア&ナンセンス”は、今の私たちにとっては陳腐だ。なんといっても、80年も前の風俗である。80年前の考え方を古臭いと感じるのは当然だろう(当時の読者は、こういう話が「面白く」「洒脱」に感じたのか…)。
逆にいえば、それは、「昭和初期」という時代の空気を十分に味わうことができるということでもある。
そう、タイを結んで、ハットをかぶり、ステッキをついて、「お嬢さん、レビューかキネマでも見に行きませんか?」と気障に決める、戦前のステレオタイプな知識階級の青年紳士像が容易に脳裏に浮かんできて、自由に動きまわる。
翻訳で食い扶持を稼ぐ青年、新進作家、雑誌の編集者、といった主人公たちは、横溝正史自身の姿だろう。気障で、おおらかで、何より若かった頃の横溝正史が、自分の頭の中に現われる、というのはなかなか面白い。
また、巻末の「解説」に詳しいが、当時、編集者だった横溝正史が、なかなか執筆の進まない江戸川乱歩の代わりに作品を書いて、乱歩名義で発表した作品、とか、初めから代筆の了解を得た上で書いて発表した作品、だとかのエピソードが載っていて、仰天した。
簡単にうなずく乱歩も、簡単に乱歩として書いてしまう横溝も、どちらも凄いが、出版黎明期の、なんと破天荒で、なんと自由だったことだろう。
同じことを今やったら、大変な問題である(タレントの自伝本のゴーストライター代筆はまったく別として)。
余談だが、同じくナンセンス物の最近の復刻では、角川書店の『喘ぎ泣く死美人』(2006.12.25発行)があるが、こちらのほうが、作品の質が高いように思う(こちらはすぐに読めてしまった)。
<『山名耕作の不思議な生活』収録作品>
・山名耕作の不思議な生活
・鈴木と河越の話ネクタイ綺譚
・夫婦書簡文
・あ・てる・てえる・ふいるむ
・角男(つのおとこ)
・川越雄作の不思議な旅館
・双生児
・片腕
・ある女装冒険者の話
・秋の挿話
・二人の未亡人
・カリオストロ夫人
・丹夫人の化粧台
2007年8月15日初刷
徳間文庫
(1977年3月 角川書店より刊行の復刻)
【裏表紙より】
なぜ彼はあんな妙な所に住まうのか。新聞記者の秘密とは?(表題作)夫がいつの間にか双子の弟と入れ替わっている!妄想に囚われた夫人の恐怖(双生児)……横溝正史は短篇の名手でもあった。当初江戸川乱歩名で発表された作品を含む傑作集!
***************************************************************
徳間文庫による横溝正史作品の復刻シリーズ。
この復刻シリーズでは、『夜光虫』(2007.4.5発行)を購入・読んでいる。
横溝正史作品といってすぐに思い出すのは、やはり金田一耕助のミステリで、私もそこから入って、『夜光虫』などの“耽美物”や、同作『山名耕作…』のような“ナンセンス”時代の作品に遡っているわけだが、ここまでガラリと何度も作風を変えてしまえるのも凄いことだ(そういう作家で、そういう時代だった)。
この柔軟性と(いい意味での)こだわりの無さはデヴィッド・ボウイに通ずるものがあるように思うがどうだろうか。
本書は、昭和5年前後、著者が20代後半の頃に書かれた短編集である。
一口に「ナンセンス」といっても、作品のテイストはバラバラで、復刻に際して寄せ集めてきた感がなきにしもあらずだ(読了まで時間がかかったのは、統一性のなさのせいにしていいだろうか……)。
正直、今は死滅してしまった“ユーモア&ナンセンス”は、今の私たちにとっては陳腐だ。なんといっても、80年も前の風俗である。80年前の考え方を古臭いと感じるのは当然だろう(当時の読者は、こういう話が「面白く」「洒脱」に感じたのか…)。
逆にいえば、それは、「昭和初期」という時代の空気を十分に味わうことができるということでもある。
そう、タイを結んで、ハットをかぶり、ステッキをついて、「お嬢さん、レビューかキネマでも見に行きませんか?」と気障に決める、戦前のステレオタイプな知識階級の青年紳士像が容易に脳裏に浮かんできて、自由に動きまわる。
翻訳で食い扶持を稼ぐ青年、新進作家、雑誌の編集者、といった主人公たちは、横溝正史自身の姿だろう。気障で、おおらかで、何より若かった頃の横溝正史が、自分の頭の中に現われる、というのはなかなか面白い。
また、巻末の「解説」に詳しいが、当時、編集者だった横溝正史が、なかなか執筆の進まない江戸川乱歩の代わりに作品を書いて、乱歩名義で発表した作品、とか、初めから代筆の了解を得た上で書いて発表した作品、だとかのエピソードが載っていて、仰天した。
簡単にうなずく乱歩も、簡単に乱歩として書いてしまう横溝も、どちらも凄いが、出版黎明期の、なんと破天荒で、なんと自由だったことだろう。
同じことを今やったら、大変な問題である(タレントの自伝本のゴーストライター代筆はまったく別として)。
余談だが、同じくナンセンス物の最近の復刻では、角川書店の『喘ぎ泣く死美人』(2006.12.25発行)があるが、こちらのほうが、作品の質が高いように思う(こちらはすぐに読めてしまった)。
<『山名耕作の不思議な生活』収録作品>
・山名耕作の不思議な生活
・鈴木と河越の話ネクタイ綺譚
・夫婦書簡文
・あ・てる・てえる・ふいるむ
・角男(つのおとこ)
・川越雄作の不思議な旅館
・双生児
・片腕
・ある女装冒険者の話
・秋の挿話
・二人の未亡人
・カリオストロ夫人
・丹夫人の化粧台