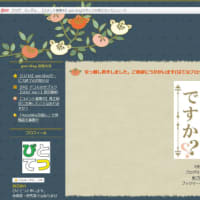中国が労働ダンピング・価格ダンピング・倫理ダンピングで米国や世界の国々の雇用先を奪った、とされている。
日本も他人事ではない。かつてのバブル日本が吊るしあげを喰らったという苦い記憶があるのだ。
いつ再び悪夢の再来となるかどうか今も決して楽観はできない。
プラザ合意と共にバブルが生まれ、金融引き締め&不動産総量規制と共にバブルがはじけて
日本は社会が根底から覆るような労働環境の悪化と製造業の産業空洞化という代償を払ったが
中国に産業空洞化というシナリオはあるのだろうか?でなければ一体どのような代償を払うのだろうか?
対中国の懸案は
世界の工場/人海戦略/焼き畑戦略/劣悪な労働環境/産業空洞化 SHEINやtiktokの攻勢
<アパレル・農産品・レアアース・電気自動車とバッテリー産業・越境ECのグローバル展開・デジタル決済/フィンテック
・半導体/通信機器・民泊・ライドシェア・シェアリングエコノミー・移民ブローカー・手招きビジネス
グローバルサウス/BRICSの台頭>
・・・そのどれもがむき出しの経済戦争のポリティックスでありどちらも譲れない熾烈な戦いである。
ひるがえって、
日本はカルチャーで世界中を席巻しているのに、世界からは恨まれることはない。コンテンツは、恨みを買わない商材だ。
これはなぜか?コンテンツという商品の特殊性がある。
コンテンツはコモディティーではないということ
工場労働者はコモディティ人材であるという事
中国の安い製品が自国の工場をつぶして雇用先を奪っていったという風な矛先認知はなぜ生まれるのか
日本の面白いアニメが自国のクリエイター産業を斜陽にもっていったという恨みはないのだろうか?
中国に提案してみてはどうか。
中国がコンテンツ産業を育成していくのに、日本からも積極的に協力していく。口先だけではない本気度を見せるために
日本のユーザーも掘り起こして、中国にとっての良きお客になれるよう市場を喚起していくお手伝いをする。
ただ日本も一方的に力添えをするのではなくて、Pエコシステムを核にした世界の電子アーキテクチャー勢力図の独立・多極化を広げていこうという目算がある。
それぞれの国がそれぞれの国独自のコンピューティング環境、文字入力環境、ネットコミュニケーション環境を目指して、
プラットフォーム自主権を確立していくのに必要なビジョンを示し日本自らがリーダーシップをとって旗振りをしていく。
この狭間で生まれる、テクノロジーと創作と商習慣と社会変容のうねりの交錯する新天地のフィールドを開拓して
そこのぴかぴかのブルーオーシャンの舞台で戦っていけばいい。
私の言う文化振興戦略はただのパッケージではなくて、すべてがペンタクラスタキーボードと絡めた、極私的な動機のもとでの化学反応に期待し企図した事象だけをもっぱら対象としている。
何を寝言を言っているという勿れ、もしものときに買っててよかった、奇貨居くべし。いまなら3割引きですよ!奥さん。
いろいろ交渉も一筋縄ではいかないだろうけれど、一つだけ言えることはこのままだと中国も世界から吊るしあげを喰らい続けているわけにはいかないだろうから、
長期的にみると中国自身も「恨みを買わない商材」・文化コンテンツの価値を再評価し貿易摩擦の緩衝材として重心を移していかざるを得ない、ということだ。
コンセンサスのアウトラインは見えているので、あとはタイミングだけだ。
ところで
日本は「コンテンツ」という財産を産業戦略の中核に据えるのはそろそろやめて世界に大胆にノウハウを還元し、次の商品を探さねばならない。
「リーダーシップ」や「提案力」、「文化コンサル」が次の商品となるのだ。
混迷する世界情勢においてどの国も今とてもリーダーシップをとれる態勢にない。これは日本の出番だ。
コンテンツは時の止まった世界でのライブラリとしての資産ではあるが、
ペンタクラスタキーボードを核とするP陣営の文化貢献はアーキテクチャールネサンスの変化のフェイズの只中にこそ活路を見出す。
ダイナミズムの中で一番重要な商品訴求力は、個々の商品の魅力だとか言うだけではなくて、
景気動向や少子高齢化やIT社会化という、トレンドをはるかに超えた大きな「流れ」を生み出すか乗るかしなければ額面以上の効果は得られない。
その「流れ」を示すようなリーダーシップやビジョンこそが一番の商品となるのだ。
それは「過剰」の力学でもある。世界経済は「過剰」によって支えられていると言ってもいいだろう。
コンテンツは、そういった世界経済の恨みを買わない、ちょっと不思議な商品で、なぜか「過剰」とも相性が良さそうだ。
コンテンツは複製が可能で拡散力がある。
コンテンツは同じものを複数買いしたりリピート買いやシェア買いしたりするのはあまり聞かない
コンテンツは所有欲を満たしてくれる
コンテンツには聖地巡礼やコラボカフェ、アニメ飯などもある
コンテンツの原料は輸入したり仕入れして組み立てるといったものではなくて、頭の中にあるものを統合し構成していく
コンテンツは新しいものが次々と生まれて旬を過ぎたものは一部の名作を除いて売れにくくなる。
コンテンツは燃料/食料/医療介護と違って常に定量の需要があるわけではなく、社会に必須という性質のものではない。
コンテンツは文化的毛繕い(コミュニケーションツール)の効用がある。
コンテンツは言語/国籍を超える
コンテンツはグッズ需要や解説屋考察屋需要やメディアミックス展開やパチンコパチスロ化、声優つながり原作者つながりスタジオつながりなどの波及効果の広がりがある
コンテンツは続編やスピンオフやアンソロジーなど派生創作もできる
コンテンツはネットミームを生み出す。
コンテンツと地域経済の連携については当ブログ「やぼ屋とヨモギと天秤棒行商」の項で目下のところ思索考察中である。
コンテンツ(文化)とアーキテクチャ(入力デバイス)の関係については文化変換(固有名詞の変換候補を呼び出す)の機能的な提案はあったが、社会構造や文化背景からの考察はまだしておらず、
いずれは材料を集めて横断的に分析していけるようにしていきたい。
日本の消費産業構造は、日用産品は中国に抑えられているし、デジタル小作人との悪名高いプラットフォームやオペレーションシステムはアメリカに握られている。
文化なんてその中間の薄いところだけを拾っている状態だ。やはりコモディティやプラットフォーマーのほうが何と言っても強い。
しかもそれらは先ほどの燃料/食料/医療介護と同じように常に需要のあるコモディティ商品で必ず買わなくてはならないという不可避性のある商品だ。
日本の文化商品は別に買いたい人だけ買えば・・・という商品で不可避性どころか悠々回避していても別に困ることもない。
いかに脆弱な消費基盤に支えられているのか、こんなんで本当に産業の中心に据えていく事を委ねていいのか、
とにかく、手を変え品を変え継続的に商品を出し続けていくしかない。
まったく、なかなかツライ板挟み状態だ。
ここまで文章を書いてきて、我ながら牽強付会に過ぎるかな・・・とセルフダメ出しをしたい。
まあ昨日思いついてばーっと乱打した勢いだけは買っているが。ちょっと衝動的にね。
日本の産業でいえば、自動車もインバウンドも頑張っているし投資収益や海外子会社利益も相当なもので、
何もアニメやサブカルだけ頑張っているわけでもないんだけどね。
今はペンタクラスタキーボードのことにやたらこじつけて考えてしまう癖が出てしまっているし、Youtubeでやたら日本すごい系の動画ばっかり流れてくるから
なんやかんや複合的要因が重なってこんな支離滅裂な文章になってしまいましたとさ。
・・・そろそろ、衣替えの季節です。