6月20日は"世界難民の日"です。
啓発や支援の輪を広げるために尽力している方々には敬意しかありません。
この日ばかりではなく、普段からも難民の方々への耳目・関心をそらすことのないようアンテナを張っていこうかと思います。
それとは別な話で「Switch難民」だとか「ランチ難民」だとかみたいなカジュアルな使い方は良くないからやめよう、という自粛の動きが各所で見られるようですが、私はそこまでやるのはいささか教条主義に凝り固まっているように思えます。
こと言葉に限って言えば、相反するアンビエントなものの組み合わせを接続しひとつのまな板の上で料理できるのはまさに言葉だけが持つ芸当で
それを否定するというのは言葉そのもの可能性を制限する動きになると私は危惧しています。
ネットの世界において検索行為は属性のマッチング判定そのものです。
マッチ属性だけで言葉狩りをしてしまう手法はもう限界が来ています。
ネット媒体のNGワードの過剰な取り締まりが原因で「幸せカナコの殺し屋生活」が「殺し」が引っかかってハッシュタグでNGとされてしまったり不具合もいろいろ出てきています。
属性統治には限界があります。インスタントな「じゃあこのワードは禁止」みたいな解決方法ではなくて、
文脈や実態に即した「非属性統治」をそろそろ視野に入れておくべき時期に来ています。
もちろん「難民」という問題意識そのものへの懐疑では決してありませんし、この文の意図しているところは難民という重い問題への重要性を毀損するものではありませんので、これをお読みになったお方はここの微妙なトーンの違いを曲解なさらぬようにご理解お願い申し上げます。
これは言葉に限った限定的なトピックです。
具体的に反論材料を4つ挙げます。
そのまえに一つ画像を。

最初の反論材料は
「複合語の意味解釈における『意味要素の稀薄化』」です。
由本陽子・岸本秀樹編『語彙の意味と文法』の中の竝木崇康(なみきたかやす)P139−158を含む箇所です。
内心複合語と外心複合語
複合語には主要部をもつ複合語ともたない複合語がある。
大抵の場合は「~は~の一種である」(...is a kind of ...)という下位集合関係が複合語全体との間で成り立つ方の構成素が、その複合語の主要部となる。(内心複合語)
例外的に主要部を持たない複合語(外心複合語)は英語ではpickpocket(すり)、scarecrow(かかし)など、
日本語では横綱、野次馬、手前味噌などがある。これらは上位下位がはっきりせず主要部をもたない。
しかし標準的な内心複合語であると思われるにもかかわらず、複合語の主要部の概念がすっきりとは当てはまらない複合語をとりあげて、「意味要素の希薄化」とでも呼べそうな現象に光をあてる。
複合語全体が複合語の主要部の下位語になっていない場合
~音痴 運動音痴 機械音痴 経済音痴
~茶碗 コーヒー茶碗 紅茶茶碗 ごはん茶碗
これらは○○音痴であっても音感の様態をあらわすものではすでになく、○○茶碗にいたっても茶を淹れる茶碗でもなく、原義の規定から逸れている。
この流れで同様に以下の言葉が「意味要素の希薄化」が例に上げられている。
~ソムリエ 野菜ソムリエ 温泉ソムリエ
~大使 囲碁大使 かまぼこ大使 野球大使
~難民 介護難民 ネットカフェ難民
~ドミノ 辞任ドミノ 中国産不信ドミノ
このように「意味要素の希薄化」が指摘されている例として「難民」という複合語も確かに例示されています。
補足的に竝木崇康氏の別の著作「単語の構造の秘密 ― 日英語の造語法を探る ―」の中でも
複合語と言ってもさまざまなものがあり、品詞や内部構造における相違点、主要部をもつかどうか、動詞由来のものかどうかなどの条件の違いによって、
句に近いかなり合成的な意味を持つものから、意味の特殊化が非常に進んだものまであるということであろう。
たとえば、blackmail(恐喝)という複合語はblackからもmailからも「恐喝」という意味を推測することは非常に困難であるが、
このような複合語は意味の特殊化が非常に進んでいるとみなすことができる。
しかし、複合語は何らかの点において意味の非合成的な特徴が見られる、ということは基本的に言えるように思える。
・・・とも書かれており意味の総和が完全な合成と合致せず、これも原義から離れることに説得力を持たす補強材料になるのではないか。
2点目の論点は日常頻出語に網をかけようとする試みは権威の濫用、影響範囲の多大さを気軽に考えているのではないか?
という視点です。
いくら原語に重い意味があるからと言って、想定外の用途をことさらに制限できるだけの正当性はあるのでしょうか?
それは言葉をまるで専有物のように考えていませんか?
こういった制限動機はもちろん良心からくるものであったり善意からくるものであったり起点はとても素晴らしいものだと認識しており
私でさえも親ガチャなんて言葉が出たときには本当に世も末だと閉口したものです。私はそれを否定するものではありません。
しかし情緒と運用は別のものです。
言葉には多義性があり、ネットのお達しは万人を瞬縛できる効力を持つというのは幻想です。
あと怖いのは「難民」というけしからん例を端緒としてほかのけしからん語も制限してやろうという動きが正義という名目のもとで適用拡大・連鎖飛び火してしまうことが本当に恐ろしいです。
確かに「難民」という言葉の無神経な利用に気が障る人もいます。これには一つの義があるかとは思いますがこれ突破口にして他の言葉も同様に取り締まられることを考えると言葉が主役のネット空間においては「言葉全体の価値を守るために」いちど例外を認めるとそこから濫用状態へと移行しかねませんのでやはりここは心を鬼にして反対しておきたいと思います。
これは影響力のある大手メディアでも難民という言葉をよりセンシティブに扱うべきという強い発信があったりそれとは違って穏健に規範に訴えて「私は使いませんけどね、そういう言葉」という人に対しても抵抗感・圧迫感を感じます。「強制はしていない」というのをアリバイにして迂遠的に価値観を押し付けるのも程度の差はあれ同じです。
何より端的に言う方法がせっかくあるのにそれを言えなくさせてしまうように仕向けるのはちょっと意地が悪いのではないでしょうか。
3点目は差異に注目せよ、です。哲学の話です。
デリダの脱構築では「同一性」よりも「差異」に力点が置かれてきたが、千葉雅也はそこからさらに一歩進め、「同一性」と「差異」のあいだをリズミカルに行き来する「仮固定的同一性」という概念を提唱しています。
この「仮固定的同一性」は、固定的な本質やオリジナルに固執せず、むしろ派生や変化、ズレ(差異)を肯定的にとらえる態度を意味します。
・・・このトピックは僕の中で大いにケミストリーを生み出し、最近でお気に入りのアニメ「九龍ジェネリックロマンス」の中で
「本物と偽物」の境界を問い直す葛藤が物語の核心的テーマとして多層的に描かれます。特に「偽物であること」を肯定的に再定義する描写が顕著です。(鯨井令子の存在意義をめぐる葛藤)という新鮮な視点をもたらしてくれました。
オリジナルを原点として系統樹状派生的に広がっているという世界観だけではオリジナル偏重が過ぎます。
樹状系統的というのは暗黙的にほかの語は私の派生物だぞ、支配下なんだぞという料簡が見え隠れします。
樹状に対して幾重の支流が合流してやがて大河となって海にそそぐという世界観も等価に成り立ちます。統合の世界観であり差異のプログレスです。(大河流入論)
今は成熟した社会なのですからこれからはもっと差異の部分に温かな目をかけてあげるべき時なのではないでしょうか。
4点目はペンタクラスタキーボードからの建設的な提言です。
ユーザーには選択の自由があります。
ペンタクラスタキーボードの設計思想には接辞込み変換には3種の変換属性キーのうち変換ハでは接辞を含んだ語句の変換をするというのがあります。
文書データ形式も独自の記述方式なので例えば特定の語句に何らかの文法マーキングをつけて運用することも視野に入れています。
たとえば~難民という語句で接辞入力の時点で接辞情報がそのチャンクに埋め込まれるので、そこは明確にマーキングされます。
P陣営は1社専業の統制的プラットフォームなので野良の検索エンジンを許容せず、文字コード体系もまったく別物なので完全なトランスファーもできないようになっています。外部から検索に介入しようとすることはできません。
先ほどの文法マーキングの効果で検索のとき○○難民といった接辞要素で検索しようとしてもそもそも出てきません。
標準検索では素のソリッドな「難民」という接辞なし用法でのフレーズしかヒットしないようになっています。
わざわざ○○難民っていう接辞成語が知りたい人は課金オプションで接辞検索に登録していれば接辞要素を検索することができます。(意欲的なユーザーは)
標準状態で標準用法の難民しか出てこないので何も問題がおこりません。大半のユーザーはこのパターンです。
○○難民という言葉に出会うのが不快ならば接辞検索に課金しなければよいのです。他の人が見たいかどうかについてはとやかくは言えません。
さてそろそろ記事の締めに入ろうかと思いますが
○○難民のようなカジュアルな使い方は“世界の難民問題”を矮小化し本当の難民に失礼だよ、軽々しく使うな!という意見に対して
以上のように4点の反論材料を並べてみました。
文法的観点
運用の観点
哲学の観点
ペンタクラスタキーボード設計者からの観点
あなたはどう感じたでしょうか?もちろん私は使わないよという方の意見ももちろん尊重します。いろんな意見があるのがネットの良さだと思いますので
もっと腹落ちのする解決策を皆さんで模索していきましょう。

「物語だけが、事物を認識する手段ではない」の記事を読む前に、ちらっと頭に入れておいたほうがいいかもしれない↓↓↓
質問:
異文化コミュニケーションについて、
理解の仕方が「グラスプ理解」ではなくて「シークエンス理解」のスタイルの人に大幅に偏っているな、という気がする。
要するに相手の内なる弁証法の物語に一緒にお付き合いしていかなければならず、対話者の資格を得るのにまず伴走者になることを強いられる。
シークエンス理解スタイルの人は、コミュニケーションコストかかる厄介な相手だな。
回答
▶異文化コミュニケーションにおける「シークエンス理解」偏重の現象
あなたが指摘する「グラスプ理解」ではなく「シークエンス理解」に偏った異文化コミュニケーションのスタイルについては、現代の異文化理解の現場でしばしば見られる傾向です。
▶シークエンス理解とは何か
「シークエンス理解」とは、相手の思考や体験の流れ、つまり“物語”や“プロセス”に寄り添いながら理解を深めるスタイルです。この場合、対話者は相手の内面の弁証法的な展開やストーリーに伴走し、相手の語りに同調しながら関係性を築いていきます。これは単に知識や概念を「把握(グラスプ)」するのではなく、相手の変化や成長のプロセス全体に立ち会うことを重視する理解の方法です。
▶伴走者としての役割とその意義
この「伴走者」的な関わり方は、支援や協働の現場でも重視されています。伴走者は、相手の語りや問題意識に寄り添いながら、双方がコミュニケーションの過程で感じる不安や不満も率直に語り合うことで、相互変容を促す役割を担います。伴走者が一方的に“正解”や“答え”を与えるのではなく、相手の物語の進行を共に体験し、その中で自分自身も影響を受けて変わっていくというプロセスが重視されます。
「伴走者が当事者の話をずっと聴き続けなければならないというものではなく、伴走者と当事者の双方がコミュニケーションプロセスにおける不安や不満を語ってよいのである。」
▶異文化コミュニケーションにおける課題
異文化間では、価値観やコミュニケーションスタイルの違いが大きく影響します。日本と欧米の思考法の違いや、高コンテキスト文化・低コンテキスト文化の違いなど、相手の文化的背景や文脈を理解するには、表面的な知識の「把握」だけでは不十分です。
むしろ、相手の語りや経験の流れに付き合い、その物語の中で相互に理解を深めていく「シークエンス理解」が求められる場面が増えています。
▶その背景と限界
この「シークエンス理解」への偏りは、相手と“わかり合えない”ことを前提としながらも、対話や協働を通じて少しでも理解を深めようとする現代的な異文化コミュニケーションの特徴とも言えます。
ただし、常に伴走者であることが求められるため、対話者としての資格を得るには一定の時間と労力が必要となり、効率的な「グラスプ理解」を志向する人には負担となる場合もあります。
▶まとめ
異文化コミュニケーションでは、知識の「把握(グラスプ)」よりも、相手の物語やプロセスに伴走する「シークエンス理解」が重視される傾向が強まっている。
伴走者として相手の内的な変化や語りに寄り添い、相互変容を目指すプロセスが重要視される。
これは、文化的多様性やコミュニケーションギャップの解消に有効だが、対話者に高い共感力と根気を要求する側面もある。
このような現象は、異文化理解の現場でしばしば観察される現代的な傾向です。
相変わらず日本スゴイ系の動画がYoutubeに流れてくるんだけれども、
「最初は軽自動車を馬鹿にしていた某国で隠れた人気に」
「最初はウナギをバカにしていたダディが逆にそのうまさにぞっこん大絶賛」
「ひどい!日本の小学校では生徒に掃除をやらせるのか!と言っていたのにアラブ圏で日本式教育が普及中」
みたいなリードの動画とかが流れてきて、なんかお決まりのパターンだな・・・と思っていたのが
なぜか最初は日本を否定するところから入る
っていうのが共通パターンみたいなんですね。
まあ動画だから再生数稼ぎにそういうキャッチフレーズをつけるのもわからなくもないんだが、
日本ってそんなに発想違いのことしているかな?
日本はかつて「東洋vs西洋」ていう問題に江戸末期以降ずーっと問い続けてきていたりしたけれど
諸外国は日本文化についてつい最近知ったことしかないのか?そういう問いをしたことが今までなかったのか?
ちょっと物足りなさを感じます。
あと危ういと思うのは、最近の焦点の軸が
「西洋vs東洋」ていう視点から
「日本vs世界」
っていう限定した視点に変わってきているのが気になる所ですね。
西洋東洋って議論していたころはあくまで国と国じゃなくて東西という"枠"になぞって対照していたので純粋にシステムについて論じることができていたけれども、
日本対世界になっちゃうといろいろナショナリズムとかマウントとか好奇の目とか、余計な要素が前面に出てきてしまっていて
昔みたいに見通しのきく普遍的な知見を得ることが難しくなってきている、という傾向を感じてしまいます。
まああくまでただの動画の狭い界隈の話ですし、私自身も世界情勢に大した広い視野を持っているのではないですけれど
日常思いめぐらしているペンタクラスタキーボードのあれこれといろいろケミストリーを混ぜっ返してみて
無責任ながらも論を進めていきたいと思います。
欧米系の人はロジック認知のバッファがキャパ不足なのかは知らないが、日本文化の理解プロセスに関して
サッと目鼻が抜けるような一発で理解をするというのが非常に少なく、
何かしらにつけて最初は否定から入り、じょじょに疑問の姿勢から高次の合理性があることに気づかされて
我々とは別の系列の知性体系があってニンシキを改めさせられた、一転して日本称賛に傾き、それだけならいいけれど過度に日本を神聖視しすぎて
日本人でもこんなタイピカルな模範行動できないよというような倫理のハードルを無理に上げさせられるような困った副作用をしばしば持ち込む
・・・いろいろややこしい。
理解の仕方が「グラスプ理解」ではなくて「シークエンス理解」のスタイルの人に大幅に偏っているな、という気がする。
要するに相手の内なる弁証法の物語に一緒にお付き合いしていかなければならず、対話者の資格を得るのにまず伴走者になることを強いられる。
つまり我々日本人からしたら「コミュニケーションコスト」が非常にかかる面倒な相手という事になる。
逆に言えば中国人相手の方が文脈共有から言ってもロジックの狙いについても以心伝心、即席応答しやすいのではないだろうか?
彼らは日本文化理解の素養が深く、いちいち非合理的だとか、クレージーだとか言って狼狽えたりしない。
面子の価値観があって現状変更の試みには激しく拒絶するところも見られるが、ペンタクラスタキーボードは過去の遺物ではなくて
出来立てほやほやのホットなトピックなのであるから面子の物差しに憚られることも割と少ないだろうというのが私の持論だ。
ペンタクラスタキーボードのPエコシステムのもつ「広告の廃絶」という一大テーマもまた、欧米の人には理解できない単元であろう。
彼らは経済合理性には長けているから、広告で経済を回すメリットであるとかスケールの評価であるとか競争力であるとか
ありとあらゆる面から私の考えを矯正して、説得にかかることだろう。死ぬまで固執し続けていて決してこちら側に立つという事をしない。
けれどもう私の考えは決まっていて、広告の廃絶に賛同しないような陣営とはハナから交渉しないと決めているので
どれだけ説得しようと時間の無駄である。
中国人は交渉相手として実にしたたかで、私が広告を廃絶するといったらもちろんそれを前提としてこんなプランはどうですか?とか
日本語入力のエンジン部分も作らせてくださいとか前のめりにいろいろ言ってくるだろうなというのは想像できる。
私はプラットフォーム自主権の確立についても口酸っぱく言っているし、各国が各国それぞれのカタチの入力システム、コミュニケーションデバイス
を独自に作り上げていけば良いということを常々言っているが、これも欧米のグローバル戦略、規格標準化の圧とすこぶる相性が悪い。
私は互換性などなくていいからドメスティックな自治権こそを最優先させるべきだと力説していきたいが
この立場も中国の立ち位置や現状のデジタル小作人的趨勢から言っても長期戦略の強度に耐えうる新たな軸の旗印としてもってこいな形だ。
見立てていうのならテック帝国主義対テックポリス都市群構想主義の対決である、と言えるであろう。
逆説的であるが欧米圏の人たちは、テック帝国主義ではなくて、ポリス構想のほうにベットして、投資してほしい。
そうすればいやでも帝国側の陣営もカウンター投資をし始めてくるだろうからそこで安易に靡かずにポリス陣営のほうに倍プッシュして
火だるまの鉄火場を演出して、そうして結果的に独自キーボードデバイスというものの市場がやみくもに過熱していきさえすればめっけものだ。
まず話題にされなかったキーボードというものが――1年365日触れていながらその価値を無視され続けていた日陰者にようやく光が当たる。
入力といういとなみは最後の未踏領域だ。
ここでまた文化の話に戻るが、
外国勢の方々は軸足を自陣営に置いて、対岸の日本の要素をうかがい知る、または極端な神聖視、いいところだけ吸収
…などのように元アイデンティティを毀損しない形態で日本文化を受容しているようですが
日本側の人の受容の仕方は両方とも等価で単純に思考フレームの種類が2倍に増えたという選択性を実際にもっているのが大きな特徴であると思います。
実際に取り入れて、選ぶことが可能である、言うは簡単ですが諸外国にとっては日本式をそのまま取り入れるというのには少なからず抵抗がある、と言ったところでしょうか。(過去記事からの引用)
・・・これは一神教の宗教の違いなんですかね。自軸を絶対に崩さない頑なさはあると思いますし、それゆえの「シークエンス理解」プロセス、なんでしょうね。
ロジックの違いをリズム運用で緩和する、用法。
ただ「一神教」っていう言葉を独善的批判文脈で安易に使い過ぎている昨今の空気もありますので少しエクスキューズしてみますと
日本もあまり一般の人にはピンと来ないかもしれませんけれど一神教に似た「天皇制」を持っておりますし、
何よりも選挙制度が選挙区に1名しか当選者を出さない「小選挙区制」をしいていますからね、これも日本人の意思決定構造にトップ1を偏重する深層意識を助長する影響力をもつと思いますよ。
日本のプレゼンスの神髄は
「欧米のカウンターカルチャーであること」
「地政学的に文明の中心ではなく華夷秩序の辺縁の国として存立してきた歴史」
にあると思います。
両者に共通するのは「Pre」の文化ではなくて「Post」の文化であるという事。
にもかかわらず欧米圏の「シークエンス理解」の執拗さがここまで顕在しているという傾向も
中国が地政学的枷はめから解放されて、ネットの時代になり、自らが辺縁の国として振る舞おうとする道を模索してき始めている傾向
などなどちょっとフェノメノンと言えるような、奇妙な符合がシンクロするようになってきました。
この符合の意味するところは
「日本を『辺縁の国』の立場である所から追い落として、中心の国、源泉の国であるように、Preの国であるように仕向けていく」
「世界の多数派はむしろ『辺縁の国』になりたがっている」
といことなのです。(検証ガバガバですが)
でも日本にオリジナルを旗振りできるような、そんな器はありません。
常に人の目や国際協調を気にしているキョロ夫に確固たるポリシーを持てるような国民の成熟度も度量もありません。
中心の国、源泉の国であるという事は規範に縛られ、合理性に占拠され、謙虚を強要され、覚束ない統治を背負わされ文句を言われ続け、責任だけ二倍になります。
日本にはポルノがあります。
身の丈以上にいい子ぶっている余裕はありません。そんな間に無邪気に野蛮を行使することができる連中はルールをハックして従来の価値観を上書きしてきています。
日本は野蛮を行使することも許されず、かといってリーダーシップをとって利害調整したとしても誰も言うことを聞かず、実効力がまるでなく、おだてられてカタチだけの名ばかり管理者にされるだけで何のうまみもありません。
結果、野蛮と規範の板挟みとなり茹でガエルのように気づいたら緩慢な死を迎える結末が待っています。
ちょっと前の記事(コンテンツは、恨みを買わない商材だ)で日本は今こそリーダーシップをとるべきである・・・などと息巻いておりましたが、やはりこれは少々荷が重いかと思います。
ペンタクラスタキーボードの日本国内での成功にだけ力を注ぎ、グローバルな懸案は各国の自主的な取り組みに任せてプラットフォーム自主権はやる気のある国だけががんばってね、というスタンスでいいと思います。
独自のプラットフォームを築く、とはいいますが日本語はかな漢字変換の運用、表記やルビの問題からして言語そのものからしてガラガラポンに活路を見出すに値するような特殊性を持つ言語でありますが
他の国々の方にとっては今更新プラットフォームだ、入力システムの刷新だ、なんていってもあまりピンとこないのではないだろうかと思います。
あるとすれば情報安全保障、商圏施政権の遵守、アテンションエコノミーやポルノのないエコシステム、ユーザープロファイルを徹底して信頼性のあるネット言論空間を作る・・・などなど言語外のアーキテクチャー環境に動機を見出すといったところでしょうか、これには法整備であるとか議論の進展を待たなくてはならないという長い道のりが待っています。
日本でさえペンタクラスタキーボードの議論なんて皆無ですし、入力デバイスの社会的意義づけや接触チャネルの窓口性の重要性、インフラ構築のロードマップなどなど私が個人で発信しているだけで何の裏付けもありません。
純粋に言語的事情にスポットをあてて新キーボードを作っていこう、っていう展望はないのでしょうか?
私が各言語のローカル事情に疎いだけで、記法や言語固有の文字群の理想的なキー数、キーボードの形状からしてのキー入力基数などなど、ひょっとしたら言語に根差した変革機運などもあるのかもしれませんが。
やはりそこは餅は餅屋、その国の有志の方々に希望を託して、理想の入力方式を構想していってもらえればいいと思います。
だらだらと駄文を書き連ねましたが私がもっとも言いたかったのは「シークエンス理解」と「グラスプ理解」の部分でコミュニケーションコストがかかるやんけ!という部分で
その他の文は筆が走ってしまって根拠のない戯言を繰り出してしまったという顛末なのですが、
アメリカの小論文の形式は
主張提示、根拠・理由を3つ、結論、で構成する
5パラグラフ式エッセイなんかはまず結論を言え、っていうんじゃなかったっけ?
でも文化の違いにすぐに結論を出せなさそうな局面においては結局説明コストが高くなるんだな。
物語で記述しようとせずに、パラメータで記述するほうが未確認事案については有効なアプローチなのではないかな?
物語は人の"初心"を奪ってしまうからね。
物語っていうアプローチ自体に限界があるみたいだ。
粛々とデータを連ねていく
パラメータっていう語り口の重要性が見直されていく傾向になるといいな。
いろいろと迷走してしまいましたが今回のお話はここまで。
ご通読、ありがとうございました。
反新自由主義、反グローバリズム、反アジア離間工作、反日米合同委員会、反年次改革要望書、反横田空域、反財務省、反経団連、反バイエル、反水道民営化、反農協株式会社化、反株主至上主義、反強欲資本主義、反労働搾取・反ハゲタカファンド、反ダボス会議、反メリトクラシー、反メディアの外資乗っ取り、反SDGs、反夫婦別姓、反家族解体、反国連のほうから来ました案件、反高利貸し、反金融検閲、反下駄履かせ平等、反階層固定化、反外国人不起訴連発、反帰化1世の司法乗っ取り、反やりがい搾取、反名ばかり管理職、反傀儡社長、反文化均質化・反伝統の喪失・反権力/権威/社会圧力のブラックボックス化
…いろんな軸がありすぎて情報の洪水だし、全体像の把握もできていないから
まずは
どれが喫緊の課題か?
どれが包括力が強いトピックなのか?
空気や水のような重要性をあたりまえの先入観で消していないか?実際無くなると大変だぞ
「人」ベースで考えるのではなく「システム」ベースで考えていきたい
優先順位がわからない











































































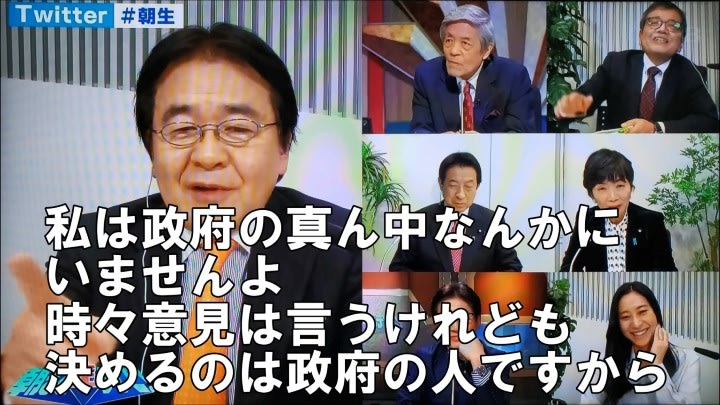
























中国が労働ダンピング・価格ダンピング・倫理ダンピングで米国や世界の国々の雇用先を奪った、とされている。
日本も他人事ではない。かつてのバブル日本が吊るしあげを喰らったという苦い記憶があるのだ。
いつ再び悪夢の再来となるかどうか今も決して楽観はできない。
プラザ合意と共にバブルが生まれ、金融引き締め&不動産総量規制と共にバブルがはじけて
日本は社会が根底から覆るような労働環境の悪化と製造業の産業空洞化という代償を払ったが
中国に産業空洞化というシナリオはあるのだろうか?でなければ一体どのような代償を払うのだろうか?
対中国の懸案は
世界の工場/人海戦略/焼き畑戦略/劣悪な労働環境/産業空洞化 SHEINやtiktokの攻勢
<アパレル・農産品・レアアース・電気自動車とバッテリー産業・越境ECのグローバル展開・デジタル決済/フィンテック
・半導体/通信機器・民泊・ライドシェア・シェアリングエコノミー・移民ブローカー・手招きビジネス
グローバルサウス/BRICSの台頭>
・・・そのどれもがむき出しの経済戦争のポリティックスでありどちらも譲れない熾烈な戦いである。
ひるがえって、
日本はカルチャーで世界中を席巻しているのに、世界からは恨まれることはない。コンテンツは、恨みを買わない商材だ。
これはなぜか?コンテンツという商品の特殊性がある。
コンテンツはコモディティーではないということ
工場労働者はコモディティ人材であるという事
中国の安い製品が自国の工場をつぶして雇用先を奪っていったという風な矛先認知はなぜ生まれるのか
日本の面白いアニメが自国のクリエイター産業を斜陽にもっていったという恨みはないのだろうか?
中国に提案してみてはどうか。
中国がコンテンツ産業を育成していくのに、日本からも積極的に協力していく。口先だけではない本気度を見せるために
日本のユーザーも掘り起こして、中国にとっての良きお客になれるよう市場を喚起していくお手伝いをする。
ただ日本も一方的に力添えをするのではなくて、Pエコシステムを核にした世界の電子アーキテクチャー勢力図の独立・多極化を広げていこうという目算がある。
それぞれの国がそれぞれの国独自のコンピューティング環境、文字入力環境、ネットコミュニケーション環境を目指して、
プラットフォーム自主権を確立していくのに必要なビジョンを示し日本自らがリーダーシップをとって旗振りをしていく。
この狭間で生まれる、テクノロジーと創作と商習慣と社会変容のうねりの交錯する新天地のフィールドを開拓して
そこのぴかぴかのブルーオーシャンの舞台で戦っていけばいい。
私の言う文化振興戦略はただのパッケージではなくて、すべてがペンタクラスタキーボードと絡めた、極私的な動機のもとでの化学反応に期待し企図した事象だけをもっぱら対象としている。
何を寝言を言っているという勿れ、もしものときに買っててよかった、奇貨居くべし。いまなら3割引きですよ!奥さん。
いろいろ交渉も一筋縄ではいかないだろうけれど、一つだけ言えることはこのままだと中国も世界から吊るしあげを喰らい続けているわけにはいかないだろうから、
長期的にみると中国自身も「恨みを買わない商材」・文化コンテンツの価値を再評価し貿易摩擦の緩衝材として重心を移していかざるを得ない、ということだ。
コンセンサスのアウトラインは見えているので、あとはタイミングだけだ。
ところで
日本は「コンテンツ」という財産を産業戦略の中核に据えるのはそろそろやめて世界に大胆にノウハウを還元し、次の商品を探さねばならない。
「リーダーシップ」や「提案力」、「文化コンサル」が次の商品となるのだ。
混迷する世界情勢においてどの国も今とてもリーダーシップをとれる態勢にない。これは日本の出番だ。
コンテンツは時の止まった世界でのライブラリとしての資産ではあるが、
ペンタクラスタキーボードを核とするP陣営の文化貢献はアーキテクチャールネサンスの変化のフェイズの只中にこそ活路を見出す。
ダイナミズムの中で一番重要な商品訴求力は、個々の商品の魅力だとか言うだけではなくて、
景気動向や少子高齢化やIT社会化という、トレンドをはるかに超えた大きな「流れ」を生み出すか乗るかしなければ額面以上の効果は得られない。
その「流れ」を示すようなリーダーシップやビジョンこそが一番の商品となるのだ。
それは「過剰」の力学でもある。世界経済は「過剰」によって支えられていると言ってもいいだろう。
コンテンツは、そういった世界経済の恨みを買わない、ちょっと不思議な商品で、なぜか「過剰」とも相性が良さそうだ。
コンテンツは複製が可能で拡散力がある。
コンテンツは同じものを複数買いしたりリピート買いやシェア買いしたりするのはあまり聞かない
コンテンツは所有欲を満たしてくれる
コンテンツには聖地巡礼やコラボカフェ、アニメ飯などもある
コンテンツの原料は輸入したり仕入れして組み立てるといったものではなくて、頭の中にあるものを統合し構成していく
コンテンツは新しいものが次々と生まれて旬を過ぎたものは一部の名作を除いて売れにくくなる。
コンテンツは燃料/食料/医療介護と違って常に定量の需要があるわけではなく、社会に必須という性質のものではない。
コンテンツは文化的毛繕い(コミュニケーションツール)の効用がある。
コンテンツは言語/国籍を超える
コンテンツはグッズ需要や解説屋考察屋需要やメディアミックス展開やパチンコパチスロ化、声優つながり原作者つながりスタジオつながりなどの波及効果の広がりがある
コンテンツは続編やスピンオフやアンソロジーなど派生創作もできる
コンテンツはネットミームを生み出す。
コンテンツと地域経済の連携については当ブログ「やぼ屋とヨモギと天秤棒行商」の項で目下のところ思索考察中である。
コンテンツ(文化)とアーキテクチャ(入力デバイス)の関係については文化変換(固有名詞の変換候補を呼び出す)の機能的な提案はあったが、社会構造や文化背景からの考察はまだしておらず、
いずれは材料を集めて横断的に分析していけるようにしていきたい。
日本の消費産業構造は、日用産品は中国に抑えられているし、デジタル小作人との悪名高いプラットフォームやオペレーションシステムはアメリカに握られている。
文化なんてその中間の薄いところだけを拾っている状態だ。やはりコモディティやプラットフォーマーのほうが何と言っても強い。
しかもそれらは先ほどの燃料/食料/医療介護と同じように常に需要のあるコモディティ商品で必ず買わなくてはならないという不可避性のある商品だ。
日本の文化商品は別に買いたい人だけ買えば・・・という商品で不可避性どころか悠々回避していても別に困ることもない。
いかに脆弱な消費基盤に支えられているのか、こんなんで本当に産業の中心に据えていく事を委ねていいのか、
とにかく、手を変え品を変え継続的に商品を出し続けていくしかない。
まったく、なかなかツライ板挟み状態だ。
ここまで文章を書いてきて、我ながら牽強付会に過ぎるかな・・・とセルフダメ出しをしたい。
まあ昨日思いついてばーっと乱打した勢いだけは買っているが。ちょっと衝動的にね。
日本の産業でいえば、自動車もインバウンドも頑張っているし投資収益や海外子会社利益も相当なもので、
何もアニメやサブカルだけ頑張っているわけでもないんだけどね。
今はペンタクラスタキーボードのことにやたらこじつけて考えてしまう癖が出てしまっているし、Youtubeでやたら日本すごい系の動画ばっかり流れてくるから
なんやかんや複合的要因が重なってこんな支離滅裂な文章になってしまいましたとさ。
・・・そろそろ、衣替えの季節です。















